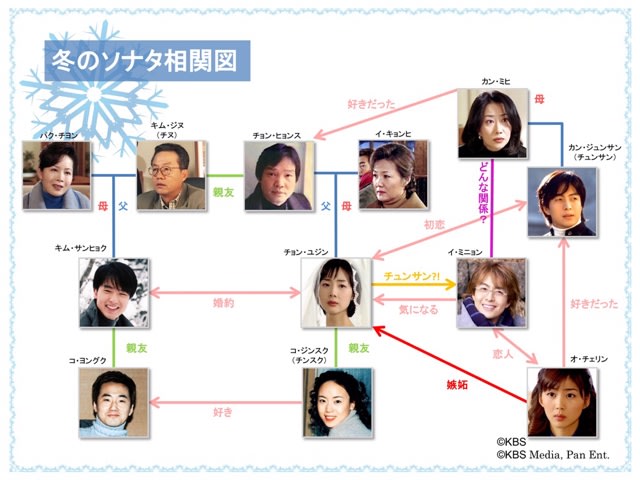
次の朝、早起きしたミニョンは、春川のバスターミナルでユジンを待っていた。相変わらずユジンは時間通りには来なくて、ミニョンは時計を見て苦笑いしていた。するとそこに、全力疾走したユジンが、勢いあまってミニョンにぶつかりながら飛び込んできた。
「待った?」
「遅いぞ。チョンユジン、ちっとも変わってないな。相変わらず『遅刻大魔王』だ。」

「なんですって?」
ユジンは口をとがらすと、さっさと行ってしまうミニョンの背中をバシッとたたいた。今の二人には何気ない会話も、昔のように心置きなくできるのでうれしかった。昔の記憶を取り戻したことで、二人の距離は確実に縮まっていた。

「ごめんね、母さん。渋滞でバスが遅れちゃって。今日はユジンと一緒に来たよ。」そういうと、ミニョンはミヒのトランクを持ちに行ってしまった。
ミヒはユジンが一緒なのを見て眉をひそめながらも挨拶をした。正直、恋人として夜を過ごしていなければ良いな、手遅れにならないように、と考えていた。
「お久しぶりね。元気?」
ユジンも同じ挨拶をしてぺこりと頭を下げた。
ミヒはユジンを見てつくづく思った。ヒョンスに似ていると。透き通るような色の白さや、少し垂れた善良そうな目、すらっとした長身のスタイル、優しい物腰や雰囲気まで彼にそっくりだったのだ。なぜ今まで気が付かなかったのか、不思議なくらいだった。
「あなたって、お父さん似なのね。」
ミヒは思わず口に出した。ユジンは一瞬びっくりして「え?」と言った。
「あの、あなたってお父さんに似ているのかしら?」
「はい、よく言われるんです。わたし、父にそっくりなんです。」ユジンははにかみながら言った。
そこに荷物を持ったミニョンが帰ってきたため、ミヒはさっさと歩きだした。ミヒがハイヤーに乗り込む前に、ミニョンは無邪気に尋ねた。
「母さん、僕に何か話があるんじゃなかったの?」
するとミヒはちらりとユジンを見て答えた。
「戻ったら話すわ」
そしてさっさと車に乗り込んだ。後ろからユジンが「お気をつけて」というのにも無反応なままに。

そんなそっけない態度のミヒを不思議そうに見るユジンだった。そして、一瞬だけ、さっきミヒが亡き父を知っているような素振りをしたことを思い出して、不思議におもうのだった。しかし、すぐに忘れてしまった。ミニョンとユジンは、ミヒの態度に苦笑しながらも、気にすることなく、お腹がすいたから、昼ご飯をどこで食べようかと顔を寄せ合って相談するのだった。その姿は幸せそのものだった。

昼からミニョンはマルシアンに出社していた。打ち合わせを終わるとキム次長がパズルを見つけていった。
「このパズルは何だよ?お前、わざわざ崩したのか?お前の考えてることってホントに分かんないわ。」
キム次長はあきれたように言ったが、ミニョンは何も言わずに笑っていた。ミニョンはユジンとミニョンとしてであった頃のことを思い出していた。そのころ、キム次長はこう言っていた。「チョンユジンさんが、パズルを作る理由を教えてくれたんだ。忘れられない思い出のかけらを集めているんだろうって。きっとお前には忘れられない女がたくさんいるんだろうな。」と。キム次長の言うことは、当たらずとも遠からずだった。ミニョンがチュンサンの記憶を取り戻したことによって、ミニョンとして作ったパズルをもう一度壊して、チュンサンとして作り直したくなったのだった。チュンサンにはまだまだ忘れたくない思い出がたくさんあるのだろう、ミニョンは一人微笑んだ。キム次長が部屋から出て行こうとしたので、ミニョンは呼び止めた。
「先輩、明日の夜は空けておいてくださいね。」
「お前どうしたんだよ?」
「うちで食事でもと思って。」すると、キム次長はそれを引っ越し祝いだと思ったようだった。本当は違ったが、ミニョンはあいまいにうなづいた。
「引っ越し祝いときたら、次はいよいよ結婚式だな。まあ最近は順番がごちゃごちゃになってるから、予行練習だと思ってお幸せに。それにしてもうらやましいな。」そういうとキム次長は出て行った。

ミニョンは楽しそうに「予行練習かぁ」ともう一度パズルに取り組み始めた。その時だった。またあの映像がよみがえってきた。なぜかキムサンヒョクの家をのぞいている様子や、体育の時間にジャージ姿でサンヒョクに絡んでいる自分、カンミヒとキムサンヒョクの父親が一緒に写っている写真が見えた。でも、なぜその映像が繰り返し頭に浮かんでくるのかさっぱりわからなかった。
その日の夜、ミニョンはユジンと待ち合わせをしてスーパーに行った。気が付くとそこでもミニョンはその映像を思い出していた。「チュンサンてばっ!」ユジンに話しかけられているのも気が付かずに、ミニョンはぼんやりしていた。ミニョンはあわてていろんな野菜をかごに入れた。
「ちょっとチュンサン、こんなに野菜を買ってどうするの?食べきれないでしょ。」
「僕が全部食べるから大丈夫だってば。」
ユジンはあきれた顔でチュンサンを見るのだった。

二人は山ほどの食料と一緒に帰宅した。そして仲良く袋から食材を取り出した。すると、ミニョンがうれしそうに言った。
「なんだか夫婦みたい」
「えっ?何が?」
「こうしていると、新居に友人を招く新婚夫婦みたいじゃない?」と嬉しそうにミニョンが言っても、ユジンはあきれたような顔をして、話題を変えた。
「そんなことより、こんなに買ったのに、全然食べきれそうもないわ。捨てたら許さないからね。」
「明日食べるから大丈夫。」
「これ全部?」

ミニョンは意を決して言った。
「うん。実は明日は僕の誕生日なんだ、、、。」
今度はユジンがびっくりする番だった。ユジンは今までチュンサンの誕生日があることすら念頭になかったのだ。もちろん、いつが誕生日かを聞いたこともなかった。
「そう、誕生日。10年もの間、誰にも祝ってもらってないから、明日はこれを全部料理して、盛大に祝ってよ。そうそう、明日はキム次長も呼んであるんだ。」

チュンサンはそういうと、食材を冷蔵庫にしまいに行った。ユジンはそんなミニョンを見て思った。チュンサンは友人含めて皆に祝ってもらいたいのだと。ユジンの記憶のチュンサンは、母親はいつも仕事で自宅におらず、食事も一人きりで食べる孤独な少年だった。しかも、10年もの間、死んだことになっていて、ミニョンとして誕生日を迎えたものの、チュンサンとしてはだれもおめでとうを言っていない。きっと寂しかったのだろう。ユジンはミニョンの言う通り、10年分のおめでとうを言って祝ってあげたいと思うのだった。その時、ミニョンがオーディオのスイッチを入れた。それは、サンヒョクがやっているクラッシックの番組を聴くためだった。ミニョンは母親が音楽家らしく、普段からクラッシックも好んで聴いていた。ミニョンはサンヒョクの選曲が好きで、よくうれしそうな顔で聴いているのだった。ユジンは、そんなミニョンの横顔を見て心を決めた。チュンサンのために皆を集めて誕生日を祝おうと。



























