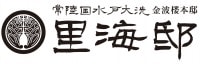以前、水戸の観光セミナーの控え室で、黒川温泉を築き上げた観光カリスマ「後藤哲也さん」とお話する機会があり、本人からこの本で勉強しなさいと勧められていたので、amazonで購入しました。ディズニーリゾートの経営幹部まで学びに来ている後藤哲也さんの観光経営の哲学をしっかりと学んでゆきたいと思います。
のっけから由布院の現状に対する疑問が展開されており、非常に読み応えがあります。
年間400万人の屈指の人気温泉地である由布院―
名所旧跡が一つもないのに人を引きつける魅力は、地元の人々が成し遂げた地域おこしの成果であり、ゴルフ場反対運動、独ヴァーデンヴァイラーへの視察、手作りイベントの数々により由布院は日本を代表する観光地に発展しました。
地域活性化を研究する上では、私にとって隅々まで吸収したい観光地づくりのノウハウが由布院にはあります。
実は大洗町は、交通的要素、地場産業構成、保養地特性などが由布院と地域モデルとして似ているところがあり、由布院の発展や現状の問題点は今後の大洗の観光の行方を考えてゆくのに学ぶところが多い観光地です。
後藤さんの由布院に対する考察を大まかに紹介します。
・・・由布院はその人気ゆえ金儲けをしようとする外部資本が大勢やってきて、メーンストリートのお店のほとんどが地元の人が経営していないので、最近は夜お店を閉めてしまうところが増えています。また由布院の雰囲気に合わない宿泊施設が増えており、本来の由布院の田舎らしさが失われている・・・・・・
・・・・・・由布院は宿泊するための観光地というより、「通過型」の観光地になりつつあります。由布院の名につられて昼間にツアーのお客さんが来ている。由布院の通りを歩く人の多さは大変な数で、土日は人の波をかき分けて進んでいくようなところで、ゆっくりと落ち着けるわけがない。その上田舎の田園風景が崩されているのだから、残念ながら「由布院らしさ」はもう消えてしまいつつあります・・・・・・
うーむ。現状の大洗も同じ道をたどっていますね。
後藤さんは、由布院と同様の事が軽井沢にも起きていると指摘しています。
軽井沢のメーンストリートのお店は東京の銀座みたいな雰囲気になってしまって、こちらも外部資本が出店しています。街が東京と同じような雰囲気で、土産ものというより東京と同じもんが並んでいるので、買おうという気にならないそうです。
どちらの観光地も交通網の発達が起点となって、外部資本のお店がどっと増えて観光地の魅力が失われてゆくのであるということです。
大洗は由布院や軽井沢とは成熟の度合いこそ異なるけれども、温泉・湯治場や、大規模な自然景勝や史跡名所で賑わう観光地とも違う「保養リゾート地」です。
誤解がないようにここに書きますが、現状の由布院や軽井沢に問題があると指摘されつつもも、これらの観光地には多くの学ぶべき事があります。実際、後藤さんの酷評はまるで大洗のことを言っているかのように感じました。
成功している観光地や流行のお店を追いかけるよりも、国内外を含め地域モデルとして大洗と類似点の多い観光地の生き様をじっくりと学ぶべきと思います。
良いところは吸収し、問題点は我が町もそうならないよう注意したいものです。
海沿いの観光地も参考になるところがあるといいんですが。。。












 でも東京の喧騒の中にこんな空間っていう非日常性を考えたら高いのは当然かも
でも東京の喧騒の中にこんな空間っていう非日常性を考えたら高いのは当然かも