
◇先週の講座は、建蔽率・容積率・斜線制限・日影規制を扱いました。
◇建蔽率の規定は、皆さんの習得率は順調で、演習結果もまあまあなので、解説は割愛します。
◇容積率は、1点だけ、図形問題で「特定道路」が絡むと、突然、間違える。
◇様々な要因がありますが、二級の過去問で、単体出題はありますが、複合出題は無い。
◇ここは一級の過去問を使って、特定道路を含む図形問題とし、レベルアップを図りました。
◇簡単な話なので、一回慣れると、あとは順調に知識を習得していくようです・・・よかった!
◇斜線制限の規定では、北側斜線の緩和条項で「公園」を含む場合に、道路斜線のように緩和されません。
◇条文をパワーポイントで比較して見せて、北側斜線では「公園」の緩和が無い事を理解させました。
◇二級の過去問でいうと、H27年問題に、この緩和条項を扱っている図形問題が出題されています。
◇この問題は、いい問題だとます・・・以後、なかなか見ない問題ですねぇ~・・・
◇今年の受講生は、2方向道路の道路斜線制限の問題に強く、解説が楽でした!
◇過去問をよく勉強している証なのか、制限距離を含む一級の問題の演習でも、難なく正答しています。
◇ただ、宅盤差がある図形問題の段差計算処理に弱みがあります・・・今週はその復習をする予定です。
◇道路斜線は、道路中心線からの高さを計算しますが、試験問題は、建築物の高さを要求してきます。
◇そう、建築物の高さは、地盤面から計算するものです・・・道路中心線からの高さとは異なります。
◇そこで受講生が躓くのは、北側斜線の緩和条項で、北側斜線の場合、同じ地盤面から計算します。
◇従って、道路斜線のような、宅盤差の調整はいらないので、この部分で混同するようです。
◇どちらも、断面図形を示して説明すると納得するので、図示解説の重要性を痛感します。
◇あと斜線制限の規定で躓くのは、建物後退緩和の適用の有無を判断する小規模建築物の規定です。
◇令135条の12の特例規定で、ここでも道路中心線からの計算から地盤面からの高さへの変換計算です。
◇総論で言えば、平面図形には強く、立体図形に少々弱みを持っているのが、今年の受講生の特徴かなっ?
2025年6月10日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者












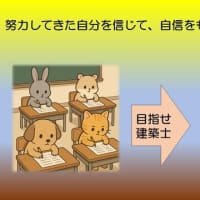
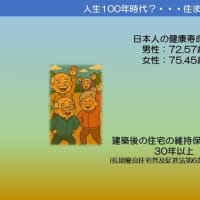
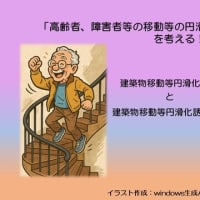
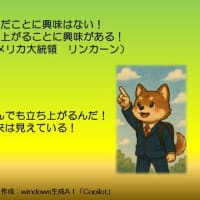

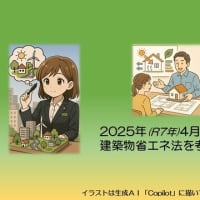






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます