「べらぼう」ゆかりの地ラン、続きです。
その1では、浅草&吉原周辺のゆかりの地や、人気の神社などをご紹介。
その2では、日本橋小伝馬町や神田周辺のゆかりの地をご紹介します。
この日廻ったルート(その1&2の全ルート)はこちら。
浅草駅→浅草文化観光センター→雷門→浅草寺→「べらぼう」江戸たいとう大河ドラマ館→待乳山聖天→正法寺(蔦屋重三郎の墓碑)→見返り柳→吉原大門跡→江戸新吉原耕書堂→吉原神社&九郎助稲荷→鷲神社→浅草橋でたい焼き→小伝馬町の蔦屋重三郎の耕書堂跡→伝馬町牢屋敷跡→十思公園内の吉田松蔭終焉の地碑→長崎屋跡→平賀源内住居跡→三越前駅ゴール。
大河ドラマ館、吉原、鷲神社を参拝したあと、江戸通りを4キロほど南へ走って日本橋小伝馬町へと向かいました。
途中、浅草駅→田原町→蔵前→浅草橋と下町の問屋街を通るのですが、魅力的なお店がいっぱいでキョロキョロしちゃった。

田原町といえば「かっぱ橋道具街」、蔵前といえば文具やレザーなどの職人街、浅草橋といえばビーズやひな人形の問屋街が昔から有名。
ですが最近は、オシャレなセレクトショップやカフェもたくさんできてきて、街ブラにぴったりなんです。
途中小腹が空いたので、何かつまむものを探していたら・・・、

神田川の手前で、たい焼きやさんを発見!
やけどしちゃうほどの焼き立てほやほや、美味しすぎる~

浅草見附跡前でたい焼きをぱくぱく。

見附横の神田川では、屋形船が停泊してました。
川を渡ると、台東区から中央区に変わります。

1キロほど走って、小伝馬町に到着。
駅前の大通りから少し入った東横INNホテルの前に「耕書堂跡」の説明板がありました。
吉原で最初の書店「耕書堂」を開いた蔦屋重三郎は、天明3年(1783)に一流版元が軒を連ねる一等地の通油町(現在の日本橋大伝馬町あたり)に新しい「耕書堂」を作りました。
今は説明板がなかったら素通りしているような裏通りの細い道ですが、江戸時代には目抜き通りの「日光街道」だったそう。
そうそう、東横INNでは、「耕書堂」跡地前の東横INN日本橋馬喰町をはじめ、東京都内16店舗で「浮世絵小部屋」宿泊プランをスタートしたそうですよ。浮世絵好きの外国人観光客に大ウケしそう。
せっかく小伝馬町まで来たので、伝馬町牢屋敷&処刑場跡、十思公園にも行ってみました。

お化けが出そうで、怖くて近寄れない。霊感はないけどゾクゾクする~
駅前の好立地だけれど、さすがにこの場所にマンションは建てられないですよね~


目の前の十思公園には、安政の大獄で処刑された吉田松陰終焉の地の碑が建っています。
かつては、このあたり一帯が牢屋敷&処刑場だったようです。

「時の鐘」。江戸の町に時を知らせていた鐘は、東京都指定文化財に指定されています。
お次は、小伝馬町のすぐ近くの新日本橋駅。

駅の出口を出たところに「長崎屋跡」の説明板が建っています。
江戸時代、薬種屋の「長崎屋」は、長崎に駐在したオランダ商館長が江戸に参府する際の定宿だったそう。
ちなみにですが、私が20代の頃ここから徒歩1分の出版社で働いていました。
当時は歴史にまったく興味がなく、今こうして歴史をたどる目的で戻って来るなんて笑っちゃいます。
そんな無知な私なので、この近くに平賀源内の住居(現在の旧今川中学校あたり)があったことも知るはずはなく・・・。

「べらぼう」で再び脚光を浴びているので、新しく説明板ができたそうです。
これにて、ゆかりの地ラン日本橋編は終了。
おまけ・・・。
別日に、大手町の神田橋の近くにある「田沼意次屋敷跡」にも行ってみました。場所は、経団連会館のお隣りです。

田沼意次といえば、「賄賂の政治家」という悪者のイメージが強いと思いますが、近年では「商業経済が政治に影響を与えた先駆け」と評価が上がっているようです。
評価が上がったからなのかはわかりませんが、静岡県牧之原市では田沼上げ がすごい!
がすごい!
初代遠州相良藩主となった田沼は相良城を築城。東海道に通ずる田沼街道を整備しました。
静岡県民の私は、もちろん田沼街道は知っていて何度も通ってましたが、まさかあの田沼が由来だったなんて!
って、無知にもほどがありますね笑笑
そんなこんなで、「べらぼう」ゆかりの地を廻ったレポート1&2でした。
ドラマファンなら、本所や菊川あたり(長谷川平蔵の住居跡など)を廻るのもおすすめです。私は以前街ランしているので今回は割愛しますが。
ちなみに、千代田区内の「べらぼう」ゆかりの地はこちらにまとめが出ています。是非巡ってみてくださいね→★













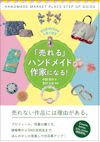

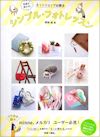






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます