

川崎宿は東海道53次の宿場として発達してきました。特に戦災を受けながら、羽田や京浜工業地帯の中心地域として発展をしており、その幹ともいえる宿の古を訪ね、又、もう一方の参詣道、大師の道をたどりながら、参道華やかな川崎大師、平間寺を訪ねます


実施日: 平成25年4月18日(土)
集 合 : 午前10時 JR川崎駅改札口前 大時計下
解 散 : 午後3時20分頃 川崎大師信徒会館
募集人員 : 30名
ガイド : NPO法人 かわさき歴史ガイド協会の皆様
参加費 : 正会員 2,000円、 準会員・一般 2,500円
(ガイド料、資料代を含みます)
コース :
JR川崎駅改札口(10時) → 佐藤本陣(上の本陣)跡 → 旧東海道と市役所通り交差点 → 問屋場跡・高札場跡 → 宗三寺→東海道かわさき宿交流館→一行寺 → 田中本陣(下の本陣)跡 → 万年屋跡 →六郷の渡し跡→ 京浜急行港町駅 → 河港水門 → 大型ショッピングモール・12時10分頃着 昼食休憩)→若宮八幡宮・金山神社→京浜急行 川崎大師駅 → 馬頭観音→ 明長寺→川崎大師平間寺→信徒会館 (ロビーにて休憩・解散 15時20分頃)
解散後 門前仲見世通り・表参道を自由散策して京急川崎大師駅へ

<お申し込みの方>
1.会員番号のある方は必ず会員番号をご記入下さい。
(ご記入の無い方は準会員・一般価格となります。)
2.緊急連絡先(携帯番号)をご記入下さい。
<当日の緊急連絡先>

國米 秀信 080-3011-1253
久保田 惣治 080-2065-5348
宮坂 英明 090-8749-2958
清水 信一 090-4177-7782
※.雨天決行です。大荒れが予想される場合には再度連絡致します

【訪問先1口メモ】
【佐藤本陣(上の本陣)跡】

別名、惣左衛門本陣といわれ、門構え、玄関付、181坪の建物でした。幕末には14代将軍家茂が京に上る際に宿泊しました。明治23(1890)年、詩人佐藤惣之助がこの家で生まれ、大正から戦前にかけて活躍し、「六甲おろし」「青い背広で」「人生劇場」など、今でも多くの人に親しまれている歌の作詞をしました
【問屋場跡・高札場跡】
問屋 場には人足と伝馬が常備されて、今でいう役所に当たるところ。当時の川崎宿は本陣も多く、大名の参勤交代が続け様にあっても対応できたのだろう。
【宗三寺】

宗三寺の創建年代は不詳ですが、鎌倉時代にあった禅宗勝福寺を起源とするものと伝えられています。勝福寺は、佐々木四郎左衛門高綱の菩提寺となり泰綱の代には檀越となるなど頗る繁栄した江戸時代、遊女を兼ねた飯盛り女達の供養等があります。
【東海道かわさき宿交流館】

東海道五十三次の川崎宿の歴史を詳しく勉強することができます。川崎宿の模型では、多摩川の渡しを越えてすぐに宿場町が広がっていたことが手に取るように分かります。フロア床にも地図が描かれています。また当時の着物も自由に試着できるようになっており、往時をしのぶ背景のセットに溶け込むように写真を撮れば、あたかも時代劇の役者気分に浸れます。
【一行寺】

川崎が東海道五十三次の宿場町として繁栄するようになり、鶴見矢向の良忠寺第十八代顕譽円超上人により、寛永八年(1631年・徳川家光の時代)この川崎上新宿の中心地に、念仏弘通の道場として開創建立されました。
別名お閻魔様で有名。仮山碑がある。
【田中本陣と休愚】

本陣は主に大名、公家、旗本などが宿泊する施設で、門構え、玄関付、延231坪の堂々たる建物でした。本陣家の主人である田中休愚は、本陣、名主、問屋の三役を兼務し、六郷の渡船権を譲り受けて、宿場の財政を立て直しました。
【万年屋跡】

万年屋(まんねんや)は、江戸時代、東海道川崎宿にあった掛茶屋。旅人のほかに、厄年の男女が川崎大師参詣の途中に多数、立ち寄ったので、とくに繁昌した。『江戸名所図会』には、挿図のみが掲載され、記事がないが、当時は説明を要しないほど知名度の高い旅館兼茶屋であった。奈良茶飯が名物であった。歌「お江戸日本橋」にも「(前略)六郷(ろくごう)わたれば 川崎の万年屋(後略)」とうたわれた。↓
江戸時代奈良茶飯で有名、皇女和宮が休憩された旅館兼茶店跡)
【六郷の渡しと旅籠街】

家康が架けた六郷大橋が洪水で流された後、200年も渡し舟の時代、華やかな旅館街となる。
【六郷の渡し跡(六郷橋)】

当初渡船は、江戸の町人が請け負っていましたが、宝永6年3月川崎宿が請け負うことになり、それによる渡船収入が宿の財政を大きく支えました。現在では、川崎側に渡船跡の碑と、明治天皇六郷渡御碑が建ち、欄干に渡船のモニュメントがあります。
【運河と水門と港町】

1918年から行われた多摩川改修工事の一環として、川崎市内を縦断する運河を造ることが計画された。川崎河港水門は、運河と多摩川を仕切る水門として、1928年3月に竣工した。川崎運河計画の一環として完成するも、社会情勢の変化により運河建設計画は中止され、部分完成していた運河はほとんどが埋め立てられ、運河は水門近くの船溜りとして残るのみとなっている。
しかし水門自体は残り、砂利の陸揚げ施設として、砂利運搬船等の出入りに現在も利用されている。
3つの願い「良縁」「子宝」「厄除」
【若宮八幡宮】

若宮八幡宮の創建年代は不詳ですが、当地周辺を開拓するために移住してきた六郷若宮八幡宮周辺の人が当社を創建したといいます。慶安元年(1648)には、徳川家光より社領3石の御朱印状を拝領、明治以後、近隣にあった藤森稲荷神社、金山神社、厳島神社(川崎区田町3-11)を遷座しています。
境内に子授かりの金山神社あり、願いの絵馬が結んであります。
【馬頭観音堂】

本尊馬頭観世音菩薩は畜生道に堕ちた人を救いあげるといいます。後に人々は馬や牛から受ける恩恵に感謝し信仰が盛んになりました。その昔、平間寺に参拝する人がお堂の格子に手綱を結ぶとどんな暴れ馬でもおとなしく待っていました。そこで赤い布に好きな人の名前を書き格子に結び良縁を願うようになり若い人のお詣りが多いといいます。
【明長寺】
天台宗寺院の明長寺は、恵日山普門院と号します。明長寺の創建年代は不詳ですが、静圓法印(永正16年1519年寂)が文明年間(1469―1487)に創建したと伝えられます。当寺所蔵の葵梶葉文染分辻ヶ花染小袖は、桃山時代に流行した絞り染めの技法といい、国重要文化財となっています。
徳川家康より拝領の「辻が花染め小袖」を秘蔵する寺
【川崎大師平間寺】

真言宗智山派寺院の平間寺は、金剛山金乗院と号し、俗に川崎大師・厄除弘法大師と称される真言宗智山派の大本山です。当地付近に住んでいた平間兼乗が川崎市夜光沖合いの海で拾い上げた弘法大師像をもとに、尊賢上人が開基となり大冶3年(1128)創建したと伝えられます。
悪いおみくじは枝に結んで厄除け!大治3(1128)年に建立、ご本尊は厄除弘法大師尊像













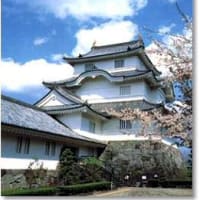







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます