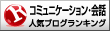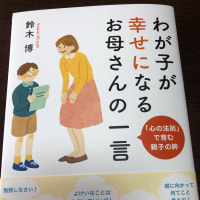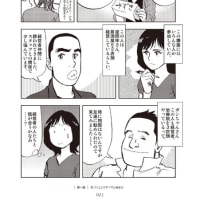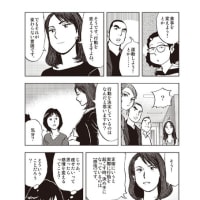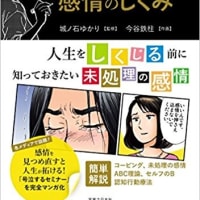フランスの経済学者、トマ・ピケティ氏の著書「21世紀の資本」は、日欧米などの租税資料300年分を分析し、1914~70年代を例外として世界で資本の集中と経済の不平等が進んでいることを指摘しました。
この「21世紀の資本」は2013年秋フランスで出版後、14年春英訳が出版、ベストセラーとなり欧米社会は衝撃につつまれました。
そんな中、ピケティは本年1月29日から2月1日まで日本にも来訪し、各地で精力的な講演活動を行いました。
今回の記事は、その中でも来日当日の1月29日夜に早くも東京都内で行われたトマ・ピケティ氏の来日講演会の記録です。日本の政財労界と活発な議論が交わされました。

ランキングに参加中です。できましたらクリックして応援お願いします!
この日のパネルディスカッションでは、なんと西村康稔内閣府副大臣が登壇していました。
実は西村君は、私の中学高校時代の同級生です。一度、衆議院選挙に落選したときには、サンテレビで吉本の名もなき芸人と温泉番組などに出ていて思わず涙した?ものでしたが、今や安倍政権になくてはならない存在になっています。
私としては、「友が皆 我より偉く見ゆる日よ 花を買ひきて 妻と親しむ」(石川啄木)の心境です。
さて、その西村副大臣は
「ピケティさんが本で書かれたように、資本が大きければ利回りが大きくなる。小さい資本だと収益性は低い」
「3.5兆円規模のハーバード大学の基金が過去10年間で10%の利回りなのに、世界最大120兆円規模の日本の年金積立金はわずか3%」
「所得の低い人であっても集めることで収益が取れる」
「従って、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の資産構成を見直してリスク資産の割合を増やすと説明しました。
と発言しました。
兵庫が誇るイケメン政治家です。
つまり、資本が大きければ利回りは大きくなるはずなのに、ハーバード大学基金の40倍の規模がある日本の年金積立金が同基金の3分の1の利回りであることは問題だ、ということですね。そこで、年金積立金がこれまで安全確実ながら低利回りの国内債券中心の運用だったものを、国内外の株式での運用に大きくシフトすることを、ピケティ教授の理論にかなうものだと発言したわけです。
これに対して、労働組合のナショナルセンターである連合の古賀会長が反論しました。
「西村副大臣、GPIFは出してほしくなかった。年金積立金のほとんどは労使が拠出したお金です。それをあまりにリスクの多い投資に回すのはいかがなものか。 拠出している労使の意見を反映できる体制を構築しなければ、われわれは自分たちのお金が高リスクの資産に取り入れられてしまうことに反対せざるを得ない」。
さて、ピケティ教授はこのやり取りに続いてどう発言したか。
『日本の年金積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が、ハーバード大学の基金と同じことをするべきだと言ったつもりはありません。米国の大学基金はハイリスクな投資先や高度なデリバティブ(金融派生商品)で運用していますが、年金積立金で同じような投資をするのは適切ではありません。
r(資本収益率)>g(経済成長率)の法則を示しましたが、rは変動性とボラティリティ(ばらつき)が高いことを考慮に入れなければなりません。富裕層が余裕資金で行う投資と、生活に必要なお金の投資は違います。』

このr>gの法則について少し説明しましょう。
ピケティ教授は、資本の収益率(r)と経済成長率=所得の伸び(g)から富裕層とそうでない人の格差について説明しています。
富裕層は働かなくても資産が毎年生み出すお金で資産をさらに増やすことできます。これに対して一般の人が労働で得た賃金の伸びがこれを下回れば格差はますます大きくなっていきますよね?
例えば資産が1億円あって利回り5%であれば、1年で500万円は働かなくても入ってきます。しかし、一般の人の年収の伸び率がそれ以下であれば格差はますます広がるということです。
そして、ピケティ教授は過去300年のうち、ごく一部の期間を除いて、資本の収益率は所得の伸び率より大きかったので、富裕層とそうでない人の格差は広がり続けたと主張しているのです。
これに対して、西村副大臣は、だからこそ日本の年金積立金の運用をもっと高利率のものにシフトすることで、年金に頼る中低所得層への還元が可能だと、GPIFの運用方針の変更を正当化しようとしたのですが、ピケティ教授は、富裕層の余裕資金の資産運用の問題と、年金生活者の生活資金の運用とは同列に論じられないと、これを退けたわけです。

めっちゃ睨んでるw 西村君、考え直して!
では、西村副大臣が支える安倍首相の「アベノミクス」に対しては、ピケティ氏はどう評価を下したのか?
『アベノミクスに対する論争を巻き起こすつもりはないが、私の見方では、消費増税は正しい方向ではありません。
それよりも低・中所得者の所得税を下げ、固定資産税を増やす。そのほうが現実の日本経済の状況に合う。特に若い世代にはプラスになります。紙幣を増刷するのがいいことなのか。税制を見直すよりも紙幣を増刷するほうが簡単なことは確かですが、増やしたお金は資産や不動産のバブルを生むだけで、適切な人が恩恵を受けるとは限りません。インフレを起こしたいのであれば、賃金を増やさなければなりません。
欧州と米国、そして日本もそうですが、金融政策に依存しすぎています。むしろ財政改革、教育改革、累進制のある税制が必要です。インフレ率は、日本にとっても2~3%あったほうが望ましい。金融緩和や紙幣の増刷だけでは不十分です。』
また、ピケティ教授は、米国で最も格差が拡大していると指摘しました。なぜ米国で一番広がっているのか。何が格差をもたらすのかについてピケティ教授はこう述べています。
『格差をもたらす要因としてグローバル化を挙げることができますが、それだけでは説明がつきません。グローバル化だけが原因なら、すべての国で同じように格差が広がるはずですが、そうではないからです。欧州・日本・米国を比較すると米国で最も格差が広がっていて、日本は米国と欧州の中間です。
グローバル化以外に格差拡大をもたらす要因の一つは、教育の機会の格差でしょう。ハーバード大学の学生の親の平均年収は、米国のトップ2%の水準に相当する。まるで所得トップ2%層の師弟から選んで入学させたかのようです。
労働政策も影響していると思います。最近、日本でも労働規制緩和の議論が進められていますが、不平等な労働政策の導入によって賃金交渉力が弱められる。米国で言えば労働組合の力が弱まり、賃金がかなり下がった。その一方で、米国のトップ経営者の報酬は、前例のない水準に上昇しています。所得税の最高税率が 高ければ、そもそも高額報酬をもらおうというインセンティブは働きません。累進性の高い所得税が必要です。
格差拡大のダイナミズムは、グローバル化だけでなく政策制度に起因する要素が大きいのです。各国がさまざまな政策を選択することで、グローバル化の便益をもっと広範囲の人たちに提供できるようにすることが重要です。』
ここで場内から質問が出ました。
「グローバル化だけが格差の原因ではないとしても、グローバル化の激化が私たちの働き方や 暮らし方に大きな影響を与えていることは事実です。民主主義と国家主権によって、グローバル化をある程度コントロールしていくべきとの考え方も示されています。では、どう実現すればいいのか。具体的な手立てはあるでしょうか?」
これに対して、ピケティ教授はこう答えました。
『富裕層が理解すべきなのは、グローバル化は「財政的な正義」を伴わなければならないということです。
多くの人々がグローバル化は自分に有利でないと感じれば、それはリスクになり、反グローバル化やナショナリズムにつながっていく。フランスで極右が台頭していることは恐ろしい問題です。すべての人がグローバル化から便益を得られるようにインクルーシブ(包摂的)な形にしなければなりません。
グローバル化と民主主義は複雑な関係にあります。グローバル化は機会をもたらすチャンスであると同時に、社会的なまとまりにとっての脅威にもなる。TPP などの自由貿易協定の交渉の機会を利用して、各国はグローバル化と「財政的な正義」が両立可能だと世論に示すべきでしょう。つまり、貿易自由化によって財政的な透明性を高めるのです。少なくとも多国籍企業に共通の法人税を課税しなければ、グローバル化はリスクになりかねません。』
さらに、ピケティ教授は
『最善の対応は、教育への投資をすることです。世界のトップ大学の9割は米国にある。将来、技術変化が起こっても多くの人が対応でき、バランスのとれた成長を達成するためにも高等教育が必要です。欧州や日本は、もっと高等教育に投資をするべきだと思います。』
『人口減少の日本で、格差に対抗するために最も重要な政策は人口を増やすこと。それには男女平等です。女性が労働市場で働きやすくし、父親たちの子育てへの関与を促す。そうでなければ子どもの数はどんどん減っていくでしょう。』
と語りました。
ピケティ教授は、格差是正の手段として教育の重要性を再三強調していましたが、OECD(経済協力開発機構 ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め34ヶ国の先進国が加盟する国際機関)加盟国の中で、日本の公教育に支出されつ公的資金は、5年連続で最下位クラスです。
日本はまず教育政策について見直さなければならないのではないでしょうか。
ランキングに参加中です。できましたらクリックして応援お願いします!
 「日本は教育に掛ける予算が少ない」と聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。宇宙開発やスーパーコンピューターの研究・開発といった科学の分野の現場でも、予算はよく話題になっていますね。しかし本当に日本は教育関連予算が少ないのでしょうか。
「日本は教育に掛ける予算が少ない」と聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。宇宙開発やスーパーコンピューターの研究・開発といった科学の分野の現場でも、予算はよく話題になっていますね。しかし本当に日本は教育関連予算が少ないのでしょうか。
■GDPに対する学校教育費は確かに低い
文部科学省が発表しているデータ『教育指標の国際比較』を調べてみました。これはOECD加盟国34カ国を対象に集計した資料を基にしています。
■OECD各国のGDPに対する学校教育費の比率 Top5(全教育段階)
第1位 アイスランド(7.9%)
第2位 韓国(7.6%)
第3位 イスラエル(7.3%)
第4位 アメリカ合衆国(7.2%)
第5位 チリ(7.1%)
同5位 デンマーク(7.1%)
第24位 日本(4.9%)※28カ国中
■OECD各国のGDPに対する学校教育費の比率 Top5(初等・中等・高等教育以外の中等後教育編)
第1位 アイスランド(5.1%)
第2位 ニュージーランド(4.5%)
第3位 ベルギー(4.4%)
第4位 デンマーク(4.3%)
第5位 スイス(4.3%)
第28位 日本(2.8%)※30カ国中
■OECD各国のGDPに対する学校教育費の比率 Top5(高等教育編)
第1位 アメリカ合衆国(2.7%)
第2位 韓国(2.6%)
第3位 カナダ(2.5%)
第4位 チリ(2.2%)
第5位 デンマーク(1.7%)
同5位 フィンランド(1.7%)
同5位 ノルウェー(1.7%)
第11位 日本(1.5%)※29カ国中
※……上記3つのランキングの「学校教育費」は「公財政支出」と「私費負担」の合計です。
全教育段階での日本の学校教育費の対GDP比は「4.9%」。データが不明の6カ国を除いて、5番目に低い数字です。
少し細かく見ると、初等・中等教育および高等教育以外の中等後教育については2.8%、高等教育では1.5%となっています。
順位に注目すると、高等教育以前ではほぼ最下位。高等教育では中の上という結果です。
■政府総支出に対する学校教育費の比率はOECD最下位クラス
GDPに対する比率を見るだけでは、政府が教育に力を入れているかどうかの判断がつきにくいですね。そこで次に政府の総支出に占める教育費支出の割合というデータを見てみます。
■OECD各国の一般政府総支出に占める公財政教育支出の割合(全教育段階) Top5
第1位 メキシコ(20.6%)
第2位 ニュージーランド(18.6%)
第3位 チリ(16.8%)
第4位 スイス(16.7%)
第5位 ノルウェー(16.0%)
第30位 日本(9.4%)※31カ国中
さらに驚きの結果になりました。日本の一般政府総支出に占める公財政教育支出の比率は、全教育段階で9.4%。これはイタリアと並び、OECDの中で最下位の記録です(計数が不明の3カ国を除く)。
■日本における学校教育費は私費が支えている?
次に、学校教育費の公私負担区分を見てみましょう。学校教育費がどのくらい公的に負担されているかを示すデータです。
■OECD各国の学校教育費(全教育段階・公財政)の公的負担の比率 Top5
第1位 フィンランド(97.4%)
第2位 スウェーデン(97.3%)
第3位 エストニア(94.7%)
第4位 ベルギー(94.3%)
第5位 アイルランド(93.8%)
第26位 日本(66.4%)※28カ国中
日本は、全教育段階において、公財政が占める比率が66.4%、私費が33.6%となっています。2/3は政府が負担しているということですね。なんと下には韓国、チリだけという、日本は公的負担の少ない国なのです。
国際的に見ると、「日本の教育費は私費に依存している部分が多く、公的には教育に費用を掛けていない」と言われても仕方がないようです。
■学校教育費における政府と地方の負担の比率は?
学校教育費を公的に負担しているといっても、中央政府が全て負担するのか、地方の自治体が負担するのか、という問題があります。これについては、2つのデータがあります。
■OECD各国の中央政府が公財政教育支出において負担している比率(初等・中等・高等教育以外の中等後教育)Top5
第1位 ニュージーランド(100%)
第2位 スロベニア(87.1%)
第3位 アイルランド(84.8%)
第4位 オランダ(84.6%)
第5位 イタリア(81.9%)
第28位 日本(0.6%)※30カ国中
■OECD各国の中央政府が公財政教育支出において負担している比率(高等教育)TOP10
第1位 アイスランド(100%)
同1位 オランダ(100%)
同1位 ニュージーランド(100%)
同1位 ノルウェー(100%)
同1位 イギリス(100%)
第6位 スロバキア共和国(99.9%)
第7位 ポルトガル(99.7%)
第8位 エストニア(99.3%)
第9位 ハンガリー(99.2%)
第10位 スロベニア(98.5%)
第18位 日本(92.2%)※29カ国中
高等教育とそれ以前で分けて集計したデータです。これによると、日本では高等教育以前では政府よりも各自治体が多く負担し、高等教育になると政府が多く負担するようになっているようです。
日本の場合、高等教育以前において最終的に中央政府が負担しているのは0.6%。では、国際的にはどうでしょうか。1%を切っている国は日本を含めてわずか4カ国でした。
高等教育では92.2%となり、一見高いように見えます。しかし、100%という国が5カ国もあるように、どの国も高めになっています。日本は18位。中の下という順位ですので、どちらかというと低い方です。
■学生1人当たりに掛ける学校教育費は?
最後に、各国が学生1人当たりに掛けている学校教育費のデータをご紹介します。就学前教育から高等教育というように、教育課程ごとに分けられています。
■OECD各国で学生1人当たりに掛ける学校教育費(就学前) Top5
第1位 ルクセンブルグ(13,460ドル)
第2位 アイスランド(10,080ドル)
第3位 アメリカ合衆国(10,070ドル)
第4位 イタリア(8,187ドル)
第5位 スロベニア(8,029ドル)
第23位 日本(4,711ドル)※30カ国中
※OECD各国平均 6,210ドル
■OECD各国で学生一人当たりにかける学校教育費(初等教育) Top5
第1位 ルクセンブルグ(13,648ドル)
第2位 ノルウェー(11,077ドル)
第3位 アイスランド(10,599ドル)
第4位 デンマーク(10,080ドル)
第5位 アメリカ合衆国(99,82ドル)
第14位 日本(7,491ドル)※31カ国中
※OECD各国平均 7,153ドル
■OECD各国で学生一人当たりにかける学校教育費(中等教育) Top5
第1位 ルクセンブルグ(19,898ドル)
第2位 スイス(17,825ドル)
第3位 ノルウェー(13,070ドル)
第4位 アメリカ合衆国(12,097ドル)
第5位 オーストリア(11,741ドル)
第15位 日本(9,092ドル)※32カ国中
※OECD各国平均 8,972ドル
■OECD各国で学生一人当たりにかける学校教育費(高等教育) Top5
第1位 アメリカ合衆国(29,910ドル)
第2位 スイス(21,648ドル)
第3位 カナダ(20,903ドル)
第4位 スウェーデン(20,014ドル)
第5位 ノルウェー(18,942ドル)
第15位 日本(14,890ドル)※30カ国中
※OECD各国平均 13,717ドル
日本は、就学前教育での教育費が平均を大きく下回っていますが、それ以外の過程では平均以上でした。幼少期の教育費に対して、特に費用を掛けていないのですね。
いかがでしたか? 今回はあくまで「費用」ということに注目して調べてみました。もちろん、費用と教育の質が一致するというわけではなく、そういう観点でもっと細かい考察・分析が必要でしょう。
ただ国際的に比較して「日本は教育に掛ける費用が少ない」というぐらいの結果は、今回の調査でも十分お分かりいただけたのではないでしょうか。
⇒データ出展:教育指標の国際比較 平成24(2012)年版
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/kokusai/_...
(藤野晶@dcp)
マイナビ 2015年3月2日
ランキングに参加中です。できましたらクリックして応援お願いします!
目の前にある結果に「自分が創ったとしたら」という立場で向かい合ったとき、あなたの「人生」「仕事」は劇的に変わる! 企業と経営者を長年見守り続けてきた著者が、ヒューマングロウス(人間成長)のエッセンスを語る。
 |
自分が源泉―ビジネスリーダーの生き方が変わる |
| 鈴木 博 | |
| 創元社 |
2万人の女性の美容をサポートしてわかった事実。
ダイエットがうまくいかない理由が、ついに判明!太る原因は、ためこんだ「怒り」だった! !
 |
怒りが消えれば、やせられる―コーピング・ダイエット |
| 城ノ石ゆかり | |
| きずな出版 |