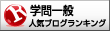観光地や温泉街は物価が高く犯罪も多い。人が集まり、お金が動くからか?
本来の観光や遊行(ゆぎょう)には、崇高な意味がこめられている。下記参考↓
鎌倉は毎日、沢山の観光客が訪れる場所だが、不思議と大きな事件をあまり聞かない。
夜になるとあたりは真っ暗だが、歓楽街がないので安全な雰囲気だ。酔っぱらいもほとんど見かけない。
夜中の12時でも帰宅する女性が、駅から真っ暗な道を一人で歩いている。安全なのだろう。
三方山に囲まれて、南は海に開けている鎌倉。入る道も出る道も限られている。
この限られた道を検問で封鎖してしまえば、犯罪者にとって逃げ場はない。
鎌倉自身が遊楽地ではなく神社仏閣が売りなので、来る方も精神性を求めた心根のよい方多いからか?
ただし、海水浴シーズンは別だ。夏になると様相が一変する。
夏になると、ガラの悪い連中が増える。海に行くのか若い連中が、車から大音響で音楽を流して仕事場の前を通る、ゴミは捨てる、困ったものだ。また、7月8月の鎌倉の海は汚い。よくあんな汚い海で泳げるものだと感心する。暴走族もクラゲも多く出る。8月頃の海に入ると必ず刺されるから要注意だ。
【観光の語源】
観光とは一般的には「日常の生活では見ることのできない風景や風俗、習慣などを見て回る旅行」を意味したが、旅行の安全性や快適性が進むにつれて、遊覧や保養のための旅行など「楽しみのための旅」全般をさすことばとして広く使用されるようになった。 日本で観光の語が現代的な意味で使用されるようになったのは、英語のツーリズムtourismの訳語としてあてられるようになった明治なかば以降である。とくに一般化したのは大正に入ってからで、とりわけ1923~24年(大正12~13)ごろ、アメリカ移住団の祖国訪問に際して新聞紙上で「母国観光団」として華々しく報道されたためだといわれる。しかし、日常的な語として広く使用されるようになったのは昭和初期以降であり、世界的な観光黄金時代を背景にして鉄道省に国際観光局が設置(1930)されたのを契機に民間機関も設立され、国内観光の気運が高まりをみせ始めたころからである。
<観光の語源と概念>
(1)日本で観光という語が使用されたのは、1855年(安政2)にオランダより徳川幕府に寄贈された木造蒸気船を幕府が軍艦として「観光丸」と名づけたのが最初である。その意図は、国の威光を海外に示す意味が込められていたといわれる。
(2)「観光」の語源は中国の『易経』の「観」の卦(か)(観察についての項)に由来している。「観国之光 利用賓于王」(国の光を観(み)るは、もって王の賓たるによろし)から生まれた語で、その本来の語義は「他国の制度や文物を視察する」から転じて「他国を旅して見聞を広める」の意味となる。また同時に「観」には「示す」意味もあり、外国の要人に国の光を誇らかに示す意味も含まれているという説もある。
※行頭のみ字下げ