ウィーンフィル恒例のニューイヤー・コンサートを聴くといつものことであるが、中学生の頃にウィンナ・ワルツがお気に入りで聴いていたことを思い出す。
父の転勤の関係で、自宅から中学校に通学できなくなってしまい、叔母の家にやっかいになっていたことがある。その叔母の家に当時としては立派なステレオがあり、音楽好きの義理の叔父がたくさんのレコードを持っており、その中にヨハン・シュトラウスのレコードがあったのだ。
その話を家内にしようと思ったとたん、そのウィンナ・ワルツのレコードが何と言うオーケストラによる演奏だったか度忘れしてしまっていることに気づいた。喉まで出かかっているにもかかわらず思い出せない。無理に記憶を探ろうとしても、エルネスト・アンセルメ指揮のスイスロマンド管弦楽団のような、あの当時聴いた他のオーケストラしか思い出せない。こうなると、ニューイヤー・コンサートを聴いていても上の空である。何とか思い出そうとするのだが、どうしても出てこない。
あのオーケストラは、クラッシックだけではなく、映画音楽やイージーリスニングと呼ばれたポピュラーな音楽の演奏でも知られていたことやカスケード・ストリングスと呼ばれるような美しいストリングスによるサウンドが特徴だったことなどのことは思い出せるのだが、肝心の名前が出てこない。
ところが、諦めて一夜を過ごした今朝のこと、いつものように朝のお茶を飲もうと急須を取り上げた瞬間に記憶が蘇った。神様が気の毒に思って知らせてくれたかのように、そのオーケストラの名前がふいに戻ってきたのである。
そのオーケストラは、マントヴァーニ管弦楽団。そのオーケストラを結成し、指揮をしていたマントヴァーニはもうすでに鬼籍の人のはずである。
中学生の時にレコードを聴きながら読んだライナー・ノートには「このオーケストラの7割はストリングスが占めている」と書かれていたことを妙にはっきりと覚えている。
そのためであろう。このオーケストラの響きは豊かで華麗で繊細で、シュトラウスのワルツやポルカを他のどんなオーケストラよりも見事に演じているように思え、いかにもウィーンの音楽に似つかわしく思えたのだ。
マントヴァーニ管弦楽団の名前は、レコードだけでなくラジオでも当時よく耳にしたものである。ただラジオでその名前を聞くのは映画音楽やシャンソンなどのポップスが放送された折のことであり、意外な思いをしたことも鮮明に覚えている。なぜなら、当時の日本のオーケストラでジャンルにこだわらずに演奏する団体は皆無に近かったからである。
なつかしいオーケストラの名前を二日がかりで思い出せたことが嬉しくて、マントヴァーニ管弦楽団のことを改めて調べてみた。
マントヴァーニはもう亡くなっているであろうから、オーケストラ自体もすでに解散してしまっているかも知れないと漠然と思っていたのだが、どうやらまだ健在のようで、マントヴァーニが亡くなってからは、スタンリー・ブラックを指揮者に迎えてますますこの管弦楽団らしい演奏活動を行っているようだ。
スタンリー・ブラックと言えば、ロンドンフェスティバル管弦楽団の指揮者としてもつとに著名な作・編曲家である。そうか、スタンリー・ブラックも健在だったのだ。
そしてロンドンフェスティバル管弦楽団と言えば、ロンドンフィルの別名で、クラシック以外の音楽を演奏する際にこの名称を使用して演奏や録音を行っていることはよく知られている。そこで棒を振っていたスタンリー・ブラックを指揮者に迎えたということは、マントヴァーニ管弦楽団らしい選択だと納得がいく。
マントヴァーニと言えば、カスケード・ストリングスと呼ばれる弦楽器の奏法で知られているが、カスケード・ストリングスとは「流れ落ちる滝のような」弦の響きを指して名付けられた奏法であるらしい。
どうやら当時は、電気的・人工的に手を加えてその効果を演出しているのではないかと受け取られることもあったようであるが、これは編曲の工夫によるもので、PAによる効果の付加によるものではなかったようである。
実際には、ロナルド・ビンジという編曲家の編み出した手法によるものと言われているが、後に「題名のない音楽会」で黛敏郎がその秘密を解き明かしている。
以下、黛の解説である。
《黛敏郎の解説》
『マントヴァーニがアレンジした場合には、バイオリンを4つの部分に分ける。その4つのグループどれが演奏しても、メロディそのものは出てこない。』
(オーケストラが、バイオリンのA~Dの4パートのうち、パートAを演奏する。)
『全然メロディを感じませんね。』
(次にパートBが演奏される。)
『有名なメロディとは似つかわしくない。』
(パートCを演奏)
『…やっと片鱗は聴こえるが、満足はできない。』
(パートDを演奏)
『お聴きのように、4つの部分がメロディの一部らしきものをやっているけれども、実際のメロディは出てこない。それは何故かといえば、分散してやっているからです。どう分散してい るかというと交互に(A~Dの)違ったグループに行ったり来たりする。それが一緒になると、他の音 が余韻となっているので、エコーのように聴こえる。これを多用したのがマントヴァーニのアレンジの秘密である。』
※この解説の部分は、「マントヴァーニ論考」というwebサイトから引用させて頂いた。
そうだったのか。それが、あの「魅惑の宵」や「シャルメーヌ」などの流れ落ちる滝のような、微妙に重なり合って舞い降りるようなサウンドを生んでいたのか。
中学生の当時には知るよしもなかったことだが、別のサイトの記事に「マントヴァーニ・オーケストとスイス・ロマンド管弦楽団という英デッカの二大看板オーケストラ」という意味のことが書かれており、優秀な録音技術を持ったレコード会社に二つのオーケストラが属していたこともわかった。
デッカと言えば、1954年にはステレオ録音を開始、1958年にはステレオ録音のLPを発売し、その録音技術で他社を圧倒したレコード会社である。そのデッカを代表する二つのオーケストラがマントヴァーニとスイス・ロマンドだったのだ。
叔父のレコードコレクションの中に、そのデッカのレコードが多くあったのだろう。
マントヴァーニ交響楽団の名を思い出せなくて記憶を探っていた折に、スイス・ロマンドやその指揮者であるエルネスト・アンセルメの名がしきりと思い浮かんだことも、決して何の脈絡もないことではなかったと妙な感心をしているところである。
どうやら、マントヴァーニのCDも制作されているようである。それを入手して懐かしいサウンドに浸ってみたいものである。
父の転勤の関係で、自宅から中学校に通学できなくなってしまい、叔母の家にやっかいになっていたことがある。その叔母の家に当時としては立派なステレオがあり、音楽好きの義理の叔父がたくさんのレコードを持っており、その中にヨハン・シュトラウスのレコードがあったのだ。
その話を家内にしようと思ったとたん、そのウィンナ・ワルツのレコードが何と言うオーケストラによる演奏だったか度忘れしてしまっていることに気づいた。喉まで出かかっているにもかかわらず思い出せない。無理に記憶を探ろうとしても、エルネスト・アンセルメ指揮のスイスロマンド管弦楽団のような、あの当時聴いた他のオーケストラしか思い出せない。こうなると、ニューイヤー・コンサートを聴いていても上の空である。何とか思い出そうとするのだが、どうしても出てこない。
あのオーケストラは、クラッシックだけではなく、映画音楽やイージーリスニングと呼ばれたポピュラーな音楽の演奏でも知られていたことやカスケード・ストリングスと呼ばれるような美しいストリングスによるサウンドが特徴だったことなどのことは思い出せるのだが、肝心の名前が出てこない。
ところが、諦めて一夜を過ごした今朝のこと、いつものように朝のお茶を飲もうと急須を取り上げた瞬間に記憶が蘇った。神様が気の毒に思って知らせてくれたかのように、そのオーケストラの名前がふいに戻ってきたのである。
そのオーケストラは、マントヴァーニ管弦楽団。そのオーケストラを結成し、指揮をしていたマントヴァーニはもうすでに鬼籍の人のはずである。
中学生の時にレコードを聴きながら読んだライナー・ノートには「このオーケストラの7割はストリングスが占めている」と書かれていたことを妙にはっきりと覚えている。
そのためであろう。このオーケストラの響きは豊かで華麗で繊細で、シュトラウスのワルツやポルカを他のどんなオーケストラよりも見事に演じているように思え、いかにもウィーンの音楽に似つかわしく思えたのだ。
マントヴァーニ管弦楽団の名前は、レコードだけでなくラジオでも当時よく耳にしたものである。ただラジオでその名前を聞くのは映画音楽やシャンソンなどのポップスが放送された折のことであり、意外な思いをしたことも鮮明に覚えている。なぜなら、当時の日本のオーケストラでジャンルにこだわらずに演奏する団体は皆無に近かったからである。
なつかしいオーケストラの名前を二日がかりで思い出せたことが嬉しくて、マントヴァーニ管弦楽団のことを改めて調べてみた。
マントヴァーニはもう亡くなっているであろうから、オーケストラ自体もすでに解散してしまっているかも知れないと漠然と思っていたのだが、どうやらまだ健在のようで、マントヴァーニが亡くなってからは、スタンリー・ブラックを指揮者に迎えてますますこの管弦楽団らしい演奏活動を行っているようだ。
スタンリー・ブラックと言えば、ロンドンフェスティバル管弦楽団の指揮者としてもつとに著名な作・編曲家である。そうか、スタンリー・ブラックも健在だったのだ。
そしてロンドンフェスティバル管弦楽団と言えば、ロンドンフィルの別名で、クラシック以外の音楽を演奏する際にこの名称を使用して演奏や録音を行っていることはよく知られている。そこで棒を振っていたスタンリー・ブラックを指揮者に迎えたということは、マントヴァーニ管弦楽団らしい選択だと納得がいく。
マントヴァーニと言えば、カスケード・ストリングスと呼ばれる弦楽器の奏法で知られているが、カスケード・ストリングスとは「流れ落ちる滝のような」弦の響きを指して名付けられた奏法であるらしい。
どうやら当時は、電気的・人工的に手を加えてその効果を演出しているのではないかと受け取られることもあったようであるが、これは編曲の工夫によるもので、PAによる効果の付加によるものではなかったようである。
実際には、ロナルド・ビンジという編曲家の編み出した手法によるものと言われているが、後に「題名のない音楽会」で黛敏郎がその秘密を解き明かしている。
以下、黛の解説である。
《黛敏郎の解説》
『マントヴァーニがアレンジした場合には、バイオリンを4つの部分に分ける。その4つのグループどれが演奏しても、メロディそのものは出てこない。』
(オーケストラが、バイオリンのA~Dの4パートのうち、パートAを演奏する。)
『全然メロディを感じませんね。』
(次にパートBが演奏される。)
『有名なメロディとは似つかわしくない。』
(パートCを演奏)
『…やっと片鱗は聴こえるが、満足はできない。』
(パートDを演奏)
『お聴きのように、4つの部分がメロディの一部らしきものをやっているけれども、実際のメロディは出てこない。それは何故かといえば、分散してやっているからです。どう分散してい るかというと交互に(A~Dの)違ったグループに行ったり来たりする。それが一緒になると、他の音 が余韻となっているので、エコーのように聴こえる。これを多用したのがマントヴァーニのアレンジの秘密である。』
※この解説の部分は、「マントヴァーニ論考」というwebサイトから引用させて頂いた。
そうだったのか。それが、あの「魅惑の宵」や「シャルメーヌ」などの流れ落ちる滝のような、微妙に重なり合って舞い降りるようなサウンドを生んでいたのか。
中学生の当時には知るよしもなかったことだが、別のサイトの記事に「マントヴァーニ・オーケストとスイス・ロマンド管弦楽団という英デッカの二大看板オーケストラ」という意味のことが書かれており、優秀な録音技術を持ったレコード会社に二つのオーケストラが属していたこともわかった。
デッカと言えば、1954年にはステレオ録音を開始、1958年にはステレオ録音のLPを発売し、その録音技術で他社を圧倒したレコード会社である。そのデッカを代表する二つのオーケストラがマントヴァーニとスイス・ロマンドだったのだ。
叔父のレコードコレクションの中に、そのデッカのレコードが多くあったのだろう。
マントヴァーニ交響楽団の名を思い出せなくて記憶を探っていた折に、スイス・ロマンドやその指揮者であるエルネスト・アンセルメの名がしきりと思い浮かんだことも、決して何の脈絡もないことではなかったと妙な感心をしているところである。
どうやら、マントヴァーニのCDも制作されているようである。それを入手して懐かしいサウンドに浸ってみたいものである。










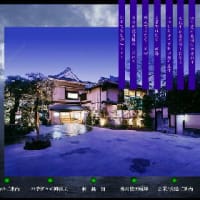
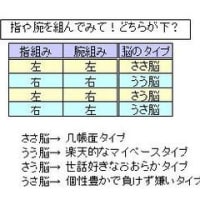




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます