
ようやく春の兆しも見えたこの時期にショックなニュースが・・・
タワーレコードと子会社のナップスタージャパンは3月1日、定額制音楽配信サービス「ナップスタージャパン」などの全サービスを終了すると発表した。ライセンス元である米Napsterの動きにともなう判断としている。5月31日までに閉鎖する予定。
ナップスタージャパンは、2006年10月より定額制の音楽配信サービスとしてスタート。900万曲以上の楽曲データを提供していた。サービス終了の判断については、ライセンス元の米NapsterがDRMフリーでの配信モデルに移行を進めていることから、日本で同様の配信モデルを構築するにはコスト面も含めて困難と判断した。日本でのユーザー数や売上については公表していない。同社広報によると、携帯電話向けサービスの会員数がPC向けを大きく上回っているという。
(某ニュースサイトより)
以前の記事でこの「Napster Japan」をかなり活用していることを書いたが、実は1~2月に手に入れた新譜も、半数強がここから携帯音楽プレイヤーに落としたものである。よってこのサービス停止は非常に痛手である。
ところで気になったのが、上のニュース記事の文中にある「DRMフリー」なる言葉である。こんなブログを書いておきながら、実は勤め先ではロクにPCを使わず、IT関係にも疎いため、全く何を意味する言葉なのか知らなかった。
そこでさっそく検索してみると・・・
DRMフリーとは、デジタル著作権管理技術(DRM:Digital Rights Management)による暗号化などの保護がかけられていない音声ファイルなどのコンテンツのこと。
デジタル化されて販売・流通される音楽や映像などのコンテンツは、暗号化などが施され、適切な権利がないとコピーや再生などができないように保護されていることが多い。このような技術をDRMと呼ぶが、そのような制限がかかっておらず、技術的には自由に複製や再生などが可能な状態で頒布されているコンテンツをDRMフリーという。
(某ITニュースサイトより)
・・・だそうである。
その他色々なところでこの「DRMフリー」という言葉を調べてみたが、今欧米では大手レコード会社、音楽配信会社がこの「DRMフリー」の方向へ実際に動いているようなのである。
「DRM」は著作権を管理するためにつくられたものである。
「iTunes Store」では購入した楽曲が違法コピーで次々に拡大することを防ぐため、「FairPlay」なるDRM技術が導入されている。これにより「iTunes Store」では音源を「iPod」にしか落とせないようになっている。
ところがこの技術に対して欧米の消費者から数年前より反発の動きが出てきた。「特定の携帯音楽プレイヤーにしか音源が落とせないのは、消費者の携帯音楽プレイヤーの『選択の自由』を妨げる」ことになるからである。
またCCCD(コピーコントロールCD)の普及に失敗した大手レコード会社も、様々なDRM技術を導入しようとしたが、稚拙な技術のため訴訟に至って多額の賠償金を支払うはめになったケースもあったようである。そのようなこともあって実質CDは「DRMフリー状態」(ごく軽いDRMが導入されているらしいが)、CDからの違法コピーは後を絶たない。
そのような流れから「DRM」は消費者の利益に反する、さらに実質それほど効果がないという結論が大手レコード会社、音楽配信会社の中で出てきたようだ。米Napsterもその流れにのることになったわけだが、日本のほうでは「同様の配信モデルを構築するにはコスト面も含めて困難」ということらしい。
どういうことか?
ここからはあくまでも推測であるが・・・日本では著作権管理に関して悪名高き「JASRAC」が君臨している。おそらくNapster JapanがJASRACに話をもっていったところ、「DRMフリー」が認められなかった、ないしは高額の楽曲使用料を請求された、そんな経緯があったのではないか。
日本では音楽配信サービスが根付いていない。唯一例外が「着うたフル」だそうだが、これには「DRM」がもちろん導入されていながら大成功している。そういうこともあってJASRACからすれば、そんな「自分たちの利益を損なう」システムを認めるわけにはいかない、ということだろう。
Napster Japanは魅力的な定額サービスコンテンツ(HM/HR関係の音源も驚くほど豊富)である。聴くだけなら月に1200円チョイ、さらに特定の携帯音楽プレイヤーに音源を落とせるサービスをつければ月に2000円弱、本国アメリカでも同内容でほぼ同額のサービスを展開しているようだ。
なぜ欧米では「DRMフリー」が拡大するのか。
それは消費者の利益をしっかり考慮していること、そしてそうすることが結果的に自分たちの利益の増加につながることがわかっているからである。Napsterで聴いて、気に入ったものはそのCDやDVDを買う・・・そういう動きが実際あるのである。自分もまさにそうである。海外ではもはや過去のものと思われたアーティストが、Napsterがきっかけで見直され、そのCDが売れた、ということも実際あったそうである。
それに対してJASRACおよび日本のレコード会社はあまりに短絡的である。彼らの頭には「音楽を色々な人に触れてもらう機会を増やす=違法コピーの増加」という図式しかない。長期的な目でみれば、「=お金がかからない宣伝(配信会社に許可するだけだから)」いや「=確実な利益の確保(許諾料が毎月一定額入ってくるとすれば)」にもなるのである。そういったことが分からないのは、JASRAC及びレコード会社の上層部が、音楽ファンではない人間が牛耳ってる故であろう。
こうしてまた日本は世界の潮流から取り残されていくのか!?
というわけで今月以降「新譜感想」が減ることになってしまいそうである・・・(悲)
タワーレコードと子会社のナップスタージャパンは3月1日、定額制音楽配信サービス「ナップスタージャパン」などの全サービスを終了すると発表した。ライセンス元である米Napsterの動きにともなう判断としている。5月31日までに閉鎖する予定。
ナップスタージャパンは、2006年10月より定額制の音楽配信サービスとしてスタート。900万曲以上の楽曲データを提供していた。サービス終了の判断については、ライセンス元の米NapsterがDRMフリーでの配信モデルに移行を進めていることから、日本で同様の配信モデルを構築するにはコスト面も含めて困難と判断した。日本でのユーザー数や売上については公表していない。同社広報によると、携帯電話向けサービスの会員数がPC向けを大きく上回っているという。
(某ニュースサイトより)
以前の記事でこの「Napster Japan」をかなり活用していることを書いたが、実は1~2月に手に入れた新譜も、半数強がここから携帯音楽プレイヤーに落としたものである。よってこのサービス停止は非常に痛手である。
ところで気になったのが、上のニュース記事の文中にある「DRMフリー」なる言葉である。こんなブログを書いておきながら、実は勤め先ではロクにPCを使わず、IT関係にも疎いため、全く何を意味する言葉なのか知らなかった。
そこでさっそく検索してみると・・・
DRMフリーとは、デジタル著作権管理技術(DRM:Digital Rights Management)による暗号化などの保護がかけられていない音声ファイルなどのコンテンツのこと。
デジタル化されて販売・流通される音楽や映像などのコンテンツは、暗号化などが施され、適切な権利がないとコピーや再生などができないように保護されていることが多い。このような技術をDRMと呼ぶが、そのような制限がかかっておらず、技術的には自由に複製や再生などが可能な状態で頒布されているコンテンツをDRMフリーという。
(某ITニュースサイトより)
・・・だそうである。
その他色々なところでこの「DRMフリー」という言葉を調べてみたが、今欧米では大手レコード会社、音楽配信会社がこの「DRMフリー」の方向へ実際に動いているようなのである。
「DRM」は著作権を管理するためにつくられたものである。
「iTunes Store」では購入した楽曲が違法コピーで次々に拡大することを防ぐため、「FairPlay」なるDRM技術が導入されている。これにより「iTunes Store」では音源を「iPod」にしか落とせないようになっている。
ところがこの技術に対して欧米の消費者から数年前より反発の動きが出てきた。「特定の携帯音楽プレイヤーにしか音源が落とせないのは、消費者の携帯音楽プレイヤーの『選択の自由』を妨げる」ことになるからである。
またCCCD(コピーコントロールCD)の普及に失敗した大手レコード会社も、様々なDRM技術を導入しようとしたが、稚拙な技術のため訴訟に至って多額の賠償金を支払うはめになったケースもあったようである。そのようなこともあって実質CDは「DRMフリー状態」(ごく軽いDRMが導入されているらしいが)、CDからの違法コピーは後を絶たない。
そのような流れから「DRM」は消費者の利益に反する、さらに実質それほど効果がないという結論が大手レコード会社、音楽配信会社の中で出てきたようだ。米Napsterもその流れにのることになったわけだが、日本のほうでは「同様の配信モデルを構築するにはコスト面も含めて困難」ということらしい。
どういうことか?
ここからはあくまでも推測であるが・・・日本では著作権管理に関して悪名高き「JASRAC」が君臨している。おそらくNapster JapanがJASRACに話をもっていったところ、「DRMフリー」が認められなかった、ないしは高額の楽曲使用料を請求された、そんな経緯があったのではないか。
日本では音楽配信サービスが根付いていない。唯一例外が「着うたフル」だそうだが、これには「DRM」がもちろん導入されていながら大成功している。そういうこともあってJASRACからすれば、そんな「自分たちの利益を損なう」システムを認めるわけにはいかない、ということだろう。
Napster Japanは魅力的な定額サービスコンテンツ(HM/HR関係の音源も驚くほど豊富)である。聴くだけなら月に1200円チョイ、さらに特定の携帯音楽プレイヤーに音源を落とせるサービスをつければ月に2000円弱、本国アメリカでも同内容でほぼ同額のサービスを展開しているようだ。
なぜ欧米では「DRMフリー」が拡大するのか。
それは消費者の利益をしっかり考慮していること、そしてそうすることが結果的に自分たちの利益の増加につながることがわかっているからである。Napsterで聴いて、気に入ったものはそのCDやDVDを買う・・・そういう動きが実際あるのである。自分もまさにそうである。海外ではもはや過去のものと思われたアーティストが、Napsterがきっかけで見直され、そのCDが売れた、ということも実際あったそうである。
それに対してJASRACおよび日本のレコード会社はあまりに短絡的である。彼らの頭には「音楽を色々な人に触れてもらう機会を増やす=違法コピーの増加」という図式しかない。長期的な目でみれば、「=お金がかからない宣伝(配信会社に許可するだけだから)」いや「=確実な利益の確保(許諾料が毎月一定額入ってくるとすれば)」にもなるのである。そういったことが分からないのは、JASRAC及びレコード会社の上層部が、音楽ファンではない人間が牛耳ってる故であろう。
こうしてまた日本は世界の潮流から取り残されていくのか!?
というわけで今月以降「新譜感想」が減ることになってしまいそうである・・・(悲)










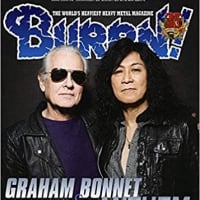


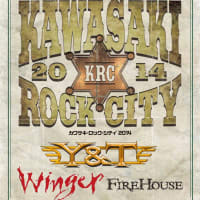
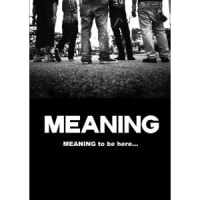


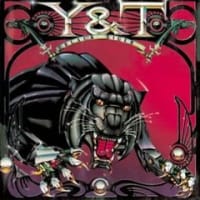
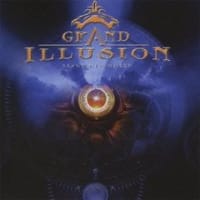

空気が読める人はよいのですが、悪意を持って無料サービスをむさぼり尽くす人もいるので収支の面で難しいのでしょう。
バイキング料理でも高そうな物は手渡しになっているのと同じかなと。
ただ海外の流れは、日本よりも違法コピー等が横行しているにもかかわらず、「性善説」のほうにシフトしています。
なぜならそのほうが実は利益が生み出せるチャンスが広がるし、「性悪説」のもとに徹底的に取り締まるシステムはもはやなく、限界が見えているからです。
そういった時代の流れを読めないJASRACや大手レコード会社はおかしいのではないか・・・と思うわけです。