地震保険に関する財務省ホームページの情報(抜粋)です。

ここの「(参考)地震保険の保険料」をクリックすると、以下の”割引制度”に関する情報が見つかりました。

対象物件は昭和56年以降に新築されたものなので、10%の割引になることが分かりました。
(免振建築物であれば、最大50%も割引されるのですか!!!)
でも、保険会社からはそれを証明するため「登記事項証明」を添付するように言われました。
そのためには法務局へ出向く必要があるのか、憂鬱になっていたのですが、以下を発見。
登記情報提供サービスのホームページ見ると、「一時利用」サービスを使えばあらかじめ申込手続きをせずにクレジットカードで入手できることが分かりました。

まず最初に一時利用者の事前登録(住所、氏名、パスワード、メールアドレス等を入力)すると、ログインIDがメール(以下)で送られてきます。

添付URLをクリック、1回のみ有効とのこと。
あとはガイドに沿って必要事項を入力していけば、OKです。 尚、不動産番号・家屋番号が必要なので、あらかじめ権利書等で確認しておく必要があります。

金額は 335円、でした。法務局で入手するより安いようです。
最後に請求ボタンをクリックすれば完了です。
請求日から3日間のみ、ログインした「マイページ」から pdf ファイルとしてダウンロードできるとあります。
(一度ダウンロードしてしまえば、何度もダウンロードする必要はありませんが。。。)
ダウンロードした pdf ファイルを印刷し、地震保険申込書に添付し提出たところ、10%割引を受けてもらえました。。。

ここの「(参考)地震保険の保険料」をクリックすると、以下の”割引制度”に関する情報が見つかりました。

対象物件は昭和56年以降に新築されたものなので、10%の割引になることが分かりました。
(免振建築物であれば、最大50%も割引されるのですか!!!)
でも、保険会社からはそれを証明するため「登記事項証明」を添付するように言われました。
そのためには法務局へ出向く必要があるのか、憂鬱になっていたのですが、以下を発見。
登記情報提供サービスのホームページ見ると、「一時利用」サービスを使えばあらかじめ申込手続きをせずにクレジットカードで入手できることが分かりました。

まず最初に一時利用者の事前登録(住所、氏名、パスワード、メールアドレス等を入力)すると、ログインIDがメール(以下)で送られてきます。

添付URLをクリック、1回のみ有効とのこと。
あとはガイドに沿って必要事項を入力していけば、OKです。 尚、不動産番号・家屋番号が必要なので、あらかじめ権利書等で確認しておく必要があります。

金額は 335円、でした。法務局で入手するより安いようです。
最後に請求ボタンをクリックすれば完了です。
請求日から3日間のみ、ログインした「マイページ」から pdf ファイルとしてダウンロードできるとあります。
(一度ダウンロードしてしまえば、何度もダウンロードする必要はありませんが。。。)
ダウンロードした pdf ファイルを印刷し、地震保険申込書に添付し提出たところ、10%割引を受けてもらえました。。。










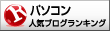















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます