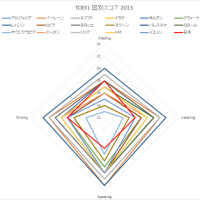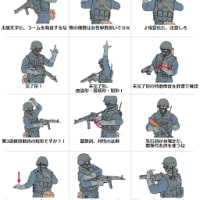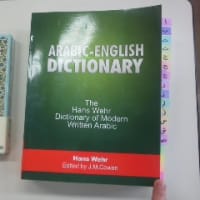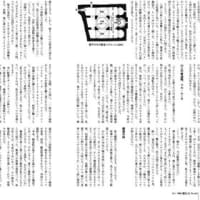今日は、都内に出てきて、ちょっと時間ができたので、国立科学博物館で開催されている企画展「砂漠を生き抜く ―人間・動物・植物の知恵―」を見ました。特別展として、ゴビ砂漠の恐竜展も今、やっているのですが、ゴビ砂漠は良いか…と、サハラ砂漠(ほんとは沙漠と書きたいのですが、企画展のタイトルに合わせました)だけにしました。
国立科学博物館に来るのは、高校時代以来です。階段の吹き抜け部分で、フーコーの振り子の実験もまだ行なわれ続けており、懐かしいです。
肝心の企画展ですが、砂漠という、本来、人間が暮らすには向かない環境に、人間たちはどのように適応していったのか、そして自然とどう共生しているのかを知ることをとおして、日本で暮らす私たちの生き方をも考え直してみようという、興味深い展示です。具体的には、アルジェリア、スーダン、エジプト、サウジアラビアの4ヶ国が取り上げられています。
中東・北アフリカ地域には、外国語の勉強という文系の立場からお世話になっていますので、科学博物館という理系の立場からの展示は、いろいろと勉強になりますし、新鮮です。
展示では、オアシスでの灌漑、ナツメヤシ栽培、マングローブやラクダという塩分に強い生物の利用などなどを紹介するとともに、メスキートという植物の植林による、砂漠開発に関しても言及がありました。メスキートは、そのお豆の栄養価が高く、また、木材もいろいろに利用できますし、何より乾燥に強いので、スーダンなどで植林が行なわれたそうです。しかし、メスキートの植林は、良いことばかりではありませんでした。この外来種は、在来種を押しのけてはびこり、水を吸い、サハラの環境を狂わせていったのです。自然と人間の共生の方法を考えさせられる事例です。
興味深かったのは、ラクダの海での活躍です。ラクダに乗って人間が海(そこそこ浅いけど)を渡り、漁をしたり、マングローブを刈ったりするそうです。砂の上を歩くイメージばかりのラクダですが、こんなこともあるんですね。
展示会場では、展示内容をカラー写真で振り返ることのできる、かなり立派なパンフレットが無料でいただけます。かなり得した気分。
開催期間は平成26年2月9日(日)まで。常設展への入場券で見ることができます。
【追記 2014/02/03】お写真追加。クリックで拡大します。

国立科学博物館に来るのは、高校時代以来です。階段の吹き抜け部分で、フーコーの振り子の実験もまだ行なわれ続けており、懐かしいです。
肝心の企画展ですが、砂漠という、本来、人間が暮らすには向かない環境に、人間たちはどのように適応していったのか、そして自然とどう共生しているのかを知ることをとおして、日本で暮らす私たちの生き方をも考え直してみようという、興味深い展示です。具体的には、アルジェリア、スーダン、エジプト、サウジアラビアの4ヶ国が取り上げられています。
中東・北アフリカ地域には、外国語の勉強という文系の立場からお世話になっていますので、科学博物館という理系の立場からの展示は、いろいろと勉強になりますし、新鮮です。
展示では、オアシスでの灌漑、ナツメヤシ栽培、マングローブやラクダという塩分に強い生物の利用などなどを紹介するとともに、メスキートという植物の植林による、砂漠開発に関しても言及がありました。メスキートは、そのお豆の栄養価が高く、また、木材もいろいろに利用できますし、何より乾燥に強いので、スーダンなどで植林が行なわれたそうです。しかし、メスキートの植林は、良いことばかりではありませんでした。この外来種は、在来種を押しのけてはびこり、水を吸い、サハラの環境を狂わせていったのです。自然と人間の共生の方法を考えさせられる事例です。
興味深かったのは、ラクダの海での活躍です。ラクダに乗って人間が海(そこそこ浅いけど)を渡り、漁をしたり、マングローブを刈ったりするそうです。砂の上を歩くイメージばかりのラクダですが、こんなこともあるんですね。
展示会場では、展示内容をカラー写真で振り返ることのできる、かなり立派なパンフレットが無料でいただけます。かなり得した気分。
開催期間は平成26年2月9日(日)まで。常設展への入場券で見ることができます。
【追記 2014/02/03】お写真追加。クリックで拡大します。