ローマ字の話です。
巷には、たくさんローマ字が現われています。
外国人の方にも分かりやすいように、ヘボン式で表示されてます。
学校だけ訓令式という形です。
日本の教育制度が、世界レベルから立ち遅れている一つの現われです。

江戸末期に来日し…
 ヘボンが創立した明治学院大学構内に立つ胸像
ヘボンが創立した明治学院大学構内に立つ胸像
江戸末期に来日し、日本初の近代的な和英辞典を編さんした米国の宣教医ヘボンは、ローマ字の表記方法を普及させたことでも知られる。音やつづりを英語風に書き表すもので「ヘボン式」という。漢字やかな文字の習得が壁となる外国人との意思疎通に、ローマ字での表記は欠かせないものだった
▲そのローマ字の表記のあり方について、政府は見直しに着手した。政府は1954年から、ヘボン式と異なり母音と子音を規則的に組み合わせる「訓令式」という方法を原則としている。複数の表記法が社会に混在しているため、「できるだけ統一的な考え方」を検討するという
▲ヘボン式で「し」は「shi」、「ちゃ」は「cha」。これが訓令式だと「si」、「tya」になる。地名や人名など固有名詞はヘボン式が使われることが多い。情報端末へのローマ字入力でもよく用いられている
▲小学校で訓令式のローマ字を教えても、英語の授業はヘボン式の表記が出てくる。当の政府も、パスポートはヘボン式だ。「訓令式は十分に定着したと言えない」と率直に認め、約70年ぶりに見直しに乗り出した形である
▲ヘボンは「これは何か」という日本語をまず覚えたという。医師として多くの人を診察しながら、貪欲に言葉を吸収していった
▲外国人観光客や労働者が増え、地名などをローマ字で記す必要性はいっそう増していく。ふたつの方式の長所と短所を見極めながら、どうまとめていくか。社会の変化も映し出すに違いない、ローマ字の未来だ。
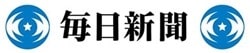 でした。
でした。
【子規365日】■5月23日
麦の秋あからあからと日はくれぬ 1892(M25)年
夏井いつき【子規365日】朝日文庫

一茶さんの句 矢羽勝幸 ジョイ・ノルトン「雪五尺 四季の一茶」信濃毎日新聞社 より


《麦の秋》の俳句
麦が熟れる頃。稲の熟れ時の爽かさと違い、熟れ麦の香は、むっとして、淡い人の体臭に似ている。
・紙の様な月が出てをり麦の秋 康 之
・留守居する子へも弁当麦の秋 俳小星
・富士の袖雲より垂れて麦の秋 柏 翠
横田正知編「写真 俳句歳時記 夏」現代教養文庫 より
西 逈さんのコメントです。
《麦秋 (西 逈)
小津安二郎監督に「麦秋」という作品があります。昔の日本の景色に泣けてきます、懐かしくなるんでしょうな。悲しい場面でもないのに、自然に涙が出てくる。何気ない日常に、日本人の良さや素直さが描かれている。お金がなくたって、そんなことは苦労に入らない。そして、原節子の美しさ! あゝ「美しき日本」、ここに在り! 映画が終わって「終」の字に合掌したくなる、それが小津映画。》
























