自己心膜によって大動脈弁尖を再建することで、人工弁置換しなくてすむ手術は、東邦大学大橋病院 心臓血管外科教授の尾崎重之先生によって考案された手術です。既に尾崎先生によって1300例以上の執刀が行われていて、その成績、長期予後も良好と言われています。自己心膜をグルタールアルデヒド処理し、尾崎先生の考案したサイザー器具によって型どおりに弁尖を作り、型にあわせて大動脈弁輪にマーキングしたとおりに縫着して再建します。弁尖がより長持ちするように改良がくわえられてきましたが、人工弁のように心膜弁尖が裂開したりすることはほとんどなく、若干感染性心内膜炎の発生によって再手術が必要になった症例があるのみで、人工弁置換よりも成績が良好だそうです。
人工弁の場合は固いステントポストに心膜弁を張り付けたりして、固い可動性がない組織に膜を張り付けるために、膜が動くたびに膜に負担がかかることが劣化の原因となるのに比較して、自分の弁輪に縫着することで、この圧を微妙に逃がして膜組織に負担がかからないことが長期にわたって膜が耐えられる理由ではないか、と尾崎先生が考察しています。
今までも胸骨部分切開などにより小開胸アプローチでのOZAKI手術も試みられてきましたが、10月に尾崎教授が横須賀市立うわまち病院にStonehenge TechniqueによるMICS-AVR(小開胸アプローチによる大動脈弁置換術)を見学に来られ、その後、筆者が東邦大学大橋病院に伺って、MICSアプローチによるOZAKI手術のお手伝いをさせていただきました。手術は腋窩動脈送血での人工心肺セットアップになりましたが、無事に4時間ほどで1例目のMICS-OZAKI手術が完遂されました。その後も1例、同様の手術が行われ、今後、MICS-OZAKI手術が標準術式として行われていくことになるそうです。
人工弁を使用しない大動脈弁再建術は、現在と特に小児心臓血管外科領域で注目されており、人工弁の適応するサイズがない小児において今後広まっていくものと思われます。現に尾崎教授が海外でも主に小児病院で同手術を執刀、指導に行かれているそうです。
人工弁の場合は固いステントポストに心膜弁を張り付けたりして、固い可動性がない組織に膜を張り付けるために、膜が動くたびに膜に負担がかかることが劣化の原因となるのに比較して、自分の弁輪に縫着することで、この圧を微妙に逃がして膜組織に負担がかからないことが長期にわたって膜が耐えられる理由ではないか、と尾崎先生が考察しています。
今までも胸骨部分切開などにより小開胸アプローチでのOZAKI手術も試みられてきましたが、10月に尾崎教授が横須賀市立うわまち病院にStonehenge TechniqueによるMICS-AVR(小開胸アプローチによる大動脈弁置換術)を見学に来られ、その後、筆者が東邦大学大橋病院に伺って、MICSアプローチによるOZAKI手術のお手伝いをさせていただきました。手術は腋窩動脈送血での人工心肺セットアップになりましたが、無事に4時間ほどで1例目のMICS-OZAKI手術が完遂されました。その後も1例、同様の手術が行われ、今後、MICS-OZAKI手術が標準術式として行われていくことになるそうです。
人工弁を使用しない大動脈弁再建術は、現在と特に小児心臓血管外科領域で注目されており、人工弁の適応するサイズがない小児において今後広まっていくものと思われます。現に尾崎教授が海外でも主に小児病院で同手術を執刀、指導に行かれているそうです。


















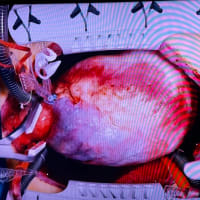

その後、MICS-OZAKI手術の進展はいかがでしょうか?
この術式は小児心臓外科領域のみならず、成人領域にも積極的に行われるのでしょうか? またその予後の成績はいかがなものでしょうか?
ご多用のところ申し訳ありません。
尾崎先生の話では、10年間の成人の成績は生体弁に匹敵するものと伺っております。今後の経過をみる必要がありますが、生体弁以上の耐久性があることが期待できるともおっしゃっておられました。ですので、たとえば、50歳未満の若年者の場合はメリットがある術式と一般に認識されております。高齢者の場合は、生体弁の成績が悪くないので、生体弁で充分と考える外科医が多いのも事実です。尾崎先生は80歳以上の症例でもOZAKI手術を実施しており、成績も良好と聞いております。では、何故日本で、および世界でOZAKI手術がスタンダードになっていないのか、というと、生体弁と比較した成績の優位性がまだ証明されていないこと、生体弁が中心となった現在の医療事情下では生体弁のメーカーの影響力が強い、その使用量を少なくしてしまうOZAKI手術のスポンサーにならないことなども影響しているものと思います。また、尾崎先生に直接執刀もしくは指導された医師に執刀された場合の成績は良好でも、それ以外の医師が執刀して、早期に再手術が必要になった報告が少なからずあり、一般化された確立した技術とはまだ必ずしも言えないことも関係していると思われます。
流れとしてはスーチャレス弁など新しいタイプの弁も出て、より短時間に設置できる低侵襲な人工弁の方に向いているかもしれません。
またTAVIとの関連から、生体弁⇒TAVI⇒再手術のようにライフステージに合わせた手術の順番なども昨今は学会で議論されておりますが、この中にOZAKI手術は一般的には考えられておりません。
今後、自己心膜で再建された大動脈弁論の耐久性が生体弁のそれを凌駕してくれば、尾﨑手術が術式の主流として位置付けられ推奨されてゆくべきと強く感じます。かつて放映された「ブラックペアン」第1話での主人公・海渡医師の名台詞の通り、「自己組織で治癒できるのに、わざわざ(外資系メーカ―の!)異物をぶち込む必要はない」わけですね。
貴院が貢献されたMICS-OZAKIの益々の展開と普及を心より期待しております。
以上、御礼が遅くなり大変申し訳ございませでした。
拝
先日、低侵襲手術学会でMICS-OZAKI手術に関係した講演を依頼されたのですが、筆者は尾崎先生のお手伝いはしましたが、実際に執刀している件数は尾崎先生が圧倒的なので直接尾崎先生にお願いするのがいいのではないか、とお断りました。
度々にて誠に恐縮ではございますが、自己心膜を使用した再建大動脈弁の耐久性につきまして、以下1点、質問させていただきたく存じます。
「自己の弁輪に心膜(再建された弁尖)を縫い付ける」とのことですが、術後の膨大な拍動数に耐えてゆく弁尖(と弁輪)の支持部は、もっぱら縫合糸のみに依存するのでしょうか? それとも弁輪と心膜(弁尖)の創傷部分がうまく癒合し、酸素や栄養素等を取り込める自己組織化した大動脈弁となり、膨大な拍動数に耐えてゆくのでしょうか?
誠に恐縮でございますが、ご教示いただければ大変幸甚に存じます。
拝
生きている弁輪組織から(血管)内皮細胞が結合組織として、移植された自己心膜へ伸長し(弁輪と自己心膜弁尖の)縫合部と縫合糸を覆って結合し癒合する。縫合糸の支持力に加え、この自己組織との結合による支持力が、術後の膨大な拍動数に耐えうる耐久性を生んいる。以上のように理解させて頂きました。
度々のご教示、誠にありがとうございました。深く感謝申し上げます。
拝