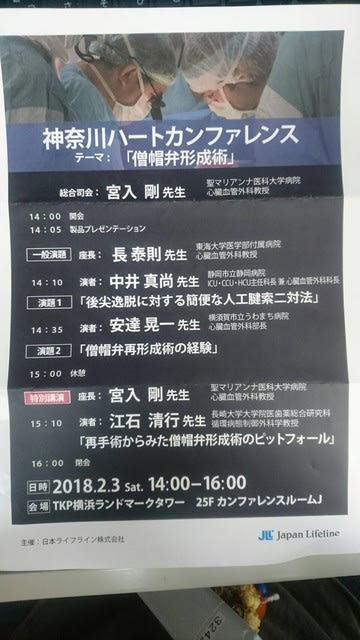大動脈弁狭窄症は、大動脈弁が硬化して可動性が低下し、心臓の収縮期にうまく開かなくなるために心不全や不整脈を呈する病気です。大動脈弁の硬化の原因として、加齢、脂質異常、高血圧、腎障害、先天性の二尖弁などがあります。昨今の高齢者の急速な増加とともに、この病気も急速に増加しています。高齢化社旗とともに増加する疾患の代表といえます。
大動脈弁狭窄症は一度発症すると、自然に治ったり、薬で治ったりすることはありません。
症状が出現してから死亡するまでの時間が短い疾患と言われています。
学生の頃、教科書に書いていたのは、胸痛や意識消失が起こるようになってからは2年以内に半分が死亡する、心不全で搬送された場合はおおむね寿命は一年以内と言われています。2年以内に半分以上が命を落とす疾患としては、進行性の肺がん、膵臓癌、Stage IVの大腸癌や乳がんなどがあり、このいわゆる末期癌と匹敵する病気といえます。
これら末期癌と大きく違うのは、大動脈弁狭窄症は手術で治癒させることが出来る病気であることです。
基本的には人工弁置換をすることで、早期に治療できれば、その後の寿命は正常の人と同じになることも可能です。心筋障害が進行してから手術した場合は、心筋の回復が十分期待できないこともあり、また手術そのもののリスクも上昇してしまうため、手術適応と判断された場合は早めに治療した方が良いといえます。
最近の心臓手術は成績も向上していることもあり、より早期に手術して良好な結果を享受する、という考え方が一般的になっています。
大動脈弁狭窄症は一度発症すると、自然に治ったり、薬で治ったりすることはありません。
症状が出現してから死亡するまでの時間が短い疾患と言われています。
学生の頃、教科書に書いていたのは、胸痛や意識消失が起こるようになってからは2年以内に半分が死亡する、心不全で搬送された場合はおおむね寿命は一年以内と言われています。2年以内に半分以上が命を落とす疾患としては、進行性の肺がん、膵臓癌、Stage IVの大腸癌や乳がんなどがあり、このいわゆる末期癌と匹敵する病気といえます。
これら末期癌と大きく違うのは、大動脈弁狭窄症は手術で治癒させることが出来る病気であることです。
基本的には人工弁置換をすることで、早期に治療できれば、その後の寿命は正常の人と同じになることも可能です。心筋障害が進行してから手術した場合は、心筋の回復が十分期待できないこともあり、また手術そのもののリスクも上昇してしまうため、手術適応と判断された場合は早めに治療した方が良いといえます。
最近の心臓手術は成績も向上していることもあり、より早期に手術して良好な結果を享受する、という考え方が一般的になっています。