| ~ 気ままに歩く 沖縄 ~ |
 |
| ( 画像; 壺屋窯場/登り窯 ) |
 |
| 【 沖縄の工芸 】 『 沖縄の焼物 その3 』を見聞しましょう。 〓 沖縄の古い窯場 〓 12世紀までの土器の時代を経て、14世紀末期から15世紀初めまでは陶器類を海外から多量に輸入した。 中国、日本、朝鮮、タイ、ベトナムなどが主な取り寄せ先であった。 特に中国陶磁器と南蛮焼陶器の輸入量が多かった。 ◇ 陶工を志す者が現る 15世紀頃からは南蛮焼を模した陶器を焼成する者があった。 製品の多くは生活用途の酒甕 水甕 壺 などであったとされる。 沖縄で焼物の発祥は15世紀頃と推定されている。 ◇ 窯場が各地で築造される ・ 16世紀頃に築造された主な窯場 喜名窯場(現;読谷村喜名)、知花窯場(現;沖縄市知花)、古我地窯場(現;名護市古我地)、作場窯場(現;大宜味村謝名城)など ・ 17世紀頃に築造された主な窯場 湧田窯場(現;那覇市泉崎)、宝口窯場(現;那覇市首里)、壺屋窯場(現;那覇市壺屋)がある。 発掘調査等で確認された窯場跡は約80箇所も存在しているとされる。 うち、壺屋窯場以外は時を経るに諸事情で廃場になっている。 〓 海外交易不振に伴う輸入品の減少 〓 ◇ アジア地域の海上交通 琉球王国は中国(明代:1368~1644年)が海禁施策を続けるなか、日本、中国、朝鮮、ベトナム、タイなど東南アジア諸国との海外交易で中心的役割を果たした。 ・ 16世紀頃からヨーロッパ諸国がアジア各地に進出 16世紀になって、中国(明)は海禁施策の緩和措置を執った。 中国人に日本を除くアジア諸国との直接交易を認める施策であった。 それを起点に15世紀中頃から海外進出に勢力的であったポルトガルを初めとするヨーロッパ諸国が東南アジア各地に貿易拠点を築き始めた。 間も無くもその拠点を基に中国や日本などとも多角的貿易を営んだ。 ・ 海上交通の変遷と琉球王府の海外交易衰退 琉球王国の経済基盤はアジア諸国との交易に依拠してきたが、その航路をヨーロッパ諸国に取って代わられる状態となって大打撃を受けた。 海上交通の世界的変化は琉球王国の海外交易を漸次衰退せしめた。 厳しい情勢に陥るも、冊封関係にあった中国との交易は縮小傾向ながらも命脈を保つ事ができた。 暫らく後には日本が鎖国政策を施行した事を以って再び他国との交易に盛り上がりをみせた。 〓 壺屋焼 〓 ◇ 壺屋窯場の草創 ・ 海外交易悪化に伴う産業振興策の拠出 16世紀末期からの琉球王国は海外交易の業績が逼迫状況にあった。 伴って、取引商品も激減傾向となり、焼物品の輸入も減少した。 海外交易が厳しさを増すなか、王府は産業振興を図る一端に陶業施策を施行した。 ・ 点在する窯場を統合 各地に点在していた主な稼動窯場を一箇所に統合した。(1682年) 知花窯場(現;沖縄市知花)、湧田窯場(現;那覇市泉崎)、宝口窯場(現;那覇市首里)の3窯場を≪那覇市壺屋地区≫に集約した。 懸かるうちに壺屋地区は一大焼物街へと変貌を遂げた。 そこに集まった進取気鋭の陶工達は技術研鑽に邁進して活気づいた。 それが ≪壺屋焼≫の始まりである。 壺屋地区焼物街は琉球王国随一の窯場となった。 壺屋窯場から産出された品を壺屋焼と称する。 壺屋焼は海外交易の輸出品として活用され、又幕府への献上品としても珍重された。 壺屋焼は400年余の歴史を歩んでいる。 ◇ 王府の陶工育成策 尚 寧 (1589~1620年)からの歴代国王は陶業振興策を推進した。 ・ 主な育成策 1617年 朝鮮人陶工を招聘して朝鮮式製陶法の伝授を図った。 1670年 陶工を中国(清)へ派遣して中国式製陶法を習得させた。 1730年 陶工を薩摩へ派遣して薩摩焼の製陶法を習得させた。 そこで習得した釉薬製法や焼成法は夫々に更なる研鑽を重ねられてオリジナリ性豊かな陶芸を創出した。 その成果は代々の若い陶工達へと伝授された。 壺屋焼は品質的に高められた伝統の製法が集約された産物であると評される。 近年まで 壺屋焼は沖縄陶器の代名詞とも称されてきた。 ◇ 壺屋焼の基本技法 焼成法は大別して≪荒焼≫と呼ばれる南蛮焼系を汲むものと≪上焼≫と呼ばれる大陸系の絵付がある。 ※ 荒 焼 14~16世紀頃にベトナム方面から伝わった技法が基本を成す。 基調となる黒土と赤土の混ぜ合わせを用い、火度調整で艶出しする。 泥釉・マンガン釉以外の釉薬は使わないで焼成する。 加飾技法と窯変制御に因る炎文様の創造が個性的作風を醸しだす。 1000℃程の熱度で焼かれた素焼き又は焼き締めである。 水甕、味噌甕、酒甕などの大型容器類が多い。 近年は日用食器として小型容器類の焼成も多くなった。 沖縄の街角で見かけるシーサー も荒焼の一種である。 ※ 上 焼 17世紀に招聘した朝鮮人陶工から授かった絵付技法が基本を成す。 赤土の上に白土を被せて化粧するのが特徴である。 下絵や赤絵で沖縄独特の紋様を描いている。 施釉、加飾での色鮮やかな絵付や彫刻紋様の施しが変化に富んでいる。 様々な釉薬を用いて、1200℃程の熱度で焼き締める。 碗、皿、鉢、壺、花器などの小型の日用品類が多い。 装飾性に富んで高級感のある品である。 〓 琉球王国崩壊と陶窯業界 〓 ◇ 琉球王国の崩壊 1869年:明治2 明治政府は全国的に版籍奉還を執行して藩制度を導入した。 1871年:明治4 明治政府は全国的に廃藩置県制度の施策を執行した。 1872年:明治5 琉球王国の場合は全国に遅れて琉球藩とされた。 1875年:明治8 明治政府は「琉球の王国制度を解体して、日本国に属する沖縄県を設置 する」旨の宣言を発令した。 1879年:明治12 廃藩置県施策に則った沖縄県が設置された。 政治制度が日本の府県制度に則して改められた。 ここにおいて、 1429年に創設され、歴代25人の国王を経て約450年間存続した琉球王国の長い歴史が終焉した。 然るに首里城は王府と王宮の地位から降りることになった。 ◇ 王国崩壊後の陶窯業界 他府県との通交が自由になって陶器商人が他所で製作された陶磁器類を持ち込んで販売するようになった。 特に有田焼の安価な商品が大量に流入してきた。 流入される日用雑器類は一般庶民の需要に浸透し拡大して行った。 壺屋焼は王府の庇護を受けながら育成・成長してきた故、押し寄せる自由競争市場の波へ対応できずに衰退の途を辿る事になった。 自由市場活動での身のこなしが未熟であった沖縄陶窯業界は深刻な危機状態に陥った。 ☆ 民芸運動家達の援護 沖縄陶窯業の危機状況を見かねて、民芸運動の第一人者であった柳 宗悦、河井 寛次郎、濱田 庄司らが来沖した。 彼らは沖縄の陶工達を指導して技術の研磨向上に精力を注いだ。 壺屋焼に美を追究した民芸陶器の姿を求めて止むことなく探究した。 その成果が芽生えると、 間を置く事なく東京や京阪神などに≪壺屋焼情報≫を発信し続けた。 そのパブリシティ効果が漸次現れて県外の陶器商人等に認知されるようになり、購買行為の広がりに繋がるようになった。 辛うじて需要が漸増する事になり、製造陶工達にも活気が戻ってきた。 壺屋焼が今日あるのは、柳 宗悦を初めとする民芸運動家達の弛まぬ尽力に因るところが多大であると伝わる。 ・ 民芸運動家達が観た壺屋焼の評価 壺屋焼は他には無い鮮やかな彩色を用いて眼を惹かせた。 庶民用の雑器類で多分な装飾性を採り入れた陶器は珍しいとされた。 彼等が注目しての高い評価は沖縄の陶工達に自信と誇りを持たせた。 彼等から直伝の指導を授かった沖縄の陶工には、後に人間国宝となった金城 次郎 や 新垣 栄三郎 らがいる。 彼等が中心となって混迷の沖縄陶工界をリードしていった。 次回に続く・・・ |
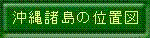 |
 |  |
| 応援クリック.とても嬉しいです! See Again! |













