| ~ 気ままに歩く 沖縄 ~ |
 |
| ( 画像; 壺屋焼/枝梅竹文赤絵碗 ) |
 |
| 【 沖縄の工芸 】 『 沖縄の焼物 その4 』を見聞しましょう。 琉球王国崩壊後の沖縄陶窯業界は自由市場の波にさらされて危機状態に陥るも本土の著名民芸運動家達からの技術指導及び市場開拓の支えを得ながら復興の道を歩んだ。 〓 第二次世界大戦と沖縄陶窯業界 〓 第二次大戦(1941~45年)は沖縄に甚大な戦禍をもたらした。 日本本土防衛の前線地とされた沖縄は日米軍の間で棲さましい地上戦が繰り拡げられた。 両軍最高指揮官が戦死するほどの激戦であった。 この沖縄戦は多数の民間人戦死者を出した。 沖縄本島や周辺離島では地形が変わるほどの激しい艦砲射撃や空爆撃があった。 とりわけ本島中南部地域は殆どの住宅地や田畑が焦土と化してしまった。又、この地域からは多数の民間人戦死者が出た。 ◇ 終戦直後から米軍統治下に置かれた沖縄県 日本の敗戦に因り沖縄県はアメリカ軍の統治下に置かれた。 伴って、沖縄県庁は解体されて琉球政府が創設される。(1952年) その後の長期をアメリカ軍施政権下の琉球政府時代が続く事になる。 ※ 時を経て、1969年に日米首脳会談で≪沖縄返還≫を合意 1971年に日米間で≪沖縄返還協定≫を締結 1972年に沖縄は≪祖国復帰≫して再び沖縄県となった。 ◇ 終戦後の沖縄陶窯業界 家族・肉親・知人・友人など多くの命が飛び散ったなか、辛うじて戦禍を免れた幾ばくかの人々は焼野原に佇み打ちひしがれ状態におかれた。 人々は途方に暮れる日々が暫く続くも、生活の糧を得るべく仮住居を構え、廃虚と化した職場の再生に取り組み始めた。 ・ 米軍が各地に散らばっていた沖縄陶工達を集めて就労させる 戦時中の壺屋窯場は全て閉鎖されていた。 壺屋地区は不幸中の幸いにも比較的軽微な戦禍を被るに止まっていた。 米軍は終戦と共に各地の収容所から陶工達を解放して壺屋へ送還した。 自らの工房に戻った陶工達は製作活動に取り組み始めた。 米軍の意図は戦禍消失した日用陶器類再生産の処置であったと伝わる。 ☆ 朝鮮戦争の勃発 戦禍からの立ち直りに取掛かる最中、朝鮮戦争が勃発した。(1950年) それに伴って、米軍基地の大規模建設工事が急速に展開された。 そして、多くの米軍人・軍属が沖縄に移動して駐留するようになった。 沖縄の米軍基地も朝鮮戦争の前線基地となっていった。 ・ 経済市場の急速的活性化 基地建設と駐留米軍人急増が要因となって人・物資の動きが急速的に活性化を呈した。 米軍は基地建設・管理要員として多種多様な業務に亘る雇用を求めた。 土木・建築・通信従事者、簡易的事務業務、車両係りなどを採用した。 当時の基地業務従事者の月収は東京の平均的サラリーマンよりも高額であったと伝わる程の好条件であった。 皮肉にも米軍基地建設が沖縄の物流市場を一気に活気付けた。 ☆ 工芸品の需要が高まる 駐留米軍人が本国へ帰還する際のお土産品に漆器や陶器が好まれた。 戦禍で被った損傷の手当てをしながら細々と再生に取り組んでいた陶窯業界にとって陶器需要の高まりは好機到来であった。 ・ 再び他府県業者の参入 沖縄市場での陶器需要の高まりは多くの他府県業者も馳せ参じた。 これまで民芸運動指導者達からの指導を受けて陶窯業界の市場性を学んで来た沖縄の陶工達は、更なる技術の研鑽に邁進してオリジナリ性豊かな陶芸を次々と創出した。 弛まぬ努力の成果が実って壺屋地区周辺には焼物専門店や窯元直営店が立ち並ぶ賑わいをみせた。 展示会などのイベントも開催されるようになった。 陶工達や関係者の汗が結実して、壺屋地区は名実共に沖縄を代表する≪焼物の街≫と称されるようになった。 〓 壺屋窯場 〓 ◇ 壺屋窯場に懸案事項 ☆ 都市への人口集中化 米軍基地建設の外因的誘導により沖縄本島は雇用需要が高まった。 働き口を求める人々が離島や遠隔地の村々から那覇市に集中した。 物流の中心街である那覇市は住宅建築工事ブームが起きて宅地の拡がりをみせた。当時に日本で最も人口密度の高い市街地となった。 壺屋窯場区域は那覇市街の真中に位置するところから窯場周辺に住宅が張り付き密集するようになった。 ・ 公害問題が発生 壺屋焼は≪登り窯≫で焼成する為、燃料には大量の薪炭が使用される。 その薪窯から吐き出される煙が深刻な公害問題となってきた。 那覇市は煙害対策の為に薪窯の使用を禁止してガス窯に転換する旨の行政措置を執行した。 窯場から伝統的な技法が失われていく事態に陶工達は戸惑いの境地に立たされた。 壺屋窯場の煙は戦火で廃墟と化した那覇市が復興への道程を邁進しているシンボルなりと誇らしく語られて来たが寄せ来る時代の要請には応えなければならなかった。 ※ 登り窯とは・・ 陶磁器等を大量に焼成する為に炉内を各間に仕切り各間に置かれた製品を一定の高温に保って焼成できるよう工夫された窯の形態。 斜面地形を利用して窯を後ろ上がりに設定する。 重力による燃焼炎の対流で製品全体に均等に炎が廻る。 釉薬を使用する場合などには製品の均質化という点で優れている。 ☆ 読谷村へ窯場移転 時を同じくして、沖縄本島の中部地域に在する読谷村は基地返還による広大な土地転用策を模索していた。 その対応策として、壺屋窯場の陶工や那覇市に対して窯元誘致の積極的な働きかけを行った。 ・ 読谷村が掲げたアプローチ 1)村の周辺には原料となる良質の陶土が豊富にある。 2)織物工芸等が根付いてきた土地柄で文化活動奨励に積極的である。 3)代表的古窯場である喜名窯場跡が在り≪焼物ゆかりの地≫である。 ☆ 陶工達の所在 陶工達にはガス窯に転換して壺屋に残る者と薪窯に拘って読谷村へ移転する者があった。 リーダー格であった金城 次郎や新垣 栄三郎を初め多くの陶工達が壺屋の地を離れて読谷村に移転する事とあいなった。(1970年頃から) 移転するに際しては、個々の窯場を構えるのではなくてグループで共同使用する≪登り窯≫を築造して製作にあたる事にした。 ・ 読谷やちむんの里 ( 方言:やちむん/焼物 ) やちむんの里開園は読谷村での陶芸村の始まりである。(1972年) 場所;読谷村座喜味(沖縄本島中部地区) MAP→やちむんの里 人里離れて緑林に覆われた丘陵地に建立されてる。 共同使用する9室連房窯や14室連房窯などの登り窯がある。 多くの陶工達が集まり、赤瓦屋根構造の窯場が点在する広い園は沖縄陶器の一大生産地を形成している。今日では≪第二の壺屋焼の故郷≫と呼ばれ、ここで焼成された陶製品を≪読谷壺屋焼≫とも称される。 陶工達が寄って製作に汗している姿が見学に訪れる人々の感心を呼んで、今では観光地ルートの一端を成している。 ★ 沖縄の陶芸 ★ 魚紋、海老紋、蟹紋などの装飾紋様が主である。 特に魚紋様は生き生きと描かれている。 海に囲まれた沖縄ならではの独創的紋様である。 鮮やかな彩色を用いた装飾を多分に採り入れている。 古陶器のシンプルな色絵が民藝調ながらもモダンな印象を与える。 唐草紋様などの植物紋様がオリエンタル的風潮を感じさせる。 と一般的に評される。 琉球王国→琉球藩→沖縄県→戦禍→琉球政府→沖縄県(現在)と自治体制が変遷した時代の荒波を被りながらも伝統技法を礎にして時の風流に応じ、オリジナリ性豊かな感性を織り込んで歩んできた沖縄陶器である。 外的誘導による幾多もの困難を克服して来た沖縄陶工達の自信と誇りは更なる成長への確信性を抱きながら歩み続けるであろう! |
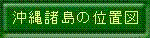 |
 |  |
| 応援クリック.とても嬉しいです! See Again! |
















