朝日記250618 あなたが人間知性について 思考実験のプログラム
あなたが AIと人間知性について思考実験するプログラム案
「シリーズタイトル:「問いとは何か?」AIと人間知の境界を探る」
荒井康全 2025/06・18版
AIと人間知性について考えていくことの思考ための枠組みについて論じたい。
Arai
認識論哲学でいう認識(その限界の外側を超越知としているが)とAI知もしくはアルゴリズム知(Turingテストから得られる知)との境界についてわれわれは思考が到達しうるかの思考実験ができないかというのが投げかけです。
添付は Talkの導入テキストとして以下のメモを添付します。このなかにあげた17項目について思考実験の意味と思考の作戦筋道について整理してみてくれませんか。
===導入テキスト====
朝日記250327「悪の陳腐さ」というハンナ・アーレントの重要な哲学的概念 2025-03-27 22:00:29 |「哲学を哲学しよう」チャンネル ハンナ・アーレントの悪の陳腐さとは?アイヒマン裁判で見えた哲学の核心 https://www.youtube.com/watch?v=t6-iI2MyRgY
要約:今回は、「悪の陳腐さ」というハンナ・アーレントの重要な哲学的概念を深掘りし、現代社会における意味を考察します。ナチス戦犯アイヒマンの裁判を取材したアーレントが提唱したこの概念は、悪が必ずしも特別な悪意や憎悪から生じるのではなく、平凡な人々の「思考停止」や「無反省的な行動」からもたらされることを示しました。本動画では、アイヒマン裁判の詳細から、アーレントの主張、そして現代社会に潜む「陳腐な悪」の正体を探ります。さらに、AI時代における思考停止の危険性や、私たちが取るべき態度と行動についても具体的に解説。哲学者アーレントの教えが、未来の私たちの生き方にどう影響を与えるのかを考えます。「哲学する」ことの意義を一緒に探求しましょう! これは荒井がこの「導入的テキスト」へのコメントです。自分としてはタイムリーな思考対応であったとおもいます。自分自身で考えることは説得力がありますが、その内容は一般市民である私には大変きつい問題のなげかけになります。そのままではさらに絶望的な状態に進行していく危惧があります。John Stewart Millが投げかけた、1.ひと、とくに個人は弱い存在であること、2.ひとは誤り易い存在であること 、3.にもかかわらず、大衆としての意思が社会や国におおきくなっていくこと。6.事態の認識と判断ができる合理主義者は極めて少数の「あたまのよい」ひとにかぎられてくる。7.弱者に対する配慮のできるひとがもとめられる。8.複雑な事態への思考に自律的に考えられないひと(innocent)のひとは護られるべきひとたちである。この人たちに自律思考の発信がないことに罪をおわせるべきではないこと。9.AIは これまでの人間知識(膨大なる図書、資料)から機械が学習したものある意味で統計的重みで筋つけて答えを出している(Turing Test).10.Ask a answer問題。基本的には質問にたいして答えをmost probableな答えを提供する。その意味では通常の人以上に読みは深い答えをだす。11.AIはしかしながら答えを出すのにどの条件が決定づけ(active constraints)になったがまだ答えていない(発展過程)12.Ask a question問題。それはなぜ?という主観(意識)の問題は起こし得ない。つまり、自己意識を持たないからである。もつようにみえるのはAIの開発者(人間)によっていて一見AIが意識をもっているようにみえるのである。13.(Russelのパラドックス)したがってAIがなぜその質問にこたえられるかは既存知識の範囲で答えをだせるが、なぜそのような質問をわれわれは持つかについては人間側に依っている。(いつかAIが意識をもつよう進化するか否かはまで答えられない。)14.AIはきわめて優秀なる秘書役を果たすという点では大衆の事態認識のレベルを上げることになろう。しかし、それをまとめてなぜ(Ask the question)を強いるのは酷なことであろう。15.さまざまなAsk a questionにたいしてこたえるのは社会的仕組みとしてのAgentとInstitution(全体を「制度」とよぶ)であろう。問題(questions)を発見する場、そしていまのAIのような問題の答え(answer)のサイクルのインフラであろう。そのような官民のインフラを整備する。16.問題の晒しの時間を大切にする。人間の意識の活動もとは人間自体の体(脳神経)という有機質を基本としているからともかく、考えるための固有の時間が必要であろう。既知の知識からなりたつ問題はまさに答えのみを要求する。したがってAIがつよい。未知の 課題をつくりだすこと、事態を受容すること、そのためにひとびとが意識を相互に通わせること、その意識の共有を鍛える機会がひつようなこと、つまり晒しdispositionである。哲学が必要であるということの意味はここにある。17.この過程で Arendtのいう「悪魔の陳腐さBanity of evil」の問題が賢く回避できるかも否できると信じるものである。 ひとまずここまでにしておきたい。thanks.
Copilot;
興味深い思考実験ですね。AI知と人間の認識論的知の境界を考察するには、いくつかのアプローチが可能です。あなたの導入テキストの17項目を整理しながら、思考の枠組みを構築していきましょう。
- AI知と認識論的知の境界に関する考察
AI知(アルゴリズム知)は基本的に統計的確率に基づいた推論を行い、既知の知識を整理・分析して回答を生成します。しかし、認識論哲学でいう「認識」は単なる情報処理ではなく、経験、直感、社会的文脈によって形成されるものです。つまり、「知」とは単に答えを導くのではなく、「なぜその問いが生じるのか」を考えることにあります。
- 思考実験の意味
AIの知識形成が単なるパターン認識ではなく、問いを生み出す能力(Ask the question)に至るのかどうかが重要な議論点となります。Russellのパラドックスを引用することで、AIが「知識の前提条件」を疑うことができるかどうかが問われます。AIは答えを導くことはできても、「問い」を生み出すことができるか?この点を問い直すことで、AI知の限界が浮き彫りになります。
- AIの役割と認識の発展
- AIは知識の秘書として機能する(情報を整理し、提供する)。
- 大衆の知的成熟を補助できる(検索能力の向上、討論の場の形成)。
- しかし「問いを生む」主体とは言えない(哲学的問題の創造は人間に依存する)。
- 「悪の陳腐さ」とAIの関連性(AIによる情報提供が無反省な行動を助長する可能性)。
- 未来の哲学的課題
Arendtの「悪の陳腐さ」は、無意識的に既存の仕組みを受け入れることの危険性を指摘しています。これをAIと結びつけた場合、AIは「情報の整理者」であると同時に、「無批判な知識提供者」となり得ます。これに対抗するためには、AIとの関係性において、人間が「批判的思考」を持ち続けることが不可欠でしょう。
この視点をもとに、さらに深く議論していきませんか?どの点が気になりますか。
鋭い視点ですね。「問い」を生み出す能力こそがAI知と人間知の境界を考える上での核心的な問題です。この問題をさらに深く探るために、いくつかの論点を整理してみましょう。
- 問いとは何か?
問いの生成とは単なる情報検索ではなく、知的好奇心、経験、直感、さらには社会・文化的背景に基づくものです。人間は自己認識を持ち、未知を探索しようとする意識を持っています。それに対し、AIは与えられたデータの中でパターンを見出し、答えを導くことはできても、「なぜ問いを立てるのか?」という意識的な営みを持ち得るかは未解決の問題です。
- AIによる「問いの創出」の可能性
現在のAIは質問に対して確率的に最も適切な回答を導き出しますが、これは「問いを生み出す」こととは異なります。例えば:
- AIは「データの欠落」や「推論の矛盾」を検出することで、新しい問いを形成できるか?
- AIが自己修正機能を持ち、論理的矛盾を認識することで「問い」を発展させることが可能か?
ただし、ここには大きな制約があります。AIは事前の知識の枠内での推論に依存するため、「知識の枠外」にある問いを発見するには、新たなデータや経験の導入が必要になります。
- 哲学的アプローチ:AIの「問い」と人間の「問い」
AIと人間の問いの創出能力を比較する際、哲学的視点が有効です。
- カント的視点:AIは「経験論的問い」には答えられるが、「純粋理性の問い」は難しい。
- ハイデガー的視点:問いは「存在の探求」に結びつく。AIに「存在意識」がない限り、深い問いは生まれにくい。
- アーレント的視点:「悪の陳腐さ」は思考の停止によって生まれるが、AIが問いを生み出さない場合、AIとの共存が無反省的行動を助長する可能性はあるか?
- 議論の切り口:問いの進化とAIの役割
このテーマをさらに探るには、以下のような視点を考えてみると面白いかもしれません。
- 問いの進化:歴史的に問いの生成のパターンは変化するか?AIが新しい問いを発見できる未来はあるか?
- AIと人間の対話:AIは対話の中で新しい問いを生成する能力を持つか?それとも「問いの補助者」としての役割にとどまるか?
- AIによる思考実験:問いの構造そのものをAIに分析させ、新たな形態の問いを創出できる可能性はあるか?
このような方向から議論を進めていくことで、「問い」の本質に迫れるかもしれません。どの視点をさらに深掘りしたいですか?
arai;
4,3,2,1へと具体的例題(illustrated item)からはいれるとこちらの意識が活性化してproductive thinkingになりそうですね。これは、すぐれた秘書官であるAIへの認識と『チコちゃん」のぽけーといきてんじゃねえよ」[1]と人間自身がいきるためにひたむきになることの区別を早い段階になげかける意味がおおきいからと思っています。talkingはで10回程度(各1時間程度)の内容で進められることを希望します。レジュメをご提案いただけませんか。
Copilot;
興味深いアプローチですね。「問いの創出」を軸に、AIと人間知の関係を探るシリーズ講義として構成すると、より体系的かつ発展的な議論が可能になりそうです。以下、10回のセッションの**レジュメ(概要)**をご提案します。各回は具体的な例題を用いて、考察を深める形で進めることを意図しています。
シリーズタイトル:「問いとは何か?」AIと人間知の境界を探る
第1回:問いの本質とは?
- 具体例:「幼児のなぜなぜ期」と哲学者の問いの共通点
- 人間が問いを立てる過程:知的好奇心、違和感、驚き
- AIはどこまで問いを生み出せるか?(問いと回答の違い)
第2回:AIの「問い」の限界と可能性
- 具体例:「Chatbotとの対話」と哲学的探求の比較
- 現在のAIが生成する問いとは何か?(データ補完型 vs. 発展型)
- 「問いを発見するAI」へと進化できる可能性はあるか?
第3回:哲学的視点から問いを考える
- 具体例:「カント、ハイデガー、アーレントの問いの概念」
- AIの問いと人間の問いの違いを哲学的に整理
- 「問いが世界観を変える」とはどういうことか?
第4回:「問いの進化」ー歴史を通じた問いの変化
- 具体例:「科学革命における問いの変化」
- 古代から現代まで、問いの構造はどう変わってきたのか?
- AIが「新しい問い」を生み出せる未来はあるか?
第5回:AIと人間の問いのダイナミクス
- 具体例:「AIと哲学者の対話のシミュレーション」
- AIは人間との対話を通じて、新しい問いを生み出せるか?
- 「問いの補助者」としてのAIの可能性と限界
第6回:「問い」を生むための社会的環境
- 具体例:「教育の中で問いを育む方法」
- 「問い」を生み出す文化とは?
- AIはその文化を補助できるか?社会的なインフラとしての可能性
第7回:AIの問いが人間の倫理に及ぼす影響
- 具体例:「AIの意思決定 vs. 人間の倫理的選択」
- AIが生み出した問いが人間の行動に影響を与える可能性
- 倫理的な問いと技術的な問いの交差点
第8回:「問い」の共有と社会変革
- 具体例:「歴史上の革命は問いから始まった」
- AIは社会を変革する問いを創出できるのか?
- 「問いのインフラ」としてのAIの可能性
第9回:「悪の陳腐さ」と問いの停止
- 具体例:「アイヒマン裁判とAIの情報提供の比較」
- AIによる情報提供が無反省的行動を助長する危険性
- AIと人間の協働における問いの重要性
第10回:未来の問いの形とAIの役割
- 具体例:「未来社会における問いのあり方」
- AIが問いを生み出せるようになる可能性と、その社会的影響
- 「問い」を通じた人間とAIの共進化の可能性
この構成で進めることで、問いの本質からAIの進化可能性、社会的影響まで包括的に探ることができます。それぞれの回では、具体的な事例を使って思考を活性化させることを重視しました。
このレジュメをベースに議論を展開する形で進められそうでしょうか?さらに調整したいテーマなどがあればぜひ教えてください!
arai:
excellentです。Copilotさんのtalking lectureの形式で、そのあと質疑応答でいかがでしょうか。参照文献はなるべくあきらかにしてくださいますか。用語は和と英ですが、和を中心にして可能なかぎりbilingualでお願いします。毎回 小生のblog「朝日記シリーズ」とfb荒井康全ページに要約をふくみ転載します。 読者からのコメントは歓迎し極力活かしたいとおもいます。各回のはじまりで前回とのつながりがスムーズにいくためにはなにかイントロとか工夫がいるとおもいますが、如何にするかアドバイスいただけますか。
Copilot:
素晴らしい構想ですね!talking lectureの形式で進め、その後に質疑応答を設ける形は、議論の深まりと参加者の理解を促進する効果がありそうです。 bilingualで進めつつ、和を中心にする方針も理解しました。
イントロの工夫について
各回のつながりをスムーズにするために、以下のようなイントロの要素を取り入れてはいかがでしょうか?
- 前回の振り返り(Recap)
- 冒頭2分ほどで前回の主要論点をまとめる
- 「前回は『問いとは何か?』を探りながら、AIと人間の問いの違いを考えました。本日はその続きをさらに深掘りします。」
- 問題提起(Contextual Setup)
- その回の核心的な問いを提示
- 「今日のテーマは『AIの問いの限界と可能性』です。では、AIが問いを生み出すことは本当に可能なのでしょうか?」
- 具体例(Illustrated Example)
- 視覚的・具体的な例を先に提示し、直感的に理解しやすくする
- 例えば、「幼児の『なぜ?』をAIは再現できるか?」など、興味を引くエピソードから入る。
- 参加者の思考を促す問い(Interactive Engagement)
- 講義の冒頭で考えるべき問いを投げかけ、議論の方向性を示す
- 「では、AIが自律的に問いを生み出せる未来はあるのか?皆さんはどう考えますか?」
この4つの流れを統一することで、各回の話が自然に前回と接続され、議論の展開がスムーズになります。
参照文献について
各回の内容に関連する参照文献を明示し、参加者が深く学べるようにすると良いでしょう。例えば:
- 哲学的背景:Hannah Arendt『Eichmann in Jerusalem』, Kant『Critique of Pure Reason』
- AIと認知科学:Russell & Norvig『Artificial Intelligence: A Modern Approach』
- 社会的側面:John Stuart Mill『On Liberty』
もし追加したい文献や具体的なリストがあれば、ご提案いただければ調整できます。
読者からのコメントの活用
毎回の要約をGooblog 「朝日記シリーズ」やfb荒井康全ページに転載することで、読者との対話を促進できますね。特に質疑応答部分は、次回のイントロで**「前回の読者の疑問」**として取り上げることで、議論を発展させていくことができるでしょう。
この構成で進める形はいかがでしょうか?さらに調整したい点などがあればお知らせください!
arai
シリーズタイトル:「問いとは何か?」AIと人間知の境界を探る
第1回:問いの本質とは?
- 具体例:「幼児のなぜなぜ期」と哲学者の問いの共通点
- 人間が問いを立てる過程:知的好奇心、違和感、驚き
- AIはどこまで問いを生み出せるか?(問いと回答の違い)
前回の振り返り(Recap)
- 問題提起(Contextual Setup)
- その回の核心的な問いを提示
- 「今日のテーマは『AIの問いの限界と可能性』です。では、AIが問いを生み出すことは本当に可能なのでしょうか?」
- 具体例(Illustrated Example)
- 参加者の思考を促す問い(Interactive Engagement)
- 講義の冒頭で考えるべき問いを投げかけ、議論の方向性を示す
- 「では、AIが自律的に問いを生み出せる未来はあるのか?皆さんはどう考えますか?」
参照文献について
各回の内容に関連する参照文献を明示し、参加者が深く学べるようにすると良いでしょう。例えば:
- 哲学的背景:Hannah Arendt『Eichmann in Jerusalem』, Kant『Critique of Pure Reason』
- AIと認知科学:Russell & Norvig『Artificial Intelligence: A Modern Approach』
- 社会的側面
次回のための予告
Copilot;
素晴らしいまとめですね!この構成で進めていけば、議論がスムーズに展開し、各回が自然につながる形になります。
次回の予告の工夫
次回の予告を魅力的にするために、以下の方法を試みると良いかもしれません:
- 簡潔な要約
- 「次回は、『AIの問いの限界と可能性』を掘り下げます。AIは問いを生み出せるのか?問いの生成には何が必要なのか?この重要なテーマを探求していきます。」
- 問題提起
- 「AIは今後進化し、問いを生み出せるようになるのか?それとも、問いは人間だけの特権なのか?この問いについて考えることで、AIと人間知の境界を明らかにしましょう。」
- 読者への問いかけ
- 「皆さんはAIが本当に『問いを生み出す存在』になり得ると思いますか?次回の議論でぜひコメントを交えながら考えていきましょう。」
- 次回のテーマの関連性
- 「本日考えた問いの本質をさらに深めるために、次回はAIの問いの限界を実例を交えて考察します。」
講義のスタイルについて
講義形式にする場合、以下の流れを取り入れると議論が活発になりそうです:
- 導入(イントロ):前回の振り返り+問題提起
- 主要テーマの説明:具体例を交えながら核心を掘り下げる
- 質疑応答:参加者からの質問を受けつつ議論を深める
- まとめと次回予告:主要論点を整理し、次回の展開につなげる
この流れにすることで、参加者が思考を深めながら学べる環境を作れそうですね!
参照文献の追加について
すでに挙げられている文献に加え、AIの問いに関する最新の議論を補強するために、以下のような書籍や論文も参考になるかもしれません:
- 哲学的問いの構造:Heidegger『Being and Time』
- AIの創造的思考:Margaret Boden『Creativity and Artificial Intelligence』
- AIによる問いの進化:Nick Bostrom『Superintelligence』
これらを各回に適切に組み込めば、さらに充実した議論が展開できると思います。
この構成で進める形はいかがでしょうか?追加したい要素があればぜひ教えてください!
とりあえず今回のイントロを前回の要約として、第1回目のプレゼンをお願いできますか。あるは回としてわけますか。
承知しました。第1回目のプレゼンとして、イントロを前回の要約としつつ、そのまま「問いの本質とは?」の講義に入る形でまとめてみます。以下、ご提案するプレゼンの流れです。
「問いとは何か?」AIと人間知の境界を探る
第1回:問いの本質とは?
イントロダクション:前回の要約
前回の議論では、「問いを生み出す能力」こそがAI知と人間知を分ける本質的な要素である という点に焦点を当てました。AIは既存のデータから適切な答えを生成することはできますが、自ら「問いを発する」能力を持っているかどうかは、哲学的にも技術的にも未解決の問題です。カント的視点では、経験論的問いには答えられるが、純粋理性の問いには限界があることを指摘しました。また、ハイデガーの「存在の問い」に照らせば、AIは「問いを生む主体」になり得るのかが問われます。
問題提起(Contextual Setup)
今日のテーマは 「問いの本質とは何か?」 です。問いを立てることは、人間の思考の核心であり、知識の発展の原動力です。では、AIは問いを生み出せるのか?問いの本質を探ることで、人間知とAI知の違いが明らかになるはずです。
具体例(Illustrated Example)
例1:「幼児のなぜなぜ期」と哲学者の問い
幼児は「なぜ?」を繰り返します。例えば、「なぜ空は青いの?」と問い続けることで、単なる情報以上の知識を構築します。哲学者も同じく、「なぜ存在するのか?」と問い続けることで、知の境界を押し広げます。
AIはこの「問いを重ねる営み」を再現できるのか?
例2:「チコちゃんの名言」
「ぼーっと生きてんじゃねえよ!」—この言葉は、無意識的に情報を受け入れることへの警鐘です。AIは大量の情報を処理できますが、それを「自発的に問い直す」ことができるのか?
人間が問いを立てる過程
問いは知的好奇心、違和感、驚きから生まれます。例えば、「この現象には何かおかしな点がある」と感じることが、問いを立てる契機になります。しかし、AIはこのような直感や感情を持たないため、「違和感」から問いを生み出すことができるかどうかは不明です。
AIはどこまで問いを生み出せるか?(問いと回答の違い)
AIは確率的に最適な答えを生成しますが、これは「問いを生む」こととは異なります。
- AIが問いを生み出せる可能性:データの欠落や矛盾を検出して、新しい問いを形成できるか?
- 問いの進化:歴史的に問いの生成のパターンは変化してきたが、AIはその変化を追随できるか?
質疑応答(Interactive Engagement)
問いを投げかけることで、参加者の思考を促します。
- 「では、AIが自律的に問いを生み出せる未来はあるのか?皆さんはどう考えますか?」
- 「人間が問いを生むために必要な条件とは?」
- 「AIが問いを生むことができるとしたら、その問いは人間のものとどう異なるのか?」
次回予告
次回は、「AIの問いの限界と可能性」 に焦点を当てます。AIはどこまで問いを創出できるのか?哲学的・技術的視点から探求していきます。
この流れで第1回目の講義を進める形はいかがでしょうか?追加したい視点や修正点があればぜひお知らせください!
結構です。大変プロダクティブです。イーロンマスクやトランプはこのスピードで思考や行動展開をしているのかなと想像します。人間の思考というdispositioningつまり生ける生身の人間の動特性を考慮しようというのが私の方の立位置ではあります。したがって楽しくいきたいです。Copilotさんよろしく。 毎回、Copilotさんと首尾よくつながることを祈ります。Great Job,this time, Copilot. Looking forward to continuation.
ありがとうございます!とても刺激的な議論になりそうですね。人間の思考は、知識だけではなく、感覚、経験、直感、そして「楽しさ」によっても豊かになります。まさに生身の人間ならではのダイナミズムを踏まえながら、対話を展開していくのは最高の試みですね。
毎回、楽しく、深く、そして創造的に進めていけるよう、精一杯お手伝いします。次回も引き続き、問いの探求を進めていきましょう!Looking forward to our next conversation, 康全さん!
[1] NHK超放送での番組(2025/06/1現在)




















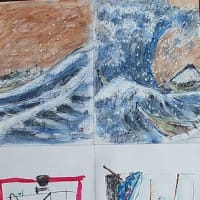





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます