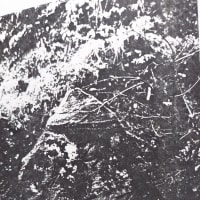2
<黒髪山>
黑髮山は霞かかりて、雪いまだ白し。
剃り捨てて黒髪山に衣更 曾良
曾良は、河合氏にして惣五郞といへり。芭蕉の下葉に軒をならべて、予が薪水(しんすい)の労を助く。このたび松島・象潟の眺めともにせんこと喜び、かつは羈旅の難をいたはらんと、旅立つ暁、髮を剃りて、墨染にさまをかへ、惣五を改めて宗悟とす。よりて黒髮山の句あり。「衣更」の二字、力ありて聞こゆ。
二十余町山を登つて、滝あり。岩洞の頂より飛流して百尺、千岩の碧潭(へきたん)にお落ちたり。岩窟に身をひそめ入りて滝の浦より見れば、裏見の滝と申し伝へはべるなり
しばらくは滝にこもるや夏の初め
・芭蕉の旅の同行者。曾良は、信州諏訪の出身で、俳人以外の別の顔を持ち、神道学に通じ、地理学にも詳しかった。とあり師芭蕉と同じく、旅に生涯を終え、不思議な魅力を感じる私です・・・・。
しばらく滝の洞窟にこもって、清冽な気を浴びていると、僧の夏の修行のように、身も心も引き締まるのです・・・・。
<那須>
那須の黒羽といふ所に知る人あれば、これより野越にかかりて、直路をゆかんとす。遙かに一村を見かけて行に、雨ふり日暮るる。農夫の家に一夜をかりて、明くればまた野中を行く。そこに野飼ひの馬あり。草刈るおのこに嘆きよれば、野夫といへども、さすがに情知らぬにはあらず。「いかがすべきや。されどもこの野は縦横にわかれて、うひうひしき旅人の道ふみたがへん、あやしうはべれば、この馬のとどまる所にて馬を返したまへ」と、貸しはべりぬ。ちいさき者ふたり、馬の跡したひて走る。ひとりは小姫にて、名を「かさね」といふ。聞きなれぬ名のやさしかりければ、
かさねとは八重撫子の名なるべし 曽良
やがて人里に至れば、価を鞍壺に結び付て馬を返しぬ。
<黒羽>
黒羽の館代浄坊寺なにがしのかたにおとづる。思ひかけぬあるじの喜び、日夜語りつづけて、その弟桃翠などいふが、朝夕勤めとぶらひ、自らの家にも伴ひて、親族のかたにも招かれ、日をふるままにひとひ郊外に逍遙して、犬追物の跡を一見し、那須の篠原をわけて、玉藻の前の古墳をとふ。それより八幡宮に詣づ。与市扇の的を射し時、「別してはわが国の氏神正八幡」と誓ひしも、この神社にてはべると聞けば、感応殊にしきりにおぼえらる。暮るれば桃翠宅に帰る。修験光明寺といふあり。そこに招かれて、行者堂を拝す。
夏山に足駄を拝む首途(かどで)かな

・みちのくの夏の山々をめざして旅に出るが、その峰々を踏破した大先輩の役の行者にあやかりたいと願って、行者の高足駄を拝んだのです・・・・。
<雲巌寺>
当国雲巌寺のおくに仏頂和尚山居の跡あり。
たてよこの五尺にたらぬ草の庵
むすぶもくやし雨なかりせば
と、松の炭して岩にかきつけはべりと、いつぞや聞こえたまふ。その跡見んと、雲巌寺に杖をひけば、人々に進んでともにいざなひ、若き人多く道のほどうち騒ぎて、おぼえずかの麓に到る。山は奥あるけしきにて、谷道遙かに、松・杉黒く、苔しただりて、卯月の天今なお寒し。十景尽くる所、橋を渡つて山門に入る。
さて、かの跡はいづくのほどにやと、後の山によぢ登れば、石上の小庵、岩窟にむすびかけたり。妙禅師の死関、法雲法師の石室を見るがごとし。
木啄(きつつき)も庵(いほ)は破らず夏木立
と、取ありへぬ一句を柱に残しはべりし。
・芭蕉の師、仏頂和尚の徳の高さを讃える句意が明らかである。庵は破らず夏木立です。
<殺生石>
是より殺生石に行く。館代より馬にて送らる。此口付のおのこ、「短冊得させよ」と乞ふ。やさしき事を望み侍るものかなと、
野を橫に馬引むけよほととぎす

殺生石は温泉の出る山陰にあり。石の毒気いまだほろびず、蜂・蝶のたぐひ、真砂の色の見えぬほどかさなり死す。
・野道の横を、ほととぎすが鳴いて通り過ぎた。さあ、馬の首を横のほうへ向けて停めておくれ。ほととぎすの声を楽しもうじゃないか。
・次回に続く・・・・。