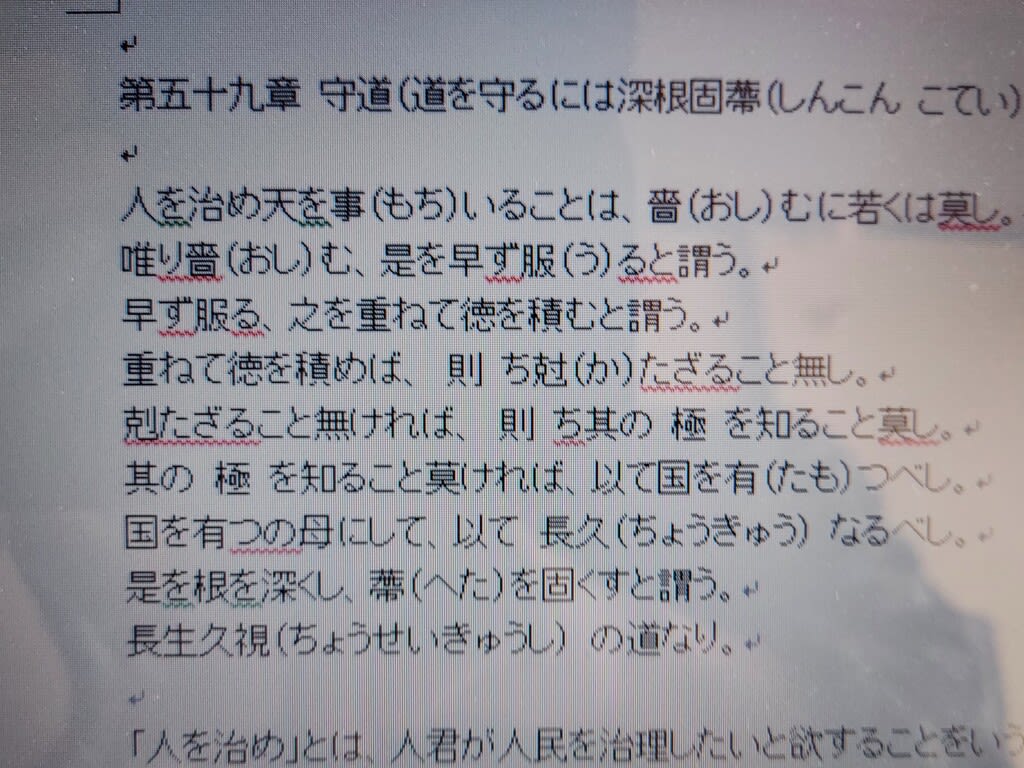第六十一章 謙徳(謙下の徳)
大国は下流のごとし。天下の交なり、天下の牝(ひん)なり。
牝は常に静を以て牡(ぼ)に勝ち、静を以て下ることを為す。
故に、大国は小国に下るを以て則ち小国を取る。
小国は大国に下るを以て則ち大国を取る。
故に、或いは下りて以て取り、或いは下りて而(しか)して取る。
大国の 過 (あやま)たざるは、人を兼ね 蓄 (やしな)わんことを欲すべし。
小国 の 過 たざるは、入りて人に事えんことを欲すべし。
各おの其の欲する 所 を得んとならば、大なる者は宜しく下
ることを為すべし。
大国は、水に於いてたとえるならば、江海のようなものである。江海は最も低い所にあるから、上流にある幾百の川谷の水は、皆此所へ流れて来るのである。
これと同様に、もし大国が腰を低く、謙譲の態度でいるならば、周囲の小国
は安心して集まって来ることができるのである。
また小国は、こちらから頭を低くしてゆくならば、大国に受けいれないということはないのである。それは、大国の本望とするところであるからである。故に、大国として頭を低くするならば、労せずして小国の民心を得ることができ、小国として頭を低くしてゆくならば、大国に受けいれられ、国の安全を保障されることになるのである。
自然界において、育て養うということは、誰から頼まれたということなく、報酬を期待することもなく、しかも高ぶらず、また、倦むということを知らないで、一生懸命になってやっていることが多いのである。
これは、遺伝的のことであって、遺伝的のことは、最も確かに効果が現れることであり、最も強いことであり、最も自然のことであり、正しいことである。