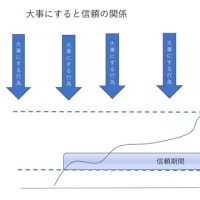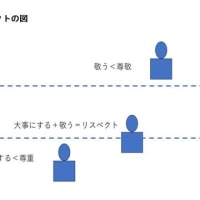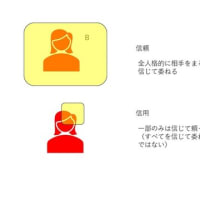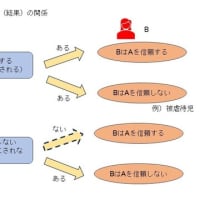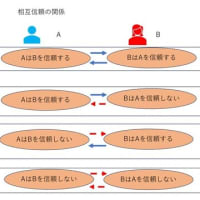スウェーデン社会研究所主催による、スウェーデン研究講座 「スウェーデン社会のリーダーシップとは」の講演を聴いてきました。
講師は、牧原ゆりえさん(一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ代表理事)です。
牧原ゆりえさんは日本におけるArt of Hostingという対話の場をつくっていらっしゃり、私もArt of Hostingに出席したことなどから縁があり、今回の会を知ることとなりました。
以下は、牧原ゆりえさんの講演内容から、当ブログで皆さんにお伝えしたいエッセンスをピックアップします。
=======講演まとめ ここから ======>>
〇ゆりえさんの願い
・体験やこれがいいと信じたことに忠実に生きていきたい。
・イノベーションは、ひとりひとりのプチイノベーションからはじまる。
それを寄せ集めれば大きなイノベーションにつながる。
・自分の価値観+次の世代の価値観をミックスする。
「持続可能な社会であなたはどんな自分でいたいですか」を探求してやってみたい。
・自分にとって、最も学習効果が高い過ごし方、快適に感じるスタイルで試す。
〇ゆりえさんの体験
・スウェーデンの首都ストックホルムから遠く南に離れた街
Karlskrona(カルスクローナ)で過ごす。
スウェーデンの庭と呼ばれるところ。
人口密度61人/平方キロ
300年以上経った今でも維持されている倉庫がある。ある種の持続可能が実現できている街。倉庫は世界遺産。ユネスコの生物圏保護区に指定されている群島
人間と自然の距離がとても近く、自然の世界に人間が入れてもらっている感じ。
都会っぽさがなく、なんでも自分でやらなければならないが、のんびりした過ごし方ができる。
・ゆりえさんのリーダーシップとの出会い
2006 MSLS※1に出会う
2009 MSLSスタート
2010 Art of Hosting(AoH)※2に出会う
2014 AoHを日本(福島)で行う
※1ブレーキンゲ工科大学修士課程'MSLS:サステナビリティのための戦略的リーダーシップを学ぶ10か月の修士課程 <MSLSの紹介動画>
※2 Art of Hosting:Art of Hostingは複雑性に対応するためのリーダシップのアプローチのひとつ。個人からシステムレベルにスケールアップすることと主に「対話」「ファシリテーション」「共創」といったイノベーションを用いていくことに特徴がある。
ゆりえさんは2009年からMSLSのコースを履修しました。
そこでの体験からリーダーシップとサスティナビリティをテーマに現在も活動されています。
〇スウェーデンで学んだリーダーシップについて
①私たちの社会の大前提
すでに私たちの社会(地球)は、持続可能ではなくなってしまっている。
よって、たくさんのイノベーションをやっていかなくてはならない。
そのためには、まず自分の価値観違う人と話すこと。
そして、もっとクリエイティブにいろいろなことをやっていこう。
また、自分たちの魅力に気づくいていこう。
②あるサーカス団の人の話
身近な例で言うと、サーカス団(シルクドソレイユのようなサーカス)のメンバーが言っていたこと。
「もう僕たちはこじんまり生きていくのはうんざり。夢を生きよう。
サーカスするために一生懸命やるとき、なんでも可能だと考える。
そのために、達成するためには何をしなくてはならないことは何かを考える。
そして、失敗ももちろんたくさんする。
狂ってると思われても、自分で価値あることをやれ
言ってるだけでなくてただちにやれ
いつか誰かがじゃなくて、一人一人が個人としてやる
そして、みんなで集まって何かをやるということ。」
③スウェーデン3.0
自分の現場に必要なことをやっていく。
ラーニング(学ぶこと)なんてくそ楽しい! よりよい教育をしていきたい。
今知りたいことをみんなが出しあって、学んでいく。
リーダーシップについて
「今足りないものは、食べ物、エネルギー、技術、知識、お金でもない。
地球規模でみたら、足りないものは何もないのだ。実はある。
足りないのは、分断や制度や国の境界を越えて繋いでいくリーダーなのだ」
④MSLSでの先生からの問い
みんながリーダーと思う人は?
どんなリーダーだったらそれができるの?
みんなはここで「何か意味あること」を一緒に作り出すために来たんだ。
さあ始めよう。未来のために何かに貢献していこう。
⑤MSLS学習
「ナチュラルステップフレームワーク※3」
「学習する組織」「リーダーシップ」
教科書のお勉強だけでなく、プレゼンやディスカッション、地域の人とコラボレーションしていくこと(2か月)。することも自分たちで見つける。
お互いにアイデアを交換するだけではなく実際に何かをやることは次元は違う。
自分でプロジェクトを実際にやってみる。やってみないとわからない。
することを大事にする。
※MSLSに似た学習に、「チームアカデミー(フィンランド)」「カオスパイロット(デンマーク)」というプロジェクト型学習プログラムがある。
カオスパイロットについては、大本綾さんがレポートをあげています。
※3ナチュラルステップについてはこちら
⑥参加型リーダーシップ
みんなが感じることを集めていくこと。それを信じて集めていくこと。
その日その日、私にできることはあきらめない。ということを決めて実行するだけ。
何が起きたとしてもやめないと決める。それだけ。
このことについて、
★ストックディールの逆説
極限状態では、期待を持った人ほど死んでいった。
極限のつらい状況にあっても、後に「この経験があったからいい人生だったと絶対に言って見せる」という強い意志があると生き残れる。
~ゆりえさんの体験~
何があっても僕には関係ない(周りを気にしない)といってニコニコしよう。
共感で道が開けることがある。
なるほどねーというスタンスで話を聞くとたいていのことは理解できた。
「なにを~」と思ったときは何か理解できるように探した。
いたい人だけがいる場の尊重(いやなら出て行っても構わない。それも尊重しよう)
⑦スウェーデンで学んだ4つのこと
1.我慢をしない
自分の気持ちと考えと言葉をシンプルにつなげ、それを認める
【日本は勝手に想像して、自分で自己規制ラインを決めている】
トイレと水飲みの許可を求めるのは日本人だけ
自分は何がしたいのかをシンプルに伝える大切さ。
オープンに伝えるとうまくいく。
お茶をよくする(”Fika”する)
ちょっとお茶する関係性や習慣があちこちにある。
自分たち同士のことを語ることでコミュニケーションも円滑になる
2.自分で決める
学校の三者面談でも子ども中心。
子どもが何をしたいかを先生がじっと聞く
自分で解決をさせる習慣。それができたとつなげていく。
自分の意思の介在を確認すると、自分に対する言い訳が減った。
バンジージャンプのようなところを想像して・・・
「自分で決めたなら飛べ(スウェーデン)」
ちなみに
「下にお金が落ちているから飛べ(中国)」
「下でかわいい女が待っている(イタリア)」
「みんな飛んでいるから飛べ(日本)」 だそう・・・
誰かに限界を定められない辛さはある。
状況のせいにはできない。
3.いつだって勉強はできる
勉強をしてもいいということを自分に許した。
(まわりからは、お母さんなのにと言われたが)
学ぶことは一つの権利というより身の回りにあるもの
勉強することが社会の財産をつくっている
できることが増えることは、人を元気にしてくれる
4.ゆっくりよく聴く
たくさん聴くと、見えるものがある
たくさん聴くと、より大きなものに繋がれる
聴いてもらえると気持ちがいい
よく聴けば互いにわかりあえる
スウェーデンでは、以下の相槌をよくうって話を聴く習慣があるのだそうです。
Ja,Ja,Ja(やあ)=うん、うん、うん
Jaha!(やっはー)=なるほどね!
Just det(ゆーすて)=なるほど。そういわれたらそうだよね。
Precis(ぷれしーす)=そのとおりだよね!
Exakt(いくさくと)=そのとおりだよね!
Javisst(やびすと)=もちろんだよ。
相手への関心、肯定的態度、受容が習慣になっていると話していても気持ちよかったということです。
〇ナチュラルステップ活動におけるリーダーシップ
・カール・ヘンリク・ロベール医学博士の言葉
「意見の相違や対立で身動きが取れなくなっている状態を打破するために、私はこう問いかけました『では一体、私たちは何についてなら合意できるのだろう」と。
・将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと
・4つの根本原因(システム条件)を考慮する。
・基本的な人間のニーズとは9つ。
生計、安全、参加、休養、創造性、愛情、理解、アイデンティティ、自由
・上記のニーズから満足があり、そのための製品やサービスが生じる。
・必要なことが満たされ、かつ、作って無駄にならないものをつくる姿勢
〇これからのゆりえさんが目指すこと
ナチュラルステップを再始動する。
自分のことを書いていく
他の人と話してみること
サスティナビリティについて、やれることをやっていく
(具体的な細かなアクションがスライドで提示されました)
<<====== 講演まとめ ここまで
講演を聴いて、スウェーデンで体験したゆりえさんのリーダーシップ、サスティナブルな社会についてイメージが膨らみました。
もう持続可能じゃなくなっていることをきちんと認めるところから。
そして、現実をみすえ、どういう未来を創っていくのか?
そのためにはいろいろな人と率直にたくさん話し合っていくこと。
相手を認めて 行動すること。
ちっちゃな1歩でいいからスタートすること。
このブログでの発信も小さな1歩になったらなぁと思います。
ありがとうございました。
講師は、牧原ゆりえさん(一般社団法人サステナビリティ・ダイアログ代表理事)です。
牧原ゆりえさんは日本におけるArt of Hostingという対話の場をつくっていらっしゃり、私もArt of Hostingに出席したことなどから縁があり、今回の会を知ることとなりました。
以下は、牧原ゆりえさんの講演内容から、当ブログで皆さんにお伝えしたいエッセンスをピックアップします。
=======講演まとめ ここから ======>>
〇ゆりえさんの願い
・体験やこれがいいと信じたことに忠実に生きていきたい。
・イノベーションは、ひとりひとりのプチイノベーションからはじまる。
それを寄せ集めれば大きなイノベーションにつながる。
・自分の価値観+次の世代の価値観をミックスする。
「持続可能な社会であなたはどんな自分でいたいですか」を探求してやってみたい。
・自分にとって、最も学習効果が高い過ごし方、快適に感じるスタイルで試す。
〇ゆりえさんの体験
・スウェーデンの首都ストックホルムから遠く南に離れた街
Karlskrona(カルスクローナ)で過ごす。
スウェーデンの庭と呼ばれるところ。
人口密度61人/平方キロ
300年以上経った今でも維持されている倉庫がある。ある種の持続可能が実現できている街。倉庫は世界遺産。ユネスコの生物圏保護区に指定されている群島
人間と自然の距離がとても近く、自然の世界に人間が入れてもらっている感じ。
都会っぽさがなく、なんでも自分でやらなければならないが、のんびりした過ごし方ができる。
・ゆりえさんのリーダーシップとの出会い
2006 MSLS※1に出会う
2009 MSLSスタート
2010 Art of Hosting(AoH)※2に出会う
2014 AoHを日本(福島)で行う
※1ブレーキンゲ工科大学修士課程'MSLS:サステナビリティのための戦略的リーダーシップを学ぶ10か月の修士課程 <MSLSの紹介動画>
※2 Art of Hosting:Art of Hostingは複雑性に対応するためのリーダシップのアプローチのひとつ。個人からシステムレベルにスケールアップすることと主に「対話」「ファシリテーション」「共創」といったイノベーションを用いていくことに特徴がある。
ゆりえさんは2009年からMSLSのコースを履修しました。
そこでの体験からリーダーシップとサスティナビリティをテーマに現在も活動されています。
〇スウェーデンで学んだリーダーシップについて
①私たちの社会の大前提
すでに私たちの社会(地球)は、持続可能ではなくなってしまっている。
よって、たくさんのイノベーションをやっていかなくてはならない。
そのためには、まず自分の価値観違う人と話すこと。
そして、もっとクリエイティブにいろいろなことをやっていこう。
また、自分たちの魅力に気づくいていこう。
②あるサーカス団の人の話
身近な例で言うと、サーカス団(シルクドソレイユのようなサーカス)のメンバーが言っていたこと。
「もう僕たちはこじんまり生きていくのはうんざり。夢を生きよう。
サーカスするために一生懸命やるとき、なんでも可能だと考える。
そのために、達成するためには何をしなくてはならないことは何かを考える。
そして、失敗ももちろんたくさんする。
狂ってると思われても、自分で価値あることをやれ
言ってるだけでなくてただちにやれ
いつか誰かがじゃなくて、一人一人が個人としてやる
そして、みんなで集まって何かをやるということ。」
③スウェーデン3.0
自分の現場に必要なことをやっていく。
ラーニング(学ぶこと)なんてくそ楽しい! よりよい教育をしていきたい。
今知りたいことをみんなが出しあって、学んでいく。
リーダーシップについて
「今足りないものは、食べ物、エネルギー、技術、知識、お金でもない。
地球規模でみたら、足りないものは何もないのだ。実はある。
足りないのは、分断や制度や国の境界を越えて繋いでいくリーダーなのだ」
④MSLSでの先生からの問い
みんながリーダーと思う人は?
どんなリーダーだったらそれができるの?
みんなはここで「何か意味あること」を一緒に作り出すために来たんだ。
さあ始めよう。未来のために何かに貢献していこう。
⑤MSLS学習
「ナチュラルステップフレームワーク※3」
「学習する組織」「リーダーシップ」
教科書のお勉強だけでなく、プレゼンやディスカッション、地域の人とコラボレーションしていくこと(2か月)。することも自分たちで見つける。
お互いにアイデアを交換するだけではなく実際に何かをやることは次元は違う。
自分でプロジェクトを実際にやってみる。やってみないとわからない。
することを大事にする。
※MSLSに似た学習に、「チームアカデミー(フィンランド)」「カオスパイロット(デンマーク)」というプロジェクト型学習プログラムがある。
カオスパイロットについては、大本綾さんがレポートをあげています。
※3ナチュラルステップについてはこちら
⑥参加型リーダーシップ
みんなが感じることを集めていくこと。それを信じて集めていくこと。
その日その日、私にできることはあきらめない。ということを決めて実行するだけ。
何が起きたとしてもやめないと決める。それだけ。
このことについて、
★ストックディールの逆説
極限状態では、期待を持った人ほど死んでいった。
極限のつらい状況にあっても、後に「この経験があったからいい人生だったと絶対に言って見せる」という強い意志があると生き残れる。
~ゆりえさんの体験~
何があっても僕には関係ない(周りを気にしない)といってニコニコしよう。
共感で道が開けることがある。
なるほどねーというスタンスで話を聞くとたいていのことは理解できた。
「なにを~」と思ったときは何か理解できるように探した。
いたい人だけがいる場の尊重(いやなら出て行っても構わない。それも尊重しよう)
⑦スウェーデンで学んだ4つのこと
1.我慢をしない
自分の気持ちと考えと言葉をシンプルにつなげ、それを認める
【日本は勝手に想像して、自分で自己規制ラインを決めている】
トイレと水飲みの許可を求めるのは日本人だけ
自分は何がしたいのかをシンプルに伝える大切さ。
オープンに伝えるとうまくいく。
お茶をよくする(”Fika”する)
ちょっとお茶する関係性や習慣があちこちにある。
自分たち同士のことを語ることでコミュニケーションも円滑になる
2.自分で決める
学校の三者面談でも子ども中心。
子どもが何をしたいかを先生がじっと聞く
自分で解決をさせる習慣。それができたとつなげていく。
自分の意思の介在を確認すると、自分に対する言い訳が減った。
バンジージャンプのようなところを想像して・・・
「自分で決めたなら飛べ(スウェーデン)」
ちなみに
「下にお金が落ちているから飛べ(中国)」
「下でかわいい女が待っている(イタリア)」
「みんな飛んでいるから飛べ(日本)」 だそう・・・
誰かに限界を定められない辛さはある。
状況のせいにはできない。
3.いつだって勉強はできる
勉強をしてもいいということを自分に許した。
(まわりからは、お母さんなのにと言われたが)
学ぶことは一つの権利というより身の回りにあるもの
勉強することが社会の財産をつくっている
できることが増えることは、人を元気にしてくれる
4.ゆっくりよく聴く
たくさん聴くと、見えるものがある
たくさん聴くと、より大きなものに繋がれる
聴いてもらえると気持ちがいい
よく聴けば互いにわかりあえる
スウェーデンでは、以下の相槌をよくうって話を聴く習慣があるのだそうです。
Ja,Ja,Ja(やあ)=うん、うん、うん
Jaha!(やっはー)=なるほどね!
Just det(ゆーすて)=なるほど。そういわれたらそうだよね。
Precis(ぷれしーす)=そのとおりだよね!
Exakt(いくさくと)=そのとおりだよね!
Javisst(やびすと)=もちろんだよ。
相手への関心、肯定的態度、受容が習慣になっていると話していても気持ちよかったということです。
〇ナチュラルステップ活動におけるリーダーシップ
・カール・ヘンリク・ロベール医学博士の言葉
「意見の相違や対立で身動きが取れなくなっている状態を打破するために、私はこう問いかけました『では一体、私たちは何についてなら合意できるのだろう」と。
・将来世代のニーズを損なうことなく現在の世代のニーズを満たすこと
・4つの根本原因(システム条件)を考慮する。
・基本的な人間のニーズとは9つ。
生計、安全、参加、休養、創造性、愛情、理解、アイデンティティ、自由
・上記のニーズから満足があり、そのための製品やサービスが生じる。
・必要なことが満たされ、かつ、作って無駄にならないものをつくる姿勢
〇これからのゆりえさんが目指すこと
ナチュラルステップを再始動する。
自分のことを書いていく
他の人と話してみること
サスティナビリティについて、やれることをやっていく
(具体的な細かなアクションがスライドで提示されました)
<<====== 講演まとめ ここまで
講演を聴いて、スウェーデンで体験したゆりえさんのリーダーシップ、サスティナブルな社会についてイメージが膨らみました。
もう持続可能じゃなくなっていることをきちんと認めるところから。
そして、現実をみすえ、どういう未来を創っていくのか?
そのためにはいろいろな人と率直にたくさん話し合っていくこと。
相手を認めて 行動すること。
ちっちゃな1歩でいいからスタートすること。
このブログでの発信も小さな1歩になったらなぁと思います。
ありがとうございました。