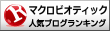・顕微鏡Microscope けんびきょう
顕微鏡も多種多様化していますが大きく分けると、細胞や細菌などを観察する生物顕微鏡(透過型顕微鏡)と、金属や半導体などを観察する金属顕微鏡があります。一般的な顕微鏡(光学顕微鏡)、エックス線顕微鏡、そして電子顕微鏡、クライオ電子顕微鏡(低温電子顕微鏡Cryo-electron microscopy:cryo-EM)の分類法もあります。毎年12月10日はノーベル賞の授賞式でダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベル(1833年~1896年)の命日で遺言によって創設しています。その一部門で2017年にジャック・デュボシェさん(Jacques Dubochet)、ヨアヒム・フランクさん(Joachim Frank)、リチャード・ヘンダーソンさん(Richard Henderson)が受賞した溶液中で生体分子を高分解能構造測定するための低温(クライオ)電子顕微鏡の開発(ノーベル化学賞)についてです。
顕微鏡は、人間の肉眼では見ることができない非常に小さな物体を拡大し観察できる装置で食品・医薬品などの研究開発、臨床検査など様々なところで使用し、社会に貢献しています。
種類は可視光線を対象物に当てて拡大する光学顕微鏡や電子線を対象物に当てて拡大する電子顕微鏡などがあります。
電子顕微鏡の内部は真空で、対象物に電子線を当て、通り抜けた電子や反射してくる電子などを検出し画像にしています。光学顕微鏡が約2000倍まで拡大することができるのに対し、電子顕微鏡は約100万倍まで拡大できます。そのため、電子顕微鏡は、光学顕微鏡では観察できないウイルス、DNA、原子などを観察することができるようになり、今日の最先端研究開発において欠かせない存在となっています。
低温(クライオ)電子顕微鏡開発の背景として通常の電子顕微鏡での観察では、放射線損傷、高真空状態が生物試料に与える影響は大きかったようです。通常の生物標本を電子顕微鏡にかける際の脱水による構造崩壊は水が残っていると真空引き時に水が抜ける為、他の溶液に置き換える作業などは無視できないものでした。水を凍らせる考え方は、以前からありましたが水が氷になる時の結晶の変化により試料を破壊する可能性があり、このことから結晶構造にならないアモルファス氷Amorphous iceの状態にする技術が求められていました。
1980年代初頭に、固体物理学を研究しているいくつかのグループが、高圧凍結または瞬間凍結などの異なる手段によって、アモルファス氷の生成を試みています。欧州分子生物学研究所のジャック・ドゥボシェJakku doubosheが率いるグループは、1984年の論文で、アモルファス化した水の層に包埋されたアデノウイルスの画像を掲載しています。 この論文が、低温電子顕微鏡法の起源であるとして世界中の多くの研究所で日常的に使用できるようなりました。
クライオ電子顕微鏡とは、透過型電子顕微鏡法の一種で、クライオ(cryo-=冷凍の)という名前が示すとおり、急速凍結させたサンプルを、極めて低い多くの場合液体窒素の温度環境下で電子顕微鏡測定を行うものです。注目を受けるに至った背景として、生命現象の理解や先端研究への応用が期待できる原子レベルでの生体分子構造解析、細胞生物学の需要の高まりがあります。タンパク質などに代表される生体分子の3次元構造を明らかにすることができるようになりました。
これまで原子レベルでの生体分子の構造を解析する分析手法はX線結晶構造解析(XRD)と核磁気共鳴(NMR)でした。X線結晶構造解析は、高分解能(分解能:微小な2点を見分けることのできる最小の距離)の解析像を得ることが出来るのですが、技術の成熟度が高くなります。結晶さえ取れてしまえば比較的簡単なのですが一方で放射線損傷を受けることもあり、「化合物を結晶化させなければならない」「均質なサンプルが必要」という問題点がありました。核磁気共鳴は、溶液状態での構造が分かり、分子の動的挙動・相互作用を追跡できるのですが一方で「分解能が低い」「直接的に3次元構造が得られない」「巨大な分子・複合体が解析できない」という問題点があります。
クライオ電子顕微鏡ではサンプル・試料を染色せずに極低温・凍結することで固定して観察することで、これまで用いられてきたX線結晶構造解析と核磁気共鳴の欠点ともいえる問題を解決しています。
◇より生体環境に近い状態で測定できる
◇巨大なタンパク質や複合体が解析できる
◇構造の議論に十分な分解能がある
◇サンプルの結晶化が不要、そのための均質なサンプル調製も不要
◇必要なサンプル量が少なくて良い
ただし、「コストが高い」「データ量が膨大」といった問題点もあることから、今後は更なる技術革新が求められているようです。
クライオ電子顕微鏡の開発は、ミクロの未知の世界まで精度の高い解析像として覗(のぞ)くことを可能にしました。これから、構造生物学の分野に限らず、様々な分野で新たな発見や研究開発が進むことでしょう。
こうした観察の中から従来の光学顕微鏡を用いて観察することは困難であったDNA鑑定は2008年よりクライオ電子顕微鏡やX線散乱の実験によって明らかにしてきました。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。