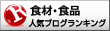◎椎茸Shiitake しいたけ
キノコは、すべて秋が旬のように思いますが、しいたけの旬は3~5月の春と、9~11月の秋とあります。秋の食材のイメージが強いですが、春のしいたけも大変に美味です。
シイタケは、朝鮮半島、中国、東南アジアからニュージーランドに至る環太平洋の温帯、亜熱帯に分布しています。原産地はアジアの熱帯高地と推定しています。日本で最初に栽培を行なうようになった食用きのこで、旨味成分(グアニル酸)が多いことから古来より広く好まれ、普及しました。学名はLentinula edodesで「江戸」の名に因んで命名と言いいますが、ギリシャ語のedodimos (食用になる)との説もあります。
キシメジ科(ヒラタケ科・マツタケ科・シメジタケ科)、日本特産で自生するものは、春と秋に広葉樹の、くり、くぬぎ、しいの木の枯れ木に生えますが、主に椎に生えるきのこから名前の由来としています。
文献で最も古いのは、1223年に道元禅師(どうげんぜんじ)が宋(中国)に留学した際、日本船が着くと寺の老僧が乾シイタケ(倭椹:わじん)を買いに来たという話で、「典座教訓(てんぞきょうくん)」に載っています(シイタケではなく、桑の実であるという説もある)。あまり記録に残っていないようです。椎茸という文字が最初に記された文書は、足利幕府の政所執事代、蛭川新右衛門地親元日記(1465年)で、伊豆の円城寺から足利義政将軍に乾しいたけを献上した記述です。
シイタケの栽培がどこで始まったのかは諸説があり、江戸時代中頃に一つは豊後国の炭焼き源兵衛が寛永(かんえい:1624-1645)の頃始めたという説です。もう一つは豊後(ぶんご)岡藩(大分県竹田市)の藩主中川家の記録で寛文(1661-1673)4年シイタケの栽培技術を導入するために伊豆国三島の駒右衛門を招いたとあります。
担子菌類、ハラタケ目に属し市販のものはほとんど人工栽培によるものです。
栽培の歴史は古く400年も以前に、大分県、静岡県(天城山)ですでに、原木栽培でクヌギ、シイに鉈目(なため)をいれ、胞子の飛来を待つ方法により行われていたようです。菌糸が定着して3年目に収穫、早くても一年がかりで旬のしいたけならではの香りや旨味、歯ごたえを存分に味わうことができます。
西日本では、大分県と宮崎県の生産量が多く、特産品としても有名です。原木栽培(自然栽培)の椎茸を乾燥させて作る乾しいたけの栽培が盛んですが、原木栽培は重労働なため、生産者が減少、天候に左右されやすく、安定的な生産が難しいという点もあり、旬の旨味が詰まった原木栽培による乾しいたけは、年々貴重なものとなっています。
収穫の時期と成育の環境によって秋に収穫する椎茸は「秋子」と呼び、張りのある身に抜群の香りがあるのが特徴で、大きいまま利用する焼き椎茸、天ぷらに、鍋物にも欠かせない食材です。冬を越えた春のしいたけは「春子」といい、厳しい寒さのなかで旨味をたっぷり蓄えて、肉厚で美味しくなります。
香りの高い「秋子」、味のよい「春子」、旬をむかえた滋味(じみ:味わい)たっぷりのしいたけは、どちらも最高の味わいです。 呼び名として更に傘の開き方によって冬菇(どんこ・冬子:初春までの気温の低い時期に徐々に成長し笠に白く亀裂が入り肉厚で最高級品)、香信(こうしん:温度、湿度が高い春から秋にかけて急成長したもの)、香菇(こうこ:中間の時期に採取される)に分けられます。
原木栽培で、落雷が発生するとその周囲でシイタケが異常発生することが、生産者の間では経験的に知られていました。稲が妻で雷が夫というのが稲妻の成り立ちだといいます。稲の成長には窒素が必要で雷が起きることにより窒素と酸素が結びつき窒素酸化物となり稲の成長を促進させるというのです。この発生の理由は雷による高電圧によって原木の窒素が固定し、窒素化合物が生成され、菌糸の養分となります。仕込んだほだ木に人工的に交流の高電圧パルスを与えた栽培実験では、1.5〜2倍の収量が得られたとの報告があります。強い電流の衝撃を受け 「危機感」 を抱いたきのこの菌糸が、子孫を残す本能で活発に生育するからではないかと言われます。
3~5月の春と9~11月の秋に主に採取し旬としていますが組み合わせによって年中栽培収穫しています。
キノコの傷みが早いことから原木しいたけは、春秋2回の収穫期に取れたものの多くを乾燥させ出荷しています。生椎茸の出荷は平成30年で静岡がトップで鹿児島、群馬の順です。
近年9割、菌糸を純粋培養し作業効率をあげています。菌床栽培、人工栽培という栽培方法で、おがくずに米ぬかや栄養剤などを加えて固めたものに菌を植え付け湿度の高い真っ暗な室内で発生を促し育てられる栽培方法です。人工的に養分を与えることで、3〜6カ月のサイクルで次々に収穫できるので、1年中出荷でき全国各地で行われています。空調管理の行き届いた室内で栽培しているので、天候に左右されることなく、安定した生産が可能です。 原木栽培に比べ、風味や香りは劣りますが、短期間で収穫できるのは大きなメリットです。さらに菌床しいたけは1年中収穫できるので、交通事情も良くなり乾燥させない生の状態で、出荷することも可能になりました。「生しいたけ」が出まわるようになったのは、菌床しいたけが普及し始めてからのことのようです。旬を意識することなく食べることができるのは、菌床栽培が盛んに行われているおかげともいえるでしょう。
最近では原木栽培または菌床栽培されたものが市場流通品の殆どを占め、2006年10月1日からは、商品に必ず原木栽培品か菌床栽培品かを表示する事が義務付けられています。
生椎茸をしばらく使う予定が無いという場合には風通しを良くした天日干しです。手軽なのは多くのキノコ類では冷凍保存が可能です。傷みやすいので石附(いしずき)を取り除き利用しやすい食べやすい一口大ぐらいに切って袋に入れて冷凍庫へ入れます。きのこ類は、一度冷凍すると細胞膜が破れ、うまみ成分が水分と共に出やすいのです。そのまま食べるよりもおいしいと感じるといいますが、見た目は生鮮に限ります。冷凍してから加熱すると、細胞膜が壊れ、酵素の働きによってうまみが増すといわれます。冷凍して、生とは異なるうまみを引き出し冷凍した、しいたけでも、応用範囲が広く汁物の椀だねや炒めもの、焼き物、揚げ物、鍋物、煮物、ソテー、パスタ、チャーハンなどに幅広く使えます。生のしいたけと同様に使えます。
100g中生でエネルギー18kcal、水分91.0g、たんぱく質3.0g、脂質0.4g、炭水化物4.9g、灰分0.7g、カリウム280mg、ビタミンD:2μg、食物繊維3.5gを含みます。
100g中干しシイタケでエネルギー182kcal、水分9.7g、たんぱく質19.3g、脂質3.7g、炭水化物63.4g、灰分3.9g、ビタミンD:12.7μgを含みます。ビタミンD効果をもつエルゴステリンを多く含んでいます。
日光に干すと旨みが増し、紫外線によってエルゴステロールがビタミンD2に変化します。最近のは、天日干しでない乾燥方法が取られていることがあり干し椎茸でも30分~1時間日光にさらすとよいでしょう。
◇ビタミンD: Vitamin D びたみんでー
カルシウム・リンの利用率を高め、カルシウムの吸収には必須の栄養素であり骨・歯の形成 に関与します。ビタミンDは肝臓に集まり、腎臓に移り、少しずつ活性化して活性型ビタミンDに変化します。血液、尿検査によって栄養状態の指標をみることができます。
日光浴で体内で7-デヒドロコレステロール7-dehydro cholesterol(プロビタミンD3)をコレステロールより生成しています。熱・酸素に安定で主に肝臓に蓄えられます。脂溶性でプロビタミンD2(エルゴカルシフェロールErgocalciferol)は植物性食品に、D3(コレカルシフェロールCholecalciferolは1936年鮪の肝油より抽出)は動物性食品に多く含みます。
最近D2は抗がん作用、D3は筋肉を作り脂肪代謝に関与することが知られるようになりました。
欠乏症として、くる病、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)、骨軟化症、骨の形成不良があります。少しは体内で生成するとも言われます。血清25ヒドロキシビタミンD(25-OH-D)の基準値15~40ng/ml、血中ビタミンD値が正常範囲内(50~75 nmol/Lとしており、体内で利用し不用となったものは、尿、便中に排泄します。欠乏症にはD剤75μg~125μg(3,000~5,000IU)をCa剤(乳酸Ca1~3g/1日)とともに服用することもあります。過剰症は、血中のCa上昇により腎結石、関節痛、筋力低下、発熱・嘔吐・消化障害を起こします。
1日の目安量5μg、上限量50μg、栄養機能食品としての上限が5.0μg(200IU)、下限0.9μg(35IU)とし示しています。
多く含む食品として100g中で、卵黄6μg、卵・ピータン6μg、さんま19μg、生鮭22μg、ほんまぐろ5μg、さば11μg、真いわし10μg、ぶり8μg、しらすぼし46μg、うなぎの蒲焼き19μg、いくら44μg、干ししいたけ12.7μg(生椎茸2μg)、乾燥黒きくらげ70μg(白きくらげ970μg)などがあります。ビタミンDと自閉症の関係の指摘、2型糖尿病はビタミンD欠乏の人たちに多く起こるといわれています。
旨みの成分は、5´グアニル酸(ヌクレオタイドの一種)です。
◇グアニル酸Guanylic acidは主にきのこに含み椎茸に多い核酸系旨み成分とし知られます。ヌクレオチド(RNA,DNA:塩基、糖、リン酸の結合)構造を持つ有機化合物の一種でグアノシン一リン酸 (Guanosine monophosphate) とも呼ばれ、GMPと略します。GMPは核酸塩基のグアニン(Guanine)、五炭糖のリボース(Ribose)、1つのリン酸(Phosphoric acid)より構成しています。
水溶性で煮だし汁に流出するので調理用とし使われることが多く、生鮮な、きのこには少なくリボ核酸(RNA)の核酸分解酵素の作用によって生成します。イノシン酸(鰹節、煮干の旨み)より旨み成分が強く、グルタミン酸と共に使用し相乗効果を生み出します。複合調味料としてグアニル酸ナトリウムが用いられますが、多量に用いると、自然の味が消され、さらに味覚を麻痺させ味覚障害を起こす原因にもなります。
干し椎茸156.5mg%、生椎茸18.5~45.4mg%、松茸64.6mg%、えのきたけ21.8mg%、ばふんうに0~6.0mg%、牛肉・豚肉2.2~2.5mg%、鶏肉1.4mg%程度含みます。
◇芳香成分は、レンチオニンLentionineです。
干しシイタケ特有の香りの成分で有機硫黄化合物のひとつであり、レンチニン酸Lentinic acid に乾燥過程や水戻しの時に酵素が働いて生じます。
有機硫黄化合物は硫黄原子を含む有機化合物で、一般的に不快な臭気を持ち、糖鎖(炭水化物の鎖)や硫黄の化合物を含み生長するときの老廃物として、自然に生成しているものです。ニンニクの臭いはアリシン、アホエンに由来し、レンチオニンはシイタケの香りの成分です。
レンチオニンは低い温度で水戻し した方がより多く生成しますので、シイタケの香りをより楽しむためには、水出しで用いるのが良いでしょう。加熱時間の経過とともに酵素活性が失われます。融点60~61℃、油溶性、水に溶けにくく、イオウを含む化合物で即席吸い物の香り付けに1~5ppm程度利用しています。更に血小板凝集能を阻害する作用があります。
他の有効成分として
◇エリタデニンEritadenine えりたでにん
アミノ酸の一種で、コレステロールを低下させ高血圧予防、肝臓の機能を活性化させるとして特に椎茸(50~90mg/100g)に多く含まれることで知られます。椎茸の他にマッシュルーム、えのきだけ、なめこにも少量含有しています。水溶性の物質で椎茸の出し汁を飲用していて血圧の低下があることは以前からよく知られていました。
β-グルカン、レンチナンLentinan(多糖類)、エリタデニンEritadenine(アミノ酸)を含み抗がん、コレステロール低下作用を有し、肝機能強化に働きます。微粒子化したレンチナン(ベータ・D・グルカン)を1日1回15mg、連続2カ月間経口摂取した試験では、抗アレルギー効果が確認しています。
しかしながら過剰摂取でラットにシイタケから抽出したベータ・D・グルカン・レンチナン1~4mg/kgを10回、生後6週のマウスの腹腔内投与して、冠動脈に対する影響を調べたところ、拡張型心筋症と冠動脈硬化症の発生率の増加を認めています。
1日4gのシイタケパウダーを薬用目的で10日以上摂取すると抗酸球増加症、不快感、皮膚病、光過敏症を引き起こす危険性があるとしています。第44回日本癌治療学会総会で千船病院(大阪市)の藤本二郎氏の報告ですが、ラットにシイタケから抽出したベータ・D・グルカンを腹腔内投与して、冠動脈に対する影響を調べたところ、拡張型心筋症と冠動脈硬化症の発生率の増加が認めていますが投与量は不明です。
レンチナンはきのこの傘が開き始めるころに含量が多く、採取した後は比較的すみやかに減少します。20℃で1週間もすると1/3に、5℃貯蔵でも7日後には採取時から約20%減少が見られ少なくなるので、なるべく新鮮なうちに調理して食べると良いでしょう。また、生シイタケを乾燥してもレンチナン含量は変わらないといいます。
キシメジ科Tricholomataceae きしめじか
菌界Fungi、担子菌門Basidiomycota、真正担子菌綱 Homobasidiomycetes、ハラタケ目Agaricales、キシメジ科のキノコの分類としている。2006年にキシメジ科からシメジ科Lyophyllaceae、ヒラタケ科Pleurotaceae、ホウライタケ科Marasmiaceae、クヌギタケ科Mycenaceae、ツキヨタケ科Omphalotaceae、タマバリタケ科Physalacriaceae、ヒドナンギウム科Hydnangiaceaeなどを分離することを公表しています。
属として78属1020種が存在を確認しキシメジ属Tricholoma(マツタケ・マツタケ属とも)、シイタケ属(シイタケ)、エノキタケ属(エノキタケ)、カヤタケ属Clitocybe、ムラサキシメジ属Lepista、ザラミノシメジ属Melanoleuca、ヒダサカズキタケ属Omphalina、スギヒラタケ属(スギヒラタケ)などが知られます。
キシメジは以前は食用のキノコとして、流水で苦味を取るなどして食べられていましたが、現在では毒キノコとして扱われ似たキノコで死亡例がでているとの事で食用にすべきではないとしています。
キシメジ科のきのこは木材腐朽菌で子実体の形態はきわめて変化に富みます。通常ひだをもちますが、時にキノコの傘の裏側に形成するチューブ状器官の管孔(かんこう・くだあな)を有するものがあります。胞子の紋は多くは白色、少数は淡色を帯び、その形態はきわめて変化に富みさまざまです。多くの属を含んでマツタケ(キシメジ属・マツタケ属 )、しいたけ、ブナシメジ、榎茸等、日本人になじみのあるキノコも含まれ形も様々で、特に共通の特徴は見られません。
古くより、日本人の食生活に馴染んできた椎茸です。お節料理には陣笠椎茸として椎茸は昔は松茸より高級品としておりその笠を戦場で下級武士が兜の代わりにした陣笠に見立てたものです。神様へのお供えとして珍重し貴重な椎茸は、元気、壮健への願いを込めています。
今の季節は、筍、こんにゃく、蕗(ふき)、ニンジン、シイタケとの煮物がいいですね。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。