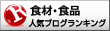・旨み成分
味は、呈味(ていみ)成分として主に甘味、酸味、苦味、鹹味(かんみ:塩味)の4つの味を基本としています。これを4原味(げんみ)、真味(しんみreal taste)と呼ばれています。これに日本、中国では辛味が、または旨みが入り5味ともしています。これに嗅覚、触覚、温覚が加わって渋味、えぐ味、金属味、アルカリ味、触味を補助的味としているのです。
しいたけ、鰹節、昆布など4原味に属さない独特の旨みがあり、この旨みを加えて5味ともしています。
旨みを大きく分けると
アミノ酸類のグルタミン酸(閾値0.03%)、アスパラギン酸(閾値.16%)、タウリン、グリシン、アラニン、テアニン(閾値[いきち]0.15%)、トリコロミン酸((閾値0.005%:ハエトリシメジ)、イボテン酸((閾値0.005%:テングダケの毒成分)、
ペプチドのカルノシン、コリン塩基のベタイン(まだこ、はまぐりなど)、カルニチン、
核酸系でイノシン酸(閾値0.025%)、グアニル酸((閾値0.0125%:干しシイタケ)、アデニル酸(アワビ、かに、えび)、キサンチル酸、
有機酸類のコハク酸((閾値0.0255%:アサリ、清酒)などがあります。
他に糖質、脂質、タンパク質、炭水化物、無機塩類などが関係しています。
料理では、動物性食品(イノシン酸が多い)と植物性食品(グルタミン酸、グアニル酸が多い)を合わせて調理することが多く旨みを引き立たせ相乗効果が得られているのです。
出し汁に使われる
花鰹にイノシン酸632mg%、グアニル酸 0、グルタミン酸26mg%、
干し椎茸(煮出し汁)イノシン酸 0、グアニル酸157mg%、グルタミン酸830mg%、
昆布ではイノシン酸 0、グアニル酸 0、グルタミン酸420mg%程度となっています。
一般に工業化、商品化されているものは、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸があります。
コハク酸は味が特異的であることから家庭用として使われることは殆どなく工業用として主に醸造(醤油、清酒など)で使用されています。アミノ酸系と核酸系の旨み成分を混合することでより旨みが増強され相乗効果が得られています。
複合調味料として
いの一番(武田薬品):グルタミン酸ナトリウム92%+5´-ヌクレオチドナトリウム(イノシン酸ナトリウム+グアニル酸ナトリウム)8%
ハイミー(味の素):グルタミン酸ナトリウム92%+5´-ヌクレオチドナトリウム(イノシン酸ナトリウム+グアニル酸ナトリウム)8%
フレーブ(ヤマサ醤油):グルタミン酸ナトリウム95%+5´-ヌクレオチドナトリウム(イノシン酸ナトリウム2.5%+グアニル酸ナトリウム2.5%)5%
ミタス(旭化成):グルタミン酸ナトリウム88%+5´-ヌクレオチドナトリウム(イノシン酸ナトリウム+グアニル酸ナトリウム)8%+クエン酸ナトリウム4%
等があります。
グルタミン酸ナトリウムMonosodium glutamate:MSG(グルタミン酸ソーダ)
1908年(明治41年)に特許を得たもので湯豆腐に使われていた昆布の旨み成分とし当時の東京帝国大学、池田教授によって取り出されたのが始まり。グルタミン酸は、殆ど全ての動植物に含まれ、酸味を緩和、甘みの複雑なコクをだす、苦味を減少させる、イノシン酸、グアニル酸等のヌクレオチドと一緒にすることでより旨みが増強され相乗効果を生み出す。アミノ酸系化学調味料で最近は、旨み調味料といわれ、吸湿性のある無色の結晶をしている。天然は、L-体でありグルタミン酸ナトリウム(味の素で代表される)の製法は、現在では、糖質、でん粉、酢酸を主成分とした発酵法が主流。小麦、脱脂大豆を原料とし抽出法(加水分解法)、L-グルタミン酸を合成、中和し製造する方法などがある。ほかの味付けの補助として用いるのがよく主にグルタミン酸ナトリウムは、食卓用として使われる。
許容量を体重50kgの成人で6g/1日と定め日本人の平均摂取量は、2g/1日で、特に問題となるナトリウムを12%程度含み、多量に用いると、高血圧を招くことにもなり、また自然の味を消してしまうことにり味覚を麻痺させ味覚障害を起こす原因ともされる。グルタミン酸で昆布素干し 1700mg% 干しのり4200mg% 精白米1300mg% いわし 2700mg% なまうに1500mg% 和牛サーロイン脂身なし2900mg% 豚肉ロース脂身なし3200mg トマト 260mg% りんご20mg% えのきだけ 320mg%程度含む。
グアニル酸Guanosin-5´-mono-phosphate:GMP(グアニル酸ナトリウム)
グアニル酸として、すい臓の核酸より1894年にHammersten、1898年にBangによって見出され、化学構造は、1930年代に決められている。1960年に日本人の国中らによって5´-グアニル酸ナトリウムが旨みを持つことが解り実用化された。
主にきのこに多く椎茸の核酸系旨み成分とし知られ、熱に対する安定性が強く水溶性で煮だし汁に流出するので調理用とし使われることが多い。グルタミン酸ナトリウムとの相乗効果は、イノシン酸より3倍の呈味と強いといわれる。
グアニル酸として干し椎茸156.5mg%、生椎茸18.5~45.4mg%、松茸64.6mg%、えのきたけ21.8mg%、ばふんうに0~6.0mg%、牛肉・豚肉2.2~2.5mg%、鶏肉1.4mg%程度含む。イノシン酸(鰹節、煮干の旨み)より旨み成分が強く、グルタミン酸と共に使用し相乗効果を生み出す。複合調味料として用いられ、多量に用いると、自然の味が消してしまうことにもなり味覚を麻痺させ味覚障害を起こす原因にもなる。
イノシン酸Inosin Mono-Phosphate
1847年ドイツのリービッヒによって牛肉のエキスより分離された。1895年にはその化学構造も解明されている。日本では、1913年に小玉新太郎によって鰹節のエキスより発見している。グルタミン酸に比べ化学構造が複雑であることから工業生産は、昭和34年(1959年)に相乗効果が得られることが解って製造が翌年には、始まった。植物性食品には、殆ど含まれていないことから動物性の旨み成分となっている。イノシン酸は、ヒポキサンチンとリボース、リン酸が結合した、旨みは、有機塩基とリン酸基が合わさったヌクレオチド類によって生じている。カツオブシの旨み成分として知られる。主に魚類、鶏肉、豚肉、牛肉の動物性食品に含まれ熟成することによって増加する。
植物性に多いグアニル酸(きのこ類)、グルタミン酸(昆布、お茶、野菜類、貝類)を合わせることによって相乗効果が得られ旨みが増す。イノシン酸ナトリウムとして単独で用いられることはない。
相乗効果は、グルタミン酸ナトリウム(MSG)とイノシン酸ナトリウム(IMP)とで濃度の和を0.05%として味の強さをみるとイノシン酸ナトリウムの配合割合が15%程度までは上昇する。
70%までは変化がなくさらに濃度を濃くすると味の減少がみられほぼ左右対称の曲線が描ける。
イノシン酸として土佐節(一級品)416mg% 土佐節(二級品)687mg% 煮干し863mg% かつお285mg% あじ265mg% さんま242mg% たい215mg% 豚肉122.2mg% 牛肉106.9mg% くるまえび91.9mg% ばふんうに0~7.1mg%程度含む。