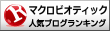・昆布Kelp,Sea tangle こんぶ
昆布とは、褐藻類でコンブ目、科(4科:コンブ科・アイヌワカメ科・ツルモ科・ニセツルモ科:14属37種)の中のコンブ科の海藻の総称で10属27種が知られている。
葉体は根、茎、葉の3部分からなり、遊走子嚢は葉を形成し、古くから食用としていた。海外で食用としているのは、中国、北アメリカ、ノルウェイぐらいで数少ない。
海藻類で一番多く産出し外洋に面した寒流水域で北海道沿岸海域の採取が多くを占める。水深10m前後の海域で春先から初夏にかけて生育がよく主に夏7~9月に採集している。
茎がしっかりしていなく横たわって成長する。3、4年経つと秋に根茎のの成長基部を残し枯れるがそこからまた新しい新芽をだし成長する。
昆布の語源はアイヌ語でコムブで海の藻を意味する説がある。乾燥させ製品化した新コンブが消費地に出回るのが11月ごろで昆布の種類は、10数種ほど知られほとんど素干しし市場に出荷している。函館付近で採取する真昆布は、調味、料理用に、利尻昆布は出し昆布、おしゃぶり昆布、昆布茶として旨みがあってよい。ホソメコンブは、とろろこんぶ、おぼろこんぶ、刻みこんぶ、佃煮、昆布巻きに、トロロコンブは、粘りがあり乾燥し刻み昆布に加工する。
素干しの真昆布100g中でエネルギー145kcal、水分9.5g、たんぱく質8.2g、脂質1.2g、炭水化物61.5g、灰分19.6g、ナトリウム2800mg(食塩相当量7.1g) カリウム6100mg カルシウム710mg、マグネシウム510mg、リン200mg、鉄3.9mg、亜鉛0.8mg、銅0.13mg、マンガン0.25mg、ビタミンA190μg(カロテン1100μg)、ビタミンD(0)mg、ビタミンE0.9mg、ビタミンK90μg、ビタミンB1:0.48mg、ビタミンB2:0.37mg、ナイアシン1.4mg、ビタミンB6:0.03mg、ビタミンB12:0μg、葉酸260μg、パントテン酸0.21mg、ビタミンC25mg、食物繊維27.1gを含む。
乾物に付着している白い粉はマンニット(ショ糖の60%の甘さ)であり旨み成分のグルタミン酸が含まれて出し昆布としての需要も多い。出しを取るのは日本だけで乾燥させ細胞を破壊し旨みを引き出している。
食物繊維(アルギン酸)、無機質、カルシュウム(71mg/乾物10g中)、ヨウ素(20mg/乾物10g中:成人推奨量150μg)、ラミニン(糖タンパク質:アミノ酸、血圧を下げる)、フコイダン、アルギン酸(多糖類、ソルギン[低分子アルギン酸ナトリウム・水溶性]のぬるぬる成分、ナトリウムの排泄)の高血圧予防によく、また食品添加物としてアイスクリーム、口紅などにも使われている。昆布科Family Laminariaceae こんぶか 真核生物Eukaryota、不等毛植物門(ふとうもうしょくぶつもん)Phylum Heterokontophyta、褐藻綱(かっそうこう)Class Phaeophyceae、コンブ目Order Laminariales4科、コンブ科として存在する。
日本には10属(コンブ属Laminaria13種、ミスジコンブ1種、トロロコンブ2種、スジメ1種、アナメ2種、ネコアシコンブ1種、クロシオメ1種、アラメ2種、カジメ3種、アントクメ属1種)27種ほどみられる。よく知られているのは、コンブ属の1)マコンブ、2)ホソメコンブ、3)リシリコンブ、4)オニコンブ、5)エナガコンブ、6)ミツイシコンブ、7)ナガコンブ、8)ガッガラコンブ、9)カラフトコンブ、10)チヂミコンブ、11)カラフトトロロコンブ、12)エンドウコンブ、13)ゴヘイコンブがある。ちなみにワカメは、コンブ目、チガイソ科Family Alariaceae、ワカメ属Genus Undariaとしている。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。