「牡丹に唐獅子」は一通り書いたが、
最後にひとつだけ。
8月27日に書いたなかで、
「柱は二階と縁の下」という一行があった。
じつはこれがどういう意味が、
頑張ってみたが、どうしてもわからない。
ネットで調べてみたところ、
この「柱は二階と…」は忠臣蔵の七段目を指していると
説明しているサイトが見つかった。
祇園一力茶屋で、敵をあざむくために放蕩をつづける由良助が、
人目をさけて、そっと密書を読む。
これを、二階にいるおかるが手鏡にうつして読み、
同じく、床下で、敵方の斧九太夫が
ほどけ落ちた巻き手紙を盗み読む。
この場面を
「柱は二階(おかる)と縁の下(斧九太夫)」と
表現しているのだという。
しかし、これだと「柱」が何なのか、
よくわからない。
私の手元に、忠臣蔵七段目の写真入りの本がある。
由良助が中村吉右衛門。
おかるは板東玉三郎。
斧九太夫は片岡芦燕。
縁近くに立ち、
密書を長々と地近くに垂らしながら
一心に読みふけっている由良助。
その真下、
縁の下にかくれた斧九太夫が
目の前に垂れてきた密書のはじを手元に引き寄せ
こっそりと読んでいる。
一方、となりの二階(中二階のような作り)にいるのがおかる。
しどけなく欄にもたれて、鏡を掲げ、
となりの階下にいる、由良助の手紙を鏡に写して
のぞこうとしている。
だが、この舞台写真でも、
どこにも柱は見あたらない。
これは、どうしてだろうか。
それなら、いっそ単純に、
意味そのままに、
「柱は二階と縁の下をつなぐもの」と受けとめて、
日本家屋の構造(とはオーバーだが)を尻取り唄に取り入れたと
考えてもいいかもしれない。
ここでいう柱は、一階と二階を通して立てている
通し柱のことだとすれば、
自然である。
残念ながら、これも確証がない。
第一、柱は二階と縁の下をつなぐもの、などという
おもしろくも何ともない文を、
尻取り唄に入れるとは、どう考えても不自然だ。
江戸の町で、
人々が皆、そうそう、その通りと、
納得するようなフレーズであることが
尻取り唄に加える条件のはずだ。
結局このフレーズは、どういう意味なのか、
私には、さっぱりわからないままである。
もし、意味をご存知の方がいらしたら、
ぜひとも教えていただきたい。
やれ、これで「牡丹に唐獅子」は
おしまいだ。
どっとはらい。
★★★
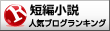 短編小説 ブログランキングへ
短編小説 ブログランキングへ
よろしければ、ひとつご協力を。
最後にひとつだけ。
8月27日に書いたなかで、
「柱は二階と縁の下」という一行があった。
じつはこれがどういう意味が、
頑張ってみたが、どうしてもわからない。
ネットで調べてみたところ、
この「柱は二階と…」は忠臣蔵の七段目を指していると
説明しているサイトが見つかった。
祇園一力茶屋で、敵をあざむくために放蕩をつづける由良助が、
人目をさけて、そっと密書を読む。
これを、二階にいるおかるが手鏡にうつして読み、
同じく、床下で、敵方の斧九太夫が
ほどけ落ちた巻き手紙を盗み読む。
この場面を
「柱は二階(おかる)と縁の下(斧九太夫)」と
表現しているのだという。
しかし、これだと「柱」が何なのか、
よくわからない。
私の手元に、忠臣蔵七段目の写真入りの本がある。
由良助が中村吉右衛門。
おかるは板東玉三郎。
斧九太夫は片岡芦燕。
縁近くに立ち、
密書を長々と地近くに垂らしながら
一心に読みふけっている由良助。
その真下、
縁の下にかくれた斧九太夫が
目の前に垂れてきた密書のはじを手元に引き寄せ
こっそりと読んでいる。
一方、となりの二階(中二階のような作り)にいるのがおかる。
しどけなく欄にもたれて、鏡を掲げ、
となりの階下にいる、由良助の手紙を鏡に写して
のぞこうとしている。
だが、この舞台写真でも、
どこにも柱は見あたらない。
これは、どうしてだろうか。
それなら、いっそ単純に、
意味そのままに、
「柱は二階と縁の下をつなぐもの」と受けとめて、
日本家屋の構造(とはオーバーだが)を尻取り唄に取り入れたと
考えてもいいかもしれない。
ここでいう柱は、一階と二階を通して立てている
通し柱のことだとすれば、
自然である。
残念ながら、これも確証がない。
第一、柱は二階と縁の下をつなぐもの、などという
おもしろくも何ともない文を、
尻取り唄に入れるとは、どう考えても不自然だ。
江戸の町で、
人々が皆、そうそう、その通りと、
納得するようなフレーズであることが
尻取り唄に加える条件のはずだ。
結局このフレーズは、どういう意味なのか、
私には、さっぱりわからないままである。
もし、意味をご存知の方がいらしたら、
ぜひとも教えていただきたい。
やれ、これで「牡丹に唐獅子」は
おしまいだ。
どっとはらい。
★★★
よろしければ、ひとつご協力を。









