〈こまる〉とは、〈困る〉ではない。
薄墨の方言で、お辞儀をする、頭を下げることを言う。
たとえば、知人などに道で出会うと、
親は子供に、
「ほれ、こまりなさい」と言い、
子供は「こんにちは」と最敬礼する。
これが、〈こまる〉の典型。
もしかしたら〈かしこまる〉の〈こまる〉から
派生した方言かなと思っていたが、
カメキチは、
「うーむ、〈こまる〉は、〈込まる〉でないかなあ」と
独自の説を唱えていた。
何かせまい中に入り込んでしまうのが「込まる」。
たとえば箱などに入り込んでしまえば、
体を小さく折り曲げなくてはならない。
これが、薄墨弁「こまる」のもとではないかという。
ただし、カメキチ説も裏付けがあるわけではなく、
あの爺さまの単なる思いつきでしかないのだが。
さて、本日は、この〈こまる〉に関連した話。
薄墨のさる大家で。
中庭に面した廊下を行くと、
どこからともなく
「こまれ」
「こまれ」
奇妙な声が聞こえてきたという。
誰の声かと見回しても、庭には誰もいない。
廊下の脇は、障子の閉められた部屋ばかり。
障子の奥の部屋に、誰かいるのかもしれない。
細く障子を開けて見ても、
座敷には人影はない。
首をひねりつつ進んでいくと、
「こまれ」の声は次第に大きくなる。
最後は割れんばかりの大声で、
「こまれぇ」と叫ぶ。
不気味になって突き当たりの部屋を、
再度のぞくと。
障子越しの、薄明るい座敷の奥、
畳に頭をすりつけて、「こまっている」一人の人物。
その姿に、見覚えがあるような気がして、
そろりと障子をさらに開き、目をこらすと、
こまっていた人がゆっくりと体を起こし、
顔を上げた。
それが、自分自身だと気づいて、
ぎょっとすると、
部屋の中でこまっていた自分が、
にたりと笑って消えたとか。
★★★★
できれば、ご協力をお願いしぁんす。
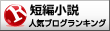
短編小説 ブログランキングへ
久しぶりで酒っこを飲んだが、うまくありぁせん。
まだ本調子ではないよった。
皆さまも、お気をつけなさんして。
薄墨の方言で、お辞儀をする、頭を下げることを言う。
たとえば、知人などに道で出会うと、
親は子供に、
「ほれ、こまりなさい」と言い、
子供は「こんにちは」と最敬礼する。
これが、〈こまる〉の典型。
もしかしたら〈かしこまる〉の〈こまる〉から
派生した方言かなと思っていたが、
カメキチは、
「うーむ、〈こまる〉は、〈込まる〉でないかなあ」と
独自の説を唱えていた。
何かせまい中に入り込んでしまうのが「込まる」。
たとえば箱などに入り込んでしまえば、
体を小さく折り曲げなくてはならない。
これが、薄墨弁「こまる」のもとではないかという。
ただし、カメキチ説も裏付けがあるわけではなく、
あの爺さまの単なる思いつきでしかないのだが。
さて、本日は、この〈こまる〉に関連した話。
薄墨のさる大家で。
中庭に面した廊下を行くと、
どこからともなく
「こまれ」
「こまれ」
奇妙な声が聞こえてきたという。
誰の声かと見回しても、庭には誰もいない。
廊下の脇は、障子の閉められた部屋ばかり。
障子の奥の部屋に、誰かいるのかもしれない。
細く障子を開けて見ても、
座敷には人影はない。
首をひねりつつ進んでいくと、
「こまれ」の声は次第に大きくなる。
最後は割れんばかりの大声で、
「こまれぇ」と叫ぶ。
不気味になって突き当たりの部屋を、
再度のぞくと。
障子越しの、薄明るい座敷の奥、
畳に頭をすりつけて、「こまっている」一人の人物。
その姿に、見覚えがあるような気がして、
そろりと障子をさらに開き、目をこらすと、
こまっていた人がゆっくりと体を起こし、
顔を上げた。
それが、自分自身だと気づいて、
ぎょっとすると、
部屋の中でこまっていた自分が、
にたりと笑って消えたとか。
★★★★
できれば、ご協力をお願いしぁんす。
短編小説 ブログランキングへ
久しぶりで酒っこを飲んだが、うまくありぁせん。
まだ本調子ではないよった。
皆さまも、お気をつけなさんして。









