 アンケートへのご協力ありがとうございました。
アンケートへのご協力ありがとうございました。 昨年10月29日に開催した、この地域の出産環境を考える勉強会をうけ、会で進めてきたアンケート調査の結果を皆さんにお伝えします。
昨年10月29日に開催した、この地域の出産環境を考える勉強会をうけ、会で進めてきたアンケート調査の結果を皆さんにお伝えします。勉強会では、この地域の実情を踏まえた上で二つの新しい構想が提案されました。
(cuore11月号に掲載しています)
●飯田産院構想・・・複数の産科医が協力し合い地域のローリスクのお産を担う構想。
●バースセンター構想・・・助産師達が中心となり医師の協力のもとローリスクのお産を担う施設を、下伊那の北部と南部に配置する構想。
この広い飯伊地域で出産場所が一ヶ所に集中してしまう事に、ここで暮らす人々は大きな不安を抱いている事が、今回のアンケート調査で明確に伝わってきます。
 アンケート調査結果
アンケート調査結果
提出者213名
 このアンケート調査は飯伊地域の市町村の保健師さんに協力を依頼、協力を得られた8町村の主に妊婦さんや子育て中の主婦を対象に行いました。
このアンケート調査は飯伊地域の市町村の保健師さんに協力を依頼、協力を得られた8町村の主に妊婦さんや子育て中の主婦を対象に行いました。 性別・・男性(13.6%)女性(86.4%)
性別・・男性(13.6%)女性(86.4%) 年齢・・10代(0%) 20代(17.8%) 30代(46%) 40代(22%) 50代(10.8%) 60歳以上(3.3%)
年齢・・10代(0%) 20代(17.8%) 30代(46%) 40代(22%) 50代(10.8%) 60歳以上(3.3%) 職業・・医師(0.5%) 看護師(3.7%) 助産師(5.2%) 保健師(10.3%) 市町村職員(12.2%) その他一般(68.1%)
職業・・医師(0.5%) 看護師(3.7%) 助産師(5.2%) 保健師(10.3%) 市町村職員(12.2%) その他一般(68.1%) A)今後の飯伊地域の産科体制についてお聞きします。
1)安全を求めて当地域の出産は飯田市立病院へ一極集約する
賛成(7%) 反対(77.1%)
2)産む側が選択できるように出産場所の分散が望ましい
賛成(97.1%) 反対(0%)
B) A)で2)賛成と答えた方々にお聞きします。
新しい産科体制として望ましいのは
イ)北部、南部に助産師中心のバースセンター構想
賛成(64.4%) 反対(14.1%)
ロ)次世代に向けた飯田産院構想(産科医の集合体)
賛成(58.8%) 反対(13.6%)
◎アンケートに寄せられたコメントの中で、助産師さんの活躍に期待する内容のものが多く見られました。
 今後の望ましい飯伊地域の産科体制についてご意見があればお聞かせください。
今後の望ましい飯伊地域の産科体制についてご意見があればお聞かせください。 中心から遠いところに住む人たちが利用しやすい体制は大事だと思います。過疎化が進んでしまうところができてくるし、核家族化が進む原因にもなると思います。
中心から遠いところに住む人たちが利用しやすい体制は大事だと思います。過疎化が進んでしまうところができてくるし、核家族化が進む原因にもなると思います。 知人が市立病院に入院中、一日に8人もの出産があったそうで、てんてこまいって感じだったそうです。医師がいつも忙しく、これ以上市立病院に負担をかけ、本来の機能を失っては、それこそ事故も起こりうると思ってしまいます。
知人が市立病院に入院中、一日に8人もの出産があったそうで、てんてこまいって感じだったそうです。医師がいつも忙しく、これ以上市立病院に負担をかけ、本来の機能を失っては、それこそ事故も起こりうると思ってしまいます。 これから地域で知恵を出し合い新たな体制を築かれることを希望します。妊娠、出産、育児と一貫して、身近で安心できるネットワークができる機会として捉えていくことが大切だと思います。市立病院の状況を見ると非常に混み合い大変なようです。やはり一極集中だけは避けるべきと思います。
これから地域で知恵を出し合い新たな体制を築かれることを希望します。妊娠、出産、育児と一貫して、身近で安心できるネットワークができる機会として捉えていくことが大切だと思います。市立病院の状況を見ると非常に混み合い大変なようです。やはり一極集中だけは避けるべきと思います。 ローリスクを扱う病院、高度医療を提供する病院、それぞれの役割が行え、産婦さんが安心して出産場所を決められるような体制に整えられることが望ましいと思う。
ローリスクを扱う病院、高度医療を提供する病院、それぞれの役割が行え、産婦さんが安心して出産場所を決められるような体制に整えられることが望ましいと思う。 地方の医師不足や都市部と地方の医療格差が広がっており、産科と小児科は特に著しい。飯伊の例をきっかけに国や医師会へ要望等をし、少子化対策を含めて頑張ってほしい。
地方の医師不足や都市部と地方の医療格差が広がっており、産科と小児科は特に著しい。飯伊の例をきっかけに国や医師会へ要望等をし、少子化対策を含めて頑張ってほしい。 この資料にもあった‘飯田産院’はとても面白いと思います。やってみる価値はあるのかなと思いました。その上で、妊婦側も‘おんぶにだっこ’ではなく、自ら体力をつけ、なるべく安産を目指す努力ができるような体制を作ったらいいと思います。だから「この産院は、こういう状況でうので、妊婦さんもこれをがんばりましょう!」みたいな、みんなで作り上げていくような産院を目指す事で新しい産科の先生も誕生していくのでは、と思いました。
この資料にもあった‘飯田産院’はとても面白いと思います。やってみる価値はあるのかなと思いました。その上で、妊婦側も‘おんぶにだっこ’ではなく、自ら体力をつけ、なるべく安産を目指す努力ができるような体制を作ったらいいと思います。だから「この産院は、こういう状況でうので、妊婦さんもこれをがんばりましょう!」みたいな、みんなで作り上げていくような産院を目指す事で新しい産科の先生も誕生していくのでは、と思いました。安心したお産ってそれぞれですし、一番は、相談できる人がいることが大切かなって思います。カウンセラーのような方がいるといいなといつも思います。(医師や助産師さんはいつも忙しそうなので。)
 各市町村に一人以上の助産師さんが必要だと思います。
各市町村に一人以上の助産師さんが必要だと思います。 産科医のバックアップがあれば、助産師中心でいいと思う。また、お産の仕方が多様化(自分のライフスタイルに合わせて選べる。)出来たほうがいいと思う。自宅出産のバックアップ体制がとれるように。(例えば、個人出張助産師)
産科医のバックアップがあれば、助産師中心でいいと思う。また、お産の仕方が多様化(自分のライフスタイルに合わせて選べる。)出来たほうがいいと思う。自宅出産のバックアップ体制がとれるように。(例えば、個人出張助産師) 自信のない助産師が多い現実。助産師がもっと勉強していく必要がある。そうした助産師の教育の場が欲しい。その上で、助産師が活躍できて母親に寄り添えるおうな、バースセンターや産院ができればいいと思う。
自信のない助産師が多い現実。助産師がもっと勉強していく必要がある。そうした助産師の教育の場が欲しい。その上で、助産師が活躍できて母親に寄り添えるおうな、バースセンターや産院ができればいいと思う。 次世代に向けた飯田産院の構想というのは、前向きな発想で素晴らしいと思います。しかし、実現した時点で、今ある開業医も高齢となり、その時にはお産をやめてしまう事も考えられるので、バースセンターも同時に進行していかなければ望ましいものになっていかないと思う。是非、実現させて欲しいです。それから、助産師不足を言われていますが、下伊那には女子短大という助産師を養成できる学校があります。女子短大の看護科ともうまく連携が取れて、育った助産師さんが下伊那に残ってくれれば助産師不足というのも将来的に解消されていくのでは・・と思います。助産師の資格を取るための補助金が市町村から出る制度があればいいのにね。
次世代に向けた飯田産院の構想というのは、前向きな発想で素晴らしいと思います。しかし、実現した時点で、今ある開業医も高齢となり、その時にはお産をやめてしまう事も考えられるので、バースセンターも同時に進行していかなければ望ましいものになっていかないと思う。是非、実現させて欲しいです。それから、助産師不足を言われていますが、下伊那には女子短大という助産師を養成できる学校があります。女子短大の看護科ともうまく連携が取れて、育った助産師さんが下伊那に残ってくれれば助産師不足というのも将来的に解消されていくのでは・・と思います。助産師の資格を取るための補助金が市町村から出る制度があればいいのにね。
 知っていますか??
知っていますか?? 

今、助産院に対する医療法の改正が進められています。
◎改正前・・・嘱託医は、特に産科医でなくても開業できた助産院。
↓
◎改正後・・・分娩を扱っている産科医を嘱託医におき一年以内に見つからなければ歴史ある助産院でも廃止になりかねない。
この法改正が適応されると、私達の産む選択の自由はますます奪われ、産む安心は更に失われてしまうのでは・・?
 次回も楽しみに
次回も楽しみに










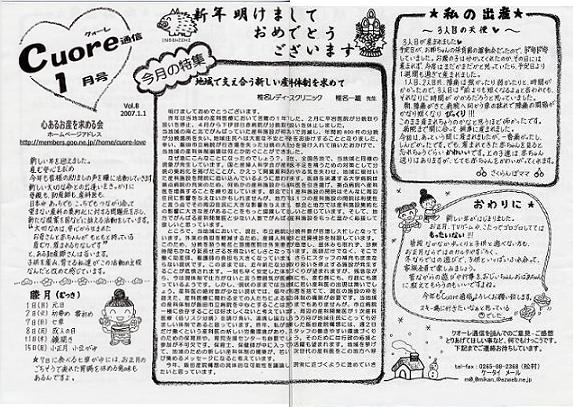
 新しい年を迎えました。
新しい年を迎えました。 今月の特集
今月の特集
 3人目の天使
3人目の天使

 していました。お腹の子はわかっていてくてたのか、その日には産まれず、今度はまだかまだかと思っていたら、予定日より一週間も過ぎて産まれました
していました。お腹の子はわかっていてくてたのか、その日には産まれず、今度はまだかまだかと思っていたら、予定日より一週間も過ぎて産まれました
 』と言われても、それなりに時間がかかるだろうと思っていました
』と言われても、それなりに時間がかかるだろうと思っていました 朝、陣痛がきて病院へ向かう車の
朝、陣痛がきて病院へ向かう車の 揺れで陣痛の間隔がかなり短くなりビックリ
揺れで陣痛の間隔がかなり短くなりビックリ


 でも、産まれてきた赤ちゃんを見ると忘れちゃうぐらい可愛いです
でも、産まれてきた赤ちゃんを見ると忘れちゃうぐらい可愛いです 上の子達は赤ちゃん返りはありますが、とても赤ちゃんをかわいがってくれます
上の子達は赤ちゃん返りはありますが、とても赤ちゃんをかわいがってくれます