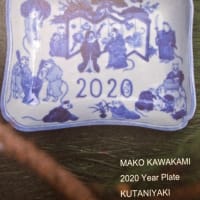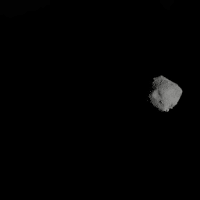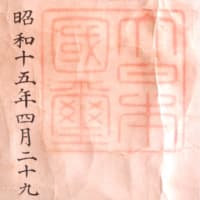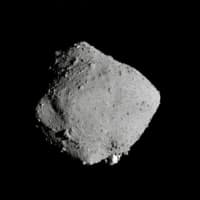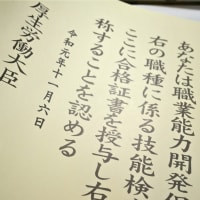鉄腕アトムが生まれるという2003年4月7日を迎えたとき、現実に自分の生活環境を顧みて「ふ~ん、未来なんてこんなもんかぁ」とか思った。けど、それをきっかけに久しぶりに読んでみたら「手塚治虫ってやっぱすごい」ってね、単純に思ったのでした。読みはじめれば手塚治虫ワールドが止まらなくなってしまって、実家までクルマを走らせて、両親には挨拶もそこそこに漫画だけを取りに帰ったりして。ひたすら「火の鳥」を読み返したりしました。
エヴァンゲリオンでは2015年に使徒がいきなり登場しますが、現実が作品世界に追いつくのはあと5年後。
今年、蝉も鳴かないほどに異様な暑さだった夏。「暑すぎると蝉って鳴かないんだね」って事実を知りつつも「ひょっとして、セカンドインパクトって本当にあった?」とか思ってしまったけど、リアルタイムに時代の空気にさらされていた人たちの心の中では、確実にそれは起こっているような気がして仕方ありませんでした。「セカンドインパクト世代」っていうのが実際に、本当にあるんじゃないかと。。。「それは自分だ」って思う人、かなりいるのではないかしら?
心理学、精神分析の概念と、旧約聖書やユダヤ教、カバラなどの背景を「これでもか!」というまでに積み上げた世界観に、僕はきっかり10年後、超乗り遅れて接したわけですが。。。それでも息のつまるような思いで目が離せませんでした。一方でちょっと気になったことがあります。ネット上には「エヴァンゲリオン=聖書」の世界観については事細かに解説してあるところがやたらとあるけれど、なぜか古事記、日本書紀に基づいた世界観の提示についてあまり説明されていないような気がしていたのです。ちょっと見つけたって思っても、ヤシマ作戦の解説で終わり。以上。。。って、そーゆーわけにはいかないでしょーよ。
なぜ仙石原にジオフロントが存在するのか?
この問いに答えられる根拠は、古事記にこそ求められるべきだと思うのですが?
それで、あれっ?!と思ったわけです。
古事記、日本書紀はすでに日本人のバックボーンではなくなってきてる?って。とりわけ若い人たちには、ほとんど眼中にないっていうか。。。
だから「決戦!第3新東京市」において、たからかに「古事記の世界をこれからちょっちやりますよ~」ってミサトさんが言っているのに、反応できる視聴者っていうのが、作り手が思っていたよりも少なかったんじゃないか?と思ったのです。
反対に、記紀に詳しい人の方では「エヴァ?なに?」ってなもんで、ちょっとうまく噛み合っていないような。。。送り手と受け手にミスマッチが起こっている。。。それとも、うまくカモフラージュされている???
登場人物の名前が帝国海軍の軍艦の名前からとられているっていう話はよく知られています。さっきから出てきているので「葛城ミサト」さんを例にとれば、葛城型スループ、「空母葛城」までは簡単に調べがつく。そしたら、その戦艦はどうしてそういう命名をされたか?ってところまであと一歩のはずなんだけど。。。
「葛城」がそうかどうかは分からないけれど、たいてい戦艦には「艦内神社」なるものがそなえられていて、神社から分霊っていうカタチでそれぞれ神様が乗っていたことになっています。山の名前なんて言うのは大元になる神社か神様を表しているようなもの。帝国海軍の艦船名が登場人物の名前にあてられているっていうことは、ほとんど「記紀」に代表される神話とその背景に由来している、っていうのと同義になるはずなのです。
葛城山には葛城一言主神社があって、ヒトコトヌシという神様を祭っています。
これは雄略天皇が「古事記」「日本書紀」で出会った神様。
天皇はその後、また葛城山におのぼりになりました。
そのときお供の人々は、みんな、赤いひものついた、
青ずりのしょうぞくをいただいて着ておりました。
すると、向こうの山を、一人のりっぱな人がのぼって行くのがお目にとまりました。
その人のお供の者たちも、やはりみんな、赤ひものついた青ずりの着物を着ていまして
だれが見ても天皇のお行列と寸分も違いませんでした。
天皇はおどろいて、すぐに人をおつかわしになり、
「日本にはわしを除いて二人と天皇はいないはずだ。それだのに、
わしと同じお供を従えて行くそちは、いったい何者だ」と、
きびしくお問いつめになりました。
すると向こうからも、そのおたずねと同じようなことを問いかえしました。
天皇はくわッとお怒りになり、まっ先に矢をぬいておつがえになりました。
お供の者も残らず一度に矢をつがえました。
そうすると、向こうでも負けていないで、みんなそろって矢をつがえました。
天皇は、「さあ、それでは名を名乗れ。お互いに名乗り合ったうえで矢を放とう」と
お言い送りになりました。
向こうからは、
「それではこちらの名まえもあかそう。私は悪いことにもただ一言、
いいことにも一言だけお告げをくだす、
葛城山の一言主神(ひとことぬしのかみ)だ」とお答えがありました。
天皇はそれをお聞きになると、びっくりなすって、
「これはこれはおそれおおい、大神がご神体をお現わしになったとは思いもかけなかった」と
おっしゃって、大急ぎで太刀や弓矢をはじめ、お供の者一同の青ずりの着物をも
すっかりおぬがせになり、それをみんな、伏し拝んで、大神へご献上になりました。
すると大神は手を打ってお喜びになり、その献上物をすっかりお受けいれになりました。
それから天皇がご還幸になるときには、大神はわざわざ山をおりて、
遠く長谷の山の口までお見送りになりました。
「古事記物語」鈴木三重吉編 とんぼのお歌 四
「悪いことにもただ一言、いいことにも一言だけお告げをくだす、葛城山の一言主神」
葛城さん(葛城山?)がサービスで次回予告をやるっていうのは、おもしろいほどに古事記的、日本書紀的なわけです。また葛城博士がセカンドインパクトで亡くなって、ミサトさんだけ生存者として一人生き残ったという話も古墳時代の史実(。。。と、とりあえず認められていること)に当てはまります。古墳時代に大和政権と密接な関係を保ちつつ、大きな権勢を誇ったとされる葛城氏の存在が、間違いなく作品には反映されているのです。
赤木リツ子さんの話も、日本書紀と古事記の関係や、赤城山、三つの赤城神社などのディテールが反映されているとして見てみると、おもしろい。
物語の環境設定についてエヴァンゲリオンのスタッフは「ここまでやったのか!」と。こちらがあきれてしまうほどに「神話」に忠実。
ですから、聖書やカバラに詳しい人だけじゃなく、記紀や古代史に詳しい人が見ると、別のおもしろさがあるように思うのです。。。というよりも、複数の読み方を可能にし、担保してくれているのは、エヴァの物語が展開している場所にある。だから、本当はだれかすっごい詳しい人が「決定版!日本の神話とエヴァンゲリオン」みたいなことやってくんないかなぁ~って、ずっと思っていたのでした。僕が知らないだけで、ひょっとしたらもうあるのかもしれないけど。
逆に、聖書や記紀のバックボーンをまったく持っていないけど、エヴァンゲリオンに無茶苦茶はまっちゃった人が「古事記」「日本書紀」をはじめとする日本の神話に興味を持ってくれたら、非常にスリリングな読みが現れてきてくれそうなんですけど。。。エヴァ・マニアの方々、どうでしょう? 読んでみませんか?
なぜ仙石原にジオフロントが存在するのか?
作り手側が恣意的に決めてしまえるはずの「設定」だけど、「任意の場所」では展開できなかったのには理由があるんだと思います。もし、それができるんなら、どこか勝手なところ、任意な場所に「ジオフロント」や「セントラルドグマ」を掘っちゃえばいいわけでしょ?
わざわざ箱根湯本だとか御殿場なんて地名を出さなくてもいいし、旧小田原、新横須賀なんて凝ったことしなくてもいい。
第弐拾壱話「ネルフ、誕生」で、こんな会話がありました。
冬月:これは…
ゲンドウ:われわれではない、誰かが残した空間ですよ。89%は埋まっていますがね。
冬月:もとはきれいな球状の地底空間か…
ゲンドウ:あれが、人類がもてる全てを費やしている施設です。
誰かが残した空間。そこにネルフ本部は建設されたわけですから。
仙石原というより、箱根(筥根)が神話的にどういう場所として考えられているか?を探ると答えらしきことの影が見えてきそうです。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(1)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(2)
エヴァンゲリオンでは2015年に使徒がいきなり登場しますが、現実が作品世界に追いつくのはあと5年後。
今年、蝉も鳴かないほどに異様な暑さだった夏。「暑すぎると蝉って鳴かないんだね」って事実を知りつつも「ひょっとして、セカンドインパクトって本当にあった?」とか思ってしまったけど、リアルタイムに時代の空気にさらされていた人たちの心の中では、確実にそれは起こっているような気がして仕方ありませんでした。「セカンドインパクト世代」っていうのが実際に、本当にあるんじゃないかと。。。「それは自分だ」って思う人、かなりいるのではないかしら?
心理学、精神分析の概念と、旧約聖書やユダヤ教、カバラなどの背景を「これでもか!」というまでに積み上げた世界観に、僕はきっかり10年後、超乗り遅れて接したわけですが。。。それでも息のつまるような思いで目が離せませんでした。一方でちょっと気になったことがあります。ネット上には「エヴァンゲリオン=聖書」の世界観については事細かに解説してあるところがやたらとあるけれど、なぜか古事記、日本書紀に基づいた世界観の提示についてあまり説明されていないような気がしていたのです。ちょっと見つけたって思っても、ヤシマ作戦の解説で終わり。以上。。。って、そーゆーわけにはいかないでしょーよ。
なぜ仙石原にジオフロントが存在するのか?
この問いに答えられる根拠は、古事記にこそ求められるべきだと思うのですが?
それで、あれっ?!と思ったわけです。
古事記、日本書紀はすでに日本人のバックボーンではなくなってきてる?って。とりわけ若い人たちには、ほとんど眼中にないっていうか。。。
だから「決戦!第3新東京市」において、たからかに「古事記の世界をこれからちょっちやりますよ~」ってミサトさんが言っているのに、反応できる視聴者っていうのが、作り手が思っていたよりも少なかったんじゃないか?と思ったのです。
反対に、記紀に詳しい人の方では「エヴァ?なに?」ってなもんで、ちょっとうまく噛み合っていないような。。。送り手と受け手にミスマッチが起こっている。。。それとも、うまくカモフラージュされている???
登場人物の名前が帝国海軍の軍艦の名前からとられているっていう話はよく知られています。さっきから出てきているので「葛城ミサト」さんを例にとれば、葛城型スループ、「空母葛城」までは簡単に調べがつく。そしたら、その戦艦はどうしてそういう命名をされたか?ってところまであと一歩のはずなんだけど。。。
「葛城」がそうかどうかは分からないけれど、たいてい戦艦には「艦内神社」なるものがそなえられていて、神社から分霊っていうカタチでそれぞれ神様が乗っていたことになっています。山の名前なんて言うのは大元になる神社か神様を表しているようなもの。帝国海軍の艦船名が登場人物の名前にあてられているっていうことは、ほとんど「記紀」に代表される神話とその背景に由来している、っていうのと同義になるはずなのです。
葛城山には葛城一言主神社があって、ヒトコトヌシという神様を祭っています。
これは雄略天皇が「古事記」「日本書紀」で出会った神様。
天皇はその後、また葛城山におのぼりになりました。
そのときお供の人々は、みんな、赤いひものついた、
青ずりのしょうぞくをいただいて着ておりました。
すると、向こうの山を、一人のりっぱな人がのぼって行くのがお目にとまりました。
その人のお供の者たちも、やはりみんな、赤ひものついた青ずりの着物を着ていまして
だれが見ても天皇のお行列と寸分も違いませんでした。
天皇はおどろいて、すぐに人をおつかわしになり、
「日本にはわしを除いて二人と天皇はいないはずだ。それだのに、
わしと同じお供を従えて行くそちは、いったい何者だ」と、
きびしくお問いつめになりました。
すると向こうからも、そのおたずねと同じようなことを問いかえしました。
天皇はくわッとお怒りになり、まっ先に矢をぬいておつがえになりました。
お供の者も残らず一度に矢をつがえました。
そうすると、向こうでも負けていないで、みんなそろって矢をつがえました。
天皇は、「さあ、それでは名を名乗れ。お互いに名乗り合ったうえで矢を放とう」と
お言い送りになりました。
向こうからは、
「それではこちらの名まえもあかそう。私は悪いことにもただ一言、
いいことにも一言だけお告げをくだす、
葛城山の一言主神(ひとことぬしのかみ)だ」とお答えがありました。
天皇はそれをお聞きになると、びっくりなすって、
「これはこれはおそれおおい、大神がご神体をお現わしになったとは思いもかけなかった」と
おっしゃって、大急ぎで太刀や弓矢をはじめ、お供の者一同の青ずりの着物をも
すっかりおぬがせになり、それをみんな、伏し拝んで、大神へご献上になりました。
すると大神は手を打ってお喜びになり、その献上物をすっかりお受けいれになりました。
それから天皇がご還幸になるときには、大神はわざわざ山をおりて、
遠く長谷の山の口までお見送りになりました。
「古事記物語」鈴木三重吉編 とんぼのお歌 四
「悪いことにもただ一言、いいことにも一言だけお告げをくだす、葛城山の一言主神」
葛城さん(葛城山?)がサービスで次回予告をやるっていうのは、おもしろいほどに古事記的、日本書紀的なわけです。また葛城博士がセカンドインパクトで亡くなって、ミサトさんだけ生存者として一人生き残ったという話も古墳時代の史実(。。。と、とりあえず認められていること)に当てはまります。古墳時代に大和政権と密接な関係を保ちつつ、大きな権勢を誇ったとされる葛城氏の存在が、間違いなく作品には反映されているのです。
赤木リツ子さんの話も、日本書紀と古事記の関係や、赤城山、三つの赤城神社などのディテールが反映されているとして見てみると、おもしろい。
物語の環境設定についてエヴァンゲリオンのスタッフは「ここまでやったのか!」と。こちらがあきれてしまうほどに「神話」に忠実。
ですから、聖書やカバラに詳しい人だけじゃなく、記紀や古代史に詳しい人が見ると、別のおもしろさがあるように思うのです。。。というよりも、複数の読み方を可能にし、担保してくれているのは、エヴァの物語が展開している場所にある。だから、本当はだれかすっごい詳しい人が「決定版!日本の神話とエヴァンゲリオン」みたいなことやってくんないかなぁ~って、ずっと思っていたのでした。僕が知らないだけで、ひょっとしたらもうあるのかもしれないけど。
逆に、聖書や記紀のバックボーンをまったく持っていないけど、エヴァンゲリオンに無茶苦茶はまっちゃった人が「古事記」「日本書紀」をはじめとする日本の神話に興味を持ってくれたら、非常にスリリングな読みが現れてきてくれそうなんですけど。。。エヴァ・マニアの方々、どうでしょう? 読んでみませんか?
なぜ仙石原にジオフロントが存在するのか?
作り手側が恣意的に決めてしまえるはずの「設定」だけど、「任意の場所」では展開できなかったのには理由があるんだと思います。もし、それができるんなら、どこか勝手なところ、任意な場所に「ジオフロント」や「セントラルドグマ」を掘っちゃえばいいわけでしょ?
わざわざ箱根湯本だとか御殿場なんて地名を出さなくてもいいし、旧小田原、新横須賀なんて凝ったことしなくてもいい。
第弐拾壱話「ネルフ、誕生」で、こんな会話がありました。
冬月:これは…
ゲンドウ:われわれではない、誰かが残した空間ですよ。89%は埋まっていますがね。
冬月:もとはきれいな球状の地底空間か…
ゲンドウ:あれが、人類がもてる全てを費やしている施設です。
誰かが残した空間。そこにネルフ本部は建設されたわけですから。
仙石原というより、箱根(筥根)が神話的にどういう場所として考えられているか?を探ると答えらしきことの影が見えてきそうです。
エヴァンゲリオン/体験
エヴァンゲリオン/体験(3)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(1)
二重の司祭/碇ゲンドウの場合(2)