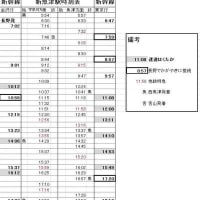年末の駅降り行動最終日、今日は東海道線の駅のうち、前回の駅降り時と違う橋上駅舎に改築された駅を降りることにした。もちろん18きっぷで。和歌山から近い駅降りしてない駅に行くには、フェリーで徳島に渡らないといけないからな。
和歌山発553、紀州時快速は運転されてないので、日根野で関空快速に乗り換える。関空快速は日根野でくろしおにも接続するが、乗換客は皆無だった。それどころがくろしお自体も乗客はわずかだった。
和歌山を出る頃には暗かった空も、天王寺に着く頃にはすっかり明るくなっていた。前から2両で座席もほとんど埋まっていた。
天王寺から阪堺電車、天王寺駅前から阿倍野間の移設区間に乗るためだ。新しい線路は西側に敷設され、緑地帯も設置された。
阿倍野で降りて、朝食を買いながら、天王寺へ小走りで移動、大阪環状線の新車323系に乗るためだ。小走りで急いだせいか、ぎりぎり間に合った。8分後も323系運用だが、これだと後のスケジュールが30分以上ずれこむことが、後々判明した。
323系の座席幅は思ったより広め、LCDでは路線図と乗車位置を表示していたが、東京のように所要時間の表示はなかった。京橋で1分停車するというので降りて撮影、それも外回りの323と並んでの撮影となさった。323の運用が固定されているなら、7時43分に京橋で並ぶことになる。
京橋から立ち席になったので、ドアスペースのクッションを体感、何か思っていたのと違う。
8時丁度の新快速で大津へ移動、秋にリニューアルされたということなので降りることにした。駅の中には商業施設も入り、すっかりあか抜けた感じになった。
大津から普通列車に乗って、野洲の一つ先の篠原で下車した。篠原の橋上駅舎では、改札・事務室が下り線上に位置、上り線ホームへは改札外と柵で仕切られたコンコースを経由することになる。山側の駅前広場は完成していたが、湖側は工事中のところもあった。
稲枝は、篠原と逆に改札・事務室が上り線上に位置する構造、こちらも山側は駅前広場が完成していたが、湖側は工事中で立ち入り禁止のところが多かった。駅舎の上には太陽光発電装置が付けられ、コンコースのモニターには発電量が表示されていた。
米原では大垣行にホーム別乗換、新幹線としらさぎの乗換客に巻き込まれる。北陸新幹線の米原ルートが消えたのだから、ホーム上接続を検討すべきなのだけどんね。まさか、リニアで余裕が出たら、FGTを走らすとか。
大垣で新快速に乗り継ぎ、正午を過ぎて名古屋に着いた時点では空席があったが、名古屋を出た時には立ち客が出てきた。一番前で刈谷の出口が近かったからね。
豊橋からは3連のために立つ羽目に。といっても新所原で降りるから最初から立つつもりではいた。
新所原の北口は、橋上化前同様天浜線駅舎に接続、新設の南口も舗装され、ロータリーのラインが引かれていた。
新所原からは4両だったが、席がほぼ埋まるくらいの利用率、まだまだ長距離利用者は多い。浜松の手前、高塚の南口はタクシーのりばの屋根が姿を現しているものの、工事中の未舗装状態、北口は自転車置き場だけが整備されていた。自転車置き場は、仮設駅舎跡の南口西側にも作る予定だ。
浜松で掛川行に乗換、ようやく長距離客と分離される。袋井は島式ホームを相対式ホームが挟む構造だが、相対式ホームは使われないので、階段降り口がシャッターで閉ざされてたり、柵で施錠されていたりする。今日降りてきた他の駅より乗降客数が多いのか、上りエスカレーターだけでなく下りエスカレーターも整備されている。南北を行き来するには、神戸寄りにも小さいアンダーパスがあるのだが、自転車も通るので危険が伴う。
袋井から安倍川まで50分移動、安倍川は元々橋上のような構造だったが改修されることになった。南口は東側の立体自転車置き場に連絡、北口はまだ工事中で狭い通路以外は立ち入り禁止だった。
草薙には5時過ぎに到着、天王寺で323系を逃していたら、暗い中での撮影になっていた。駅周辺には、美術館や図書館といったアカデミックなものが多いので、駅舎内装にはレンガが使われ、落ち着いた感じになっている。降り口はスペースの兼ね合いか、階段とエスカレーターが直列、南口は再開発ビルと昔ながらの商店が混在、北口は新幹線の下にあり、近くに静岡銀行の高層ビルがある。
草薙からは熱海行、沼津で宇都宮行に乗換、茅ヶ崎を出るとボックスシートの客が目まぐるしく変わる。品川で常磐線に乗り換え、品川駅での配線切り替え後、初めての品川発常磐線になるわけだが、田町まで4分以上かかっていたのが2分半に短縮した。その代わり、田町から流して走っていた気がしたのだけど。