おはようございます。
⇒
帯締め入れ 房の管理ケース 和の小物「優舞美」 茶木ちさと でございます
着付け教室に通うまでは 自分なりの着付けをしておりましたので
着物を着ても 今日は上手に着付けが出来たな~ 今日はダメだったな~・・・と 出来具合がバラバラでした私!
若かりし頃に教えて頂いた着付けは
ただ着物を着れるようになるというものでしたので
帯のたれの長さは 大体人差し指を使って図っていましたので 何となく着付けは出来ておりました。
しかし お太鼓の大きさは 大体このへんだな~という所で 借り紐を当てて 折り曲げていましたので
その時その時で 違った大きさのお太鼓が出来ていたのです。
以前は 基本を無視と言うより 知らないでお太鼓を作っていたのです。
今現在教えて頂いている先生は
理論を交えて 基本を丁寧に教えてくださるので その基本をもとに着付けが出来
毎回 ある程度同じ大きさのお太鼓が作れて お太鼓を作ることが楽しくなってきています

スムーズに 手が動くようになって とっても嬉しいです(^o^)
同じ着付け教室の先生でも ただ着るようになればよいというやり方で教えられる先生もいらっしゃる中
私たち母娘が教えて頂いている先生は 厳しいところはありますが優しいところもあり・・・
とにかく 「基本が大切」 「習うよりも慣れろ」 「バランスが大切」 「所作の大切さ」 「心の大切さ」
「日本人としての心のあり方」etc.・・・色々なことを教えて頂き 本当に感謝しております母娘です。
と言う事で
今日は名古屋帯のお太鼓の大きさを決めるときの基本的な事は・・・
借り紐を手に持ち 体に巻きつけた半幅になったところに借り紐を当てて お太鼓の大きささを決める・・・
これが基本です。
文章での説明なので イメージしながら読んでみてくださいね。
借り紐が真っ直ぐなるようにしながら中央で帯を上にまくりあげ
両手でたれの長さを一指し指の長さになるようにしながらお太鼓を作る・・・
一応基本を覚えてお太鼓を作ると 毎回同じ大きさのお太鼓を作ることが出来るのです
でも その方その方の 体格により 全体のバランスがありますので
背の高い方は 少しお太鼓が大きくしないとバランスが取れないですし 小柄な方は 少し小さめに・・・
最後はバランスがとっても大切ですが 基本を知った上で 自分なりのお太鼓の大きさを作る・・・
基本を知っておくだけで とってもスムーズに 綺麗にお太鼓が出来るのですよね。
このやり方を教えて頂いて とっても助かっております私です

これが「優舞美」です。⇒
布製なので 帯び締めを傷める事がありません。
⇒
帯び締めの房をマジック部分に入れ込み管理すると 帯び締めが常に綺麗な状態になっています。
【優舞美】ホームページはこちらへ ⇒ http://www.yumaimi.com

 にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村 登録してます!!応援して下さい。
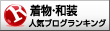 人気ブログランキング登録しています!!こちらも応援して下さい
人気ブログランキング登録しています!!こちらも応援して下さい
⇒

帯締め入れ 房の管理ケース 和の小物「優舞美」 茶木ちさと でございます

着付け教室に通うまでは 自分なりの着付けをしておりましたので
着物を着ても 今日は上手に着付けが出来たな~ 今日はダメだったな~・・・と 出来具合がバラバラでした私!
若かりし頃に教えて頂いた着付けは
ただ着物を着れるようになるというものでしたので
帯のたれの長さは 大体人差し指を使って図っていましたので 何となく着付けは出来ておりました。
しかし お太鼓の大きさは 大体このへんだな~という所で 借り紐を当てて 折り曲げていましたので
その時その時で 違った大きさのお太鼓が出来ていたのです。
以前は 基本を無視と言うより 知らないでお太鼓を作っていたのです。
今現在教えて頂いている先生は
理論を交えて 基本を丁寧に教えてくださるので その基本をもとに着付けが出来
毎回 ある程度同じ大きさのお太鼓が作れて お太鼓を作ることが楽しくなってきています


スムーズに 手が動くようになって とっても嬉しいです(^o^)
同じ着付け教室の先生でも ただ着るようになればよいというやり方で教えられる先生もいらっしゃる中
私たち母娘が教えて頂いている先生は 厳しいところはありますが優しいところもあり・・・
とにかく 「基本が大切」 「習うよりも慣れろ」 「バランスが大切」 「所作の大切さ」 「心の大切さ」
「日本人としての心のあり方」etc.・・・色々なことを教えて頂き 本当に感謝しております母娘です。
と言う事で
今日は名古屋帯のお太鼓の大きさを決めるときの基本的な事は・・・
借り紐を手に持ち 体に巻きつけた半幅になったところに借り紐を当てて お太鼓の大きささを決める・・・
これが基本です。
文章での説明なので イメージしながら読んでみてくださいね。
借り紐が真っ直ぐなるようにしながら中央で帯を上にまくりあげ
両手でたれの長さを一指し指の長さになるようにしながらお太鼓を作る・・・
一応基本を覚えてお太鼓を作ると 毎回同じ大きさのお太鼓を作ることが出来るのです

でも その方その方の 体格により 全体のバランスがありますので
背の高い方は 少しお太鼓が大きくしないとバランスが取れないですし 小柄な方は 少し小さめに・・・
最後はバランスがとっても大切ですが 基本を知った上で 自分なりのお太鼓の大きさを作る・・・
基本を知っておくだけで とってもスムーズに 綺麗にお太鼓が出来るのですよね。
このやり方を教えて頂いて とっても助かっております私です


これが「優舞美」です。⇒

布製なので 帯び締めを傷める事がありません。
⇒

帯び締めの房をマジック部分に入れ込み管理すると 帯び締めが常に綺麗な状態になっています。
【優舞美】ホームページはこちらへ ⇒ http://www.yumaimi.com
にほんブログ村 登録してます!!応援して下さい。











 ・・・
・・・

