黒潮の流れに沿って、太平洋岸に西方から東へと文化はもたらされた、と言うのが私の仮説です。そこで、房総半島の東岸、勝浦市・御宿町の祭りの郷土食「ほうちょう」をたずねています 祭りの日には「ほうちょう」を作って食べる。小麦粉と白玉粉を混ぜて、よく練ってふかしたり、ゆでたりする。それを魚の形に切って、あんこや、黄粉をつけたりして食べる。鍋で煮て食べることもあった。
※大分県あたりでは、「ほうちょう」と言う郷土食がある。それは、うどんのように切って汁で煮る。山梨県の「ほうとう」と似ているので、語源は同じであろう。岩和田集落には、西方より伝わったのであろう。
麦の栽培と、小麦粉の食べ物の発祥は、中東か南米であろうが、タクラマカン砂漠のウイグル族は、小麦粉を直径30センチぐらいの円形に伸ばし、焼いて食べる。南米のインカ系は、石釜の裏側へ小麦粉をせんべい状にしたものを張り付けて焼いて食べる。いずれも香ばしく、せんべいに煮ている。
※勝浦市の屋代良守さんのお話し
勝浦市では、部原・川津と鵜原で今も天王様の祭りの時に「ほうちょう餅」を作る。鵜原では、白と、ヨモギの葉を入れた緑色の2色をつくる。それは、昔のこと、殿さまが見回りに来るのにご馳走が出せない。そこで鮑の腸に似せた2色の餅を出したと言う伝承がある。今でも鵜原地区では作っている。だから「鮑腸」と書く。
以下にインターネットで分かったことをコピーしますので、情報をご提供ください
参考『庖丁』
料理をするときに欠かせない「包丁」。食べ物を切る道具ですよね。「包」という漢字は代字で、本来は『庖丁』と書きます。『庖』の「广(まだれ)」は家の屋根を表しています。「包」は外からまるくおおうという意味なので、『庖』は【食べ物を包んで保管する場所=台所】をいうことばです。一方、『丁』は"よぼろ"という意味で【働き盛りの男子】を表しています。実は『庖丁』は、もともと【料理をする人、料理人】のことをいうのです。中国から伝わったことばで、紀元前に書かれた「荘子」には"庖丁"という料理の名人が登場したということですよ。平安時代、米を主食に魚が中心に食べられていました。料理法は簡単だったため「庖丁(料理人)」にとって、魚をどう切るか、どうさばくかが腕の見せどころだったそうです。宮中の宴会では、客の目の前で魚をさばいて披露したり、貴族が自ら魚をさばいてみせたこともあったといいます。そのため『庖丁』は料理人のことだけでなく、切り方など料理の方法や作法のこと、また料理の腕前などもいうようになったのですね。『庖丁』にさまざまな意味が含まれるので、料理人は「庖丁師」「庖丁人」などともいいました。そして料理のときに使う(小)刀を「庖丁刀」といったのです。「庖丁師」「庖丁人」はその後、職業として定着していき、江戸時代になると「板前」と呼ばれるようになります。今の日本料理の料理人のことですね。こうして『庖丁』は、本来の料理人という意味よりも「庖丁刀」のことと定着していき、一般的となっていったのですね。
ほうとう(餺飥)
山梨県(甲斐国)を中心とした地域で作られる郷土料理。2007年には農林水産省により各地に伝わるふるさとの味の中から決める「農山漁村の郷土料理百選」の中の1つに選ばれている。
調理・具材 おざら 小豆ぼうとう
語源 「餺飥」語源説 ハタク・ハタキモノ語源説 その他の説
小麦粉を練りざっくりと切った麺を、野菜と共に味噌仕立ての汁で煮込んだ料理の一種である。一部地域では小麦粉以外の穀物を使用する場合もある。また、すいとん的な小塊も地域によっては見られることから、必ずしもうどん[1]状の長い形であるとは限らない。一般のうどんのように煮た麺に各種素材や味噌などの調味料を加えた調理法を取ることも稀である。
なお、富士北麓の郡内地方にはほうとうと同一の粉食文化の起源を持つ郷土料理である「吉田のうどん」が存在する。また、県外一般には、「ほうとう鍋」と呼ばれる料理もある。
呼称は「ほうとう」が一般的である。一部地域では異称として「おほうとう」や「ニコミ(ニゴミ)」(山梨県内郡内地方の一部)、「ノシコミ(ノシイレ)」(山梨県内河内地方)と呼ぶ場合もある。
ほうとうの生地は木製のこね鉢(民俗語彙では「ゴンバチ」)で水分を加えた小麦粉を素手で練り、出来上がった生地はのし棒を使って伸ばされ、折り重ねて包丁で幅広に切り刻む[2]。うどんと異なり、生地にはグルテンの生成による麺のコシが求められず、生地を寝かせる手法は少ない。また塩も練り込まないため、麺を湯掻いて塩分を抜く手順が無く、生麺の状態から煮込むところに特色がある。そのため、汁にはとろみが付く。
鮑腸(ほうちょう) (大分市)
★作り方★ (十二~十三人分)
(1)小麦粉一キロと塩三十五グラムを混ぜ、よくこねる。ぬれぶきんに包んで約十五分置く。
(2)生地を二十グラムずつちぎり、手のひらでもんで細長くする。ぬれぶきんをかぶせて約二十分置き、さらに細長く伸ばす。
(3)めんをゆがき、冷水に取り出す。一人分をどんぶりに盛り、熱湯を注ぐ。
(4)シイタケ、だし昆布、いりこを別の鍋で煮込み、だしを作る。昆布を取り出し、削り節を入れて火を止める。しょうゆ、みりん、塩で味を調える。
(5)だしをふきんでこし、薬味を加えて出来上がり。
▲手でもんで「鮑腸」のめんを2メートル以上に伸ばしていく
つい最近まで、年に数回、地域のイベントでしか味わえなかった料理が大分市にある。同市戸次地区に伝わる「鮑腸」だ。見た目はうどんのようだが、一本のめんの長さは二メートル以上あり、「はしごにのぼって食べる」という話もあるほど。この長いめんをつゆにつけて食べる。
名前の由来は諸説あるが、戦国時代、アワビ(鮑)が不漁だった時に、大友宗麟の家来が小麦粉をこねてアワビの腸に似せたものを作ったら、アワビ好きの宗麟がとても喜んだ―というのが最も有力。
現在は「戸次鮑腸保存会」(保月美智子会長・二十人)が伝統を受け継ぐ。保存会は一九六七年に発足。伝統の味を次の世代に伝えていくため、毎月一回、第三土曜日に練習会を開いている。
「ここに来るとよう笑うけん、しわがのびるんよ」とメンバーが話すように、練習会は和気あいあいのムード。保月会長は「みんなが上達するために、味や出来具合について率直に話せる、楽しい雰囲気をつくることが私の仕事です」と話す。
めんを作る様子は、まるであやとりをしているように見える。手でこねた生地をもんで細長くする。それをさらにこよりのように細く伸ばしていくと長いめんになる。ゴムのようにどんどん伸ばしていくのだが、不思議なことに切れない。生地をしっかりこねているからだ。
めんをつけるつゆの味も先輩のアドバイスを受けながら調える。四種類の食材でだしを取り、しょうゆとみりんで味を付ける。薬味はカボス、ゴマ、ネギ、ショウガ。食材にはこだわっており、地元でとれたものだけを使う。
めんはかみ応えがある。つゆはだしの甘みにカボスのさわやかな酸味とショウガのほどよい辛さが見事にマッチ。めんがツルツルと口の中に吸い込まれていく。 鮑腸はもともと、お祝いや法事の席など特別な時に振る舞われた。調理はすべて手作業。時間と手間をかけるため、家人の”もてなし”の心がストレートに相手に伝わる料理だ。
手間がかかりすぎるせいか、今では一般の家庭ではほとんどつくらなくなった。三月までは「大分市生活文化展」「元気戸次まつり」などの会場でしか食べることができなかったが、四月から練習会で作った約四十食を地区内の滋野米穀店直売所で販売を始めた。人気があり、一時間ほどで売り切れてしまうという。
※大分県あたりでは、「ほうちょう」と言う郷土食がある。それは、うどんのように切って汁で煮る。山梨県の「ほうとう」と似ているので、語源は同じであろう。岩和田集落には、西方より伝わったのであろう。
麦の栽培と、小麦粉の食べ物の発祥は、中東か南米であろうが、タクラマカン砂漠のウイグル族は、小麦粉を直径30センチぐらいの円形に伸ばし、焼いて食べる。南米のインカ系は、石釜の裏側へ小麦粉をせんべい状にしたものを張り付けて焼いて食べる。いずれも香ばしく、せんべいに煮ている。
※勝浦市の屋代良守さんのお話し
勝浦市では、部原・川津と鵜原で今も天王様の祭りの時に「ほうちょう餅」を作る。鵜原では、白と、ヨモギの葉を入れた緑色の2色をつくる。それは、昔のこと、殿さまが見回りに来るのにご馳走が出せない。そこで鮑の腸に似せた2色の餅を出したと言う伝承がある。今でも鵜原地区では作っている。だから「鮑腸」と書く。
以下にインターネットで分かったことをコピーしますので、情報をご提供ください
参考『庖丁』
料理をするときに欠かせない「包丁」。食べ物を切る道具ですよね。「包」という漢字は代字で、本来は『庖丁』と書きます。『庖』の「广(まだれ)」は家の屋根を表しています。「包」は外からまるくおおうという意味なので、『庖』は【食べ物を包んで保管する場所=台所】をいうことばです。一方、『丁』は"よぼろ"という意味で【働き盛りの男子】を表しています。実は『庖丁』は、もともと【料理をする人、料理人】のことをいうのです。中国から伝わったことばで、紀元前に書かれた「荘子」には"庖丁"という料理の名人が登場したということですよ。平安時代、米を主食に魚が中心に食べられていました。料理法は簡単だったため「庖丁(料理人)」にとって、魚をどう切るか、どうさばくかが腕の見せどころだったそうです。宮中の宴会では、客の目の前で魚をさばいて披露したり、貴族が自ら魚をさばいてみせたこともあったといいます。そのため『庖丁』は料理人のことだけでなく、切り方など料理の方法や作法のこと、また料理の腕前などもいうようになったのですね。『庖丁』にさまざまな意味が含まれるので、料理人は「庖丁師」「庖丁人」などともいいました。そして料理のときに使う(小)刀を「庖丁刀」といったのです。「庖丁師」「庖丁人」はその後、職業として定着していき、江戸時代になると「板前」と呼ばれるようになります。今の日本料理の料理人のことですね。こうして『庖丁』は、本来の料理人という意味よりも「庖丁刀」のことと定着していき、一般的となっていったのですね。
ほうとう(餺飥)
山梨県(甲斐国)を中心とした地域で作られる郷土料理。2007年には農林水産省により各地に伝わるふるさとの味の中から決める「農山漁村の郷土料理百選」の中の1つに選ばれている。
調理・具材 おざら 小豆ぼうとう
語源 「餺飥」語源説 ハタク・ハタキモノ語源説 その他の説
小麦粉を練りざっくりと切った麺を、野菜と共に味噌仕立ての汁で煮込んだ料理の一種である。一部地域では小麦粉以外の穀物を使用する場合もある。また、すいとん的な小塊も地域によっては見られることから、必ずしもうどん[1]状の長い形であるとは限らない。一般のうどんのように煮た麺に各種素材や味噌などの調味料を加えた調理法を取ることも稀である。
なお、富士北麓の郡内地方にはほうとうと同一の粉食文化の起源を持つ郷土料理である「吉田のうどん」が存在する。また、県外一般には、「ほうとう鍋」と呼ばれる料理もある。
呼称は「ほうとう」が一般的である。一部地域では異称として「おほうとう」や「ニコミ(ニゴミ)」(山梨県内郡内地方の一部)、「ノシコミ(ノシイレ)」(山梨県内河内地方)と呼ぶ場合もある。
ほうとうの生地は木製のこね鉢(民俗語彙では「ゴンバチ」)で水分を加えた小麦粉を素手で練り、出来上がった生地はのし棒を使って伸ばされ、折り重ねて包丁で幅広に切り刻む[2]。うどんと異なり、生地にはグルテンの生成による麺のコシが求められず、生地を寝かせる手法は少ない。また塩も練り込まないため、麺を湯掻いて塩分を抜く手順が無く、生麺の状態から煮込むところに特色がある。そのため、汁にはとろみが付く。
鮑腸(ほうちょう) (大分市)
★作り方★ (十二~十三人分)
(1)小麦粉一キロと塩三十五グラムを混ぜ、よくこねる。ぬれぶきんに包んで約十五分置く。
(2)生地を二十グラムずつちぎり、手のひらでもんで細長くする。ぬれぶきんをかぶせて約二十分置き、さらに細長く伸ばす。
(3)めんをゆがき、冷水に取り出す。一人分をどんぶりに盛り、熱湯を注ぐ。
(4)シイタケ、だし昆布、いりこを別の鍋で煮込み、だしを作る。昆布を取り出し、削り節を入れて火を止める。しょうゆ、みりん、塩で味を調える。
(5)だしをふきんでこし、薬味を加えて出来上がり。
▲手でもんで「鮑腸」のめんを2メートル以上に伸ばしていく
つい最近まで、年に数回、地域のイベントでしか味わえなかった料理が大分市にある。同市戸次地区に伝わる「鮑腸」だ。見た目はうどんのようだが、一本のめんの長さは二メートル以上あり、「はしごにのぼって食べる」という話もあるほど。この長いめんをつゆにつけて食べる。
名前の由来は諸説あるが、戦国時代、アワビ(鮑)が不漁だった時に、大友宗麟の家来が小麦粉をこねてアワビの腸に似せたものを作ったら、アワビ好きの宗麟がとても喜んだ―というのが最も有力。
現在は「戸次鮑腸保存会」(保月美智子会長・二十人)が伝統を受け継ぐ。保存会は一九六七年に発足。伝統の味を次の世代に伝えていくため、毎月一回、第三土曜日に練習会を開いている。
「ここに来るとよう笑うけん、しわがのびるんよ」とメンバーが話すように、練習会は和気あいあいのムード。保月会長は「みんなが上達するために、味や出来具合について率直に話せる、楽しい雰囲気をつくることが私の仕事です」と話す。
めんを作る様子は、まるであやとりをしているように見える。手でこねた生地をもんで細長くする。それをさらにこよりのように細く伸ばしていくと長いめんになる。ゴムのようにどんどん伸ばしていくのだが、不思議なことに切れない。生地をしっかりこねているからだ。
めんをつけるつゆの味も先輩のアドバイスを受けながら調える。四種類の食材でだしを取り、しょうゆとみりんで味を付ける。薬味はカボス、ゴマ、ネギ、ショウガ。食材にはこだわっており、地元でとれたものだけを使う。
めんはかみ応えがある。つゆはだしの甘みにカボスのさわやかな酸味とショウガのほどよい辛さが見事にマッチ。めんがツルツルと口の中に吸い込まれていく。 鮑腸はもともと、お祝いや法事の席など特別な時に振る舞われた。調理はすべて手作業。時間と手間をかけるため、家人の”もてなし”の心がストレートに相手に伝わる料理だ。
手間がかかりすぎるせいか、今では一般の家庭ではほとんどつくらなくなった。三月までは「大分市生活文化展」「元気戸次まつり」などの会場でしか食べることができなかったが、四月から練習会で作った約四十食を地区内の滋野米穀店直売所で販売を始めた。人気があり、一時間ほどで売り切れてしまうという。










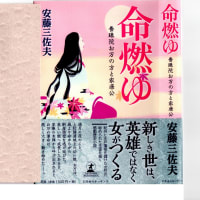
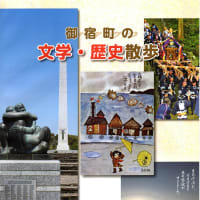
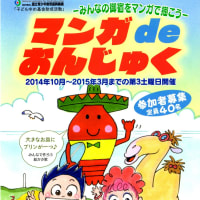



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます