知人に勧められて小説を講談用にまとめましたので、あとは文体を工夫して仕上げてもらいます
講談 養珠院お万の方 あらすじ
「徳川御三家」と言えば泣く子も黙る尾張と紀州と水戸藩でありまする。この紀州家と水戸家の藩祖は、房総正木家の息女お万さまのお子さまであります。
映画やテレビで「この紋所が目に入らぬか!」と、葵の紋の印籠(いんろう)を掲げるのは、水戸黄門様の付け人の助さん、格さんのお役目ですが、この黄門さまは、じつは房総勝浦城の領主正木家の御息女お万さまのお孫の一人なのです。
お万さまは、天正5年春の4月に勝浦城で産声をあげられました。幼い時から利発で可愛いので城中の者たちの人気者で御座いました。ところが、3歳の時のことであります。にわかにご城内が騒がしくなり、お万さまはお母上に背負われて落ち延びるのであります。これは、今でも土地の人々に語り継がれる「お万布さらし」の話であります。
またこんな歌も御座います。
三つとせぇ
身の毛もよだつ絶壁を
布をさらしてお母様
背負うて城を抜け出だす
これは、大多喜城の正木大膳亮憲時(まさきたいぜんのりとき)が安房上総を自分の領地にしようと兵を挙げたこの争いは、お万さまのお父上の正木頼忠(よりただ)と、安房の里見氏によって無事に治められたのですが、幼いお万さまには、いかほどに怖いことでありましょうか、後々までこの世の平和を願い、各地にお寺を寄進された理由は、この幼心からで御座いましょう。
お万様は、戦国の世のならいで戦火を逃れ、苦労に苦労を重ねられますが、三島の宿で徳川家康公に見初められて、めでたく大奥に入ります。何しろ近郷近在に誰知らぬ者のいない器量よしで働き者で御座います。
それは、徳川家の記録には、このように書かれております。
「背丈高くして、器量よく、博学多識にして、文筆を良くし、謡曲音楽を好み、薙刀(なぎなた)は達人の域にあり、仏教を研鑽して信心深く、じつに優れたる大賢婦なり」とあります。
まぁ言ってみれば、マリリンモンロウとブリジットバルドウとオードリィヘップバーンを足して、壇密を掛けても余りある才色兼備の女性でありました。
何しろ土地の者たちは
「お万髪の毛 七尋八尋(ななひろやひろ)
三つつなげば 江戸までとどく」
とまで歌われております。それほどの評判の美女でありましたから権勢並ぶもののない家康公も一目ぼれであったのです。家康公51歳、お万さま18歳の時に御座いますが、家康公には正室が長い間おりませんから若いお万さまを「万よ、万よ」と可愛がられたのです。
仲人を務めた人物は、韮山(にらやま)の代官として名高い第28代江川太郎左衛門英長さまです。
この江川家は、大御所の覚え目出度く、江戸時代の2百数十年にわたって代々韮山の代官の地位にありましたが、こういう例はほかにはないのです。
みなさんは「韮山の反射炉」が世界文化遺産に推薦されたことをご存知でしょう。あれも幕末の江川代官家の大事業で、第36代目の英龍(えいりゅう・ひでたつ)様と37代目の英敏(ひでとし)様によってなされたのです。
ところで、なかなか子宝に恵まれないお万の方は、家康公のお許しを得て子宝の湯として有名な伊豆の吉奈の湯に出向きました。ここはお万さまがお母上と弟と娘時代に暮らした思い出の地であります。この温泉でゆっくりとして、近くの善名寺(ぜんみょうじ)に「どうか、子宝に恵まれますように」と、朝に夕べにお祈りして、家康公のおられる伏見城に帰られたのです。
天城小唄には、こう歌われております。
「所かわれば吉奈にござれ
吉奈子宝 湯の香り
さっても昔のお坊様
ここに杖突き お湯が出て
お湯が出たのでお万さま
来ればめでたや 子が出来て」
関ヶ原や大阪の陣の戦いが終わると、この日本は戦国乱世の世から世界にも稀な平和な国になりましたが、その礎を築いたのは、大御所家康公と、信仰心の厚い側室お万の方に御座います。
家康公も落ち着いてお万さまと伏見城で仲睦まじくお暮しになられましたので、2年続けてお万さまはご懐妊なされ、男のお子さま「長福丸」君と「鶴千代」君の二人をもうけられたのであります。これは、側室にとっては大手柄のことで、ますます大御所様のご寵愛を独り占めに致しました。
世界の王侯貴族は、多くの女性を抱えておりましたが、その理由の一つには子孫を絶やさないためと言うことがありましたから続けて二人のお世継ぎを出生なされたお万さまは、大奥に並ぶもののない存在となりました。
大御所様は、すでに60歳にもなられていて、急に二人もの男の子を授かりましたからそれはそれは大変なお喜びようで御座いました。お忙しいのにもかかわらず朝に夕べにお子さまのご様子をのぞきに来ました。それはもうおじい様と孫のような年齢の差ですからこれを「孫かわいがり」と言うのでしょうか。
「おお、よしよし。笑いおった」
「兄の方は、白い歯が出て来たではないか」
「乳は足りておるかのう」
「風邪をひかすではないぞ」
などと、毎日うるさいぐらいのです。
侍女たちは「大御所様の子煩悩にもお困り申しまする」などと陰口をきいているほどでした。
江戸から駿府城に移られて、お子様もお元気な日々でしたが、一大事が起こったのであります。
それは、お万さまが若いころより帰依なさっておられる身延山久遠寺のご住職日遠上人が大御所様のお怒りに触れてしまったのです。
徳川家の信仰する芝増上寺の浄土宗のお坊様と、お万さまの信仰する日蓮宗のお坊様とが宗派論争を江戸城で行ったのであります。その時、日蓮宗の主張が負けたので、身延山の日遠上人がもう1度論争をさせてほしいと申し出たのです。大御所様は「もう宗派の論争はやめることじゃ」と前もって言い渡してあったので激怒なされて、日遠上人を安倍川の河原で打ち首にすることを命じたのであります。
愛するお万さまが、いくら取り成しても大御所様のお怒りは解けずに処刑の日が近づきました。
お万さまは、白装束を2着、心を籠めて手縫いをして、1着を身延山の日遠上人にお届けなされ、処刑の日を待っておりました。
とうとうその日がまいりました。お万さまは、白装束を身につけて朝早くに大御所様のお部屋にうかがいました。
「何じゃ、お万よ、こんな早朝に?」
と大御所様が振り返ると、白装束のお万さまが、額を床に擦り付けて
「今朝は今生のお別れに参りました。わが子、二人の行く末をよろしゅうお願い致しまする」
と、きっぱりと申しました。
「ううむ、そちは、そこまで信仰が厚いのでじゃな。困ったことよのう」
大御所様は絶句なされて静かに目をつむられていたそうに御座りまする。
「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経」
お万さまは、早駕籠で処刑場の安倍川を目指した。日遠上人と共にお命を絶とうと言う思いが募るばかりであった。
今にも上人様が磔柱に縛られようとした時であった。
ドッ、ドッ、ドッ、ド、ド、ド、早馬が駆けつけて来て
「上意、上意、処刑を待たれよ!」
と言う大声がした。
竹矢来の外でお題目を唱えていた多くの人々は、その声の方を見た。駿府城の御家老様が、馬上から降りて来られて申し伝えた。
「大御所様のご上意であるぞ。日遠上人の処刑はなきものとする」
そこへお万さまもお着きになって、日遠上人に申された。
「宜しゅう御座りまするか、ご上人様、しばらくは伊豆の下田の乗安寺にてご静養下され。このお駕籠をお使い下されば、今日中にはお着きになられると存じまする」
今でもこの時のお駕籠は乗安寺に置かれているので河津桜の花時にお寄り下されよ。
このお万の方のお話は、口から口へと伝えられて、ついには京の都の後陽成天皇のお耳にまでも達したので、帝はとても感激なされて「南無妙法蓮華経」と書かれた大きな書と、直筆の御書状を賜われたのでありまする。
慶長14年、お万さまは、かねてより念願の菩提寺を身延山の麓の大野に建立し、「大野山本遠寺」と名付け、ここに日遠上人を後にお迎えします。
日蓮聖人の「いづくにて死に候とも墓をば身延の沢にせさせ候べく候」にならい、ご自分もこの地にお墓を考えたのでありまする。
元和2年4月17日家康公は駿府城にてご逝去なさり、「東照大権現」として久能山に埋葬されまする。後に日光東照宮が造営されて、ますます家康公の御遺徳は世に広まりまする。
お万の方は感応寺にて受戒剃髪をなさり「養珠院」と称しまするが、当時の女人貴族は、連れ合いの逝去にともない院号をいただくのが常でありました。
寛永17年、家康公の25回忌を本遠寺にて行い、崇敬なさる七面大天女の祀られる七面山に周囲の反対を押し切り登山を致します。女人禁制の修験道の1400メートル余りのきついお山でありまするが、養珠夫人の御威光にてそれ以後は女人も登れるようになりまする。日蓮聖人の教えには、男女の差別はないと言うかねてからの思いを実行なされたのでありまする。
晩年の養珠院さまは、江戸の紀州家屋敷にお暮しになられ、水戸家の孫の光坊(のちの徳川光圀)などに囲まれ、文筆と読経三昧の生活をしておりましたが,承応2年8月21日、御長男の紀州家藩祖頼宜(よりのぶ)公、次男の水戸家藩祖頼房(よりふさ)公などに看取られてご逝去なされまする。享年77歳、波乱万丈の清廉潔白の生涯でありまする。
その間、身延山久遠寺や小湊誕生寺、さらに八日市場飯高寺など全国各地の寺院数百か所への喜捨と三島玉沢の妙法華寺を初めとする多くの寺院の建立に浄財を献じ、さらに世の弱者へのいたわりの救済は数を知れず、人々から惜しまれて永遠の眠りに就かれたのであります。
「養珠院妙紹日心大姉」の御戒名は大野山本遠寺の小高い墓地の石碑に今も刻まれて参詣の人を静かに見守っておられまする。font>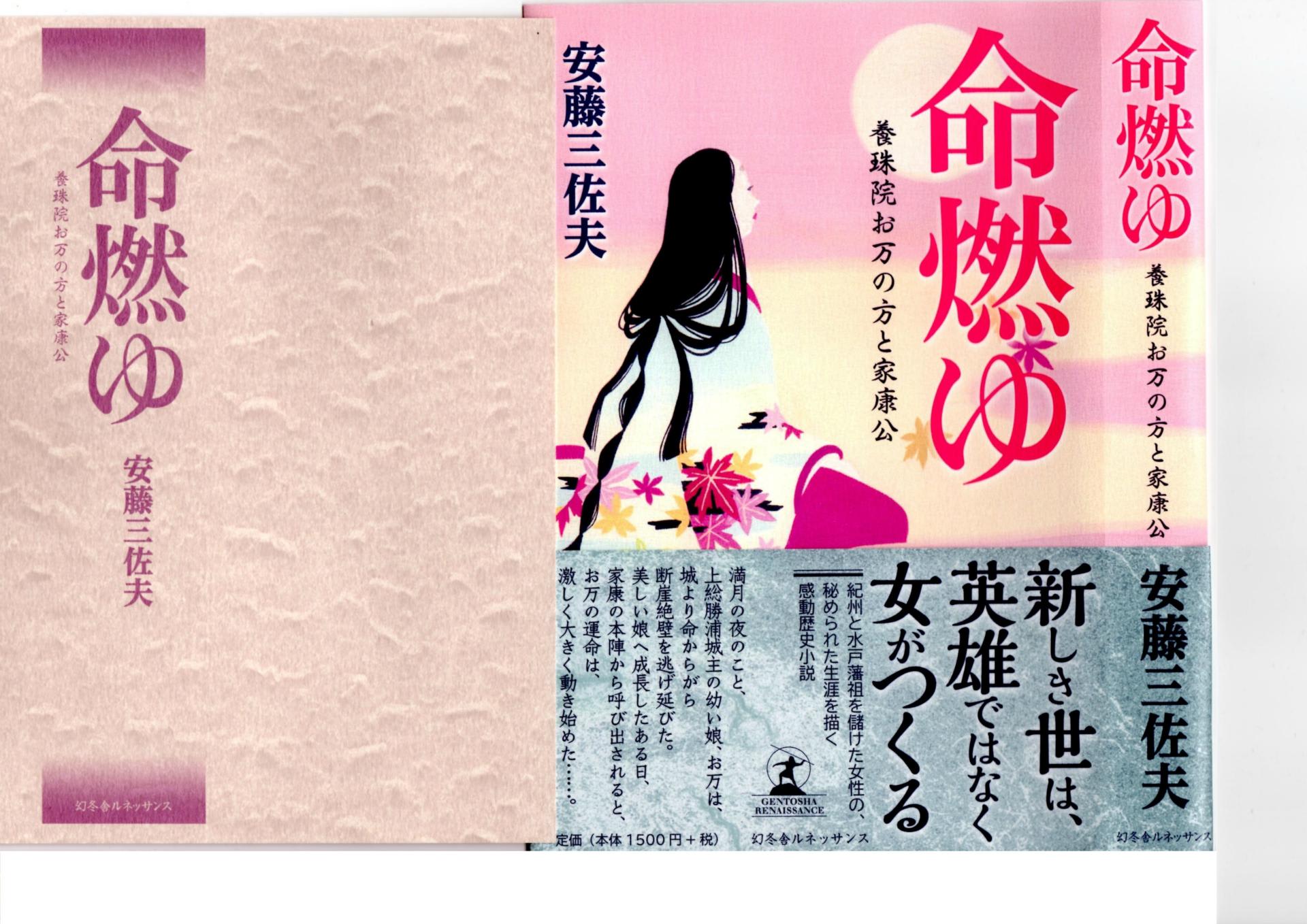
※本遠寺=ほんのんじ 養珠院=ようじゅいん 久遠寺=くおんじ 七面山=しちめんざん
修験道=しゅげんどう 日遠上人=にちおんしょうにん 駿府城=すんぷじょう
飯高寺=はんこうじ 吉奈=よしな
講談 養珠院お万の方 あらすじ
「徳川御三家」と言えば泣く子も黙る尾張と紀州と水戸藩でありまする。この紀州家と水戸家の藩祖は、房総正木家の息女お万さまのお子さまであります。
映画やテレビで「この紋所が目に入らぬか!」と、葵の紋の印籠(いんろう)を掲げるのは、水戸黄門様の付け人の助さん、格さんのお役目ですが、この黄門さまは、じつは房総勝浦城の領主正木家の御息女お万さまのお孫の一人なのです。
お万さまは、天正5年春の4月に勝浦城で産声をあげられました。幼い時から利発で可愛いので城中の者たちの人気者で御座いました。ところが、3歳の時のことであります。にわかにご城内が騒がしくなり、お万さまはお母上に背負われて落ち延びるのであります。これは、今でも土地の人々に語り継がれる「お万布さらし」の話であります。
またこんな歌も御座います。
三つとせぇ
身の毛もよだつ絶壁を
布をさらしてお母様
背負うて城を抜け出だす
これは、大多喜城の正木大膳亮憲時(まさきたいぜんのりとき)が安房上総を自分の領地にしようと兵を挙げたこの争いは、お万さまのお父上の正木頼忠(よりただ)と、安房の里見氏によって無事に治められたのですが、幼いお万さまには、いかほどに怖いことでありましょうか、後々までこの世の平和を願い、各地にお寺を寄進された理由は、この幼心からで御座いましょう。
お万様は、戦国の世のならいで戦火を逃れ、苦労に苦労を重ねられますが、三島の宿で徳川家康公に見初められて、めでたく大奥に入ります。何しろ近郷近在に誰知らぬ者のいない器量よしで働き者で御座います。
それは、徳川家の記録には、このように書かれております。
「背丈高くして、器量よく、博学多識にして、文筆を良くし、謡曲音楽を好み、薙刀(なぎなた)は達人の域にあり、仏教を研鑽して信心深く、じつに優れたる大賢婦なり」とあります。
まぁ言ってみれば、マリリンモンロウとブリジットバルドウとオードリィヘップバーンを足して、壇密を掛けても余りある才色兼備の女性でありました。
何しろ土地の者たちは
「お万髪の毛 七尋八尋(ななひろやひろ)
三つつなげば 江戸までとどく」
とまで歌われております。それほどの評判の美女でありましたから権勢並ぶもののない家康公も一目ぼれであったのです。家康公51歳、お万さま18歳の時に御座いますが、家康公には正室が長い間おりませんから若いお万さまを「万よ、万よ」と可愛がられたのです。
仲人を務めた人物は、韮山(にらやま)の代官として名高い第28代江川太郎左衛門英長さまです。
この江川家は、大御所の覚え目出度く、江戸時代の2百数十年にわたって代々韮山の代官の地位にありましたが、こういう例はほかにはないのです。
みなさんは「韮山の反射炉」が世界文化遺産に推薦されたことをご存知でしょう。あれも幕末の江川代官家の大事業で、第36代目の英龍(えいりゅう・ひでたつ)様と37代目の英敏(ひでとし)様によってなされたのです。
ところで、なかなか子宝に恵まれないお万の方は、家康公のお許しを得て子宝の湯として有名な伊豆の吉奈の湯に出向きました。ここはお万さまがお母上と弟と娘時代に暮らした思い出の地であります。この温泉でゆっくりとして、近くの善名寺(ぜんみょうじ)に「どうか、子宝に恵まれますように」と、朝に夕べにお祈りして、家康公のおられる伏見城に帰られたのです。
天城小唄には、こう歌われております。
「所かわれば吉奈にござれ
吉奈子宝 湯の香り
さっても昔のお坊様
ここに杖突き お湯が出て
お湯が出たのでお万さま
来ればめでたや 子が出来て」
関ヶ原や大阪の陣の戦いが終わると、この日本は戦国乱世の世から世界にも稀な平和な国になりましたが、その礎を築いたのは、大御所家康公と、信仰心の厚い側室お万の方に御座います。
家康公も落ち着いてお万さまと伏見城で仲睦まじくお暮しになられましたので、2年続けてお万さまはご懐妊なされ、男のお子さま「長福丸」君と「鶴千代」君の二人をもうけられたのであります。これは、側室にとっては大手柄のことで、ますます大御所様のご寵愛を独り占めに致しました。
世界の王侯貴族は、多くの女性を抱えておりましたが、その理由の一つには子孫を絶やさないためと言うことがありましたから続けて二人のお世継ぎを出生なされたお万さまは、大奥に並ぶもののない存在となりました。
大御所様は、すでに60歳にもなられていて、急に二人もの男の子を授かりましたからそれはそれは大変なお喜びようで御座いました。お忙しいのにもかかわらず朝に夕べにお子さまのご様子をのぞきに来ました。それはもうおじい様と孫のような年齢の差ですからこれを「孫かわいがり」と言うのでしょうか。
「おお、よしよし。笑いおった」
「兄の方は、白い歯が出て来たではないか」
「乳は足りておるかのう」
「風邪をひかすではないぞ」
などと、毎日うるさいぐらいのです。
侍女たちは「大御所様の子煩悩にもお困り申しまする」などと陰口をきいているほどでした。
江戸から駿府城に移られて、お子様もお元気な日々でしたが、一大事が起こったのであります。
それは、お万さまが若いころより帰依なさっておられる身延山久遠寺のご住職日遠上人が大御所様のお怒りに触れてしまったのです。
徳川家の信仰する芝増上寺の浄土宗のお坊様と、お万さまの信仰する日蓮宗のお坊様とが宗派論争を江戸城で行ったのであります。その時、日蓮宗の主張が負けたので、身延山の日遠上人がもう1度論争をさせてほしいと申し出たのです。大御所様は「もう宗派の論争はやめることじゃ」と前もって言い渡してあったので激怒なされて、日遠上人を安倍川の河原で打ち首にすることを命じたのであります。
愛するお万さまが、いくら取り成しても大御所様のお怒りは解けずに処刑の日が近づきました。
お万さまは、白装束を2着、心を籠めて手縫いをして、1着を身延山の日遠上人にお届けなされ、処刑の日を待っておりました。
とうとうその日がまいりました。お万さまは、白装束を身につけて朝早くに大御所様のお部屋にうかがいました。
「何じゃ、お万よ、こんな早朝に?」
と大御所様が振り返ると、白装束のお万さまが、額を床に擦り付けて
「今朝は今生のお別れに参りました。わが子、二人の行く末をよろしゅうお願い致しまする」
と、きっぱりと申しました。
「ううむ、そちは、そこまで信仰が厚いのでじゃな。困ったことよのう」
大御所様は絶句なされて静かに目をつむられていたそうに御座りまする。
「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経」
お万さまは、早駕籠で処刑場の安倍川を目指した。日遠上人と共にお命を絶とうと言う思いが募るばかりであった。
今にも上人様が磔柱に縛られようとした時であった。
ドッ、ドッ、ドッ、ド、ド、ド、早馬が駆けつけて来て
「上意、上意、処刑を待たれよ!」
と言う大声がした。
竹矢来の外でお題目を唱えていた多くの人々は、その声の方を見た。駿府城の御家老様が、馬上から降りて来られて申し伝えた。
「大御所様のご上意であるぞ。日遠上人の処刑はなきものとする」
そこへお万さまもお着きになって、日遠上人に申された。
「宜しゅう御座りまするか、ご上人様、しばらくは伊豆の下田の乗安寺にてご静養下され。このお駕籠をお使い下されば、今日中にはお着きになられると存じまする」
今でもこの時のお駕籠は乗安寺に置かれているので河津桜の花時にお寄り下されよ。
このお万の方のお話は、口から口へと伝えられて、ついには京の都の後陽成天皇のお耳にまでも達したので、帝はとても感激なされて「南無妙法蓮華経」と書かれた大きな書と、直筆の御書状を賜われたのでありまする。
慶長14年、お万さまは、かねてより念願の菩提寺を身延山の麓の大野に建立し、「大野山本遠寺」と名付け、ここに日遠上人を後にお迎えします。
日蓮聖人の「いづくにて死に候とも墓をば身延の沢にせさせ候べく候」にならい、ご自分もこの地にお墓を考えたのでありまする。
元和2年4月17日家康公は駿府城にてご逝去なさり、「東照大権現」として久能山に埋葬されまする。後に日光東照宮が造営されて、ますます家康公の御遺徳は世に広まりまする。
お万の方は感応寺にて受戒剃髪をなさり「養珠院」と称しまするが、当時の女人貴族は、連れ合いの逝去にともない院号をいただくのが常でありました。
寛永17年、家康公の25回忌を本遠寺にて行い、崇敬なさる七面大天女の祀られる七面山に周囲の反対を押し切り登山を致します。女人禁制の修験道の1400メートル余りのきついお山でありまするが、養珠夫人の御威光にてそれ以後は女人も登れるようになりまする。日蓮聖人の教えには、男女の差別はないと言うかねてからの思いを実行なされたのでありまする。
晩年の養珠院さまは、江戸の紀州家屋敷にお暮しになられ、水戸家の孫の光坊(のちの徳川光圀)などに囲まれ、文筆と読経三昧の生活をしておりましたが,承応2年8月21日、御長男の紀州家藩祖頼宜(よりのぶ)公、次男の水戸家藩祖頼房(よりふさ)公などに看取られてご逝去なされまする。享年77歳、波乱万丈の清廉潔白の生涯でありまする。
その間、身延山久遠寺や小湊誕生寺、さらに八日市場飯高寺など全国各地の寺院数百か所への喜捨と三島玉沢の妙法華寺を初めとする多くの寺院の建立に浄財を献じ、さらに世の弱者へのいたわりの救済は数を知れず、人々から惜しまれて永遠の眠りに就かれたのであります。
「養珠院妙紹日心大姉」の御戒名は大野山本遠寺の小高い墓地の石碑に今も刻まれて参詣の人を静かに見守っておられまする。font>
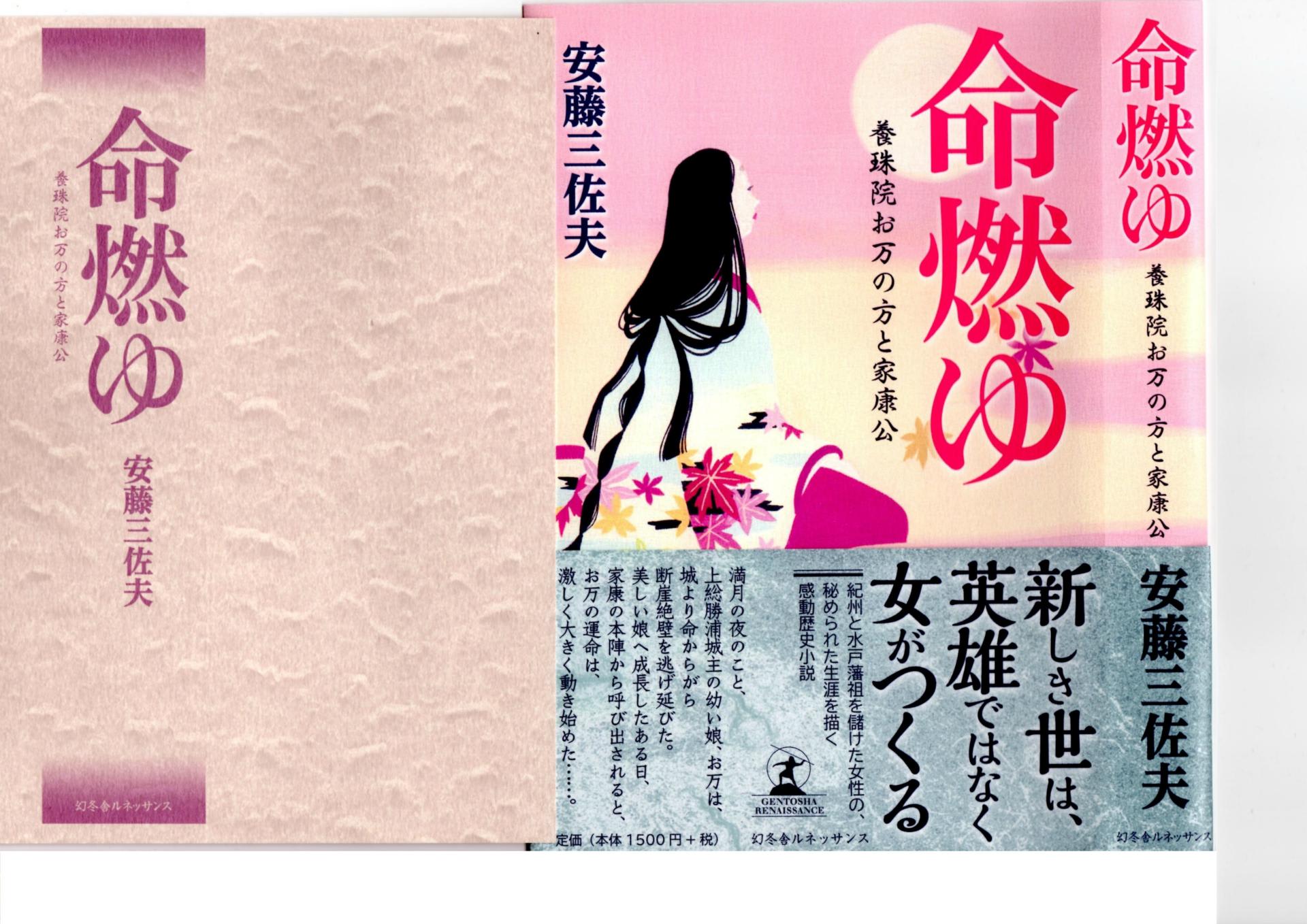
※本遠寺=ほんのんじ 養珠院=ようじゅいん 久遠寺=くおんじ 七面山=しちめんざん
修験道=しゅげんどう 日遠上人=にちおんしょうにん 駿府城=すんぷじょう
飯高寺=はんこうじ 吉奈=よしな









