 利根川を銚子に引き、江戸の水害を防いだが、印旛沼周辺は大洪水!
利根川を銚子に引き、江戸の水害を防いだが、印旛沼周辺は大洪水!天正18(1590)年に徳川家康が江戸に入府すると、今まで江戸(東京)湾に注いでいた利根川を洪水から町を守るために太平洋へ流路を付け替える工事にかかった。
「利根川東遷事業」
1、文禄3(1594)年―「会の川」しめきり
2、元和7(1621)年―新川どおり(渡良瀬川の結合)・赤堀川の開削工事
3、寛永年代(1624~1643)―江戸川・権現堂川・逆川の開削工事
4、承応3(1654)年―赤堀川の開削通水工事
60年にわたる大工事で江戸の町を洪水から守り、灌漑・新田開発・船運整備に成功した。しかし、これによって印旛沼は3年に1度の洪水に見舞われるようになってしまった。
そこで、印旛沼の水を江戸湾に流し洪水を防ぎ、さらに新田開発・船運に役立てようとする工事が、江戸時代に3度も行われたが、すべて失敗に終わった。
1、享保の掘割工事
享保9(1724)年、平戸村名主染谷源右衛門らが平戸川~花見川間、約17kmの掘割工事を幕府に願い出て、6,000両の資金が貸与されて許可される。工事を始めて2年後に花島観音周辺の軟弱の泥土と資金難(請負人78名破産)で工事は挫折した。(総工費は約30万両)
2、天明の掘割工事
安永9(1780)年、草深新田村名主平左衛門と島田村名主治郎兵衛が、平戸川~花見川間の掘割工事と、長門川(利根川~印旛沼)に3基の扉(水門)設置の目論見書を幕府に提出。老中田沼意次によって、天明2(1782)年7月、掘割工事に着工した。しかし、不運にも3分の2が進捗していた工事現場の諸施設が、天明6年の大豪雨で堆積していた浅間山の火山灰の汚泥によってすべて破壊されてしまった。工事は再開の予定であったが、将軍家治が死去し、意次が失脚して中止になってしまった。
3、天保の掘割工事
老中水野忠邦「天保の改革」に並行して、天保14(1843)年に洪水防止と水運整備を目的として、次の5藩に掘割工事を命じた。
(平戸~横戸)沼津藩 水野忠武 (横戸~柏井)庄内藩 酒井忠発
(柏井~花島)鳥取藩 松平慶行 (花島~畑) 請西藩 林 忠旭
(畑~検見川浜)秋月藩 黒田長元※手伝い普請(藩が資材や人足を負担)
工事は3ヶ月で9割がたは進捗したが、花島周辺が難航し、また、老中水野忠邦が失脚し、弘化元(1844)年6月10日に工事は中止された。
印旛沼周辺の住民の願いであった干拓工事は、長い中断の末に終戦による海外からの引揚者の就労対策と食料対策として「印旛沼手賀沼国営干拓事業」が、昭和21年に始められ、昭和38年には「印旛沼開発事業」として京葉工業地帯の工業用水としても利用することになった。
干拓・水害防止・用水供給のために沼の中央部を埋め立て、西部と北部に分け水路で結び、約1310haの貯水池と約934haの干拓地を昭和44(1969)年3月、ついに造成された。この間、じつに245年の長い歳月がかかったのである。











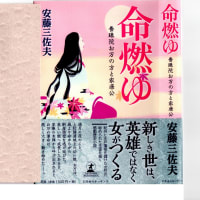
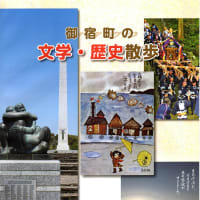
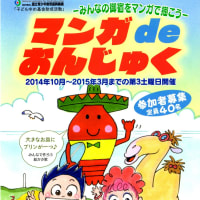



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます