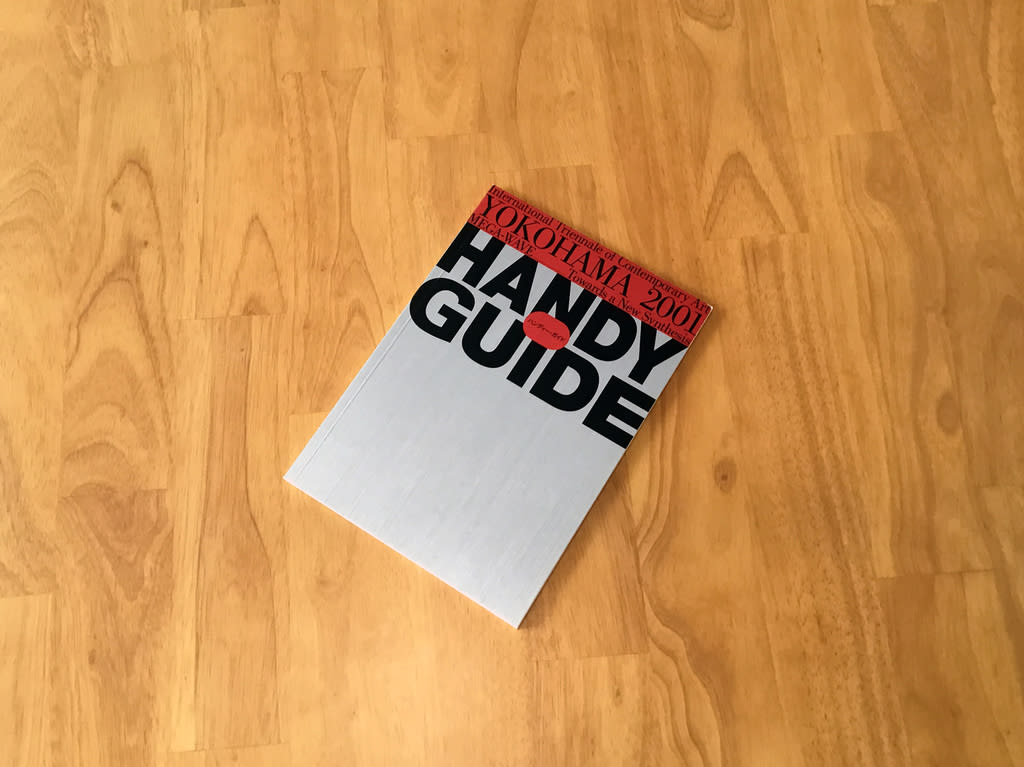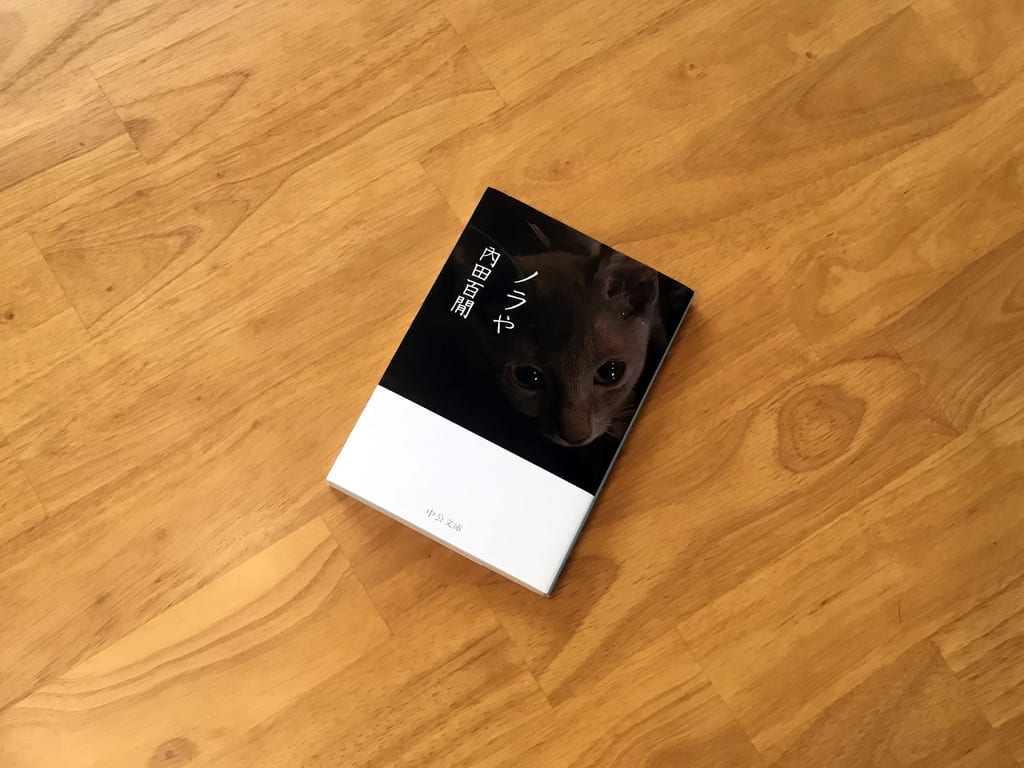ぼたんを診てもらっている動物病院は
けっこう人気のようで、いつも混んでいます。
ネット予約して、順番が近づいてから行くにも関わらず
だいたい1〜2時間待つ。
なので、待合室用の本を持っていきます。
いまは通院2〜3回で1冊読むペース。
今回読んだのは『文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒』。
けっこう人気のようで、いつも混んでいます。
ネット予約して、順番が近づいてから行くにも関わらず
だいたい1〜2時間待つ。
なので、待合室用の本を持っていきます。
いまは通院2〜3回で1冊読むペース。
今回読んだのは『文豪怪奇コレクション 恐怖と哀愁の内田百閒』。

読書日記[46]で書いた、『ノラや』が良かったのですが
内田百閒先生の本って読んだことないな〜、と思って
手っ取り早くアンソロジーを読んでみました。
『ノラや』は旧仮名・旧字体で、昭和初期の雰囲気があって好きですが
こちらは新仮名になっていて、ふりがなもついて読みやすい。
(『ノラや』も改訂版がでているのでこちらは新仮名かも)
最近の本は内容の展開が早く、どんどん進んでいくものが多いせいか
大正〜昭和初期のこの本の文章は、
とってもゆっくり時間が進んでいく気がします。
「由比駅」という話の最後(P279)
↓
耳許(みみもと)ががんとして、耳鳴りがする。松も鳴っている。ボイの白い顔と白い上衣が、境目がなくなった。
この一文が、なんだかこの本の全てを表している気がする。
今は昼なのか夜なのか、夢なのか現実なのか、話し相手は知人なのか別人か、
ここにいる自分は果たして生きているのか死んでいるのか。。。
いつのまにかあらゆる境界がなくなって、ぬる〜っとした感覚が残る。
そんな感じの本でした。
なんとなく、この時代の感じが良くて続けて読んだ同じシリーズ、
『文豪怪奇コレクション 耽美と憧憬の泉鏡花〈小説篇〉』。

こちらは、また少し内容が変わって
「向こう側」の世界に足を踏みれてしまったところから始まる話が多かった。
明らかに夢ではない、何かがおかしい世界。
そして自分に深く関わっていて、本能が逃げたいと告げるのに逃げられない。
あまりこういう感じの本を読んだことがありませんでした。
なんだか怖い夢を見てうなされている気分になります。
個人的に好きなのは、読後にじわじわとくる『恐怖と哀愁の内田百閒』。
このシリーズ、他の作家さんもちょっと読んでみたいです。
この2冊を読んでいたら、
とある漫画を読みたくなりまして。
『鬼を飼う』(吉川景都)

(画像は購入したebookから拝借)
ちょっと方向性はかわるのですが、昭和初期の奇獣もの。
絵も綺麗だし、話もまとまっていて、7巻で完結するのも良い。
久しぶりに読みました。
明治から昭和初期は、こういう話が合います。
異界とか、異能とか、奇獣とか。