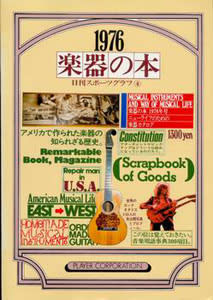
ホームページの方でも以前に書いたことだが、私がギターを初めて手にしたのが中学の時。
よくあるパターンだが、最初はまず F というバレーコードに面くらった。
人差し指1本で全弦を押さえるなんて、とんでもないことのように思えた。
Fでさえ辛いのだから、B♭というコードなど、人間技じゃないとも思えた。
だが、少しずつ練習し、Fをなんとか押さえられるようになり、B♭は自分なりの弾き方で弾けるようになり。
すると、それまでに練習したC、D、E、G、A、Bなどのメジャーコードやマイナーコードを混ぜれば、ギター1本で、かなりの曲が弾けるようになった。
そうなるとギターそのものが楽しくなった。
すると、ギター関係の本も読むようになった。
そこには、色んなミュージシャンの愛用ギターなどの話もふんだんに載っていた。
そういう記事を読むうちに、ミュージシャンが愛用するギターや、そのメーカーの名前なども覚えるようになった。
マーチン、ギブソン、フェンダー、リッケンバッカー、ギルド、グレッチ、オベイション、その他、その他。
なかでも、マーチン、ギブソン、フェンダーの3社は花形だった。
ロゴには後光が差しているように思えた。
ほとんどのミュージシャンが、それらのギターメーカーのギターのどれかを愛用してることも分かった。
だが、まだその頃は、それらの有名メーカーは、有名ミュージシャンと同様の「スター」であり、同時に「手の届かない存在」であった。
それらのメーカーの楽器の値段も知らなかった。どうせ手が出ない値段であろうし、自分には関係ない・・・というか、諦めに似た気持ちだった。
そのため、有名ミュージシャンがそうであるように、有名メーカーの楽器もまた「憧れ」の存在にしか過ぎず、遠い存在でもあり、身近なものではなかった。
欲しいという気持ちはあっても、現実感はなかった。
そんな毎日を過ごしていたある日、書店で私は1冊の本を見つけた。
それはギターのカタログ本であった。
名前は「1976 楽器の本」。
この本によって、私のギターライフは、大きく変わった。
その本には、日本の安いギターと共に、マーチンやギブソン、フェンダーなどの世界の有名メーカーのギターも紹介されており、値段も記してあった。
なので、マーチンやギブソンやフェンダーなどのメーカーから、主にどんなモデルが出ていて、それぞれいくらぐらいの値段なのかも分かった。
国産の安いギターも、海外の高額なギターも、どちらもギターという商品であることには変わりない。
まあ当たり前のことなのだが、モデルに見合ったお金さえあれば、自分も入手することができる・・ということを、あらためて実感。
それ以来、このカタログ本ばかりを・・それこそ「穴があくぐらい」毎日毎日見続けた。
マーチンやギブソンやフェンダーのギターを身近に感じるようになったわけだ。入手の対象として、現実的なものとして捉えるようになったのだ。
今でこそ私は、当時憧れた有名メーカーの楽器を何本も持っているが、この「1976楽器の本」を見なければ、ずっとコピーモデルだけで我慢してたかもしれない。
いや、社会人になって1本くらい買ったかもしれないが、その1本以外はコピーでも満足してたかもしれない。
この「楽器の本」を見てると、色んなメーカーの色んな楽器がほしくてたまらなくなった。
この本を見ながら、欲しいギターのリストを作ったりもした。
また、本の中には、すでにこの頃からビンテージギター(オールドギター)の価値についても、スティーブン・スティルスによって語られており、私がビンテージギターに興味を持つようになったのも、この本がきっかけだった。
つまり・・この本に私の人生観・・・ギター観は変えられてしまったのだ。
で、有名メーカーの有名ギターを、あれこれ買うようになった・・・というわけだ。
この本は、ギターカタログの集合体であると同時に、ギター探求という迷宮(?)への入り口でもあった。
当時の私は、舶来有名メーカーのギターなど買えるわけもなく、とりあえず有名メーカーのロゴ欲しさに、有名ギターメーカーのピックで代用し、ピック探求の道から始まってしまったけれど(笑)。
一応、有名メーカーから出ているピックには、そのメーカーのロゴが描かれていたし、ピックなら1枚100円ぐらいで買えたから。
買ったマーチンやギブソン、ギルド、フェンダーなどのピックに描かれたメーカーロゴを、まじまじと見つめたものだった。
このロゴが、ギター本体の・・・主にヘッドの部分に誇らしげについているんだなあ・・などと思いながら。
おかげで、この当時、私の手元には色んなメーカーのピックが集まったものだった。
というか、ロゴが集まった(笑)。
だが、同じロゴでも、やはり代用品みたいな感覚はぬぐい去れず、いつかはギター本体を!という夢は膨らんでいった。
今家の中に色んなギターがあるが、それらが我が家に集まったのは、すべてはこの本から始まった・・と言っても過言ではない。
私が今、音楽を細々とでもやり続けているのは、この本にも多少の責任(?)があるのかもしれない(笑)。
私のギターへの関心を飛躍的にアップさせた本であるから。
まさに、私の人生の一部を変えた1冊である。
たかがカタログ本とみなすなかれ。あなどれないのだ。
色々な意味で、罪つくりな1冊であった。
この本が出版された1976年・・・・つまり1970年代に製作されたギターの中では、今では「セミ・ビンテージ」として、ビンテージ楽器として扱われているギターもある。
今現在「新品」として製作されているギターが、今から数十年後にビンテージ扱いされるギターは、どれぐらいあるのだろう。
それは未来の人でないと分からない。
ただ、いつの時代であっても、そんなギターが製作され続けていってほしいと切に思う。










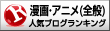


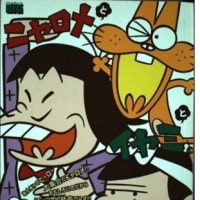















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます