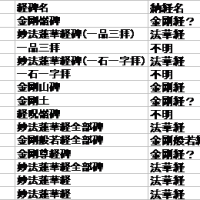「古典女踊り」の「柳」は、琉歌2題に三線の伴奏で踊られる。演目のタイトルは、歌の2題目
柳は緑 花は紅 人は唯情 梅は匂い
の「柳は緑」にちなむ。
上句の「柳は緑 花は紅」は7・7、続く下句「人は」以下が8・6となっている。琉歌の歌形8・8・8・6と一部違っているのは、琉球の知識人にも親しまれた和歌の五七調を意識していて、「柳は緑 花は紅」が輸入された和語であることを示している。
私の理解では、歌意はいくつか考えられる。まず「柳は緑(そのまま) 花(牡丹)は紅(そのまま) 人はただ情け(そのまま) 梅は(その)匂い(そのまま)」、というもので、「あるがまま(でいい)」というニュアンスになる。次は「比較級」にあたる解釈で、「緑は柳がいい 花は(牡丹の)紅がいい 人は情けに限る 梅の良さは何といっても匂いだ」として、それぞれの持ち味を評価するもの。3つ目は「緑はなんと言っても柳の緑 紅はなんと言おうと(牡丹の)紅 情けこそ人の本性 匂いは梅に勝るものはない」という「最上級」の評価。
「柳は緑 花は紅」の対句は、北宋の詩人蘇軾(1037-1101)の「柳緑花紅真面目」に見える。「真面目」は「しんめんもく」と読まれ、「ありのままのすがた。本来そのままのすがた」(『新字源』)の意である。『広辞苑』では「本旨。趣旨」とする語釈がそれであろう。禅の世界で引用されることで知られていて、蘇軾は禅や禅語に親しむ環境にいたようだ。
日本の場合で言えば、たとえば禅僧・一休和尚の歌に
見るほどに みなそのままの 姿かな 柳は緑 花は紅
禅僧・沢庵和尚の歌に
色即是空 空即是色 柳は緑 花は紅 水の面に 夜な夜な月は通へども 心もとどめず 影も残さず
がある。
いずれの歌も、「(結局)柳は柳のまま、牡丹は牡丹のまま」ということで、他と比較せず、おのれを主とせよ(随所に主となれば、立処皆真なりー臨済)という禅の思想に通じる。その文脈からすると、上記琉歌の解釈は1番目が近いということになる。『琉歌全集』における島袋盛敏の解釈がこれ。しかし、柳や牡丹、梅の枝を採物にして踊るあでやかな女踊りからすると、禅的な解釈は逆に説教じみておもしろくない。せめて2番目の解釈、できれば強引の感はあるが3番目の最上級の解釈を私はとりたい。多様な解釈ができるところに、文学の「真面目」がある。
(『芸道40周年記念高嶺久枝の会ー琉球芸能の源流を探る』(同会編集・発行、09.12)
<補注>
1.岩波『仏教辞典』では、「禅宗において、悟りの心境とはどのようなものかを示すときに好んで用いられる語句」として、「緑の葉や赤い花という何の変哲もないありのままの自然を示すことにより、悟りは日常生活そのものの中にあるとする禅宗の立場を端的に言い表している」と説明している。同辞典では南宋初期(13世紀)の禅僧道川の語句「目前に法無し、さもあらばあれ、柳は緑、華は紅」を紹介している。
2.同辞典は謡曲「放下僧」のセリフにもこの語句があることを紹介している。岩波日本古典文学大系・謡曲集下からその前後を添えて引用しよう。「されば大小の根機を問わず、持戒・破戒を選ばず、有無の二辺に落つることなく、皆成仏する例あり。かるがゆゑに草木も法身の姿を現はし、柳は緑花は紅なる、その色々を現はせり」。
柳は緑 花は紅 人は唯情 梅は匂い
の「柳は緑」にちなむ。
上句の「柳は緑 花は紅」は7・7、続く下句「人は」以下が8・6となっている。琉歌の歌形8・8・8・6と一部違っているのは、琉球の知識人にも親しまれた和歌の五七調を意識していて、「柳は緑 花は紅」が輸入された和語であることを示している。
私の理解では、歌意はいくつか考えられる。まず「柳は緑(そのまま) 花(牡丹)は紅(そのまま) 人はただ情け(そのまま) 梅は(その)匂い(そのまま)」、というもので、「あるがまま(でいい)」というニュアンスになる。次は「比較級」にあたる解釈で、「緑は柳がいい 花は(牡丹の)紅がいい 人は情けに限る 梅の良さは何といっても匂いだ」として、それぞれの持ち味を評価するもの。3つ目は「緑はなんと言っても柳の緑 紅はなんと言おうと(牡丹の)紅 情けこそ人の本性 匂いは梅に勝るものはない」という「最上級」の評価。
「柳は緑 花は紅」の対句は、北宋の詩人蘇軾(1037-1101)の「柳緑花紅真面目」に見える。「真面目」は「しんめんもく」と読まれ、「ありのままのすがた。本来そのままのすがた」(『新字源』)の意である。『広辞苑』では「本旨。趣旨」とする語釈がそれであろう。禅の世界で引用されることで知られていて、蘇軾は禅や禅語に親しむ環境にいたようだ。
日本の場合で言えば、たとえば禅僧・一休和尚の歌に
見るほどに みなそのままの 姿かな 柳は緑 花は紅
禅僧・沢庵和尚の歌に
色即是空 空即是色 柳は緑 花は紅 水の面に 夜な夜な月は通へども 心もとどめず 影も残さず
がある。
いずれの歌も、「(結局)柳は柳のまま、牡丹は牡丹のまま」ということで、他と比較せず、おのれを主とせよ(随所に主となれば、立処皆真なりー臨済)という禅の思想に通じる。その文脈からすると、上記琉歌の解釈は1番目が近いということになる。『琉歌全集』における島袋盛敏の解釈がこれ。しかし、柳や牡丹、梅の枝を採物にして踊るあでやかな女踊りからすると、禅的な解釈は逆に説教じみておもしろくない。せめて2番目の解釈、できれば強引の感はあるが3番目の最上級の解釈を私はとりたい。多様な解釈ができるところに、文学の「真面目」がある。
(『芸道40周年記念高嶺久枝の会ー琉球芸能の源流を探る』(同会編集・発行、09.12)
<補注>
1.岩波『仏教辞典』では、「禅宗において、悟りの心境とはどのようなものかを示すときに好んで用いられる語句」として、「緑の葉や赤い花という何の変哲もないありのままの自然を示すことにより、悟りは日常生活そのものの中にあるとする禅宗の立場を端的に言い表している」と説明している。同辞典では南宋初期(13世紀)の禅僧道川の語句「目前に法無し、さもあらばあれ、柳は緑、華は紅」を紹介している。
2.同辞典は謡曲「放下僧」のセリフにもこの語句があることを紹介している。岩波日本古典文学大系・謡曲集下からその前後を添えて引用しよう。「されば大小の根機を問わず、持戒・破戒を選ばず、有無の二辺に落つることなく、皆成仏する例あり。かるがゆゑに草木も法身の姿を現はし、柳は緑花は紅なる、その色々を現はせり」。