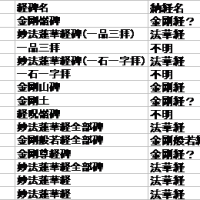私には姉も妹もいない。どちらか一人でもいたら、私の人生や人生観も変わっていたかもしれない。それはそれとして、そもそも兄弟にとって姉妹とはどのような存在なのか。推測の域を出ないが、姉妹とはその兄弟にとって「もっとも近く、もっとも遠い関係である」と言っておこう。もっとも近いとは「親を共有している異性である」ということであり、もっとも遠いとは、「異性でありながら結婚してはならない」というタブーにしばられているということである。物語はここから始まる。とりあえず「兄と妹の物語」と題することにしよう。分析の素材としては神話・伝説と民間信仰。
<strong>昇華</strong>
有名なところでイザナギ・イザナミの物語。現在の神話学では2人は兄・妹となっている。自ら造った国土に天降りした二人は次に、島づくりに移る。そのための「みと(陰部)のまぐはひ(交接)」をするにあたって初めて行ったのは、天の御柱を廻ること、そして愛の言葉をかけあうこと。ところが生まれた子は「ひるこ」、次に「淡島」でともに「子の例」に合わない。そこで「天つ神」に上申したところ、神が占って言うには、女から先に愛の言葉をかけるのがよくない。そこで2人は再度地上に戻り、柱廻りと言葉の掛け合いを実践し、8つの島を生んだ。この話は「神話」の位相からすると、国土創生と合わせて、「性差」の認識と性交、出産の起源神話と見なすことができる。
本稿の文脈に戻して言えば、柱廻りと愛の言葉の掛け合いは、「兄妹」という近親間の相姦のタブーを超克し、「男女」の関係に移行するための儀礼=イニシエーションと解される。琉球の島々に伝わる伝説から類例を探そう。たとえば石垣島白保に伝わるところでは、日神がアマン神に命じて八重山諸島を造らせた。次に日神は人種子を下し、池の周りに立たせて互いに反対に巡るよう命じた。そうしたところ、出会った2人は初めて性の道を知り、3男2女の子宝に恵まれた(喜舎場永珣『新訂増補八重山歴史』)。波照間島に伝わる伝説では、あるとき突如として「油雨」が降り、島に住む人々はことごとく死滅したが、2人の兄妹は洞窟に隠れて生き延びた。成人して夫婦となるが、生まれた子はボーズという魚のような子なので、土地柄のせいかと住処を変えた。ところが今度はハブのような子供が生まれた。三度目の引っ越しの後に人間らしい子が生まれ、その後繁盛した(宮良高弘『波照間島民俗誌』)。ここでは住まいの地相が悪いとして住居を移動することが、近親関係から社会関係に移行する行為とみなされている。
ここで「イニシエーション」の定義を『文化人類学辞典』(弘文堂)から引用しておこう。「広義では、ある社会的・宗教的位置から別の地位への変更を認めるための一連の行為を意味する。この際、儀礼を伴うのが一般的である」。子供から大人へ、近親から社会人へ移行するにあたって、互いの性差を確認したうえで、人間としての繁殖=再生産を図る非日常的な転換行為。上記の神話伝説における「一連の行為」がイニシエーションという名の「儀礼」に相当すると見なすことに異論はないだろう。
『旧約聖書・創世記』におけるアダムとイブの物語も、以上の文脈の一環として読むことができる。まず、男アダムが神の手でつくられ、そのあばら骨から女イブがつくられる。すなわち2人は「骨肉を分けた」兄と妹である。2人は与えられた土地「エデンの園」になるどの木の実も食べてよいとされたが、唯一「善悪を知る木」の実は取って食べてはならないと禁じられた。その実を食べると死ぬからだというのである。ところがイブは狡猾な蛇の誘いに乗ってアダムとともにその実を食べた。そうすると二人は互いに裸であることに気づき、イチジクの葉をつづり合わせて腰にまいた。異変に気付いた神は2人をエデンの外に追い出し、男には労働の苦しみ、女には出産の苦しみ、そして2人に死すべき運命を与えた。いうまでもなく、創世記の場合、儀礼にあたるのは、神の命に背いておのれの意思で「善悪を知る木」の実を食べることであった。
「創世記」がいう「善悪を知る」とは何か。「性差」を知ることであり、「生死」を知ること、労働=生産と「消費」「遊び」の違いを知ること、子供と大人の差異を知ること、総じていえば「神と人間の差異」を知ることである。これらの「差異」を知るためには相応の「試練」を潜り抜けなければならないことも、2人は知らされた。エデンの園の外に待っていたのは、数々のイニシエーションであった。これらのイニシエーションを経由することで、人々は人間として生きること、自然の一員であり、一員でしかないことの幸と不幸を知った。
<strong>対立</strong>
アマテラスとスサノオ、この貞潔な姉と荒ぶる弟の場合はどうか。2人は父イザナギが黄泉の国から帰還し、禊ぎをするときに生まれた。父神は姉には天上を弟には地上を支配するように命じたが、弟はこれをいやがり、ために姉弟は対立するにいたった。2人は和睦を期する契約を行ったが、結局姉は弟の狼藉をきらって洞穴に隠れ、世は暗闇に変わった。姉は八百万の神たちの計らいで外に引き出され、弟は下界に追放される、という物語である。「契約」という名の儀礼によっても2人の和解は実現できず、2人は天と地に引き裂かれたままで物語は終わる。言い換えれば姉と弟の対立は終わることがなかった。
沖縄では旧暦12月8日に、サンニン(月桃)の葉に包んだ餅を食する風習があるが、その由来は兄と妹の対立・対決の物語として伝わっている。言い伝えの詳細は他に任せるとして、<a href="https://www.city.okinawa.okinawa.jp/sp/about/1610/1617" target="_blank">この伝説</a>では、人食い鬼と化した兄に、固い異物交じりの餅を食わせた妹が、おのれの性器をひけらかし、鬼を食らう口だと脅して、兄をがけ下に落とすというあらすじになっている。兄と妹の「性」を介した食うか食われるかの物語である。
<strong>協和</strong>
兄と妹、姉と弟の協和は、沖縄・奄美では「をなり(姉妹、ウナイ、丁寧語ではウミナイ)」が「ゑけり(兄弟、ウィキー)」を守護する霊力を持つという「をなり神信仰」として知られている。具体的には、兄弟が出航・航行あるいは出陣の場面で、時に姉妹の手織りの手ぬぐいや持ち物などに付随するセヂとして顕現した。
ウニヌ(御船の) タカトゥムニ(帆柱の先に) シラトゥヤヌ(白鳥が) イチョン(止まっている)
シラトゥヤヤアラン(白鳥ではない) ウミナイウシジ(姉妹の霊力の化身だ)
兄弟姉妹であるが故の、兄弟姉妹であるがままの、儀礼抜きの協業・役割分担がそこにあった。
<strong>関係</strong>
兄弟と姉妹は、「親縁かつ疎遠な両義的存在」であり、「聖と俗」両界の間を揺れ動く関係なのである。