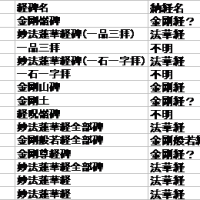「道教」研究の碩学として知られた東京大学名誉教授・窪徳忠先生が亡くなられたのは、2010年10月2日。97歳で天寿を全うされたが、先立たれた奥様と再会されてからすでに2年余が過ぎたことになる。
先生に初めてお目にかかったのは、私が東大文学部宗教学・宗教史学専攻に籍をおいていた頃で、紹介してくださったのは、主任教授の堀一郎先生であった。時に1969年、「東大紛争」の余韻が残る時期である。その後断続はあったものの、奥様ともども40余年のご厚誼をいただいた関係上、先生の訃報に接した時は万感胸に迫るものがあった。葬儀には、当時の南島研究所長の上原静氏、専任所員の崎浜靖氏とともに参列させていただいた。以下の文章は、参列に先立ってしたため、ご霊前に奉献した文章に若干の加筆・修正を施したものである。
ところで、本誌を借りて先生のご業績の一端を紹介しようというのは、私が大学卒業後の1973年に沖縄県立博物館の工芸担当学芸員として職を得て以降、「宗教研究」から離れて今日に至っている立場からすれば、荷が重い話であり、不遜とすら言えよう。とはいえ、先生の沖縄調査で運転担当をはじめとする「お手伝い」をさせてもらい、その間に先生からお聞きし、垣間見た調査研究の方法や内容、いただいた論文やご高著の記述、そして知り得た先生のお人柄まで、思い起こせば私にも何か書けることがあるかも知れない。それが執筆の動機である。
先生のご研究の柱と業績はいくつもあろうが、その中でまちがいなく重要なテーマの一つが、「中国文化からみた」「沖縄の民間信仰」である。この一文をしたためる主因であるが、まずは、私が理解できる範囲での先生のご研究の概要について触れさせてもらいたい。
さて、「道教」と言えば、すぐに老子や荘子の「老荘思想」を連想される方が多いと思う。しかし、台湾を含む中国文化圏においては、道教の「神々」を祀る多数の「廟」があり、参詣者が絶えない。いいかえれば、道教とは中国においてはまず「宗教」なのであり、先生のお説によれば、「儒教については、宗教とみる説と、そうでないとする説との両説があるので、これを別にすれば」「中国人のあいだからおこった唯一の宗教」(『中国宗教における受容・変容・行容』、1979年、山川出版社。以下引用はすべて同書)なのである。
先生が着目されたのは民間で信仰される道教の内容、その歴史や実態である。調査・研究の範囲は、中国から日本、琉球・沖縄、台湾、東南アジアまで多岐にわたる。先生のご研究の方法は、一貫している。漢文史・資料と研究史の渉猟、徹底したフィールドワークに基づく「実証的な調査」、および「比較研究」がそれである。
略歴をひも解くと、先生が東京帝国大学(現東大)文学部東洋史学科をご卒業なされたのは1937年。その後、兵役召集、東方文化学院研究員、東京大学東洋文化研究所研究員を経て、1949年に東洋文化研究所助教授に着任された。この当時の研究上の主要なご関心は「中国宗教」、特に道教の日本における「伝来」であり、まず注目したのが「道教的にいえば三尸(さんし)説、日本流にいえば庚申信仰であった」。ともに「長生」を念じる人々の間で流布する民間信仰だが、先生は日本のそれを中国からの「受容と変容」で解釈されたのである。とはいえ、お説を詳しく説明をする紙数の余裕も能力もない。この分野の調査研究成果については、第一書房刊『窪徳忠著作集』(全9巻)中の『新訂 庚申信仰の研究』(上・下・年譜編・島嶼編の4巻)に譲ることにしよう。
若干追記するならば、先生のご研究の根底にあったのは、まずは庚申信仰を「日本固有」としたうえで、そのような「固有」の「民俗」に調査研究を限定する柳田國男の民俗学に対する批判であった。そして、柳田・折口信夫の流れを汲んで、日本の「古俗」や文化の「源流」を沖縄に求めようとする余り、中国や東南アジアなど周辺地域との「比較研究」がおろそかになりがちな従来の「沖縄学」の潮流に対する懸念があった。
「源流」や「伝来」、あるいは「ルート」の研究の前提になるのは、文献とフィールドの両分野からする「分布」の広範かつ精密な調査である。日本における庚申信仰の分布を精力的に調査される一方で、伝来の経路として先生がまず想定したのは朝鮮半島経由、続いて沖縄経由。前者については「道教の信仰や三尸説が、土着の信仰や習俗とふかく習合しながら、人々に受け容れられていることがわかった」。
初めての「南西諸島」調査は、沖縄がまだ米軍の直接統治下にあった1966年7月のことであった。先生の「身元引受人」は、琉球大学の学長も務められた動物学の高良鉄夫教授であったと聞いている。その後の度重なる調査の「中間報告」が大著『沖縄の習俗と信仰』(1971年、東大出版会)であり、その「増補新訂」版を私たちは、上記著作集第4巻(1997年)として入手できる。沖縄調査で先生は、「三尸説や庚申信仰の片鱗すらみいだすことができなかったけれども、道教関係の信仰は、朝鮮半島の場合と同様に、土着の信仰と密接に習合し」、「信仰や習俗として人々に受容されていた」ことを知る。
先生の沖縄研究の成果を、一般にも手に取りやすく、わかりやすい文章で書かれたのが『中国文化と南島』(1981年、第一書房)、『沖縄の民間信仰―中国文化からみた』(1989年、ひるぎ社)、『目でみる沖縄の民俗とそのルーツ』(1990年、沖縄出版)である。
これらの本から私たちは、身近にあるシーサーや石敢当、台所で見られるヒ(火)ヌカン(神)、ウチカビ(打紙)と呼ばれる紙銭、ウサンミと呼ばれるお供え物、あるいは木造屋根の棟木に書かれた「紫微ラン駕」、屋敷門の突き当たりに設置されたヒンプン、トゥーティークン(「土帝君」)と呼ばれる土地神、さらにはお墓の左(向かって右)に在するフィジャイと呼ばれる神、などが中国の民間信仰に由来するとともに一部はアジア各地に伝わり、しばしば「変容」を遂げながらそれぞれの地で「受容」されたことを知らされる。
外来の宗教、広く外来の「文化」が、当該地域に「伝播」し、受容されるにあたっては、受け入れる側の取捨選択が働くとともに、土地の事情や習俗に合わせた「書き換え」がなされつつ受け継がれていく、あるいは消えていくというのが、文献と地域を広い範囲で調査され、深く研究された先生の実感であり、結論であった。繰り返すことになるがそれは、文化における「固有」とは何か、を鋭く問う提起でもあった。沖縄とて例外ではないのである。先生のご功績は、得られたデータと研究・考察の範囲にとどまらない。その方法論やスタンスにおいてもまた、得るところ大であると私は考えている。
ここでの記述は先生の沖縄研究における成果に比重を置いたが、ご研究の総体を概観したいという方は、著作集の他の巻、すなわち第6巻『東アジアにおける宗教文化の伝来と受容』、第7巻『道教と仏教』、第8巻『道教とアジアの宗教文化』、第9巻『奄美のカマド神信仰』にも眼を通していただきたい。全9巻の構成とタイトルを見るだけでも、先生のご研究の範疇と範囲と方法、すなわち業績と功績の全般をうかがうことができるはずだ。
先生の論文や著作の末尾あるいは序文に、例外なく添えられる文章があった。その一例。「諸篇は、手を加えたとはいうものの、あくまで中間報告にすぎない。解決をのちに残した点も多く、考えも十分に熟していない。資料の見方も不足であり、独断、曲解も多いであろう。このような多くの欠点を承知しながら、あえてこのような形で発表するのは、ひとつには、博雅の示教をえて、将来の私の研究続行の指針に資そうと思ったために他ならない。お気付きの点について、細大となく御指摘いただければ、まことに幸いである。」
博雅の先生にしてなお、この謙虚さ・・・。若い研究者たちには、研究の姿勢と態度においてもまた、先生から得るところが大きいだろうと考えるのは、私の「老婆心」がなせる業か。
先生は、調査研究と並行して東大東洋文化研究所長や日本民族学会(現文化人類学会)会長、日本宗教学会理事・評議員、日本道教学会発起人・理事・評議員、など学界の要職にも就かれたが、沖縄研究関係では南島史学会の会長・理事・評議員としてその運営にも携われた。もうひとつ特筆されるべきは、沖縄国際大学に浄財とご蔵書7800冊を寄贈されたことだ。同大学は、これを契機にして1996年に「窪徳忠琉中関係研究奨励賞基金」を創設、先生を審査委員長として多くの若き学徒が表彰され、先生亡き後も継続していると聞く。とはいえこの分野ではこれ以上、先生の業績をくわしく紹介する字数もないし、任とも思えない。
一言付記すれば、私にとって最後の職場となった那覇市立壺屋焼物博物館の開館にあたって、先生が参考図書購入費用の一部にと祝い金を贈ってくださり、ありがたくお受けしたことがある。それも今だから、ここでなら活字にできるし、公開したいと思う次第である。
最後にご尊顔を拝したのは、10月8日の告別式会場であった。このとき、先生のご身体は献花できれいに飾られたのだが、「俺の柄じゃないよ」と、いかにも恥ずかしそうにしておられるように見えて、涙をこらえることができなかった。心残りがなかったはずはないが、少なくても沖縄研究については、「やったよ、渡名喜君」と話しかけてくださっているようにお見受けした。
あらためて振り返ってみると、先生のご長命は「道教の神々」からのプレゼントのようにも受け取れるのだが、先生が選んだ菩提寺は奥様の縁故もあって浄土宗のそれであり、ご住職の「引導」によって渡ったのは、阿弥陀如来のまします「極楽浄土」であった。今頃は浄土で、阿弥陀如来から「聞き取り調査」でもなさっておられるのだろうか。道教と仏教の比較研究においても精力的であられたようだから、先生が「彼の地」において調査を継続しておられるとしても不思議ではない。それどころか、今となってはあたりまえのようにすら思えてくるのである。(2013.2.10)
先生に初めてお目にかかったのは、私が東大文学部宗教学・宗教史学専攻に籍をおいていた頃で、紹介してくださったのは、主任教授の堀一郎先生であった。時に1969年、「東大紛争」の余韻が残る時期である。その後断続はあったものの、奥様ともども40余年のご厚誼をいただいた関係上、先生の訃報に接した時は万感胸に迫るものがあった。葬儀には、当時の南島研究所長の上原静氏、専任所員の崎浜靖氏とともに参列させていただいた。以下の文章は、参列に先立ってしたため、ご霊前に奉献した文章に若干の加筆・修正を施したものである。
ところで、本誌を借りて先生のご業績の一端を紹介しようというのは、私が大学卒業後の1973年に沖縄県立博物館の工芸担当学芸員として職を得て以降、「宗教研究」から離れて今日に至っている立場からすれば、荷が重い話であり、不遜とすら言えよう。とはいえ、先生の沖縄調査で運転担当をはじめとする「お手伝い」をさせてもらい、その間に先生からお聞きし、垣間見た調査研究の方法や内容、いただいた論文やご高著の記述、そして知り得た先生のお人柄まで、思い起こせば私にも何か書けることがあるかも知れない。それが執筆の動機である。
先生のご研究の柱と業績はいくつもあろうが、その中でまちがいなく重要なテーマの一つが、「中国文化からみた」「沖縄の民間信仰」である。この一文をしたためる主因であるが、まずは、私が理解できる範囲での先生のご研究の概要について触れさせてもらいたい。
さて、「道教」と言えば、すぐに老子や荘子の「老荘思想」を連想される方が多いと思う。しかし、台湾を含む中国文化圏においては、道教の「神々」を祀る多数の「廟」があり、参詣者が絶えない。いいかえれば、道教とは中国においてはまず「宗教」なのであり、先生のお説によれば、「儒教については、宗教とみる説と、そうでないとする説との両説があるので、これを別にすれば」「中国人のあいだからおこった唯一の宗教」(『中国宗教における受容・変容・行容』、1979年、山川出版社。以下引用はすべて同書)なのである。
先生が着目されたのは民間で信仰される道教の内容、その歴史や実態である。調査・研究の範囲は、中国から日本、琉球・沖縄、台湾、東南アジアまで多岐にわたる。先生のご研究の方法は、一貫している。漢文史・資料と研究史の渉猟、徹底したフィールドワークに基づく「実証的な調査」、および「比較研究」がそれである。
略歴をひも解くと、先生が東京帝国大学(現東大)文学部東洋史学科をご卒業なされたのは1937年。その後、兵役召集、東方文化学院研究員、東京大学東洋文化研究所研究員を経て、1949年に東洋文化研究所助教授に着任された。この当時の研究上の主要なご関心は「中国宗教」、特に道教の日本における「伝来」であり、まず注目したのが「道教的にいえば三尸(さんし)説、日本流にいえば庚申信仰であった」。ともに「長生」を念じる人々の間で流布する民間信仰だが、先生は日本のそれを中国からの「受容と変容」で解釈されたのである。とはいえ、お説を詳しく説明をする紙数の余裕も能力もない。この分野の調査研究成果については、第一書房刊『窪徳忠著作集』(全9巻)中の『新訂 庚申信仰の研究』(上・下・年譜編・島嶼編の4巻)に譲ることにしよう。
若干追記するならば、先生のご研究の根底にあったのは、まずは庚申信仰を「日本固有」としたうえで、そのような「固有」の「民俗」に調査研究を限定する柳田國男の民俗学に対する批判であった。そして、柳田・折口信夫の流れを汲んで、日本の「古俗」や文化の「源流」を沖縄に求めようとする余り、中国や東南アジアなど周辺地域との「比較研究」がおろそかになりがちな従来の「沖縄学」の潮流に対する懸念があった。
「源流」や「伝来」、あるいは「ルート」の研究の前提になるのは、文献とフィールドの両分野からする「分布」の広範かつ精密な調査である。日本における庚申信仰の分布を精力的に調査される一方で、伝来の経路として先生がまず想定したのは朝鮮半島経由、続いて沖縄経由。前者については「道教の信仰や三尸説が、土着の信仰や習俗とふかく習合しながら、人々に受け容れられていることがわかった」。
初めての「南西諸島」調査は、沖縄がまだ米軍の直接統治下にあった1966年7月のことであった。先生の「身元引受人」は、琉球大学の学長も務められた動物学の高良鉄夫教授であったと聞いている。その後の度重なる調査の「中間報告」が大著『沖縄の習俗と信仰』(1971年、東大出版会)であり、その「増補新訂」版を私たちは、上記著作集第4巻(1997年)として入手できる。沖縄調査で先生は、「三尸説や庚申信仰の片鱗すらみいだすことができなかったけれども、道教関係の信仰は、朝鮮半島の場合と同様に、土着の信仰と密接に習合し」、「信仰や習俗として人々に受容されていた」ことを知る。
先生の沖縄研究の成果を、一般にも手に取りやすく、わかりやすい文章で書かれたのが『中国文化と南島』(1981年、第一書房)、『沖縄の民間信仰―中国文化からみた』(1989年、ひるぎ社)、『目でみる沖縄の民俗とそのルーツ』(1990年、沖縄出版)である。
これらの本から私たちは、身近にあるシーサーや石敢当、台所で見られるヒ(火)ヌカン(神)、ウチカビ(打紙)と呼ばれる紙銭、ウサンミと呼ばれるお供え物、あるいは木造屋根の棟木に書かれた「紫微ラン駕」、屋敷門の突き当たりに設置されたヒンプン、トゥーティークン(「土帝君」)と呼ばれる土地神、さらにはお墓の左(向かって右)に在するフィジャイと呼ばれる神、などが中国の民間信仰に由来するとともに一部はアジア各地に伝わり、しばしば「変容」を遂げながらそれぞれの地で「受容」されたことを知らされる。
外来の宗教、広く外来の「文化」が、当該地域に「伝播」し、受容されるにあたっては、受け入れる側の取捨選択が働くとともに、土地の事情や習俗に合わせた「書き換え」がなされつつ受け継がれていく、あるいは消えていくというのが、文献と地域を広い範囲で調査され、深く研究された先生の実感であり、結論であった。繰り返すことになるがそれは、文化における「固有」とは何か、を鋭く問う提起でもあった。沖縄とて例外ではないのである。先生のご功績は、得られたデータと研究・考察の範囲にとどまらない。その方法論やスタンスにおいてもまた、得るところ大であると私は考えている。
ここでの記述は先生の沖縄研究における成果に比重を置いたが、ご研究の総体を概観したいという方は、著作集の他の巻、すなわち第6巻『東アジアにおける宗教文化の伝来と受容』、第7巻『道教と仏教』、第8巻『道教とアジアの宗教文化』、第9巻『奄美のカマド神信仰』にも眼を通していただきたい。全9巻の構成とタイトルを見るだけでも、先生のご研究の範疇と範囲と方法、すなわち業績と功績の全般をうかがうことができるはずだ。
先生の論文や著作の末尾あるいは序文に、例外なく添えられる文章があった。その一例。「諸篇は、手を加えたとはいうものの、あくまで中間報告にすぎない。解決をのちに残した点も多く、考えも十分に熟していない。資料の見方も不足であり、独断、曲解も多いであろう。このような多くの欠点を承知しながら、あえてこのような形で発表するのは、ひとつには、博雅の示教をえて、将来の私の研究続行の指針に資そうと思ったために他ならない。お気付きの点について、細大となく御指摘いただければ、まことに幸いである。」
博雅の先生にしてなお、この謙虚さ・・・。若い研究者たちには、研究の姿勢と態度においてもまた、先生から得るところが大きいだろうと考えるのは、私の「老婆心」がなせる業か。
先生は、調査研究と並行して東大東洋文化研究所長や日本民族学会(現文化人類学会)会長、日本宗教学会理事・評議員、日本道教学会発起人・理事・評議員、など学界の要職にも就かれたが、沖縄研究関係では南島史学会の会長・理事・評議員としてその運営にも携われた。もうひとつ特筆されるべきは、沖縄国際大学に浄財とご蔵書7800冊を寄贈されたことだ。同大学は、これを契機にして1996年に「窪徳忠琉中関係研究奨励賞基金」を創設、先生を審査委員長として多くの若き学徒が表彰され、先生亡き後も継続していると聞く。とはいえこの分野ではこれ以上、先生の業績をくわしく紹介する字数もないし、任とも思えない。
一言付記すれば、私にとって最後の職場となった那覇市立壺屋焼物博物館の開館にあたって、先生が参考図書購入費用の一部にと祝い金を贈ってくださり、ありがたくお受けしたことがある。それも今だから、ここでなら活字にできるし、公開したいと思う次第である。
最後にご尊顔を拝したのは、10月8日の告別式会場であった。このとき、先生のご身体は献花できれいに飾られたのだが、「俺の柄じゃないよ」と、いかにも恥ずかしそうにしておられるように見えて、涙をこらえることができなかった。心残りがなかったはずはないが、少なくても沖縄研究については、「やったよ、渡名喜君」と話しかけてくださっているようにお見受けした。
あらためて振り返ってみると、先生のご長命は「道教の神々」からのプレゼントのようにも受け取れるのだが、先生が選んだ菩提寺は奥様の縁故もあって浄土宗のそれであり、ご住職の「引導」によって渡ったのは、阿弥陀如来のまします「極楽浄土」であった。今頃は浄土で、阿弥陀如来から「聞き取り調査」でもなさっておられるのだろうか。道教と仏教の比較研究においても精力的であられたようだから、先生が「彼の地」において調査を継続しておられるとしても不思議ではない。それどころか、今となってはあたりまえのようにすら思えてくるのである。(2013.2.10)