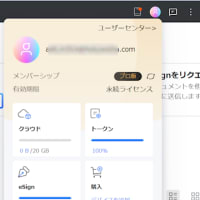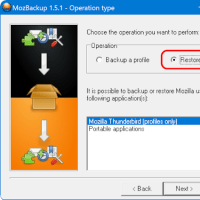いやぁ、便利なツールがあるものですねぇ・・・
Windows PC に Linux 用のハードディスクを接続して、
そのハードディスクのフォルダー/ファイルをコピーするツールを見つけました。
Windows から Linux のディスクを扱う必要性は(たいていの場合は)無いと思いますが、
たまたまその必要が生じたのでツールのお世話になりました。
さて、その必要とは・・・(長い話になります、ご覚悟下さい)
ある友人がメールサーバーなどの環境を用意して、
仲間たちのメーリングリストとして(他のサービスも)提供してくれていました。
10年以上に渡り、我々はこの恩恵に浴してきました。
ところがこのサーバーが不調になりました。
修復できないエラーがハードディスクに発生したのです。
で、2基のハードディスク(*1)を預かって中身(ファイル)を取り出すことにしたのですが、
なにぶん10年以上前から使われていたものです。
昨今の Serial ATA のディスクではなく、例の 40 pin - IDE(ATA)のディスクです。
(*1)1基目はおそらくシステムが入ったディスク、
2基目はおそらくメールデータ、画像、音楽などが入ったディスクでしょう。
別の友人から IDE(ATA)-- USB 変換アダプターを借用して
Windows PC に USB接続したのですが、なぜか認識されません。
(リムーバブルデバイスとして認識されることを期待していたのですが・・・)
やむなく大昔のPCを出してきました。
これだと IDE のドライブを接続することができるからです。
SATA ドライブは接続できません (^_^;)
さすがにこのPCだと IDE ドライブが認識されて(Linux 用ハードディスクが認識できて)、
OSが起動しました(Vine Linux でした)。
が、システムドライブに修復できないエラーがあり、X-Window まで到達できません。
♯ 事情があって、ユーザーアカウント、パスワードも不明なので、
X-Window が立ち上がっても、あるいはすっぴんの Linux 起動状態でも、
お手上げではありますが、何とかデータだけは吸い上げたい。
はてさてどうしたものか・・・
実は、この大昔のPCですが・・・
2年ほど前に Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP が起動できるようにしていました。
名前は忘れましたが、リムーバブルなHDDカートリッジがありましたよね。
PCのフロント、5" ベイにベースとなるアダプターを入れて、
HDDを入れたカートリッジをそこにガチャンコと挿入して使うやつです。
幾つかのカートリッジを用意しておけば、それらを入れ替えていろんな環境に切り替えられます。
2つのカートリッジがあって、1つ目には Windows 98SE のシステムHDDを入れていました。
2つ目には Windwos 2000、Windows XP のデュアルブートHDDを入れていました。
で、今回はデュアルブート用カートリッジを使い、Windows XP を起動しました。
もちろん Linux 用HDDもPCに接続しています。
Windows XP では、Linux HDDはベアドライブとしては認識できたものの、
その中身にアクセスできません(不明なドライブと認識されています)。
パーティション構造すらどうなっているか分かりません。
・・・で、本題に戻ります。
何とか Windows で Linux HDD(の中身)を読めないものだろうか。
探したところ・・・ありました。
"DiskInternals Linux Reader" なるソフトです。
Linux で使われているファイルシステム、Ext2/Ext3/Ext4 を扱えるとのこと。
で、"DiskInternals Linux Reader" をダウンロード&インストールしました。
起動しました・・・う~ん、スゴイ!
エクスプローラーのような画面が現れ、
左にはドライブが、右には選択したドライブの詳細(リストビュー?)が見えました。
これで Linux ハードディスクのファイルがコピーできます。
# 最初は NAS にコピーしようとしましたが、
旧式PCでは 100Mbps(100BASE-T)の NIC で、
なぜかネットワーク経由でコピーし始めると CPU 使用率が 100% になってしまいました。
(svchost が CPU をバカ食いしていました)
これじゃコピー完了まで2、3日かかりそう・・・
Windows 2000、XP デュアルブートの IDE ハードディスクには、どちらのパーティションにも十分な空き容量がありました。
なので、Win2K 用のパーティションにコピーすることにしました。
(それでも相当時間がかかりましたが・・・)
さて、DiskInternals Linux Reader のおかげで
Win.XP から Linux ハードディスクの中身をコピーすることができました。
(その間に旧友たちとの飲み会があったので、コピー途中で外出して、帰宅したらコピーが終わっていました)
さらに今後のことを考えて、
旧PC(の IDE ハードディス)からコピーした中身を USB 接続・外付けHDD(実際はSSD)にコピー中です。
旧PCをいつまでも出しておくわけにはいきませんし(モニターは女房殿のを借用中ですし)、
何をするにも快適・快速とはいえないからです。
# ちなみに旧PCのマザーボードは(AOpen)AX6BC Pro II というものです。
グラフィックカードは AGP スロットに挿した(AOpen)GeForce3 Ti200。
(AGP なんてオールドファンには懐かしいでしょ)
CPU は Slot-1 に挿した Pentium III 600E。
(Slot-1 は短命でした、Intel 焦りすぎの仕様だったと思います)
このマザーは一応 USB にも対応しているのですが、USB 1.1 です。
この USB ポートに、最新 USB 3.0 対応の外付け SSD を接続してコピー・・・
「リービッヒの最小律」がここでも有効で、
合計 30GB ほどですが、なかなかコピーが終わりません。
というわけで、オヤヂにはちょっと感動的だった "DiskInternals Linux Reader" の第1回記事はおしまいです。
明日にはコピーが終わっているでしょうから、続編を書いてみたいと思います・・・
Windows PC に Linux 用のハードディスクを接続して、
そのハードディスクのフォルダー/ファイルをコピーするツールを見つけました。
Windows から Linux のディスクを扱う必要性は(たいていの場合は)無いと思いますが、
たまたまその必要が生じたのでツールのお世話になりました。
さて、その必要とは・・・(長い話になります、ご覚悟下さい)
ある友人がメールサーバーなどの環境を用意して、
仲間たちのメーリングリストとして(他のサービスも)提供してくれていました。
10年以上に渡り、我々はこの恩恵に浴してきました。
ところがこのサーバーが不調になりました。
修復できないエラーがハードディスクに発生したのです。
で、2基のハードディスク(*1)を預かって中身(ファイル)を取り出すことにしたのですが、
なにぶん10年以上前から使われていたものです。
昨今の Serial ATA のディスクではなく、例の 40 pin - IDE(ATA)のディスクです。
(*1)1基目はおそらくシステムが入ったディスク、
2基目はおそらくメールデータ、画像、音楽などが入ったディスクでしょう。
別の友人から IDE(ATA)-- USB 変換アダプターを借用して
Windows PC に USB接続したのですが、なぜか認識されません。
(リムーバブルデバイスとして認識されることを期待していたのですが・・・)
やむなく大昔のPCを出してきました。
これだと IDE のドライブを接続することができるからです。
SATA ドライブは接続できません (^_^;)
さすがにこのPCだと IDE ドライブが認識されて(Linux 用ハードディスクが認識できて)、
OSが起動しました(Vine Linux でした)。
が、システムドライブに修復できないエラーがあり、X-Window まで到達できません。
♯ 事情があって、ユーザーアカウント、パスワードも不明なので、
X-Window が立ち上がっても、あるいはすっぴんの Linux 起動状態でも、
お手上げではありますが、何とかデータだけは吸い上げたい。
はてさてどうしたものか・・・
実は、この大昔のPCですが・・・
2年ほど前に Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP が起動できるようにしていました。
名前は忘れましたが、リムーバブルなHDDカートリッジがありましたよね。
PCのフロント、5" ベイにベースとなるアダプターを入れて、
HDDを入れたカートリッジをそこにガチャンコと挿入して使うやつです。
幾つかのカートリッジを用意しておけば、それらを入れ替えていろんな環境に切り替えられます。
2つのカートリッジがあって、1つ目には Windows 98SE のシステムHDDを入れていました。
2つ目には Windwos 2000、Windows XP のデュアルブートHDDを入れていました。
で、今回はデュアルブート用カートリッジを使い、Windows XP を起動しました。
もちろん Linux 用HDDもPCに接続しています。
Windows XP では、Linux HDDはベアドライブとしては認識できたものの、
その中身にアクセスできません(不明なドライブと認識されています)。
パーティション構造すらどうなっているか分かりません。
・・・で、本題に戻ります。
何とか Windows で Linux HDD(の中身)を読めないものだろうか。
探したところ・・・ありました。
"DiskInternals Linux Reader" なるソフトです。
Linux で使われているファイルシステム、Ext2/Ext3/Ext4 を扱えるとのこと。
で、"DiskInternals Linux Reader" をダウンロード&インストールしました。
起動しました・・・う~ん、スゴイ!
エクスプローラーのような画面が現れ、
左にはドライブが、右には選択したドライブの詳細(リストビュー?)が見えました。
これで Linux ハードディスクのファイルがコピーできます。
# 最初は NAS にコピーしようとしましたが、
旧式PCでは 100Mbps(100BASE-T)の NIC で、
なぜかネットワーク経由でコピーし始めると CPU 使用率が 100% になってしまいました。
(svchost が CPU をバカ食いしていました)
これじゃコピー完了まで2、3日かかりそう・・・
Windows 2000、XP デュアルブートの IDE ハードディスクには、どちらのパーティションにも十分な空き容量がありました。
なので、Win2K 用のパーティションにコピーすることにしました。
(それでも相当時間がかかりましたが・・・)
さて、DiskInternals Linux Reader のおかげで
Win.XP から Linux ハードディスクの中身をコピーすることができました。
(その間に旧友たちとの飲み会があったので、コピー途中で外出して、帰宅したらコピーが終わっていました)
さらに今後のことを考えて、
旧PC(の IDE ハードディス)からコピーした中身を USB 接続・外付けHDD(実際はSSD)にコピー中です。
旧PCをいつまでも出しておくわけにはいきませんし(モニターは女房殿のを借用中ですし)、
何をするにも快適・快速とはいえないからです。
# ちなみに旧PCのマザーボードは(AOpen)AX6BC Pro II というものです。
グラフィックカードは AGP スロットに挿した(AOpen)GeForce3 Ti200。
(AGP なんてオールドファンには懐かしいでしょ)
CPU は Slot-1 に挿した Pentium III 600E。
(Slot-1 は短命でした、Intel 焦りすぎの仕様だったと思います)
このマザーは一応 USB にも対応しているのですが、USB 1.1 です。
この USB ポートに、最新 USB 3.0 対応の外付け SSD を接続してコピー・・・
「リービッヒの最小律」がここでも有効で、
合計 30GB ほどですが、なかなかコピーが終わりません。
というわけで、オヤヂにはちょっと感動的だった "DiskInternals Linux Reader" の第1回記事はおしまいです。
明日にはコピーが終わっているでしょうから、続編を書いてみたいと思います・・・