「NPO法人炭鉱の記憶推進事業団」の理事長・吉岡宏高さんによる「空知の炭鉱」に関する本です。
「NPO法人炭鉱の記憶推進事業団」といえば、何度かそらち炭鉱の記憶マネジメントセンターを訪れたことがあります。
今年の2月に行った「記録映像 上映会」でMCをされていたのも吉岡さんでした。
「記録映像 上映会にいってきました~」
「愛と希望の炭鉱、他」
というわけで、炭鉱的なアレやコレに興味を持つようになったので、この本を読んでみました。
A-COLORは北海道生まれ北海道育ちです。
そうとう古い家で、石炭ストーブを使っていたのを目撃したことがありますが、実際に石炭を手にしたことはありません。
炭鉱といえば、小学生のころに夕張の炭鉱で大事故が起こったのをテレビで見ていた、程度の知識しかありません。
そもそも事故以前の炭鉱がどのようなものだったのか知らないし、むしろ夕張といえば観光の町で「バリバリ夕張!」ぐらいの印象しかない。
っていうか、むしろ炭鉱=暗くて怖いイメージがあります。
それを端的に表現しているのが、公共広告機構のCMでしょう。
</object>
YouTube: 公共広告機構「軍艦島」 CM
程度の違いはあっても、たぶん我々と同年代の人も似たような感じじゃないでしょうか。
そんな程度の知識の人が読んでみても、第1章で炭鉱に関する用語の解説があり、文体も難しくないので、炭鉱的なアレやコレに興味にある方なら読みやすいと思います。
第1章を読むと、炭鉱遺構がどうしてこのようになっているのか、多少なりとも理解が深まることでしょう。
第2章と第3章で、吉岡さんが産炭地で生まれ育った記憶や経験を元に、炭鉱での仕事と生活が綴られています。
あくまでも吉岡さんのという個人の経験がベースなので、すべてに当てはまるわけではなく、それこそ山本作兵衛さんの炭鉱画とも違っていて当然です。
(その理由も本書では触れられています)
でも、炭鉱での生活の一部分がこうして語られることで、公共広告機構的な炭鉱ではない、人が住んでいた炭鉱の姿を知ることができます。
それと同時に「なぜ、炭鉱が廃墟になってしまったのか」、単純にエネルギー政策の転換だけが理由ではない、というのが浮き彫りになります。
そして、第4章にいたって我々が炭鉱に「暗くて怖い」イメージを持つ理由について、吉岡さんという当事者からの分析が語られます。
補助金がらみのくだりは、ウワサ話程度には聞いていましたが、このように語られると「やっぱり本当だったのかな」と思ったりします。
私的にはここが一番おもしろかったですが、さほどページが割かれていないのが残念なところ。
最後の第5章でNPO法人炭鉱の記憶推進事業団が目指す、空知のまちづくりに関して語られています。
我々が知っている炭鉱の姿といえば、この部分にあたります。
炭鉱がらみの書籍は産業史的に語られるものが多いです。
また、廃墟関係の書籍で炭鉱遺構の紹介もあります。
本書では炭鉱が興り、そして没落し、現在はまちづくりの資産となっていく、という一連の流れを追っています(駆け足ですが)。
繰り返しになりますが、本書は空知の炭鉱(幌内)を中心に書かれたもので、決して日本の炭鉱のすべてを語ったものではありません。
それでも子どものころからの「暗くて怖い」イメージの炭鉱と、最近になって訪れるようになった炭鉱遺構(と、その周辺)に見られる好意的なイメージとのギャップを埋めるのに、最良の一冊と言えるでしょう。
 |
明るい炭鉱 価格:¥ 1,680(税込) 発売日:2012-08-08 |













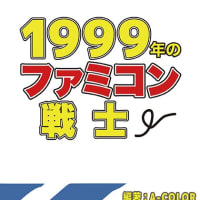

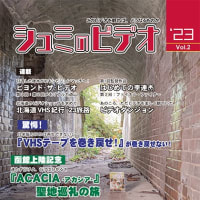


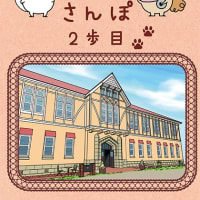
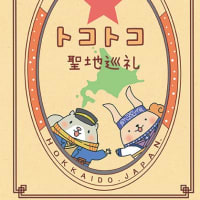

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます