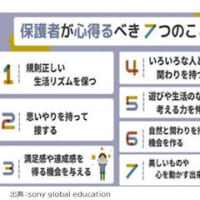今日12月12日は、地域の中学校で福祉教育のお手伝いに参加しました。
内容としては、一つは、車いす体験です。中学校の体育館内でマットによる段差とカラーコーンでジグザグ走行をすることを、押す役・乗る役の2人1組で体験しました。
もう一つは、視覚障がい者の歩行誘導です。障がい者役は、白杖を持って進んでもらいますが、肘を持て掴まった手を通して動きを感じてもらいながら、階段の段差では声をかけて安全な歩行を体験してもらいました。


二時限の授業時間でしたが、二通りの体験で障害のある人たちの生活の一部を疑似体験しました。
福祉教育で肝心なのはそのような障害のある人とのコミュニケーションの取り方だと思います。
街で困った方を見たら声を掛け、その方の気持ちを聞いてからお手伝いをするという、目配り・気配り・心配りが大切なのです。その時に障がいのある方が介助を必要としているのか、自分で出来るのか判断して、行動に移すことが福祉教育なのだと思うのです。
昨今は人を思いやる心が廃れてきたような気がしていましたが、子供たちが体験を通じて、心優しい大人に成長してくれることを願って止みません。


まず、最初に車いす体験です。子供たちは車いすを動かせるようにして、別の子どもに乗ってもらいます。そしてフットレストに足を乗せてから、ブレーキを解除し、「押しますよ」と声をかけて進みます。マットでこしらえた段差にかかると、「上がりますよ」と声をかけて前輪をあげ、降ろすときはマットの上にのせてターンし、「降ろしますよ」と声をかけてゆっくり降ります。あとはコーンの間をターンしながら進み、同じことをして、元の場所に戻ります。


続いて、視覚障がい者の方の歩行体験をしました。地域には様々な方が、障がいを持ちながら生活しています。特に今回は,アイマスクをして目の不自由な方が廊下を歩いたり階段を昇り降りしたりするときの気持ちを体験したり、まわりの人が目の不自由な方に対して出来ることを考えたりしました。とても貴重な経験ができたと思いますので,これからの生活にぜひ生かして欲しいと思います。
アイマスクの代わりに黒いマスクを着けてブラインドウォークを体験してもらったのですが、階段の場面では、子供たちは怖いと言いながらゆっくり降りていく子どもや、慣れた階段なので、お手伝いの私が驚くほどスイスイと降りていく子供など、様々な子供たちの対応にびっくりしました。
この体験において子どもたちが、普段の生活にかかわりを持って、多くの気付きがある中で、地域に住んでいる人たちの生活に触れ合いながら、身をもって体感する事が出来たるのだなあと思います。
一方では同じように、今は自転車のマナー無視の危険走行によって歩行者が隅に追いやられ、窮屈に歩く状況が大きな問題になり、交通法規も厳しくなりました。
でも、今から一人一人が思いやりを持って接していくことで、未来には本当に安心して暮らせる人に優しい地域社会が生まれると思います。むしろ、そんな子供に育ってくれることを願ってお手伝いを終えました。
内容としては、一つは、車いす体験です。中学校の体育館内でマットによる段差とカラーコーンでジグザグ走行をすることを、押す役・乗る役の2人1組で体験しました。
もう一つは、視覚障がい者の歩行誘導です。障がい者役は、白杖を持って進んでもらいますが、肘を持て掴まった手を通して動きを感じてもらいながら、階段の段差では声をかけて安全な歩行を体験してもらいました。


二時限の授業時間でしたが、二通りの体験で障害のある人たちの生活の一部を疑似体験しました。
福祉教育で肝心なのはそのような障害のある人とのコミュニケーションの取り方だと思います。
街で困った方を見たら声を掛け、その方の気持ちを聞いてからお手伝いをするという、目配り・気配り・心配りが大切なのです。その時に障がいのある方が介助を必要としているのか、自分で出来るのか判断して、行動に移すことが福祉教育なのだと思うのです。
昨今は人を思いやる心が廃れてきたような気がしていましたが、子供たちが体験を通じて、心優しい大人に成長してくれることを願って止みません。


まず、最初に車いす体験です。子供たちは車いすを動かせるようにして、別の子どもに乗ってもらいます。そしてフットレストに足を乗せてから、ブレーキを解除し、「押しますよ」と声をかけて進みます。マットでこしらえた段差にかかると、「上がりますよ」と声をかけて前輪をあげ、降ろすときはマットの上にのせてターンし、「降ろしますよ」と声をかけてゆっくり降ります。あとはコーンの間をターンしながら進み、同じことをして、元の場所に戻ります。


続いて、視覚障がい者の方の歩行体験をしました。地域には様々な方が、障がいを持ちながら生活しています。特に今回は,アイマスクをして目の不自由な方が廊下を歩いたり階段を昇り降りしたりするときの気持ちを体験したり、まわりの人が目の不自由な方に対して出来ることを考えたりしました。とても貴重な経験ができたと思いますので,これからの生活にぜひ生かして欲しいと思います。
アイマスクの代わりに黒いマスクを着けてブラインドウォークを体験してもらったのですが、階段の場面では、子供たちは怖いと言いながらゆっくり降りていく子どもや、慣れた階段なので、お手伝いの私が驚くほどスイスイと降りていく子供など、様々な子供たちの対応にびっくりしました。
この体験において子どもたちが、普段の生活にかかわりを持って、多くの気付きがある中で、地域に住んでいる人たちの生活に触れ合いながら、身をもって体感する事が出来たるのだなあと思います。
一方では同じように、今は自転車のマナー無視の危険走行によって歩行者が隅に追いやられ、窮屈に歩く状況が大きな問題になり、交通法規も厳しくなりました。
でも、今から一人一人が思いやりを持って接していくことで、未来には本当に安心して暮らせる人に優しい地域社会が生まれると思います。むしろ、そんな子供に育ってくれることを願ってお手伝いを終えました。