
【連載】藤原雄介のちょっと寄り道(95)
ロンドンの野良狐と東京の野良狸
ロンドン郊外ハムステッドの自宅の裏庭には、時々4~5匹のキツネの家族が遊びに来ていた。
休みの日など、3階(英国では2階と呼ぶ)の部屋のベランダから庭の奥の方に固まってあくびをしながら寝そべっている親キツネ、追いかけっこをして遊ぶ子ギツネたちを眺めるのはとても心癒やされる時間だった。
ただ、よく観察すると、何匹かのキツネは皮膚病に冒されて赤くただれた皮膚をもどかしそうに掻きむしっている。無残な姿だ。

▲ハムステッドの自宅の裏庭(春)。この写真の奥の方にキツネの家族がよく遊びに来ていた

▲ハムステッドの自宅の裏庭(冬)

▲庭に遊びにきたリス
ロンドンには、野良犬や野良猫はいないのに、郊外だけではなく、市の中心部にも驚くほど多くの「野良ギツネ」がいる。
ガーディアン紙の古い記事(2017年)によると、イングランドには約15万匹の狐(Red fox=アカキツネ)が棲息しており、その内、1万匹がロンドンで都会暮らしをしているらしい。
大量の残飯、自然豊かで広大な多くの公園、古い建物の隙間の隠れ家、郊外に多いdetached houseと呼ばれる庭付き一軒家、寒い冬には地下鉄の排気口から温かい風が吹き出して寒さをしのげる…ロンドンなどの都会は郊外よりむしろ狐にとって食と住に恵まれていると指摘する研究者もいる。
しかし、キツネにとって良いことばかりではない。毎年、ロンドンのキツネの60%は交通事故で死んでいくし、美味しい(?)人間の残飯は、自然界には存在しない高い脂質や糖分を含み、更には添加物だらけである。
だから、多くのキツネは成人病や皮膚病に冒されることが多く、健康な個体はほとんどいないのが現状だ。

▲自宅近くのHampstead Heathの森――ハリー・ポッターやロード・オブ・ザ・リングに出てくる魔物の住む森のよう

▲都会の真ん中でくつろぐキツネ

▲脂肪と糖質、食品添加物まみれのゴミと残飯を漁るキツネ――成人病や皮膚病に罹ってしまう(ウツミチ「ロンドン暮らし」から)
キツネが都会に進出し始めたのは100年くらい前からだというが、たった100年の間に、都会暮らしの狐と田舎の狐の間には、顕著な差が現れているそうだ。
英国のThe Royal Society(王立協会・1660年にロンドンで創設された科学に関する団体。「自然についての知識を改善するためのロンドン王立学会」)の記事をバッサリ要約すると、「都会の狐は、頭が小さく、マズル(口吻)が短く幅広、雄雌の体格差が小さい」ということだ。
彼らの食事の37%は人間の残飯で、口吻を地中に突き立てて小動物を捕らえることが少なくなったことも頭蓋骨(口吻)が変形した要因の一つとされている。
都会の狐同士の交配が進み、こうした傾向はますます強まっているらしい。これは「家畜化症候群」と呼ばれ、狐に限らず、人間のそばで暮らすようになった狼やネコ科動物、鼠にも見られるとある。
以前、ヒトに全くなつくことがないと言われるオオカミを数世代に渡って可愛がりながら飼育したところ、まるで犬のように尻尾を振ってヒトになつく個体が増えたというドキュメンタリーを見たことがある。このような事象は、人間の世界にも当てはまるようで、少し怖い気がした。
野良犬、野良猫、はたまたインドや東南アジア辺りでは、野良牛や野良ヤギ、野良ブタまでいる。私は勝手に野良キツネなどという言葉を使っているが、これは国語的には無理があるだろう。
そもそも「野良…」というのは、「飼い主がいない家畜やペット」を指す言葉である。もともと飼い主などいないキツネを野良狐と呼ぶのは、やはりヘンだ。
かといって、都会を我が物顔に闊歩するキツネを「野良キツネ」以外にどう呼べば良いのか、私の貧弱な語彙に適当な言葉は見つからない。
因みに、英語では、犬、猫、狐、牛、山羊…総てひっくるめて「迷子の、はぐれた、家のない、宿なしの、飼い主がいない」を意味する ’stray’ で事足りるようだ。ただし、ロンドンのキツネは、特別待遇で、’urban fox’(都会の狐)と呼ばれる。
さて、日本ではキツネではなくタヌキの都会進出が著しい。日本のタヌキは線路沿いの環境を好むことで知られているが、英国のキツネも線路が好きなようだ。
深夜から早朝にかけて電車は止まっているし、線路脇の草むらや側溝は身を隠すのに都合がよい。更に線路は柵で仕切られているので、ヒトが近寄ってくることはない。良いことずくめではないか。
NHKがまとめた日本全国のタヌキ目撃情報によると、東京がブッチギリの1位である。意外なことに、東北や九州は極めて少ない。
私が住む千葉県は、神奈川に次いで第3位だ。因みに、我が家の近所の公園で最後にタヌキを目撃したのは、3年ほど前だろうか。
以前、紹介したグリーンレンジャーという環境保護団体の活動で、葛の蔦やササダケを相当駆除したので、身を隠す場所が減ったのではないかと密かに気に病んでいる。

▲東京のタヌキの家族
少し脱線するが、最近の欧州では、Re-wilding(リワイルディング=再野生化)という活動が広まっているらしい。これは、ヒトの手が入る以前の植生や生き物が住みやすい自然環境に戻そうという活動である。
私が住む千葉ニュータウンは、自然の地形を残しつつ開発された街だ。Re-wildingを試みるのは難しい。与えられた環境下で私が目指したいのは、「人草木鳥獣魚」総てにとって快適な環境作りだ。
英国では、昔からキツネは、農作物を荒らしたり家畜を襲ったり、また病原菌をまき散らす害獣扱いされてきた。では、現在はどうか。難しい問いかけである。
キツネは、庭を掘り起こして作物を荒らし、花壇をメチャメチャにする。そして、そこら中に糞をする厄介者だ。
一方、畑荒らしの狼藉ではキツネの比ではないウサギを捕食してくれるし、ネズミも退治してくれる。
ウサギはその可愛らしい姿とは裏腹に、いかに畑や花壇を荒らす酷いヤツラかは、ピーターラビットの映画をご覧になった人なら思わず頷いてしまうだろう。
という訳で、ロンドンにおけるキツネの社会的地位は、功罪相半ばする微妙なもののようだ。
貴族のスポーツとして知られたキツネ狩りは、2002年のスコットランドを皮切りに、2004年にはグレートブリテン全体で禁止された。
英国、キツネ、というキーワードが出れば、「キツネ狩り」に触れない訳にはいかないだろうが、今日はこの辺でおしまい。またの機会に。
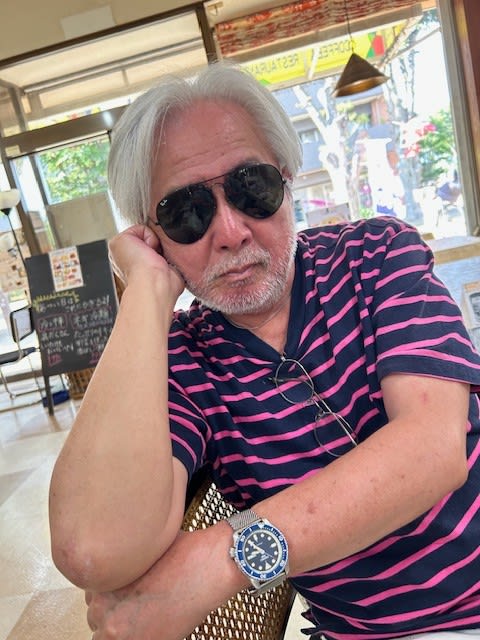
【藤原雄介(ふじわら ゆうすけ)さんのプロフィール】
昭和27(1952)年、大阪生まれ。大阪府立春日丘高校から京都外国語大学外国語学部イスパニア語学科に入学する。大学時代は探検部に所属するが、1年間休学してシベリア鉄道で渡欧。スペインのマドリード・コンプルテンセ大学で学びながら、休み中にバックパッカーとして欧州各国やモロッコ等をヒッチハイクする。大学卒業後の昭和51(1976)年、石川島播磨重工業株式会社(現IHI)に入社、一貫して海外営業・戦略畑を歩む。入社3年目に日墨政府交換留学制度でメキシコのプエブラ州立大学に1年間留学。その後、オランダ・アムステルダム、台北に駐在し、中国室長、IHI (HK) LTD.社長、海外営業戦略部長などを経て、IHIヨーロッパ(IHI Europe Ltd.) 社長としてロンドンに4年間駐在した。定年退職後、IHI環境エンジニアリング株式会社社長補佐としてバイオリアクターなどの東南アジア事業展開に従事。その後、新潟トランシス株式会社で香港国際空港の無人旅客搬送システム拡張工事のプロジェクトコーディネーターを務め、令和元(2019)年9月に同社を退職した。その間、公私合わせて58カ国を訪問。現在、白井市南山に在住し、環境保全団体グリーンレンジャー会長として活動する傍ら英語翻訳業を営む。
























