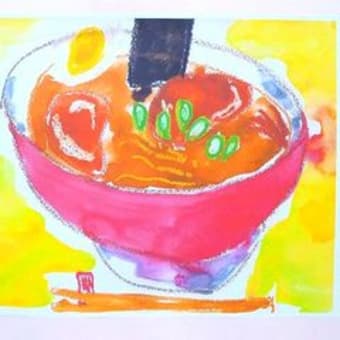「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」
造形リトミック教育研究所 玉野摩知佳
*楽しいからのパートナー
*新しく知るからのパートナー
*ちょっと簡単からのパートナー
 おはようございます。造形リトミック教育研究所の玉野 摩知佳です。
おはようございます。造形リトミック教育研究所の玉野 摩知佳です。もうひとつの教材、「エアコン」。エアコンは最初、クーラーだけでした。つまり冷房だけ。暖房は、ガスや石油のストーブやヒーターを使っていました。
私が小学生のころ、家はもちろん、学校や役所や店などにもクーラーさえありませんでした。電車も、昔は扇風機が天井についていました。車にも、クーラーはついていませんでした。今では考えられませんが、真夏の炎天下は窓全開で走っていました。ですから、渋滞でしかも風がないときは、「蒸し風呂」などと呼んでいたことが思い出されます。
中学生のころ、クーラーのあるところは人気がありました。そのひとつが図書館です。図書館には、よく通いました。夏休みなどは、早くから行って開館を待っていました。
現在のエアコンは、クーラーとヒーターの両機能を備えている進化した機械です。どんどん薄型、コンパクトになって、価格も下がってきました。テクノロジーの進化は確実に生活を豊かにしています。
知的障害や発達障害の方には、暑さが寒さより苦手という方も少なくありません。快適な環境での学習は、グンと効果が上がります。
今月は、この「エアコン」を教材として学んでいます。色、形、メーカー名、デザイン、大きさ、機能、価格・・・いろいろと広がりのある生きた教材です。
家庭でのエアコンの利用の仕方も、学習テーマのひとつです。
・適切な設定温度を知る
・風量や風向を調節する
・数字や記号での表示で、温度の高低や量の多少、向きを知る
・体感としてそれらを感じる
・節電の意識を育てる(省エネ)
・地球の温暖化という現代の問題に触れる
・社会参加の意識と自覚を育てる
何れも指示されて生活するのではなく、積極的に意識的に生活する糧となります。そこに喜びが生じます。
教室の生徒さんは、「エアコンがあって当たり前」という世代です。が、エアコンの快適さとは別に、秋のこの時季の自然のさわやかさも味わい感じてもらえればとも思います。
* 写真は、観覧車の動力部分です。「一体どうなっているのかな?」素朴な疑問
から興味はひろがります。ひとりひとりが自分の世界をみつけ広がっていくこと
は大きな力になります。
info@zoukei-rythmique.jp 造形リトミック教育研究所