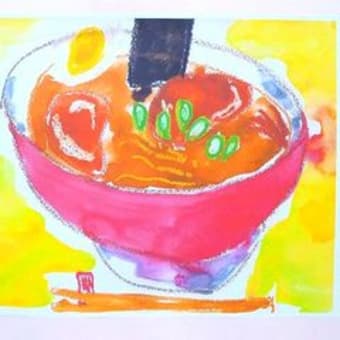「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」: 造形リトミック教育研究所
秋から初冬の今、落ち葉拾いやどんぐり集めは、太陽の光を浴び、ピリッとした空気や風の冷たさを感じる格好の楽しみとなります。それと同時に、数の存在を感じ、数感覚を育むとても良い機会ともなります。
机の上に積み木やミニチュアの果物などを並べて、いきなり「これはいくつ?」と尋ねたり、「~を ○つください」などと指示を出して数の理解をさせようとしても、なかなか数概念を獲得できないことが多いものです。心理テストで数の理解度を測るのならばそれでもよいのですが、数概念を育てるための学習として行うのならば、これは得策ではありません。
数えることを求めたり、合計数を答えさせようとする前に、1個ずつ、1個ずつというものの操作やものの移動を遊びとしてたくさん行いましょう。カップの中に何かものを全部入れる、入れたらまた全部出す、そしてまた入れる、また出す・・・、ものの増えたり減ったりを自分の操作を通して心いくまで体験させるのです。
発達テストの中に、カップの中に積み木を10こ入れさせたり、ものを並べて遊ぶようなことがあるかどうかを尋ねたりする項目があります。たいていの幼児は幼児期に、自然に遊びとしてそんなことを行っているからです。そんな遊びを通して、数感覚を獲得していっているのです。
発達テストことにスクリーニングテストは、まずは被検児が通常の基準どおりに発達しているかを測るものですから、通常の幼児が発達のプロセスでたいてい行うこと自体がテスト項目となっています。言い換えれば、発達テストで問われる課題はたいていの幼児が通過していく課題です。
ハンディのあるお子さんは、幼児期にまだ手先が器用でなかったり、集中力が十分でなかったり、ものの認知が明確でなかったりするために、このような遊びの時期を通過することなく、いわゆる「数学習」へと突入してしまうことがあります。ですから、いっそう数学習の進みが鈍くなってしまうのです。悪くすると、数ぎらいにさせてしまいます。
数ぎらいにさせずに、1ステップずつ数の学習を進めていくためには、このたいていの幼児が行う遊びを十分に行うチャンスを作ってあげましょう。尋ねたり指示したりと迫らずに、ものを移動させたりものを並べたりすることを一緒に楽しんであげましょう。このような遊びの中で、数学習にとって不可欠な数感覚が育まれていくのです。
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp