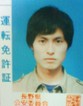5/18(土)、新潟市美術館「もしも猫展」を見に行ってきました。
江戸時代から幕末にかけて描かれた浮世絵の中には、猫を描いたものがたくさんあった。
その中で今回は、猫が人間のように服を着たり歩いたりする「擬人化」を描いた作品を紹介。
猫の擬人化で代表的なものは、有名な浮世絵の人間の格好や服装を猫に置き換えたもので、そういう遊び心ある浮世絵が江戸時代にはたくさん描かれていた。
どうして、こんな絵が描かれていたのか…?というところから発想が広がるように、様々な浮世絵を紹介していく。
浮世絵には猫以外にも動物や道具などの擬人化が描かれた作品がたくさんあることが紹介され、浮世絵における擬人化文化の奥深さを知る。
その擬人化文化の背景には、日本人の中にある無機物にも命が宿る、動物も人間と同じように行動するという、自然観、宗教観があるのではないかと、百鬼夜行図も紹介されていました。
さらに江戸時代の文化が栄えると、人気の歌舞伎役者の浮世絵が今でいうアイドルのブロマイドのように販売されていたそうですが、それが規制された時代もあったそうです。
しかし、そんな時代にも、猫などの顔を有名な歌舞伎俳優に似せることで、規制を掻い潜って販売すると同時に、そんな社会に対する風刺も込めていたという、江戸の浮世絵師たちの抵抗を知れるのも面白い。
これは猫以外にも、色々な動物や妖怪にも応用し、妖怪図、百鬼夜行図に見えて、実は当時の幕府を風刺している作品などもありました。
なんというか、世の中の理不尽に対して遊び心で抵抗するあたり、まさに風刺漫画の走りのようでした。
有名人の似顔絵を猫で描く上で、表情の描き分けはすごく大切だったそうですが、その手本となった作品として有名な北斎漫画も紹介。
有名な浮世絵師が活躍することで、その文化が次の世代へと伝わり、発展していく、本当に豊かな文化だったのだと思いました。
そして、銭湯、料理屋、遊郭などの江戸の文化や風俗を紹介する浮世絵を、擬人化した猫によって描いた作品は大人気で、紙を組み立てて作るおもちゃまで販売されていたとのこと。
まるで漫画のキャラクターがプラモデルとしても人気になるような豊かな文化を感じました。
そんな感じで、猫の擬人化を中心に、江戸時代の人達がいかに遊び心に溢れた豊かな文化を楽しんでいたのかが伝わる展示でした。
新潟市マンガの家では「こんにちは こりすのぽっこちゃん 太田じろうの世界展」が開催中ですが、そういう動物のキャラクターを描いた絵本や漫画の世界は、江戸時代から続いてきた文化だったのかと思わされました。












![【お知らせ】「ローサ大喜利」vol.13[6/16(日) 14:00、よろっtoローサ]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/26/29/7e848a8b7a91cc651dc330a8d990fa45.jpg)