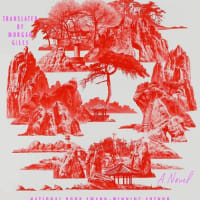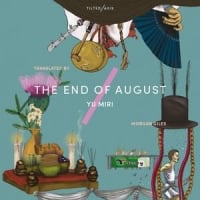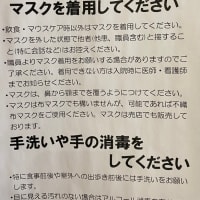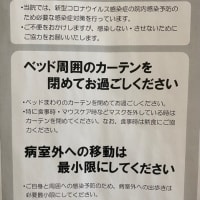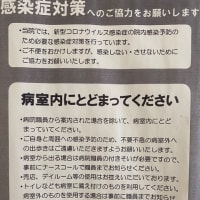昨年末から相馬藩における真宗移民について調べていて、何冊か本を読んでいたのですが、
文献ではわからないことがあるので、勝縁寺と常福寺のご住職に、お話をうかがいたい、とお手紙を書き、お返事をいただいていたのです。
【鹿島区 勝縁寺】
文化七年に加賀越中の移民を檀家として寺を開く。鋭意開墾に従事し、その利潤米を以て毎年10戸ずつの移民を勧誘した。天保5年寺号を許される。
【原町 常福寺】
越後蒲原郡堤村、光円寺の次男、文化八年五月当地に来て草庵を建つ。発教とともに移民勧誘に尽力した。
200年前、相馬藩は北陸から開拓移民を勧誘し、弘化2年(1844)までには1800戸に達していた。
相馬藩は、真言宗や禅宗寺院が多く、加賀、越中からの移民は浄土真宗門徒だったために、
(当時、真宗は、仏教の中で唯一火葬を行なっていた。他宗は土葬)
「加賀者(かがもの)」と差別され、土間までしか上げてもらえなかった。
一方で、真宗移民たちは、元から相馬に住んでいた人たちを「土着様(どちゃくさま)」と呼んで区別していた。
『宗教・習俗の生活規制に関する調査研究』に「檀家帳から見た相馬藩真宗移民の分布と所属寺院」が記してあるのだが、
今回津波被害が大きかった地域に、真宗移民が多い。
わたしの知り合いで、津波で家を流された何人かのひとも、先祖は真宗移民で、金沢や富山の方にはよくある苗字だと聞いた。
移民が、開墾せよと与えられたのは、海沿いや山中の荒れた土地しかなく、差別と闘いながら必死に開墾して、200年間この地で子孫を繁栄させたのに、津波と原発事故で全てを失うなんて――。
「われわれは流浪の民ですから……」
という勝縁寺ご住職の湯澤義秀さんの言葉を、ずっと考えつづけています。
それはおそらくわたしが、60年前に祖国を離れ、三代に渡って異国で暮らしている在日韓国人だからです。
文献ではわからないことがあるので、勝縁寺と常福寺のご住職に、お話をうかがいたい、とお手紙を書き、お返事をいただいていたのです。
【鹿島区 勝縁寺】
文化七年に加賀越中の移民を檀家として寺を開く。鋭意開墾に従事し、その利潤米を以て毎年10戸ずつの移民を勧誘した。天保5年寺号を許される。
【原町 常福寺】
越後蒲原郡堤村、光円寺の次男、文化八年五月当地に来て草庵を建つ。発教とともに移民勧誘に尽力した。
200年前、相馬藩は北陸から開拓移民を勧誘し、弘化2年(1844)までには1800戸に達していた。
相馬藩は、真言宗や禅宗寺院が多く、加賀、越中からの移民は浄土真宗門徒だったために、
(当時、真宗は、仏教の中で唯一火葬を行なっていた。他宗は土葬)
「加賀者(かがもの)」と差別され、土間までしか上げてもらえなかった。
一方で、真宗移民たちは、元から相馬に住んでいた人たちを「土着様(どちゃくさま)」と呼んで区別していた。
『宗教・習俗の生活規制に関する調査研究』に「檀家帳から見た相馬藩真宗移民の分布と所属寺院」が記してあるのだが、
今回津波被害が大きかった地域に、真宗移民が多い。
わたしの知り合いで、津波で家を流された何人かのひとも、先祖は真宗移民で、金沢や富山の方にはよくある苗字だと聞いた。
移民が、開墾せよと与えられたのは、海沿いや山中の荒れた土地しかなく、差別と闘いながら必死に開墾して、200年間この地で子孫を繁栄させたのに、津波と原発事故で全てを失うなんて――。
「われわれは流浪の民ですから……」
という勝縁寺ご住職の湯澤義秀さんの言葉を、ずっと考えつづけています。
それはおそらくわたしが、60年前に祖国を離れ、三代に渡って異国で暮らしている在日韓国人だからです。