民国時代も後期に入った1930年代、糞業の改革への声が高くなってきたのは、
こうした競争激化により生存環境の悪化した糞夫や糞覇らが、暴力集団化してきたからである。
もはや座視できぬところまで市民の日常生活に影響を及ぼしつつあったのだ。
糞業界を戦闘集団に鍛え上げる大きな要因のなったのが、「跑海」の存在だ。
縄張り、雇用主を持たぬ腕一本の「盗っ人」である彼らは、己の機微と才覚一本で真剣勝負する命知らずの戦士である。
「跑海」も次第に増えつつあった。
これも鶏が先か卵が先かの関係にあり、根本的な原因は糞業への新規参入者の激増による悪循環だ。
新たに参入してきた、肉体のほか何ら資本のない男どもが「糞道」の権利を買い取れるはずはなかった。
また新規参入が多くなると、糞道の権利の値段も上がり、余計に手が出なくなる。
そうなると、糞道を持つ主人の下で雇われて働くしかないが、
後から後からどんどんと希望者がいくらでも入ってくる状況であれば、
雇う側としては次第に待遇を落としていくのも自然の摂理だ。
何しろ悪条件でも働かないと、いくらでも代わりはいるということになる。
働いても働いても暮らしがよくならぬ、まさに老舎の「駱駝のシャンツ」のようなワーキングプア状態だ。
そんな中、少しでも自分の腕っぷしと要領に自信があれば、
雇い主に搾取されるよりは自分の腕しだいで利益を挙げられる「跑海」をあえて選ばん、と考える輩も多かったことは、容易に想像できる。
もうこれ以上、下はない、というところまで追い詰められれば人間、怖い物もなくなる。
そんな「跑海」らの被害を蒙る一般糞夫らは、たまったものではない。
雇われ糞夫ならご主人様の糞が少々減ろうが、自分の腹は痛まないが、
自前の糞道を持つ「自作」糞夫なら、生活がかかっているからこちらも本気を出して迎え撃つ。
当時の新聞の糞夫インタビューを見ると、鼻息荒い。
「あいつら(跑海)は、隙を狙っては未回収の糞を盗みやがる。
出くわした日には、ただじゃあおかねえ。
腕力のすべてを賭け、持っているあらゆる道具を総動員して死闘を繰り広げる。
口で罵り、拳骨をお見舞いし、糞勺で殴りつけ、相手を青あざだらけにし、顔を腫れ上がらせ、
頭から血をどくどく流させるまで容赦はしない。
最後に相手の糞桶と糞勺を差し押さえる。
俺の糞道は命の源。
誰にも侵させるわけにいかねえ」
(1936年6月18日、北平晨報)
糞夫らが暴力集団化した背景には、こうした「跑海」らを相手として日々繰り広げる戦闘があるらしい。
毎日の日常で青あざが絶えず、生傷が癒える暇もなければ、気性が荒くなり、命知らずになるのは、当然の起因だ。
日常的な戦闘態勢で研ぎ澄まされた反射神経と鋭い刃物を振り回すかの如き気性の荒々しさを誇示する集団と化した糞夫らは、
しだいに大きな社会問題となってくる。
糞業は、近代までは完全に民間の自然の摂理に任され、行政が介入することはなかった。
介入が起こったのは、民国も中期になってからである。
1928年、国民党政権が北平で「糞夫工会」を組織した。
「工会」は、日本でいう労働組合である。
労働組合とは名ばかり、糞夫らを雇う側の「糞覇」らも加入していたから、
労働者の立場と待遇を守るためにあるはずの労働組合の意味を成していない。
それでも組織化することにより、少しは前進もあった。
工会が正式な糞道の証明書を発行したのである。
それまでは「既成事実」としての糞道の権利があったが、
合法ではないため、トラブルが絶えず、糞夫らは互いに自らの権利を主張して暴力沙汰が頻繁に起こっていた。
この証明書発行により、「糞道」の存在と権利が、初めて合法的に認められたことになる。
2年後の1930年6月19日には、『北平市城区糞夫管理規則』なるものが公布される。その内容は:
1、糞夫の許可証制度の導入。糞夫の通し番号を発行する。
2、糞車の統一。糞夫として登録すると、ナンバープレートを配布するので、これを糞車の前にかける。今の時点では、プレート料金は徴収しない。
3、住民にチップを求めてはならない。
4、指定のルートで、指定の時間帯に城外に運び出し、城内に貯めてはならない。散在させたり、糞車に規定以上の重量を積んではならない。
さらに4ヵ月後の10月には、糞夫工会が『管理糞夫工友規則』を作る。
1、毎日汲み取りを行い、雨、強風など、如何なる天候の時でも怠ってはならない。
2、報酬を勝手に値上げしてはならないほか、住民をゆすってもならない。
3、工友(=労働組合メンバー)は、住民に平和な態度で臨むべし。
4、工友はおまるの洗う際、清潔にし、四方にこぼしてはならない。
つまりは、守られていなかったからこそ、規則を決めなければならなかった現状が浮かび上がってくる。
一般的な糞夫は、毎日汲み取りに行くとは限らず、雨が降った、風が吹いたといっては汲み取りに来ないカメハメハの子供たちの如き習性があり、
何かにつけて値上げや揺すりを住民にかけ、
まったく平和的でない態度で接し、おまるを洗う時も粗雑に洗っては、あちこちのこぼしまくっていたということである。
改革が強く叫ばれるようになったのには、もう一つの理由もある。
それは1900年以後、全国的に伝染病が頻繁に流行するようになったことがある。
1917年―1948年までの間に死者が1万人を超える疫病が、全国で12箇所も発生している。
中国でも西洋とも接点が多くなってきたこともあり、
西洋医学、細菌病理学、植民地の熱帯医学を踏まえてその原因を分析するようになり、
糞業が病原菌を運ぶ昆虫、ハエの温床になっているという見方が広がりつつあった。
規則の中に「糞車」のナンバープレート発行が盛り込まれていたが、糞車の改革をまず単独で追いたい。
糞夫らの抵抗の経緯の中に挟みこむと、前後の順序が追いにくいからだ。
北京の人口が増え出し、最も市民らを閉口させたのは、「あの糞車はどうにかならないか」ということである。
前述のとおり、糞夫らの標準スタイルは背負い桶に長い糞勺だが、こ
れは個々の狭い路地に入ったり、四合院の中に入る際、移動に便利なようにするためであり、
大通りには糞車を置き、桶の中身を入れて移動させていた。
ごくたまに車さえなく、背中に桶を背負ったまま城外の糞場まで運ぶ糞夫もいたが、
その数はごくわずか、糞夫の中でも最下層にある人々のみである。
糞車は清代から変わらない一輪車の両側にイバラの蔓(つる)で編んだカゴをつるしたスタイル。
蔓編みだから当然密封性はよろしくなく、蔓の間から糞尿がぽたぽたと落ちることになる。
伝統的にフタをつける習慣もなく、下からはぼたぼたこぼしまくり、
上からは臭気を撒き散らすという極めて愉しくない移動物であった。
さらに一輪車のため、安定性が悪く、
雨の日、厳寒の道が凍りつく冬の日、雪が降った日、少しでも足元がすべれば、かごの中身は道路に真っ逆さま。
大事な飯の種なので、拾い集めることはもちろんだとしても、
そうそうきれいにこそぎ取れるものでもなく、その残骸や液体のしみ込んだ地面は何日も通行人に悪臭を散じ続けた。
城内の人通りが増え、並行的に糞車の通行の頻度も上がってくると、当然「どうにかしろ」という声が高くなってきたのである。
辛亥革命の成立まもなく、京師警察庁が糞具の改革を呼びかけたことがあったが、
業界の激しい反対に逢い、未遂に終わった。
1918年、市政の公所が警察所とともに、イバラ蔓カゴにフタを命じる条例の可決を試みたが、
またもや業界からの強い圧力を受け、実施が難航しているところに時局が変化し、政権が代わって再びうやむやに終わった。
悪評高かったイバラ蔓のぼたぼたカゴを廃止できたのは、実に1936年。
当時の処理糞便事務所が、緑色の木の箱桶を製作した上、これを糞夫らに支給した時である。
一輪車もほとんど安定性のある二輪車に変えた。カゴ一つの改革になんと30年の月日がかかっている。

最終スタイル
ふたをつけましょう、というごく理にかなったことに思える提案に、なぜそこまで反対が強かったのか。
おそらく経費を糞夫側に負担させようとしたことと社会的に蔑視されている彼らの反発心もある。
普段は自分たちを「屎壳郎(シーコーラン、=フンコロガシ)」と陰口をたたいて忌み嫌っているくせに、
へえそうかい、わしらに頼みごとがあるんかい、というわけだ。
**************************************************************************
写真: 恭親王府。2005年。続き。
来賓休憩室の中です。
オリンピック前後になり、画期的に違うのは、こういった名所旧跡の室内調度品ですな。
外の建築は昔も今もあまり変わらないのですが、10年ほど前までは、部屋の中は空っぽか、もしくはお粗末な調度品しかありませんでした。
こういうところで国力の充実を感じますな。




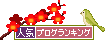
 にほんブログ村
にほんブログ村 



こうした競争激化により生存環境の悪化した糞夫や糞覇らが、暴力集団化してきたからである。
もはや座視できぬところまで市民の日常生活に影響を及ぼしつつあったのだ。
糞業界を戦闘集団に鍛え上げる大きな要因のなったのが、「跑海」の存在だ。
縄張り、雇用主を持たぬ腕一本の「盗っ人」である彼らは、己の機微と才覚一本で真剣勝負する命知らずの戦士である。
「跑海」も次第に増えつつあった。
これも鶏が先か卵が先かの関係にあり、根本的な原因は糞業への新規参入者の激増による悪循環だ。
新たに参入してきた、肉体のほか何ら資本のない男どもが「糞道」の権利を買い取れるはずはなかった。
また新規参入が多くなると、糞道の権利の値段も上がり、余計に手が出なくなる。
そうなると、糞道を持つ主人の下で雇われて働くしかないが、
後から後からどんどんと希望者がいくらでも入ってくる状況であれば、
雇う側としては次第に待遇を落としていくのも自然の摂理だ。
何しろ悪条件でも働かないと、いくらでも代わりはいるということになる。
働いても働いても暮らしがよくならぬ、まさに老舎の「駱駝のシャンツ」のようなワーキングプア状態だ。
そんな中、少しでも自分の腕っぷしと要領に自信があれば、
雇い主に搾取されるよりは自分の腕しだいで利益を挙げられる「跑海」をあえて選ばん、と考える輩も多かったことは、容易に想像できる。
もうこれ以上、下はない、というところまで追い詰められれば人間、怖い物もなくなる。
そんな「跑海」らの被害を蒙る一般糞夫らは、たまったものではない。
雇われ糞夫ならご主人様の糞が少々減ろうが、自分の腹は痛まないが、
自前の糞道を持つ「自作」糞夫なら、生活がかかっているからこちらも本気を出して迎え撃つ。
当時の新聞の糞夫インタビューを見ると、鼻息荒い。
「あいつら(跑海)は、隙を狙っては未回収の糞を盗みやがる。
出くわした日には、ただじゃあおかねえ。
腕力のすべてを賭け、持っているあらゆる道具を総動員して死闘を繰り広げる。
口で罵り、拳骨をお見舞いし、糞勺で殴りつけ、相手を青あざだらけにし、顔を腫れ上がらせ、
頭から血をどくどく流させるまで容赦はしない。
最後に相手の糞桶と糞勺を差し押さえる。
俺の糞道は命の源。
誰にも侵させるわけにいかねえ」
(1936年6月18日、北平晨報)
糞夫らが暴力集団化した背景には、こうした「跑海」らを相手として日々繰り広げる戦闘があるらしい。
毎日の日常で青あざが絶えず、生傷が癒える暇もなければ、気性が荒くなり、命知らずになるのは、当然の起因だ。
日常的な戦闘態勢で研ぎ澄まされた反射神経と鋭い刃物を振り回すかの如き気性の荒々しさを誇示する集団と化した糞夫らは、
しだいに大きな社会問題となってくる。
糞業は、近代までは完全に民間の自然の摂理に任され、行政が介入することはなかった。
介入が起こったのは、民国も中期になってからである。
1928年、国民党政権が北平で「糞夫工会」を組織した。
「工会」は、日本でいう労働組合である。
労働組合とは名ばかり、糞夫らを雇う側の「糞覇」らも加入していたから、
労働者の立場と待遇を守るためにあるはずの労働組合の意味を成していない。
それでも組織化することにより、少しは前進もあった。
工会が正式な糞道の証明書を発行したのである。
それまでは「既成事実」としての糞道の権利があったが、
合法ではないため、トラブルが絶えず、糞夫らは互いに自らの権利を主張して暴力沙汰が頻繁に起こっていた。
この証明書発行により、「糞道」の存在と権利が、初めて合法的に認められたことになる。
2年後の1930年6月19日には、『北平市城区糞夫管理規則』なるものが公布される。その内容は:
1、糞夫の許可証制度の導入。糞夫の通し番号を発行する。
2、糞車の統一。糞夫として登録すると、ナンバープレートを配布するので、これを糞車の前にかける。今の時点では、プレート料金は徴収しない。
3、住民にチップを求めてはならない。
4、指定のルートで、指定の時間帯に城外に運び出し、城内に貯めてはならない。散在させたり、糞車に規定以上の重量を積んではならない。
さらに4ヵ月後の10月には、糞夫工会が『管理糞夫工友規則』を作る。
1、毎日汲み取りを行い、雨、強風など、如何なる天候の時でも怠ってはならない。
2、報酬を勝手に値上げしてはならないほか、住民をゆすってもならない。
3、工友(=労働組合メンバー)は、住民に平和な態度で臨むべし。
4、工友はおまるの洗う際、清潔にし、四方にこぼしてはならない。
つまりは、守られていなかったからこそ、規則を決めなければならなかった現状が浮かび上がってくる。
一般的な糞夫は、毎日汲み取りに行くとは限らず、雨が降った、風が吹いたといっては汲み取りに来ないカメハメハの子供たちの如き習性があり、
何かにつけて値上げや揺すりを住民にかけ、
まったく平和的でない態度で接し、おまるを洗う時も粗雑に洗っては、あちこちのこぼしまくっていたということである。
改革が強く叫ばれるようになったのには、もう一つの理由もある。
それは1900年以後、全国的に伝染病が頻繁に流行するようになったことがある。
1917年―1948年までの間に死者が1万人を超える疫病が、全国で12箇所も発生している。
中国でも西洋とも接点が多くなってきたこともあり、
西洋医学、細菌病理学、植民地の熱帯医学を踏まえてその原因を分析するようになり、
糞業が病原菌を運ぶ昆虫、ハエの温床になっているという見方が広がりつつあった。
規則の中に「糞車」のナンバープレート発行が盛り込まれていたが、糞車の改革をまず単独で追いたい。
糞夫らの抵抗の経緯の中に挟みこむと、前後の順序が追いにくいからだ。
北京の人口が増え出し、最も市民らを閉口させたのは、「あの糞車はどうにかならないか」ということである。
前述のとおり、糞夫らの標準スタイルは背負い桶に長い糞勺だが、こ
れは個々の狭い路地に入ったり、四合院の中に入る際、移動に便利なようにするためであり、
大通りには糞車を置き、桶の中身を入れて移動させていた。
ごくたまに車さえなく、背中に桶を背負ったまま城外の糞場まで運ぶ糞夫もいたが、
その数はごくわずか、糞夫の中でも最下層にある人々のみである。
糞車は清代から変わらない一輪車の両側にイバラの蔓(つる)で編んだカゴをつるしたスタイル。
蔓編みだから当然密封性はよろしくなく、蔓の間から糞尿がぽたぽたと落ちることになる。
伝統的にフタをつける習慣もなく、下からはぼたぼたこぼしまくり、
上からは臭気を撒き散らすという極めて愉しくない移動物であった。
さらに一輪車のため、安定性が悪く、
雨の日、厳寒の道が凍りつく冬の日、雪が降った日、少しでも足元がすべれば、かごの中身は道路に真っ逆さま。
大事な飯の種なので、拾い集めることはもちろんだとしても、
そうそうきれいにこそぎ取れるものでもなく、その残骸や液体のしみ込んだ地面は何日も通行人に悪臭を散じ続けた。
城内の人通りが増え、並行的に糞車の通行の頻度も上がってくると、当然「どうにかしろ」という声が高くなってきたのである。
辛亥革命の成立まもなく、京師警察庁が糞具の改革を呼びかけたことがあったが、
業界の激しい反対に逢い、未遂に終わった。
1918年、市政の公所が警察所とともに、イバラ蔓カゴにフタを命じる条例の可決を試みたが、
またもや業界からの強い圧力を受け、実施が難航しているところに時局が変化し、政権が代わって再びうやむやに終わった。
悪評高かったイバラ蔓のぼたぼたカゴを廃止できたのは、実に1936年。
当時の処理糞便事務所が、緑色の木の箱桶を製作した上、これを糞夫らに支給した時である。
一輪車もほとんど安定性のある二輪車に変えた。カゴ一つの改革になんと30年の月日がかかっている。

最終スタイル
ふたをつけましょう、というごく理にかなったことに思える提案に、なぜそこまで反対が強かったのか。
おそらく経費を糞夫側に負担させようとしたことと社会的に蔑視されている彼らの反発心もある。
普段は自分たちを「屎壳郎(シーコーラン、=フンコロガシ)」と陰口をたたいて忌み嫌っているくせに、
へえそうかい、わしらに頼みごとがあるんかい、というわけだ。
**************************************************************************
写真: 恭親王府。2005年。続き。
来賓休憩室の中です。
オリンピック前後になり、画期的に違うのは、こういった名所旧跡の室内調度品ですな。
外の建築は昔も今もあまり変わらないのですが、10年ほど前までは、部屋の中は空っぽか、もしくはお粗末な調度品しかありませんでした。
こういうところで国力の充実を感じますな。























底抜けに汚くパソコン越しに臭ってきそうなお話がとても面白かったので堪らずコメントしてしまいました。
胡同トイレ物語を読んで火野葦平の『糞尿譚』を思い出しました。
その小説の主人公は汲み取り業者で家々を回っては人糞の処理を低賃金で引き受けていました。しかし彼は町にとって必要な存在であるはずなのに住民からは嫌われ、糞を値切られたり、あまつさえ他の業者に変えるぞと脅されたりで散々な目に遭います。
そしてそれより以前の日本では糞は大切な肥料なので汲み取り業者が糞を買っていたそうです。
だから住民が肥溜めに水を入れて水増しするのを防ぐために、業者の方は肥溜めに棒を差して粘り気を確かめて水増しを見破っていたそうです。
中国でも最初は住人が汲み取り業者に自分の糞を売っていたのでしょうか。
また日本では富豪の家の肥溜めは良い肥料になったようですが、やはり中国でも金持ちの家は人気があったのでしょうか。
初めてコメントするのにこんな質問だらけの冗長な内容でご迷惑をおかけします。
今後も素敵な記事を楽しみにしております。
>だから住民が肥溜めに水を入れて水増しするのを防ぐために、業者の方は肥溜めに棒を差して粘り気を確かめて水増しを見破っていたそうです。
なるほどー。それは面白い話ですね。
中国のテレビドラマにおかゆの配給に箸を立てる場面が出ていました(笑)。政府から支給された予算で炊き出しを行う役人が、途中で米をちょろまかさないように、検査にきた役人が箸をたててチェックするという話です。
>中国でも最初は住人が汲み取り業者に自分の糞を売っていたのでしょうか。
どうやら、規模が小さいと逆に汲み取り代を払っていたようですね。但しこれは北京での話で、田舎では違っていたのかもしれません。
>また日本では富豪の家の肥溜めは良い肥料になったようですが、やはり中国でも金持ちの家は人気があったのでしょうか。
おっしゃるとおりで、私も記事の初期の頃にどこかで書いたか、忘れてしまいましたが、貧乏人は糞もあまり価値がなかったようです。