デカルトは、文字による学問を放棄して、自分自身のうちに、あるいは「世界という大きな書物」のうちに見つかるかもしれない学問を求めてヨーロッパの旅に出た。 そして、近代化への扉を開けた。
近代の終焉(ラストモダン)を迎えている今、石川仁は「自然という書物」を求めて旅をする。近代化の先端にあるアメリカ、アメリカの母体であるヨーロッパ、文明の発祥の地インドと歴史を遡る旅の後、 人間の生まれる前を想像する場所としてアフリカのサバンナに行き、ついには何もない場所、サハラ砂漠をラクダとともに2700キロの旅に出た。
それは、死の恐怖と生の喜びを体感する旅であり、ときどきラクダに「オマエなー」と呼びかけ、いつまでもついてくるハエに「ウルサイなー、どこかへ行けよ」と語りかける以外に仲間はない。そこは、自分と対話することで、自分の歴史を振り返り、本当の自分と向き合える場所であったという。
それで旅は終わらない。空の青と茶色の砂以外は何もない砂漠の次は、白一色のアラスカの世界、さらに南米コロンビアのジャングルの川を下り、 高い山々のアンデスを旅し、チチカカ湖で葦舟と出会う。葦舟の古代船を復元したマタランギ号で古代の「海の道」を検証する旅に加わり、今は、日本で建造した葦舟で太平洋横断の実験実証の旅に出る夢を育てる。 その夢は、太古の智慧を尊ぶ心から湧き出でる。太古の智慧とは、自然と共に生きること。それが旅の辿りつく場所。
現代では「常識」を意味しているコモン・センスという言葉は、もともとアリストテレス以来、五感を統合する根源的能力を意味する「共通感覚」という言葉として使用されていた。石川仁の旅は、デカルト以来「知識」という殻に閉じ込められてしまった「共通感覚」を呼び覚ます学問の旅だと、私は思う。
デカルトは「世界という大きな書物」のうちに見つかるかもしれない学問を求めたが、結局は理性と感性を分断し、「書かれたもの」を通じての理性の学問を肥大化させた。 しかし、石川仁は「書かれたもの」を残そうとしない。葦舟をつくり、それに乗ることで、自然とのつながりを実感し、「自然という書物」から得られる感性を伝えようとする。
デカルトにより肥大化したプラクシス(意識的行為)に石川仁のプラティーク(無意識的行動)を重ね合わせることで、脱近代への学問の扉が拓かれるように私には思える。
三谷克之輔(2008.5.24 更新)
-----------------------------------------------
■旅するときは風にのる :石川 仁(いしかわ じん)■
『Open-J BOOMERANG』vol.363 2003.8.4より転載
葦船は人が行きたい場所に自由にいける乗り物ではない。 かといって、自然によって勝手に運ばれるかって言うと、それじゃ漂流物といっ しょ。葦船は、自然と人が話し合って行くべき場所にたどり着く船なんだと思う。
僕は、都会で生まれ育った。でも何かが違うんだって思ったとき、すでに旅が始 まっていた。理由はいつも後からついてくる。理由は存在してればいいんだと思う。だから、気づいたときにはアメリカにいたしヨーロッパにいたし、インド の土の上に居た。
インドはみんなが言うように、何かを変えてくれるところだと思う。もうちょっと正確に言うと自分が閉じこもっている「殻」を割ってくれるところ。インドには手ぶらでいった。先入観を持たないために、地図もガイドブックも見 ない旅だった。(そんな自分に酔っているところもあったんだけど) それはさておき、感じたんだ。
漁師のおじさんの家に連れてってもらったときのこと。 彼の家は椰子の葉っぱでできていて、床は土、その上にゴザを敷いてランプをともして家族五人が住んでいた。カレーをご馳走してくれたんだけど、皿なんかなくてもぎたてのバナナの葉っぱの上にご飯を盛ってカレーをかけて右手で食べる。
歯のかけたお父さんと、黄色いサリーを着たおかあさんと、ちっちゃい子供がニコニコして、僕がうまそうにカレーを右手で食べるのを見ている。もちろん言葉 んて通じない。言葉はね。そのとき感じたんだ。
豪華な家でも食事でもないし、学歴なんて言葉もないこの場所で、心地よい時間と空間が僕の周りをゆっくりとながれているのを。 そして、そのときに「じゃあ、一体この心地よさはどこから来るのだろう?」
そのシンプルな疑問が、頭に浮かんだとき、僕の周りにあった「殻」にひびがは いった。
「便利なものがあれば、お金があれば、地位が上がれば幸せになれる。」と教え られてきた殻が。それから、僕の時間をさかのぼる旅が始まった。カバンの中には、「幸せって何だろう? 文明社会って何だろう? お金って何だろう? いいこと 悪いことって何だろう? 人間ってなんだろう?」 なんて言葉が詰まっていたかどうかは知らないけど、気づいたらアフリカで野 生動物を目の前にウットリしている僕が居た。
「人間が、この地球に生まれる前ってこんな風だったのかなぁー」 キリンが地平線を優雅に歩いているのを観ながら、サバンナが奏でる自然のハー モニーを心で聴いていた。
その次、ハッ!と気づいたらサハラ砂漠をラクダといっしょに一人で(すごく暑 いのに)歩いていた。 「幸せって何だろう?」 そうだ!「いま、生きているだけで幸せだ」と、感じることができること。
それだったら、一回「死」を体験してみよう。 生と死のボーダーラインの上を歩いて、死の恐怖と生の喜びを体感したい。 バカだよね。 こうして一人で半年間、サハラ砂漠をラクダの「ダン」とともに2700キロの 旅に出た。 砂漠は、簡単に本当の自分と向き合える場所のひとつだと思う。
毎日毎日、瞳に写るのは、「青」と「茶色」の非常に単純な世界。 しかも、「死ぬかもしれない!」なんていう、大げさじゃないプレッシャーが肩にはいつも乗っている。バカ暑のなか歩きながら、バーっとある星を眺めながら、 歌える歌はすべて歌った。思い出せる過去の記憶はすべて思い出した。想像できる将来のことはすべて想像した。とにかく、時間だけは、無限にあったから。
ほかには何にもなかったけど、僕の心の中は果てしなく広がっていた。 「地球の始まりって、こんなだったのかなー」なんてことも何度か、「フッ」と思った。
砂漠での半年の間に、歌える歌は全部歌って、思い出せることは全部思い出して、 想像できる将来は全部想像した。心の部屋の中を大掃除するみたいに。 ゴールに着く当日、「あと三時間も歩けばいいんだ、もう、水のことも、食べ物 のことも、死ぬことも心配しなくていいんだ。僕は生きている。」 そう思ったとき、「からっぽ」になった。
そして次にふと気づくと白い世界に居た。アラスカの一番北の町でイヌイットの人たちと暮らした。上も下も右も左も前も後ろも、真っ白な氷の上に一人で立ったときのこと。「地球」が一人の友達みたいに思えてついつい話しかけてしまった。
「地球さん、環境が汚れちゃって大変じゃない?」 「そう言う君も、いろいろ大変そうだね」 「でも、うれしいこともあるんだよね」 「そうそう、うれしいこともあるんだよね」 「これでいいのかもね」 「これでいいんだよ」
ジャングルを丸木舟で河下りするまで死にたくない! マラリアが発病し高熱で頭がヘンテコリンになりそうなとき(ちなみに日本で)、その思いだけが絞り出てきた。そして、幻覚が現実になったとき、コロンビアのジャングルの中にいた。
緑の世界は、何百万の種類の、植物、動物、昆虫、菌類、魚がうごめいている。 一歩間違えば大混乱を招くような、生き物のオンパレード。でもそれが、不思議と美しい。ちょうど、ありとあらゆる楽器を持ちよったオーケストラが、ひとつ のシンフォニーを奏でているような。
ジャングルの中を一人で歩いたり、寝たりするのはすごく怖いけど、その音楽が 僕の深い何かと共鳴するのがとにかく心地いい。 茶色い水の流れの上をカヌーでスーっと進ませると、川イルカが遊びに来て水を かけたりもした。何百万年も変わらないハーモニー。意味もなく涙がこぼれた。
僕は葦船って乗り物がすごく好きなんだ。 何千年も前の古代船に揺られて、魚を釣りながら毎日過ごしていると、何かが変 わってくる。もちろん最初の1、2週間は陸のことを思い出したり懐かしんだりもする。 でもそれが過ぎると船の上だけが僕らの世界になっていく。
昼飯を食べた後(マグロの刺身と味噌汁と白米が基本)、ごろりと竹でできた甲板でねっころがって雲なんか見上げていると、すごい昔、航海してた人たちと何 にも変わんない生活のなかにいる。タイムマシーンに乗ったみたいに、いきなり縄文時代にトリップしたみたいな感覚。
生活自体は毎日同じことの繰り返し。船の舵を取って、食べて、寝る。 ただ、それだけの毎日が続く。
そうすると、心の深いところが、働き始めるような気がする。 そのときに、人が船とひとつになり、船が海と空と風がひとつになる。その心地よい感覚が自然との一体化なのだと思う。
千葉FMラジオ局Bay FM(2004.02.29放送)/ゲストトーク・リスト/ザ・フリントストーン
カムナ葦舟プロジェクト
石川仁さんインタビュー
近代の終焉(ラストモダン)を迎えている今、石川仁は「自然という書物」を求めて旅をする。近代化の先端にあるアメリカ、アメリカの母体であるヨーロッパ、文明の発祥の地インドと歴史を遡る旅の後、 人間の生まれる前を想像する場所としてアフリカのサバンナに行き、ついには何もない場所、サハラ砂漠をラクダとともに2700キロの旅に出た。
それは、死の恐怖と生の喜びを体感する旅であり、ときどきラクダに「オマエなー」と呼びかけ、いつまでもついてくるハエに「ウルサイなー、どこかへ行けよ」と語りかける以外に仲間はない。そこは、自分と対話することで、自分の歴史を振り返り、本当の自分と向き合える場所であったという。
それで旅は終わらない。空の青と茶色の砂以外は何もない砂漠の次は、白一色のアラスカの世界、さらに南米コロンビアのジャングルの川を下り、 高い山々のアンデスを旅し、チチカカ湖で葦舟と出会う。葦舟の古代船を復元したマタランギ号で古代の「海の道」を検証する旅に加わり、今は、日本で建造した葦舟で太平洋横断の実験実証の旅に出る夢を育てる。 その夢は、太古の智慧を尊ぶ心から湧き出でる。太古の智慧とは、自然と共に生きること。それが旅の辿りつく場所。
現代では「常識」を意味しているコモン・センスという言葉は、もともとアリストテレス以来、五感を統合する根源的能力を意味する「共通感覚」という言葉として使用されていた。石川仁の旅は、デカルト以来「知識」という殻に閉じ込められてしまった「共通感覚」を呼び覚ます学問の旅だと、私は思う。
デカルトは「世界という大きな書物」のうちに見つかるかもしれない学問を求めたが、結局は理性と感性を分断し、「書かれたもの」を通じての理性の学問を肥大化させた。 しかし、石川仁は「書かれたもの」を残そうとしない。葦舟をつくり、それに乗ることで、自然とのつながりを実感し、「自然という書物」から得られる感性を伝えようとする。
デカルトにより肥大化したプラクシス(意識的行為)に石川仁のプラティーク(無意識的行動)を重ね合わせることで、脱近代への学問の扉が拓かれるように私には思える。
三谷克之輔(2008.5.24 更新)
-----------------------------------------------
■旅するときは風にのる :石川 仁(いしかわ じん)■
『Open-J BOOMERANG』vol.363 2003.8.4より転載
葦船は人が行きたい場所に自由にいける乗り物ではない。 かといって、自然によって勝手に運ばれるかって言うと、それじゃ漂流物といっ しょ。葦船は、自然と人が話し合って行くべき場所にたどり着く船なんだと思う。
僕は、都会で生まれ育った。でも何かが違うんだって思ったとき、すでに旅が始 まっていた。理由はいつも後からついてくる。理由は存在してればいいんだと思う。だから、気づいたときにはアメリカにいたしヨーロッパにいたし、インド の土の上に居た。
インドはみんなが言うように、何かを変えてくれるところだと思う。もうちょっと正確に言うと自分が閉じこもっている「殻」を割ってくれるところ。インドには手ぶらでいった。先入観を持たないために、地図もガイドブックも見 ない旅だった。(そんな自分に酔っているところもあったんだけど) それはさておき、感じたんだ。
漁師のおじさんの家に連れてってもらったときのこと。 彼の家は椰子の葉っぱでできていて、床は土、その上にゴザを敷いてランプをともして家族五人が住んでいた。カレーをご馳走してくれたんだけど、皿なんかなくてもぎたてのバナナの葉っぱの上にご飯を盛ってカレーをかけて右手で食べる。
歯のかけたお父さんと、黄色いサリーを着たおかあさんと、ちっちゃい子供がニコニコして、僕がうまそうにカレーを右手で食べるのを見ている。もちろん言葉 んて通じない。言葉はね。そのとき感じたんだ。
豪華な家でも食事でもないし、学歴なんて言葉もないこの場所で、心地よい時間と空間が僕の周りをゆっくりとながれているのを。 そして、そのときに「じゃあ、一体この心地よさはどこから来るのだろう?」
そのシンプルな疑問が、頭に浮かんだとき、僕の周りにあった「殻」にひびがは いった。
「便利なものがあれば、お金があれば、地位が上がれば幸せになれる。」と教え られてきた殻が。それから、僕の時間をさかのぼる旅が始まった。カバンの中には、「幸せって何だろう? 文明社会って何だろう? お金って何だろう? いいこと 悪いことって何だろう? 人間ってなんだろう?」 なんて言葉が詰まっていたかどうかは知らないけど、気づいたらアフリカで野 生動物を目の前にウットリしている僕が居た。
「人間が、この地球に生まれる前ってこんな風だったのかなぁー」 キリンが地平線を優雅に歩いているのを観ながら、サバンナが奏でる自然のハー モニーを心で聴いていた。
その次、ハッ!と気づいたらサハラ砂漠をラクダといっしょに一人で(すごく暑 いのに)歩いていた。 「幸せって何だろう?」 そうだ!「いま、生きているだけで幸せだ」と、感じることができること。
それだったら、一回「死」を体験してみよう。 生と死のボーダーラインの上を歩いて、死の恐怖と生の喜びを体感したい。 バカだよね。 こうして一人で半年間、サハラ砂漠をラクダの「ダン」とともに2700キロの 旅に出た。 砂漠は、簡単に本当の自分と向き合える場所のひとつだと思う。
毎日毎日、瞳に写るのは、「青」と「茶色」の非常に単純な世界。 しかも、「死ぬかもしれない!」なんていう、大げさじゃないプレッシャーが肩にはいつも乗っている。バカ暑のなか歩きながら、バーっとある星を眺めながら、 歌える歌はすべて歌った。思い出せる過去の記憶はすべて思い出した。想像できる将来のことはすべて想像した。とにかく、時間だけは、無限にあったから。
ほかには何にもなかったけど、僕の心の中は果てしなく広がっていた。 「地球の始まりって、こんなだったのかなー」なんてことも何度か、「フッ」と思った。
砂漠での半年の間に、歌える歌は全部歌って、思い出せることは全部思い出して、 想像できる将来は全部想像した。心の部屋の中を大掃除するみたいに。 ゴールに着く当日、「あと三時間も歩けばいいんだ、もう、水のことも、食べ物 のことも、死ぬことも心配しなくていいんだ。僕は生きている。」 そう思ったとき、「からっぽ」になった。
そして次にふと気づくと白い世界に居た。アラスカの一番北の町でイヌイットの人たちと暮らした。上も下も右も左も前も後ろも、真っ白な氷の上に一人で立ったときのこと。「地球」が一人の友達みたいに思えてついつい話しかけてしまった。
「地球さん、環境が汚れちゃって大変じゃない?」 「そう言う君も、いろいろ大変そうだね」 「でも、うれしいこともあるんだよね」 「そうそう、うれしいこともあるんだよね」 「これでいいのかもね」 「これでいいんだよ」
ジャングルを丸木舟で河下りするまで死にたくない! マラリアが発病し高熱で頭がヘンテコリンになりそうなとき(ちなみに日本で)、その思いだけが絞り出てきた。そして、幻覚が現実になったとき、コロンビアのジャングルの中にいた。
緑の世界は、何百万の種類の、植物、動物、昆虫、菌類、魚がうごめいている。 一歩間違えば大混乱を招くような、生き物のオンパレード。でもそれが、不思議と美しい。ちょうど、ありとあらゆる楽器を持ちよったオーケストラが、ひとつ のシンフォニーを奏でているような。
ジャングルの中を一人で歩いたり、寝たりするのはすごく怖いけど、その音楽が 僕の深い何かと共鳴するのがとにかく心地いい。 茶色い水の流れの上をカヌーでスーっと進ませると、川イルカが遊びに来て水を かけたりもした。何百万年も変わらないハーモニー。意味もなく涙がこぼれた。
僕は葦船って乗り物がすごく好きなんだ。 何千年も前の古代船に揺られて、魚を釣りながら毎日過ごしていると、何かが変 わってくる。もちろん最初の1、2週間は陸のことを思い出したり懐かしんだりもする。 でもそれが過ぎると船の上だけが僕らの世界になっていく。
昼飯を食べた後(マグロの刺身と味噌汁と白米が基本)、ごろりと竹でできた甲板でねっころがって雲なんか見上げていると、すごい昔、航海してた人たちと何 にも変わんない生活のなかにいる。タイムマシーンに乗ったみたいに、いきなり縄文時代にトリップしたみたいな感覚。
生活自体は毎日同じことの繰り返し。船の舵を取って、食べて、寝る。 ただ、それだけの毎日が続く。
そうすると、心の深いところが、働き始めるような気がする。 そのときに、人が船とひとつになり、船が海と空と風がひとつになる。その心地よい感覚が自然との一体化なのだと思う。
千葉FMラジオ局Bay FM(2004.02.29放送)/ゲストトーク・リスト/ザ・フリントストーン
カムナ葦舟プロジェクト
石川仁さんインタビュー

















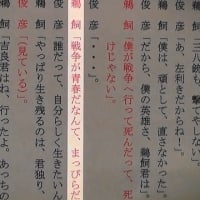



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます