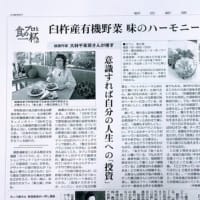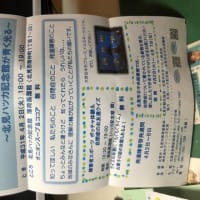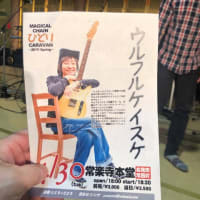北見市9月定例議会 質問は、この件と、常呂の風力発電についての2件を質問しました。
質問内容は、以下の通りです。
質問1)通告に従い質問させていただきます。
9月質問・・障がい者の「地域生活拠点」整備の取り組みについて
2020年1月に国内で初めて新型コロナウイルスが確認されてから9カ月目に入っています。急速な感染拡大は、同時に私たちの社会のあり方に計り知れない影響を与えています。▼北見市は、医療的ケアなど、最も重い重複障がいを抱えながら在宅で生活を送る当事者の皆さんに対し、いち早く、新型コロナ感染症対策支援の情報提供を行うなど、その機敏な対応に当事者、関係者のみなさんに代わりお礼を申し上げます。
▼その一方で、先の質問にもありましたが、コロナ差別という社会現象の渦中でもあります。全ての人が大変に不安な思いをされているとはいえ、社会全体の自粛規制は、障がいのある人たちを取り巻く環境も例外ではなく、障がい者の地域生活に多くの課題を突き付けました。感染の不安を抱えながら、不自由な生活を未だに強いられているのが現状です。▼その障がいの特性からマスクの着用ができない人もいますし、知的障害や自閉症の障がいであれば、学校の休校や支援事業所の休所など「突然の予定変更」に理解ができず混乱し見守る家族の負担が増したり、医療的ケアの必要な人の場合、感染リスクを避けようとすると、体調を整えるリハビリや療育、訪問支援、定期受診も自主的に制限せざる負えい家庭も少なくなかったと確認しています。▼障がい支援事業所においては、できる限りの感染リスクの回避策を講じながら、「感染者がでませんように」と祈る思いで可能な限りの支援事業に取り組んでいますが、未だに以前のような和やかな生活支援の回復目処が見えてこない状況です。
▼残念な話ですが、自粛の閉塞感の中で何が起きているか。障がいを持つ青年が、6月に一人でバスを待つ北見交通ターミナルにおいて、心ない若者たちから抵抗できない状態で足を踏み続けられ腫れあがったという暴力行為のあったことを当事者家族の声として聞いております。自分の目には映らないからと言って、無いことにはできない現実が身近な地域にもあるということ。自粛警察、同調圧力社会は少数者を排除へと導く無言の圧力でもあります。みんな同じ北見市民です。そんな行為がまかり通る社会にしてはいけません。
▼この新型コロナウイルス感染症対策を求めて、様々な障がい者団体から国に対し、緊急要望書が提出されていますが、全国肢体不自由児者父母の会連合会から国に提出された要望書には、その要望項目の最初に「いかなる状況においても、第三者による命の選別は行わないこと」と訴えておりました。昭和の時代、戦後に有った優生思想に基づく命の選別、そして現代の同調圧力、その意識の底流に流れる障がい者差別、同類の危うさを感じます。▼北見市においても、分け隔てなく障がい児者への適切な配慮を求めることともに、障がい者差別の無い街づくりを推進する積極的かつ継続的な市民への啓発、発信に努めていただきたい。
●では、質問に入ります。
現在、進められている障がい者の「地域生活支援拠点」の取り組みについてお聞きします。▼この事業、地域拠点整備とは、どういうものか?家族の病気、高齢化等による支援能力の低下、当事者の心身の不調、虐待事件など、様々な要因で急に手厚援が必要になったり、専門的な支援や環境調整が必要になることが、障がいのある人には起こります。大変な時に一歩踏み込む、一緒に支えてくれる支援が必要です。その「地域生活拠点」を、北見市単独では無く定住自立圏協定を結んだ1市4町を区域として、令和3年度からの運用を目指し、北見市が中心になり現在準備が進められています。
▼準備期間は残すところ半年を切りました。新型コロナ感染症対応等による準備不足が懸念されます。 ▼その具体的な整備内容は、「多面的な拠点整備」として、北見市内に拠点の総合窓口となる「基幹相談支援センター本体」を第1多機能拠点として設置、さらにエリア内で唯一の医療的ケアが必要な重症心身障害児者や発達障がい児者への支援に取り組む病院・施設のある美幌町を第2機能拠点(基幹相談センターサテライト)と位置付け、さらなる機能拡充を図るとともに、それぞれを複数の法人に委託し運営する体制づくりをするものと認識していますが、これまでの進捗状況に関してお聞きします。
▼国は、この拠点整備に5つの機能拡充を求めています。▼相談支援機能について、24時間体制で対応できる地域の相談支援体制づくりを求めています。1市4町を対象に24時間の相談支援体制をどのように組み立てる考えか?おきかせください。▼次に、緊急時の受け入れ・対応機能についてお聞きします。家族と同居する知的障害者の場合、家族の緊急時に「何とかしてくれる」短期入所を中心とした緊急時の支援体制の構築は欠かすことができません。北見市は平成30年度に制度化された新しいタイプ「日中サービス支援型」のGHを併設するとのことです。重度障がい者や高齢期を迎えた障がい者を受け入れることが期待されていますが、短期入所も別定員で併設することになっています。GHという夜間支援を提供する事業所の特性を生かす手法として、緊急時の短期入所といった支援にも対応すると理解をしていいのでしょうか?お聞きします。▼3つ目、体験の機会・場の提供機能について。主に入所施設や精神病院から地域生活へ移行する際や、家族との生活から自立した生活へ移行するための支援機能が求められていますが、どのように対応するのか?お聞かせください。▼次に専門的人材の確保・養成機能について、特に重い発達障害や行動障がいのある人、医療的ケアを必要とする人への支援を担う人材は不足した状況です。専門的人材の育成は、以前からその確保について求めてきたところですが、仮に相談支援や緊急対応の体制が整備されても、これまでのように既存の施設において、行動障がいなどを理由に受け入れ拒否されてしまっては意味が有りません。重度とされる障がいのある人でも対応できる支援員の養成が求められています。どのように専門的な人材を確保、養成するのか?お聞かせください。▼求められる5つ目の機能は、地域の支援体制づくり機能です。この「地域生活支援拠点」の取り組みは1市4町が対象です。そのイメージ図では、医療機関や就労継続支援事業所、訪問看護ステーション、入所施設、GHを主な拠点に連携するとしています。面的整備は既存の病院や事業所等の関係機関を想定しているようです。新たな建物の整備や核となる施設等の指定が不要ですから、カタチは素早くできるかもしれませんが、それぞれに対し、必要とする機能を明確化しないと、単なる現状維持になってしまう懸念があります。特に、それぞれの既存施設や事業所が何を求められているのか。どのような機能を拡充すればいいのか。その機能拡充には、どういう段取りと行政支援が必要なのか。そのことを明確化する事前検討が必要と考えます。
▼新型コロナ感染症防止による会議も開催できない状況下で、北見市と美幌町に拠点を二か所配置しても、各地域に暮らす人たちの具体的な課題に、どこまで掘り下げた議論ができているのか?3月までの完成品を求めれば既存の病院や障がい福祉、事業所の連携を「面的整備」と位置付けて完結してしまうのではないかと心配もします。この面整備の具体的な取り組みの準備として、1市4町に暮らし、この支援拠点の利用が想定されるみなさんの生活実態を事前に把握しておくことが求められます。必要に応じた個別のサービス利用計画と同時に、緊急事態の発生時に対応するための「クライシスプラン(危機対応計画)」の作成も必要です。●そのことを、どう進めているのか、お聞きします。
▼この地域生活拠点整備に、当事者のみなさんの意見はどのように反映されるのか?各自治体には障がい者の地域生活の向上に関する話し合いの場として、当事者、関係者で組織する自立支援協議会が設けられています。●その自立支援協議会が、この拠点整備にどのように関わるのか?▼また地域生活拠点の利用対象となる個別の障がい者団体との意見交換、連携も欠かせないと思います。どのような対応が図られているのか現状をお聞きかせください。
◆再質問・地域生活拠点について
北見市の自立支援協議会(ネットワーク)は、今回、整備する拠点に事務局を置いて、今後の対応を考えているとのことでした。自立支援協議会の役割からすると、その選択は理解するところです。▼自立支援協議会メンバーには、障がい者団体連合会の代表者は参加しておりますが、代表者が、全ての課題を把握しているわけではありません。▼特に、この支援拠点の整備に求められる、この地域に社会資本の少ない発達障がいや医療的ケアの必要な方たちの地域生活を支える取り組みです。北見市と美幌町に整備する機能拠点の機能を活かしながら、訓子府町、置戸町、津別町に暮らす当事者のみなさんの、それぞれの街で安心して地域生活をおくれる環境づくりです。●では来年、4月以降のについて、求められる拠点機能の達成度、進捗管理は、どこがするのか?見解をお聞かせください。
◆再々質問)意見
▼地域生活拠点について・・・限られた時間での地域生活拠点整備です。地域の体制づくり強化・24時間の相談体制について、クライシスプランの対応を図ることで、現段階では想定していないとの事ですが、安心の地域生活支援には欠かすことができない機能と考えます。運営当初からの体制づくりに努力いただきたい。▼来年3月に「完成形」は求めてもできるものではないと理解しています。ですが、「完成図作り」は着実に進めてほしいです。▼一昨年、福祉民生常任委員会の行政視察研修として、この事業を全国に先駆けて取り組んだ千葉県柏市を訪問しました。その時、柏市の担当者からは「拠点施設の建設が要ではあるが、それ以上に市内の各施設をネットワーク化し、相談者や利用者の目線で対応を行っていくこと。各施設をネットワーク化することで、すべての障がい者の受け入れを目指しています」と、完成図を目指し関係者が一体的に動いていることを感じさせる力強い言葉を耳にしました。この定住自立圏の支援拠点の整備は「5つの機能」がどのような状態になったらOKといえるのか。その到達点・完成図を1市4町の関係者全員が共有し進めることが、来年3月までに求められると思います。基幹拠点に自立支援協議会の事務局を配置する考えですが、1市4町の自立支援協議会と連携することも欠かせません。
▼辻市長は、今年度の市政執行方針で、この事業を「北見地域定住自立圏共生ビジョン」の取り組みとして位置付けています。定住自立圏として自治体間、関係者との連携・協議と、時間の無い中で大変とは思いますが、初めての1市4町が連携して取り組む事業です。今後の自治体間の信頼関係づくりにも試金石になると考えます。定住自立圏の中心都市として、しっかりと取り組んでいただきたい。よろしくお願いします。