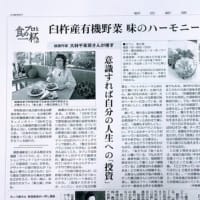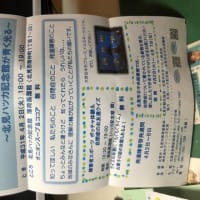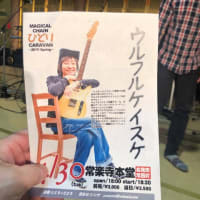12月定例議会質問
②医療的ケア児支援法に基づく地域支援について
本年6月、国会で、新たな法律として議員提案による「医療的ケア児支援法」が可決されました。人工呼吸器や痰の吸引などの医療行為を日常的に受けることが不可欠な児童を対象に、国や地方公共団体の責務として位置づけられています。保育所、学校への看護師の配置支援、そして卒業後も配慮をした支援、家族の離職防止、ワンストップで相談に当たる「支援センター」の設置等地域社会に支援体制の確立を責務として求めています。日常生活や社会生活を地域社会全体で支える仕組み作りとして、保育所、学校に配慮する看護師に加え研修を受けた介護福祉士らも育成し活用するとのことです。北見市の医療的ケア児の支援状況と今後の課題についてお聞きします。
これまで北見市内の医療的なケアが必要な児者を含めた重症心身障害児者の在宅支援に取り組む事業所は、その看護師の配置を含めた支援体制確保の難しさもあり、一つの事業所に負荷が集中してきましたが、本年6月より病院内に併設して開業した看護小規模多機能型居宅介護事業所が、医ケア児の放課後デイ1名の受け入れを開始。週末土曜日だけの日中一時支援に取り組んでいた高齢者デイサービス事業所が受け入れ人数を2名から3名に増やしたなど、少しずつ支援は拡充されています。しかし医ケア児の生活介護や日中支援に関しては、当事者家族からの利用環境の拡充を求める声には応えられる状況には至っておりません。
近隣自治体の状況を見ても、医ケア児も含めた重症児者の受け入れ事業所は無く、現在は北見市にある医療的ケア児の日中活動の中心的な事業所には、網走市在住の学校を卒業した青年が1名通っていますが、来春には北見支援学校高等部を卒業する美幌町在住の重症児者1名が加わると見込まれています。幼児期から青年期の若者までが混在する中、日中活動に取り組んでいただいていますが、希望通りに通えない状況にあるとの青年期を迎えた利用者・家族の声も聴こえています。
北見市内に暮らす医療的ケア児は微増傾向ですが、学校卒業後の利用者の社会参加、家族の負担軽減を考える時、医療的ケア支援法が対象とする幼児期から学齢期、青年期の支援を、北見市ばかりでなく北見地域定住自立圏協定をむずぶ周辺自治体以外からも、その児から者への切れ目の無い支援、地域格差の無い支援を求められてくることが今後は予想されます。
▼近隣自治体の医ケア児を含めた重症児者の日中活動の場の確保、事業所拡充の見込みはあるのでしょうか?▼また短期入所の受け入れの現状と、▼医ケア児支援法が目指す幼児期・学齢期・青年期との支援体制づくりを、自治体の責務として今後、どのように社会資源の整備に取り組んでいくのか。考えをお聞かせください。
◆再質問・意見)
医療的ケア児を対象とした放課後デイに関しては、あらたに市内の病院内に事業所が開設されたと確認していますが、最初の質問でも言いました。現状は、まだまだひとつの事業所が放課後デイ、生活介護と幼児期から青年期までを対象とした支援をしています。そこに選択の余地もありません。
やはりこれからは、学齢期までと支援学校卒業後の日中活動に特化した支援の住み分けを図る事業所の早急な実現を求められます。医療的ケア児を含めた重い重複障がいを持つ重症心身障害児の地域生活支援は、北見市及びオホーツクの自治体にとって、その人数が他の障がい特性を持つ人たちと比較すると少数者であることから、福祉施策として必要な社会資源の整備が滞ってきた現実があります。
今後、周辺自治体とも情報交換をしながら、必要な社会資本整備を着実に進めていただきたい。
また今年、北見市を含めた定住自立協定自治体の取り組み第1号として4月に障がい者基幹相談センター「ささえ~る」が開設されました。そこには医療的ケア児の相談支援コーディネーターの資格を持った職員も配置されています。国は、この医療的ケア児支援法において、都道府県に基幹相談センターの設置も義務付けています。今後、広い北海道ですから、他の障がい同様に幾つかのブロックに区域を分け、基幹センター設置を北海道は計画するはずです。障がい者基幹相談センターささえ~るは、定住自立圏エリアばかりでなく、その社会的役割としてオホーツク、道東ブロックを対象とした基幹相談センターの機能を北海道より求められるかもしれません。周辺自治体と相互理解の上で、オホーツク・さらに道東エリアの医療的ケア児の支援拠点を北見市につくるべきと提案して意見とします。